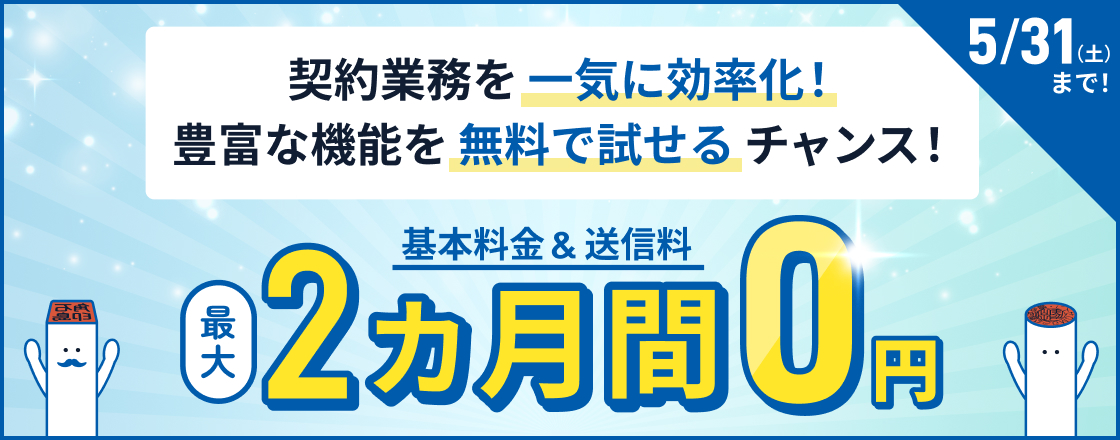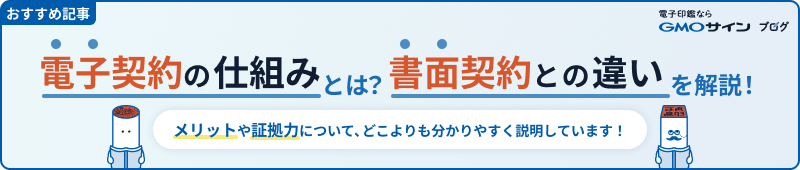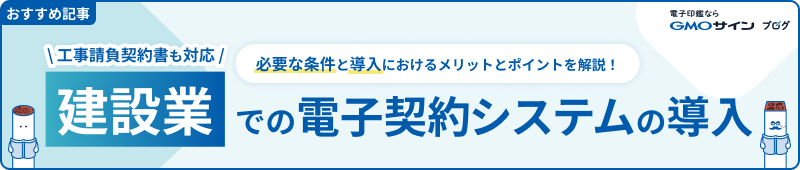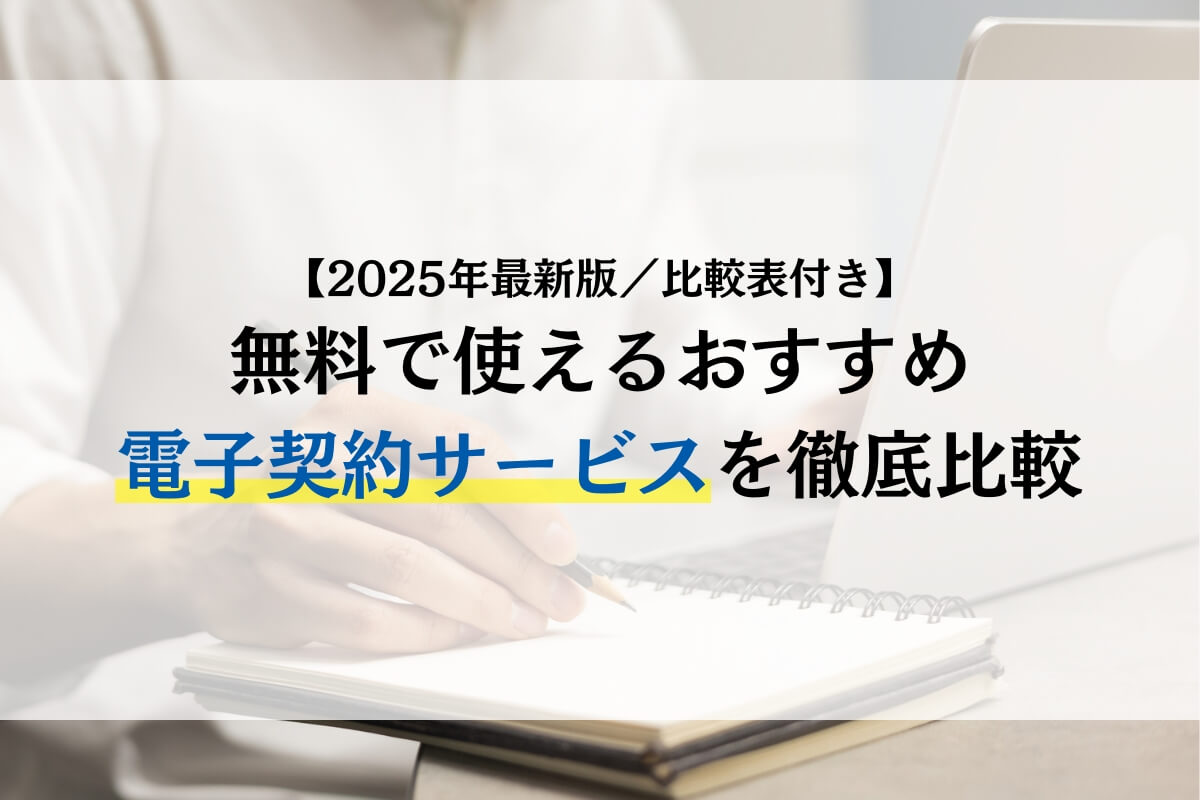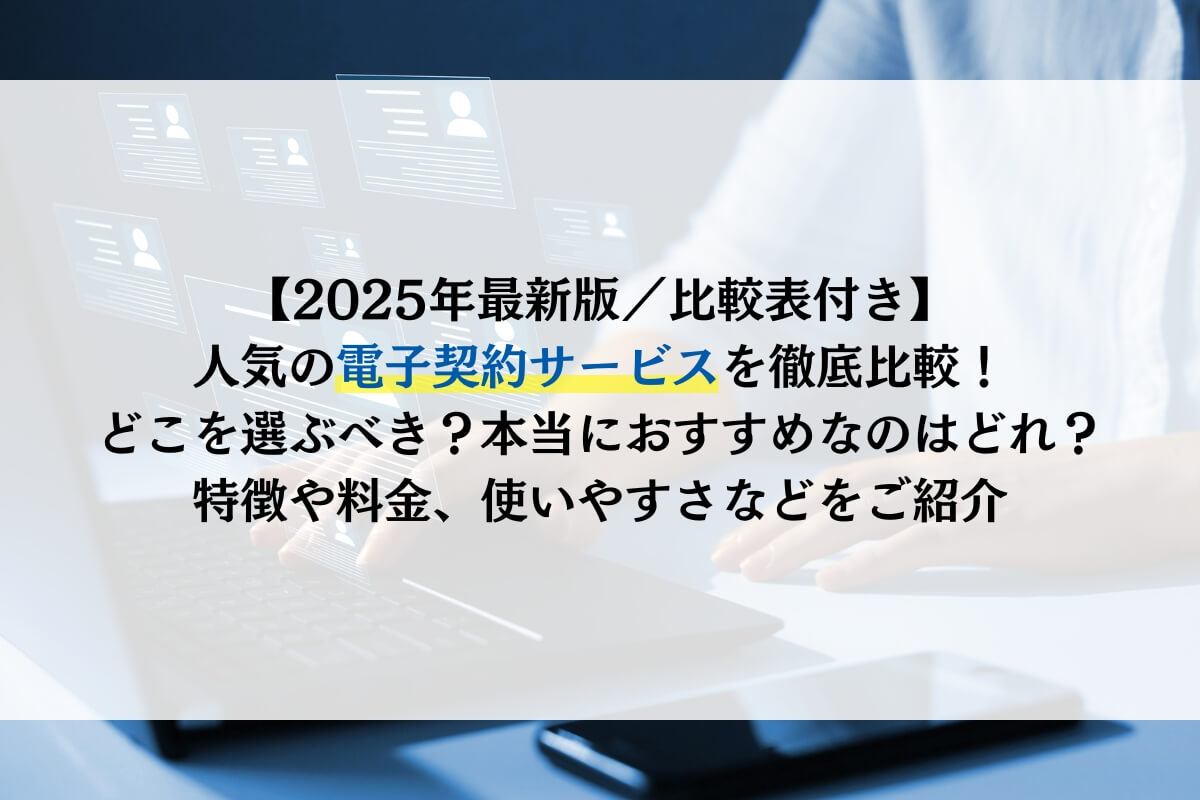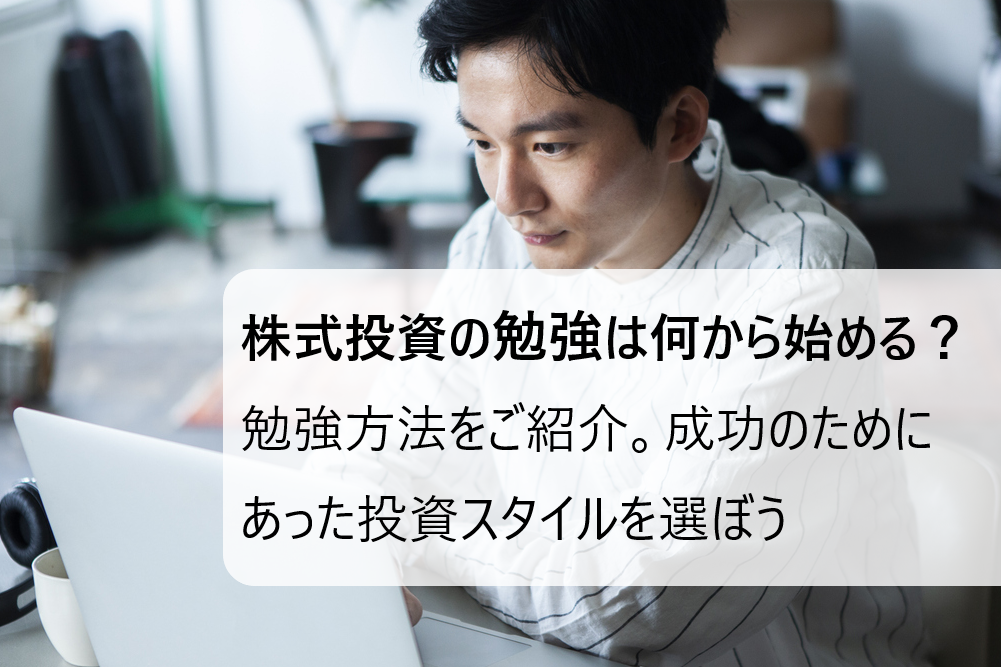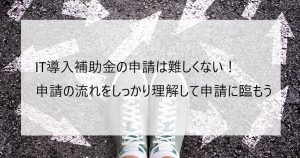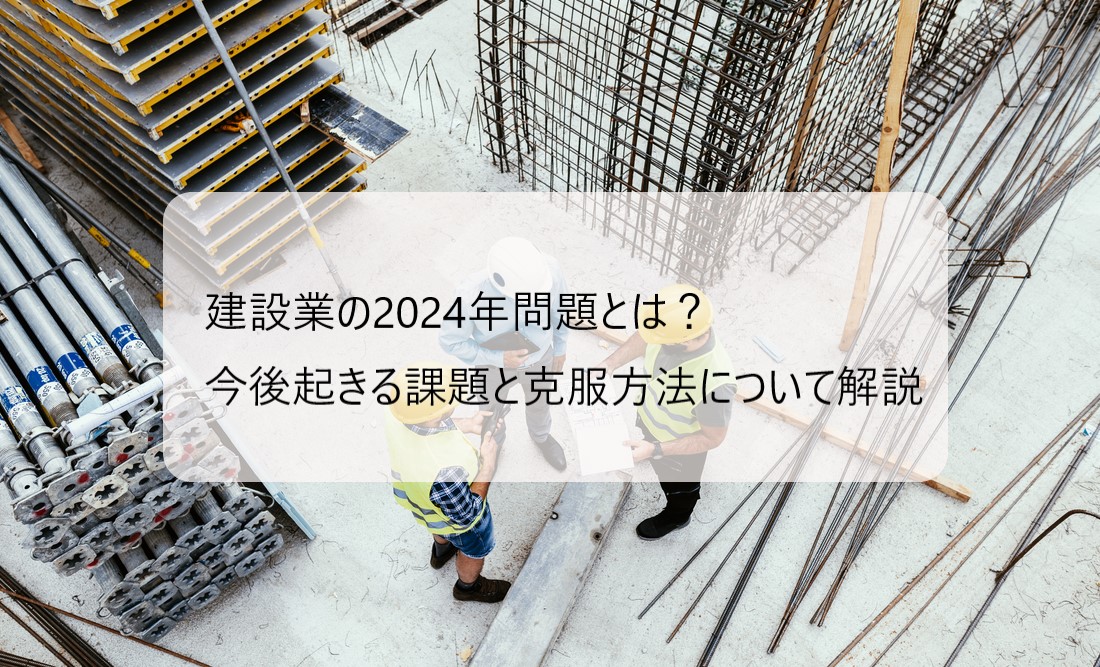成年・未成年の定義は、社会の基盤となる重要なルールの一つです。このルールは、商品・サービスの提供や契約に際し、年齢による利用制限や保護者の同意確認をするフローなどの形で、企業経営にも大きな影響を及ぼしています。
2022年、民法の改正により成年・未成年の定義が一部変更され、企業によっては利用規約や業務フローなどが影響を受けることになりました。
今回は、民法の改正内容を概観したうえで、成年・未成年の定義変更が企業にどのような影響を与えたのか、またどのような対策が必要となったのかご説明します。
目次
未成年者が契約するには原則として親権者の同意が必要
民法第5条によると、未成年者は原則として法定代理人の同意がなければ法律行為を行うことができません。ここでの法定代理人とは、未成年者の親権者などの成人を指します。ここでいう法律行為とは、契約の締結や訴訟などが挙げられます。
未成年者は、成年者と比べて経験や知識、判断能力が不足しているため、法律行為を単独で行った場合には詐欺などのトラブルに巻き込まれるリスクが高くなってしまいます。そのため、未成年者保護の観点から、法定代理人の支援(同意)が必要とされているのです。仮に未成年者が同意を得ずに法律行為を行った場合、法定代理人は契約を取消して無効にすることができるようになっています。
たとえば、未成年者だけで携帯電話利用の契約を結ぶことはできません。必ずしも法定代理人が店舗へ同行する必要はないのですが、法定代理人が記入した同意書や法定代理人の本人確認書類のように、契約の締結が許可されていることを示す書類を、未成年者が自分で持参しなければなりません。一人暮らしをするための賃貸借契約や、クレジットカードの作成なども同様です。
こうなると、「一般的なスーパーやコンビニなどの買い物も未成年者だけではできないのか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。この場合は、支払う代金がお小遣い(正確には「法定代理人から処分を許された財産」)の範囲内であると考えられるため、未成年者本人だけでもできます。
一方、お小遣いの範囲では支払えないような高額商品・サービスを父母に無断で子供が購入・利用する契約を締結するのは、許容範囲を逸脱すると考えられるため、親権者の同意が必要となります。
【出典】参考:基礎知識「未成年者契約の取消し」(東京くらしWEB)
法定代理人の同意なしに未成年者が行った契約は、原則として取消すことが可能とされています。つまり、その契約によって不利益を被るような場合には、相手方に対して取消通知を送ることで契約を取消し、契約自体を初めからなかったことにすることができるのです。
この取消権の時効は未成年者が成年になったときから5年間、または契約の時から20年間とされています。また、取消せる法律行為に対して、後からその行為を取消さないと意思表示することもできます。これを追認といいます。
民法改正の前後で成年・未成年の定義がどう変わったのか?
改正前の民法では成年や未成年がどのように定義されていたのか、そして2020年に行われた民法改正後にどのように変わったのかを押さえておきましょう。
(1)改正前の民法における成年・未成年の定義
改正以前の民法第4条では、「年齢二十歳をもって、成年とする」と定められていました。言い換えれば、20歳に満たない人が未成年とされていたのです。このため、「20歳からが成人」というのが日本の常識でした。
(2)2022年の民法改正による変更点
2022年4月、民法が改正され成年・未成年に関する定義が変更されました。民法第4条で定められた成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたのです。これによって、男女を問わず18歳以上であれば、成人として法定代理人の同意を得ずに契約締結をはじめとした法律行為を行えるようになりました。
<法律の要点>
| 1 成年年齢の引下げ(民法第4条) |
①一人で有効な契約をすることができる年齢
②親権に服することながなくなる年齢 |
いずれも 20 歳から18 歳に引き下げ、「成年」と規定する他の法律も18 歳に変更 |
| 2 女性の婚姻開始年齢の引上げ(民法第 731条) |
(改正前)
男性 18 歳
女性 16 歳 |
(改正後)
女性の婚姻開始年齢を18 歳に引き上げ
婚姻開始年齢は男女とも18 歳に統一 |
他にも大きな変更点としては、女性の結婚可能年齢が挙げられます。改正前の民法では16歳でしたが、改正民法では男性と同じ18歳へ引き上げられました。
一方、喫煙や飲酒などが可能になる年齢は、以前と変わらず20歳のままです。また、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が短縮されるわけではない点にも注意が必要です。
成年年齢の引き下げの背景には、日本における「18歳」という年齢の重要性が増していること、そして世界的な潮流が挙げられます。もともと日本での成年年齢は明治9年以来、20歳と定められてきました。しかし、公職選挙法に基づく選挙権年齢や、憲法改正国民投票の投票権年齢が2018年より18歳へ引き下げられたことで、市民生活を規定する民法も足並みをそろえるべきではないかという議論が高まり、改正民法による引き下げにつながったと考えられます。
また、世界的にみた場合、アメリカやイギリスをはじめ、成年年齢を18歳とする国の方が多いという事情もあります。改正法施行前の時点において経済協力開発機構(OECD)諸国で20歳を成年年齢としていたのは、日本とニュージーランドだけでした。社会の高齢化が進む中で、18歳や19歳の「市民」の権利を拡充し、その自己決定権を尊重するとともに、積極的な社会参加を促すことも成年年齢引き下げの目的とされたのです。
【出典】民法改正 成年年齢の引下げ (2ページ目)

今回の民法改正は、既に2022年4月1日から施行されています。このため、現在の未成年者は男女を問わず18歳の誕生日に成年に達します。
成年年齢の引き下げによる企業への影響と対策
成年年齢が引き下げられたことで、企業やサービスはどのような影響を受けているのでしょうか。
BtoB企業、取引先が主に法人や企業が多い場合の影響は小さいかもしれません。しかし、未成年者を含む幅広いターゲットに商品・サービスを提供しているBtoC企業の場合、申込や契約、サービスの利用規約などの修正、情報システムや業務フローなどの変更が必要です。

(1)約款や利用規約の修正が必要
現行の約款や利用規約で未成年者をまだ20歳未満と定義している場合、内容の変更を行いましょう。たとえば、携帯電話会社やクレジットカード会社などの利用規約を見ると、「契約時に20歳未満の方が登録される場合は、法定代理人の同意を得ているものとする」といった趣旨の条項が記載されているケースも多いでしょう。これらを全て洗い出し、変更を加える必要があります。
こうした内容の確認や修正、法務チェックなどには、多大な手間がかかるものです。若者層をターゲットに含む限り、変更作業を避けて通ることはできませんが、この際年齢を指定せず「未成年」という表記に変えれば万全です。
(2)サービス登録者のステータス変更が必要
サービスの中には、未成年者または年齢で利用を制限ないし禁止しているものも多いでしょう。
改正民法の施行によって、2022年4月1日以降に18歳の誕生日を迎える人(および同日の時点ですでに18歳の誕生日を迎えているが20歳未満の人)はすべて成年に達することになりました。
まだ登録可否ステータスなどを切り替える作業を行っていない場合には、できるだけ早くシステム改修をする必要があります。
まとめ|企業は法改正の動きを見逃さずに対策を
2022年の民法改正によって行われた成年年齢の引き下げは、社会にとって重要な変化の一つであることは間違いありません。したがって、社会を支える一部である企業にとっても、この変化が重要なものであることもまた確かです。
業界に関連する法律や個人情報保護法などだけではなく、民法のように企業へ影響する法律の変化にも企業は目を配っておく必要があります。約款や利用規約、契約条件、システム、業務フロー、事業ポリシー、ビジネスモデルなどが影響を受ける範囲を明確にし、確認を怠らないようにすることが大切です。