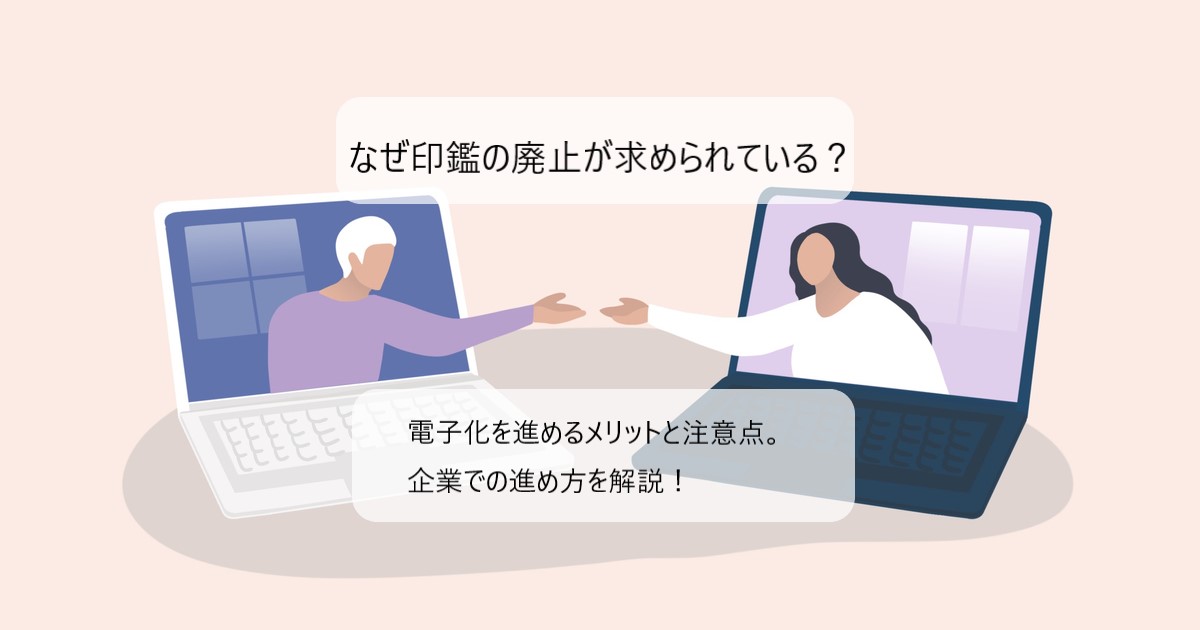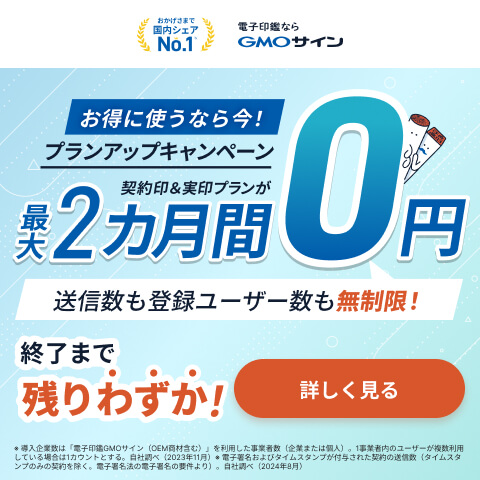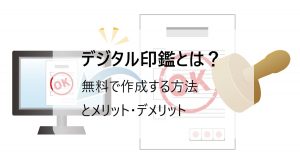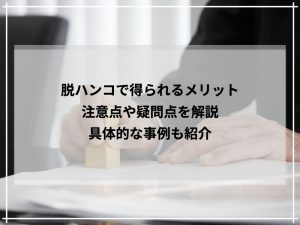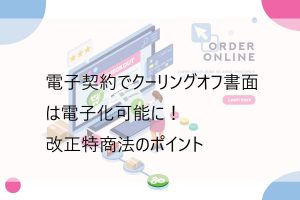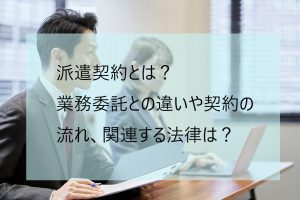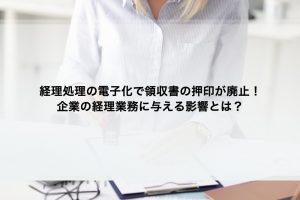2021年9月1日のデジタル庁創設に伴い、業務のデジタル化およびテレワーク普及の推進から、行政手続きにおける押印事務の見直しが行われました。また民間から行政に対して行う手続きでも、押印(印鑑)廃止の動きが進んでいます。
印鑑の廃止(電子化)は、コスト削減や生産性向上などのメリットが期待できます。しかし、印鑑を使用する場合とは異なる注意点も存在するため、事前に把握しておきましょう。
そこで本記事では、印鑑の廃止(電子化)が求められている理由や導入するメリットを解説します。印鑑廃止にあたっての取り組みの流れや注意点も紹介しますので、印鑑の廃止をすすめたい企業担当者の方に必見の内容です。
目次
印鑑の廃止(電子化)が求められている背景
印鑑の廃止(電子化)が求められている背景としてまず挙げられるのが、デジタル改革関連法の成立です。デジタル改革関連法とは、2021年5月12日に参議院本会議で可決されたデジタル社会の実現を目指す6つの法律の総称です。デジタル改革関連法の柱の一つに、印鑑の廃止(電子化)が位置付けられています。
デジタル改革関連法が成立した背景には、データの多様化や大容量化の進行に伴い、社会的にデータの活用が必要不可欠となったことが挙げられます。また新型コロナウイルス感染拡大対策として実施された政府から国民への給付金支給に伴う行政手続きで、行政のデジタル化の遅れが顕在化したことから立法が後押しされました。
さらに現在の日本では、少子高齢化の進行による労働力不足の解消が喫緊の課題とされています。この課題を解決するには、育児しながら働いたり、介護しながら仕事を続けられたりするなど、場所に縛られずに働き方を柔軟に選択できる仕組みが必要です。この仕組みを作るうえで、印鑑の廃止(電子化)は欠かせない施策と言えます。
印鑑の廃止によるメリット
印鑑を廃止した企業に期待されるメリットには、さまざまなものが挙げられます。本項目では代表的な4つのメリットを挙げ、詳しく解説します。
コスト削減につながる
コスト削減効果は、印鑑の廃止で得られる大きなメリットです。印鑑を用いて紙の契約書を他の会社と締結する場合では、以下のようなさまざまなコストが発生します。
- 契約書を印刷する → 印刷用紙・プリンターにかかる費用
- 製本する→ホチキス・製本用テープにかかる費用
- 担当者が契約書に捺印する→インクにかかる費用
- 捺印された契約書を封筒に入れる→封筒にかかる費用
- 送付状を作成し封入する→印刷用紙・プリンターにかかる費用
- 郵送する→郵送にかかる費用
- 所定のフォルダに紙の契約書を収納・管理する→フォルダや保管スペースにかかる費用
また担当者の人件費がかかるほか、契約書の種類や内容によっては数万円の印紙税が求められるケースもあります。
しかし、印鑑を廃止するだけで上記で取り上げた費用をすべて削減することが可能です。
生産性や業務効率の向上に役立つ
印鑑の廃止によって、生産性や業務効率の向上も期待できます。
従来のハンコ文化のデメリットとして、多くの方が以下のような生産性の低下につながる問題を感じています。
- 紙に捺印をもらわないと、業務が進められない
- 捺印をもらうためだけに会社へ行かなければならない
- 社外や遠方拠点の部署の捺印をもらうために、郵送でやり取りする必要があるためプロジェクトの進行が滞る
このようなケースでも、印鑑を廃止すれば多くのデメリットを解消できるため、生産性や業務効率が向上します。また従業員が本来の業務に集中できるようになるため、仕事の出来栄えやサービスの質が向上するでしょう。
テレワークなど多様な働き方を促進できる
近年の日本でスタンダードになりつつある「テレワーク」など多様な働き方を推進できる点も、印鑑を廃止するメリットの一つに挙げられます。たとえテレワークを推進したいと考えていても、従来の印鑑を使用している会社では「押印のためだけに出社しなければならない」というケースが発生してしまいます。
東京商工リサーチの調査(2020年実施)によれば、「ハンコ文化が在宅勤務の妨げになっている」と回答した企業は43.2%に上り、従来の仕事の見直しが課題として浮き彫りになっています。
そこで印鑑を廃止すれば、在宅勤務の妨げになる問題を解消でき、テレワークをスムーズに導入・推進できるようになります。
【引用】東京商工リサーチ第8回「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査【有効回答1万3,166社】2020年9月15日
コンプライアンス強化につながる
印鑑の廃止に伴い、各種書類を電子化すればコンプライアンス強化にもつながります。
紙の書類では、人為的なミスや不十分な管理体制などから紛失や置き忘れなどのリスクがあります。
しかし、書類を電子化すれば適切なセキュリティ対策を施せるため、コンプライアンスを強化できるのです。
印鑑を廃止する取り組みの流れ
本項目では、企業内で印鑑廃止の取り組みを行う際の大まかな流れを3つのステップに分けて解説します。社内での印鑑廃止は自社のみで進められますが、社外取引では印鑑廃止において取引先の了解が求められるため、その点を踏まえて計画を立てることが大切です。
STEP1:企業内での書類で押印の必要性を判断する
まずは、企業内で押印している書類について、本当にハンコが必要かどうかチェックしましょう。
なお、e-文書法や電子帳簿保存法などの整備を受けて、現在では社内の書類だけでなく請求書や領収書などでも押印が不要とされており、印鑑の廃止と電子化が広く導入されています。
押印が不要な文書の種類を把握したら、優先順位をつけて脱ハンコを進めましょう。基本的には、社内文書など扱いやすいものから脱ハンコをするのがおすすめです。なお、ハンコ文化が根強い会社の場合、社内の意識改革から始めるケースもあります。
STEP2:ワークフローシステムを導入する
社内での印鑑の廃止は、ワークフローシステムを導入すればスムーズに進みます。ワークフローシステムとは、企業内におけるさまざまな種類の書類を電子化して業務の効率化を図る電子稟議システムです。
ワークフローシステムを導入すれば、稟議書の承認や休暇申請や有給取得など、社内で押印が必要だった手続きのオンライ上での承認作業が可能になるため承認フローの電子化が可能となります。
STEP3:電子契約サービスを導入する
社外との取引などでの印鑑の廃止を進めるにあたっては、電子契約サービスの導入が効果的です。電子契約サービスとは、取引に必要な契約を電子化する仕組みを指します。
電子契約サービスを活用すれば、電子文書への署名とタイムスタンプの付与によって、法的効力が発生します。また、取引先が同一のサービスを使用していない場合でも電子契約を締結できるツールもあるため、そういったツールを利用すると印鑑廃止をスムーズに進められます。
電子契約サービスを初めて導入する場合は、電子印鑑GMOサインがおすすめです。電子印鑑GMOサインは、「電子文書+電子署名」で契約締結するクラウド型の電子契約サービスです。導入企業数No.1の電子契約サービスであり、圧倒的なコストパフォーマンスと優れた機能性に特徴があります。
電子印鑑GMOサインでは、同水準の他社サービスと比べて、1送信あたりの料金をほぼ半額に抑えつつ、利用できる機能が充実しています。また、電子契約ならではの権限設定や閲覧制限などの機能によってガバナンス強化も実現できます。
圧倒的コスパのGMOサイン
印鑑廃止の取り組みを進める際の注意点
印鑑の廃止(電子化)に取り組む際は、電子印鑑の法的効力に注意しなければなりません。
例えば、印面の画像データの場合は容易に改ざんできるため、法的効力は基本的に認められません。
電子契約書類に法的効力を持たせるには、電子署名やタイムスタンプを付与し、電子文書の原本性・本人性・非改ざん性を確保する必要があります。そのため印鑑廃止を進める際は、以上の仕組みを備えた電子契約サービスを導入しましょう。
また電子契約サービスの導入にあたっては、コストが発生する点に注意しましょう。具体的にかかるコストは以下のとおりです。
- システム導入費:電子契約サービスを導入する際に発生するコスト
- 利用費:電子契約サービスを利用する際にかかるコスト(月額〇〇円など)
- メンテナンス費:企業の既存システムと連携管理していく際にかかるコスト
印鑑廃止に伴い電子契約サービスを導入する際は、予算を確保しておく必要があります。
印鑑廃止(オンライン化)が進んでいる領域とは?
近年、新型コロナウイルス感染拡大の影響によってテレワークへの移行が進むなか、IT業界を筆頭に印鑑やファックスの利用を見直して印鑑廃止を決める企業が増加しています。また昨今では、受発注書や覚書など紙による締結書類が多く残っている不動産や建設・建築業などの業界などでも印鑑廃止の動きが進んでいる状況です。
印鑑廃止は、企業が発行する各書類のほか、行政手続きや銀行口座開設などさまざまな領域で進んでいます。代表例を以下にまとめましたので、ご覧ください。
| 書類、手続き |
動向 |
| 契約書類における印鑑 |
多くの企業で印鑑廃止の動きが進んでおり、近年は印鑑を押す機会が減っている。 |
| 見積書・発注書・請求書など経費処理に必要な印鑑 |
契約書と同様に、電子化が進んでいる。 |
| 法人登記・商業登記における印鑑届出書 |
2021年2月15日より、登記申請をオンラインで行う場合、印鑑届出書もオンラインで提出することが認められている。 |
| 銀行への届出印 |
近年、大手金融機関でも銀行印の届け出が省略された「印鑑レス口座」が登場している(個人向け中心)。 |
| 生命保険の加入における印鑑 |
従来は対面で契約手続きを行っていた生命保険会社でも、オンラインでの新規契約を実施する会社が増えている。 |
| 税務書類の印鑑 |
確定申告において、e-Taxの導入で印鑑廃止が進んでいる。 |
電子化で廃止できる主な押印作業一覧
印鑑の電子化によって廃止できる主な押印作業は、以下のとおりです。
- 契約書の押印
- 収入印紙の消印
- 帳簿の訂正印
- 書類確認・回覧時の押印
また申請書・請求書・領収書なども押印を廃止できますので、企業活動に必要な多くの書類が電子化可能です。
ただし「事業用定期借地契約」など、現時点では法律上書面に押印が必要な契約も存在します。さらに下請法3条書面など、相手方の承諾がないと電子化できない書類もあるため注意が必要です。
印鑑廃止で業務効率化を進めよう
本記事では、印鑑の廃止(電子化)が求められている理由や導入するメリットなどを解説しました。
印鑑の廃止(電子化)によって、企業ではコスト削減だけでなく、生産性や業務効率の向上につながります。ただし、印鑑を廃止する際は法的効力の確保や電子契約サービスの導入コストなどに注意しましょう。
「どの電子契約サービスを導入すればよいのかわからない」ときは、一番選ばれている電子印鑑GMOサインがおすすめです。圧倒的なコストパフォーマンスと豊富な機能で、多くのお客様から支持を得ています。
無料プラン(お試しフリープラン)と有料プラン(契約印&実印プラン)をご用意しておりますので、まずは無料プランから使ってみてはいかがでしょうか。
【2024年最新版】印鑑廃止とは?|非効率な業務を削減する5つの行動