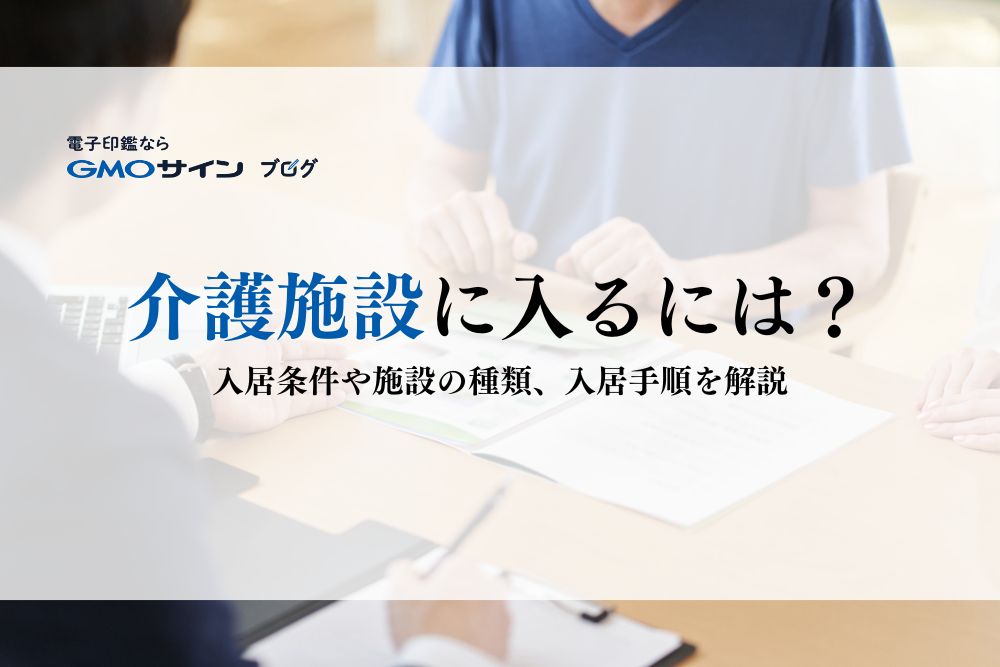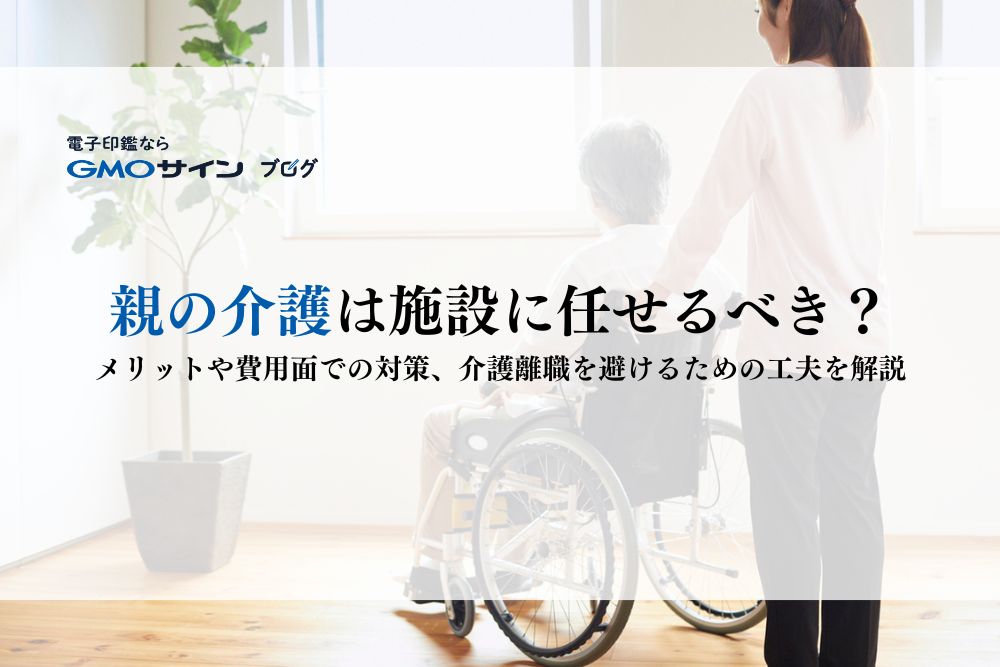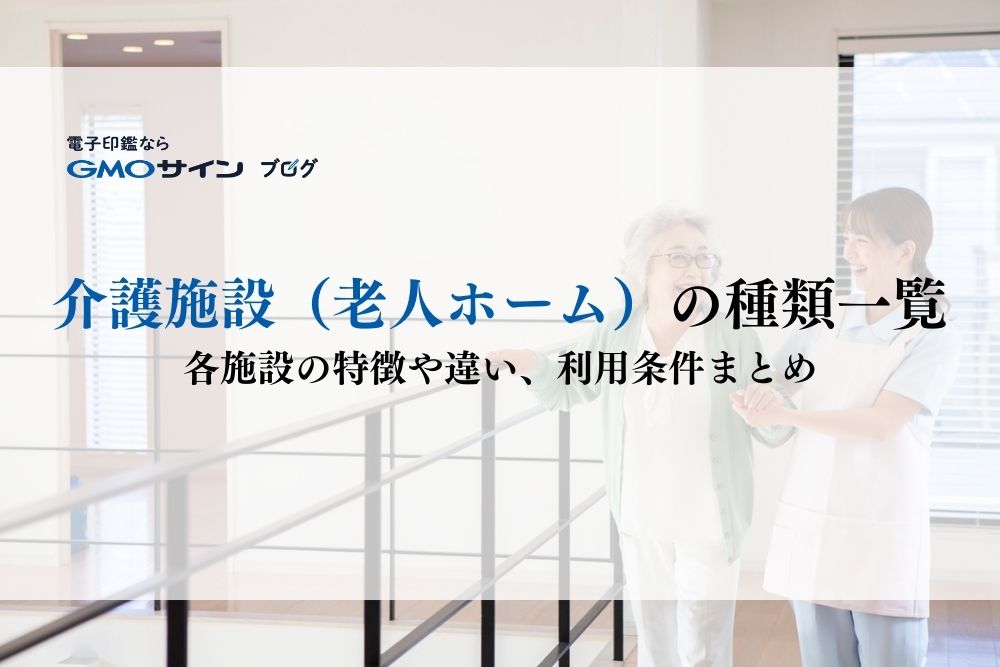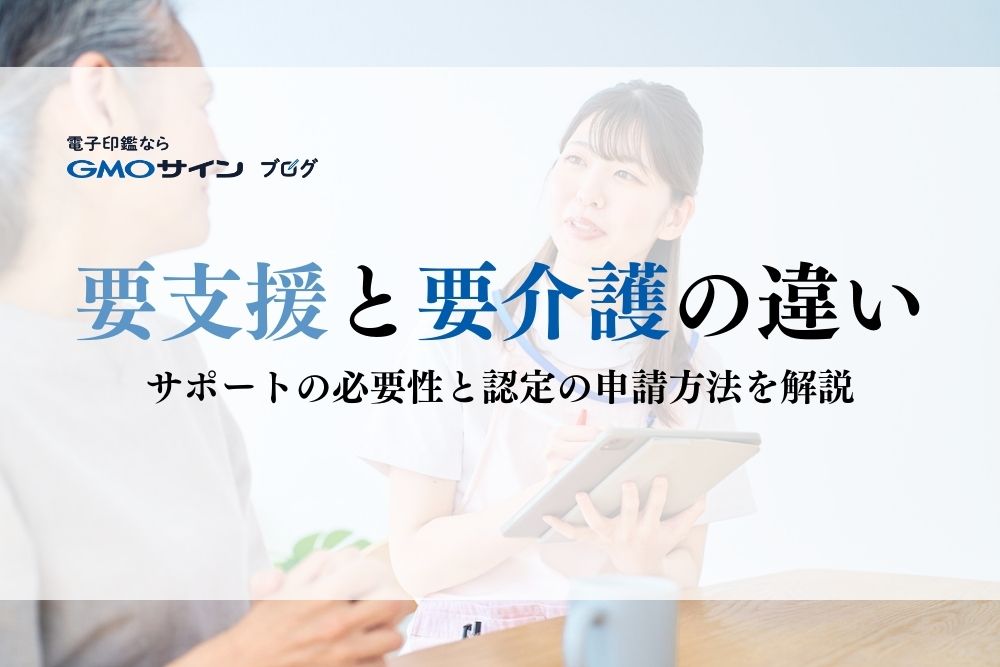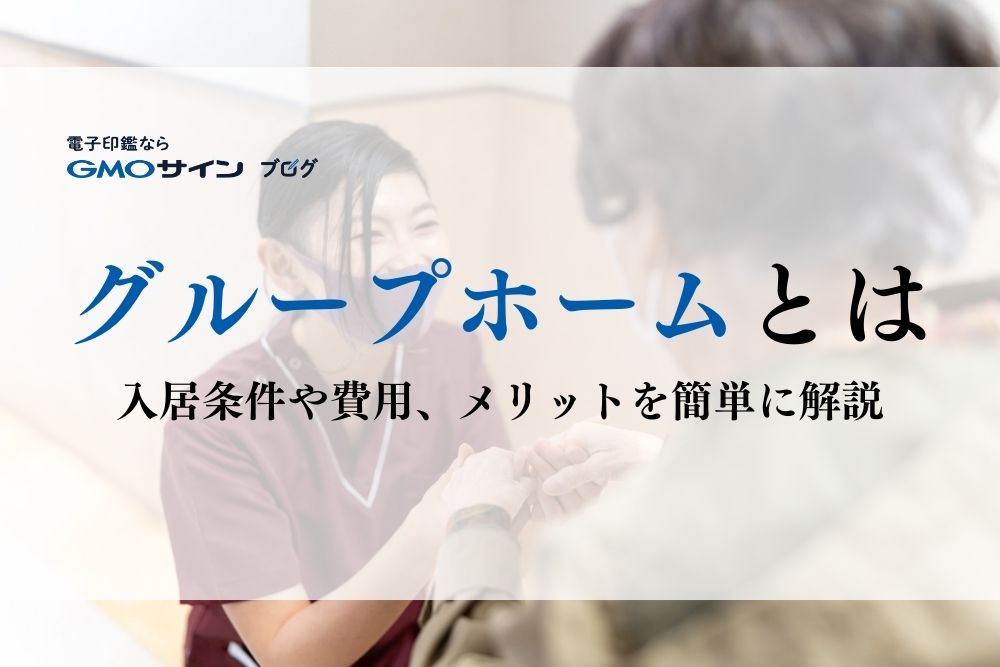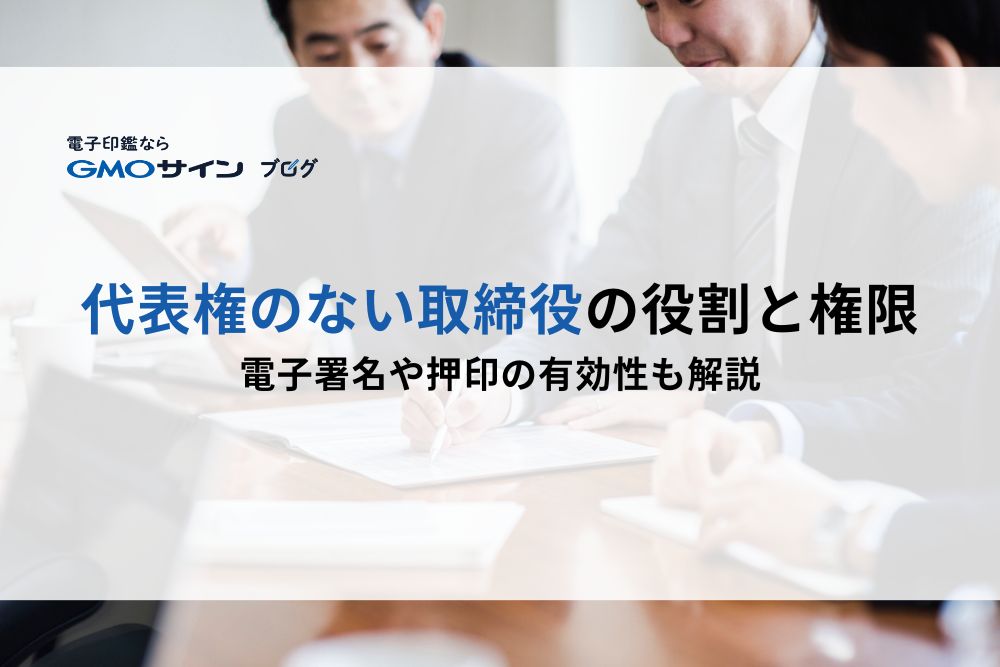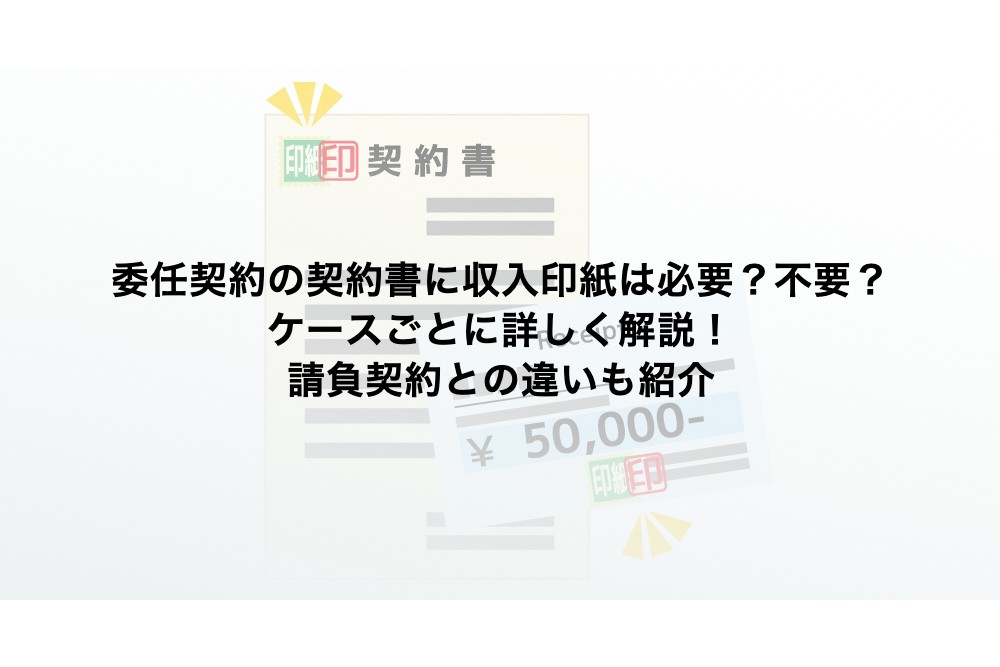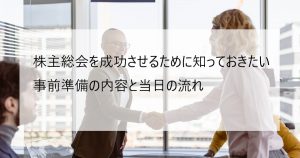日本には、民間の老人ホームや地方自治体が運営する施設など、さまざまな介護施設が存在します。いざ介護施設を利用したいと思っても、一体どのような条件を満たせばそれらの介護施設を利用できるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
介護施設には種類によって役割があるほか、入居条件も施設によってさまざまです。本記事では介護施設の入居条件を施設の種類や入居手順などとともに解説します。
現在介護業界ではDX化が急速に進んでいます。DX化の要素の一つ「電子契約」について、次の記事で詳しく解説しています。介護業界で業務改善に取り組まれている方必見の内容です。ぜひご覧ください↓
あわせて読みたい
介護業界で電子契約を活用!具体的なメリットや導入手順を徹底解説
日本の介護業界は、少子高齢化により要介護者数が増加し、人手不足が深刻化しています。この問題を解決するためには事務作業の効率化が急務ですが、救世主として注目さ...
目次
介護施設の入居タイミング
自宅で介護している場合、介護する人が身体的や精神的な疲労を大きく感じたときが、家族に介護施設に入居してもらう一つのタイミングかもしれません。また独りで暮らす高齢者においては、介護できる人が身近にいないために不安や危険を感じるようになったときが、介護施設への入居タイミングだといえます。
できるだけ介護サービスには頼りたくないと考える方も多いと思いますが、在宅での生活が少しでも厳しいと感じるようになったら、介護施設への入居や介護サービスの利用を検討する時期といえるでしょう。
まずは自治体やかかりつけ医に相談してみることをおすすめします。
あわせて読みたい
親の介護は施設に任せるべき?メリットや費用面での対策、介護離職を避けるための工夫を解説
親が高齢になり介護が必要になった際、自分で介護するのか、それとも施設に入所してもらうのかは非常に悩ましいテーマです。介護サービスの利用に対する費用面の問題は...
介護施設の入居手順
介護施設に入ることの本格的な検討が始まったら、以下の手順に沿って介護施設への入居まで進めていきます。
STEP
施設探しを始める
入居条件は介護施設ごとに決められています。そこで後述する項目「介護施設の種類」を参考にして、入居する人の心身状態から施設を検索していきます。
介護施設は、要介護度や認知症の有無などで受け入れ対応が異なります。なによりも本人や家族の希望、介護施設の入居費用や月額料金などを考慮しながら最適な施設探しをしましょう。
なお、すでになんらかの形で介護サービスを利用しているのであれば、担当しているケアマネジャーに介護施設への入所を相談します。担当ケアマネジャーであれば本人に適した施設を紹介してくれますし、必要に応じて介護施設との連絡調整も行ってくれます。また、介護施設へ入居する予定の本人が入院中であれば、入院している医療機関に在籍しているソーシャルワーカー(生活相談員)に相談を行いましょう。
あわせて読みたい
ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?仕事内容や役割を簡単に解説
初めての介護はわからないことが多いものの、誰かに相談したくても知り合いには話しにくい、専門家の伝手(つて)もないといった場合、頼りになるのがケアマネージャー...
STEP
資料請求を行う
気になる介護施設が見つかったときには、施設のホームページや電話などで資料請求をします。送られてくる資料には、設備や料金プラン、サービス内容などの詳細が掲載されています。
STEP
現地を見学する
届いた資料を見て入居したい介護施設が見つかったら、実際に施設見学をします。見学の際には働いているスタッフに質問をしてみましょう。可能であれば入居者の表情も見ておくことも大事です。穏やかな表情の入居者が多ければ、その介護施設では落ち着いた生活ができているといえるでしょう。
STEP
契約をして入居を行う
希望する施設が決まったら、施設スタッフと面談を行い入居審査が始まります。その後、審査が通過すれば正式に入居が決定します。入居後に施設で必要になる日用品を施設スタッフに確認し、施設の入居日までに揃えておきましょう。
なお、入所審査が通った後に「体験入所」があり、その体験入所に納得したら、本入所へと進む介護施設もあります。
介護施設の種類
「介護施設」と聞くと、「老人ホーム」という言葉が頭に浮かぶかもしれません。「介護施設」は介護サービスを提供する施設全般を指し、主に「要介護者」に特化した施設のことです。一方、「老人ホーム」は高齢者が居住するための施設を指し、必ずしも介護が提供されるわけではなく、自立生活をサポートする施設も含まれます。介護施設や老人ホームには、大きく分けて公的な施設と民間が運営する施設の2つがあります。さらに、公的施設も民間施設も入居条件や入居目的などにより、さらに細分化されています。
民間介護施設の種類と特徴
民間施設には、大きく分けて以下のような4タイプが存在します。
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- グループホーム
施設への入居費用や月額利用料は事業者ごとに異なり、高額な設定がされている施設もあれば、比較的低価格の介護施設も存在します。
また施設によって、
- 「自立」できる人
- 「要介護」が高めの人
- 「認知症」の人
など、入居対象者が異なるため、利用者の経済状況やニーズに合わせて選ぶことができます。
公的施設の種類と特徴
行政が管轄している公的施設は、要介護度が重い人や低所得者の人など、在宅介護が困難な人を優先的に受け入れています。
公的施設には主に、以下のような4タイプが存在します。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- ケアハウス(介護型)
これらの施設は行政管轄となっていますので、月額利用料は民間施設よりも低額で済みます。ただ、特別養護老人ホームは要介護3以上の認定を受けている人、介護老人保健施設と介護医療院は要介護1以上の認定を受けている人が入所条件となっています。また、特別養護老人ホームとケアハウスは待機者も多く、地域やタイミングによっては入所までに一定期間の待機が必要となることもあるでしょう。
あわせて読みたい
介護施設(老人ホーム)の種類一覧 | 各施設の特徴や違い、利用条件まとめ
健康なうちに介護施設について調べておきたいけれど、種類が多すぎてよくわからないとお悩みではありませんか。介護サービスを受けられる施設は複数あり、それぞれで入...
介護施設入居時のポイント
介護施設に入居する際、たいていの介護施設には入居する人の条件が設けられています。その入居条件にはさまざまなものが存在しています。ここでは、その入居条件を5つのポイントにまとめました。
施設入居時の年齢
介護保険法では、介護保険を適用した介護サービスを利用できるのは65歳以上(第1号被保険者)が対象です。そのため、介護サービスを提供する介護施設の利用も原則65歳以上となっています。なお、法令で定められた特定疾病の罹患が認められると、40歳以上65歳未満の第2号被保険者であっても入居できる場合があります。
また、民間施設の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、公的施設のケアハウスなどへの入居で介護サービスを利用しない場合は65歳以下の人でも入居が可能な場合があります。
あわせて読みたい
介護保険とは?仕組みや対象者、要介護認定をわかりやすく解説
介護が必要になり、介護サービスを利用する際には介護保険を利用することが可能です。介護保険は健康保険とは異なり、40歳以上のすべての国民に加入が義務づけられてい...
保証人や身元引受人
施設への入居時には、保証人や身元引受人が必要です。保証人や身元引受人は、下記のような事項に対応しなくてはいけません。
- 施設利用料の支払い
- 緊急連絡先の提供
- ケアプラン(介護サービス計画書)や治療方針の承諾
- 入院時や急病時、死亡時などの対応
単身者でありまったく身元引受人がいない人は、施設がリスクを負うことになるため、入居を断られる場合があります。しかし近年では民間企業が身元引受人代行サービスを行っています。単身者の場合はこのようなサービスの利用も検討すると良いでしょう。
要支援度や要介護度のレベル
民間施設の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、公的施設のケアハウスを除いて、一般的に介護施設に入居する場合には要支援か要介護の認定が必要です。そのため、要支援や要介護の認定を受けていない場合、市区町村の地域包括支援センターに相談するか、役所の高齢者福祉窓口に申請をして、認定を受ける必要があります。
なお、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅以外の民間施設、ケアハウス以外の公的施設は、要介護1以上(グループホームは要支援2以上、特別養護老人ホームは要介護3以上)の認定を受けていることが入居条件です。
あわせて読みたい
要支援と要介護の違いは?サポートの必要性と認定の申請方法を解説
介護サービスを利用する可能性を視野に入れ、準備として今から要支援と要介護の違いを把握しておきたいと考えていませんか。要支援と要介護は、審査によって認定されま...
必要となる医療的ケア
介護施設に入居する人が、どの程度の医療的ケアが必要なのかについても重要なポイントです。入居途中に病気や怪我などで医療行為が必要となったとき、対応する医療体制が整っていない介護施設の場合、退去を求められ病院への入院を求められることがあります。
施設への支払い能力
月額利用料などの費用が払えなくても、即時退去を求められることはありません。ただし、おおむね3カ月以上の料金滞納が発生すると、身元引受人などに退居勧告がなされます。
介護施設はいったん入居すると長期間利用料を支払うことになりますので、無理をせずに、本人や家族などの収入に見合った施設を選ぶようにしましょう。なお、生活保護を受けている人でも、支給される生活保護の範囲内で支払いができるのであれば、介護施設への入居は可能です。また、民間施設の有料老人ホームでも、入居金が不要で、月々の支払い金額が比較的低額の施設も存在します。
認知症の有無と程度
認知症の方を受け入れる主な介護施設は以下の通りです。
- グループホーム
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- ケアハウス(※軽度の認知症ならOK)
- 有料老人ホーム
ただし、施設によっては、認知症の症状が進行して介護度が著しく重くなったときには、退去する必要が生じる可能性があります。入居を決める前に、どういった心身状況までなら対応できるのかなど、契約内容をよく確認しておくようにしましょう。
あわせて読みたい
グループホームとは?入居条件や費用、メリットを簡単に解説
認知症の高齢者にとって、住み慣れた地域でできる限り自立した生活を送ることは、心身ともに大きなメリットがあります。グループホームは、そのような希望を叶える介護...
まとめ:介護施設への入居基準
入居条件を施設のジャンルごとにまとめてみましたので、どの介護施設が良いのか、施設を選ぶときの参考にしてみてください。
スクロールできます
| 施設の種別 | 入居条件 |
|---|
| 有料老人ホーム | 自立している人から要介護5に認定された人まで(施設によって異なる)。 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 自立している人から要介護5に認定された人まで(施設によって異なる)。 |
| グループホーム | 要支援2、あるいは要介護1以上に認定され認知症の診断を受けた人で、グループホームがある市区町村に住民登録をしている人。 |
民間介護施設の種類と入居基準スクロールできます
| 施設の種別 | 入居条件 |
|---|
| 特別養護老人ホーム | 日常でも介護が必要な要介護3~要介護5に認定された65歳以上の人。
※要介護1、2の人でも、特別な事情があれば入居が認められることもある。 |
| 介護老人保健施設 | 要介護1〜要介護5に認定された65歳以上の人で、リハビリテーションによる機能回復を目的としている人。※入居期間は、原則として3カ月〜6カ月まで。 |
| 介護医療院 | 要介護1〜要介護5に認定された原則65歳以上の方で、主に長期にわたり療養が必要な人。 |
公的介護施設の種類と入居基準電子印鑑GMOサインは、介護業界に最適な電子契約サービスです。スマートフォンを持っていない方や使い方がよくわからない方との契約も安心して行えるよう、さまざまな機能を提供しています。介護施設や介護サービスを利用する際の申込書や同意書などのほか、介護業界における雇用契約書や業務委託契約書を簡単にできるようになります。
介護業界が抱える課題を「GMOサイン」が解決します!
高齢化社会がますます加速する日本国内において、介護業界は「人手不足」「現場の負担の増大」「地域格差」など、さまざまな課題を抱えています。
電子印鑑GMOサインは、そんな介護業界を「契約」の面で徹底的にサポートします。
GMOサインは国内シェアNo.1(※)の電子契約サービスです。介護サービス提供時には利用者との間で契約を交わします。サービス提供者は契約の確認や署名捺印のために利用者のもとを何度も訪れなければならない、そのようなケースもあるでしょう。また、遠方で暮らす家族の方の同意を得なければいけない場面もあります。
そのような介護における契約時に役立つのが、自宅にいながらでも契約書の確認から署名まで行える電子契約サービスです。利用者の利便性向上はもとより、紙の契約書の廃止によるコスト削減、また契約締結までの時間短縮など、電子契約サービスは今後の介護業界において必須のツールになります。
GMOサインは、電子契約におけるあらゆる基本機能の提供はもちろん、パソコンやスマートフォンを利用しない高齢者のためにタブレット端末を利用した手書きサイン機能も用意しております。さらにGMOサインは、利用者との契約だけでなく、現場で働く方々との雇用契約や業務委託契約にもおすすめです。

まずはお試しフリープランにて、電子契約の一連の流れや操作性をぜひ体感してみてください。
※1 「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)
※2 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2023年12月)