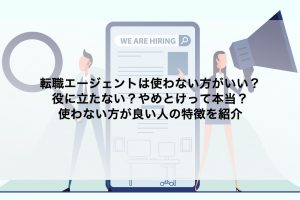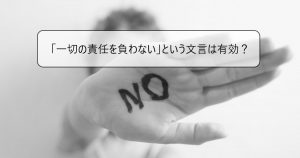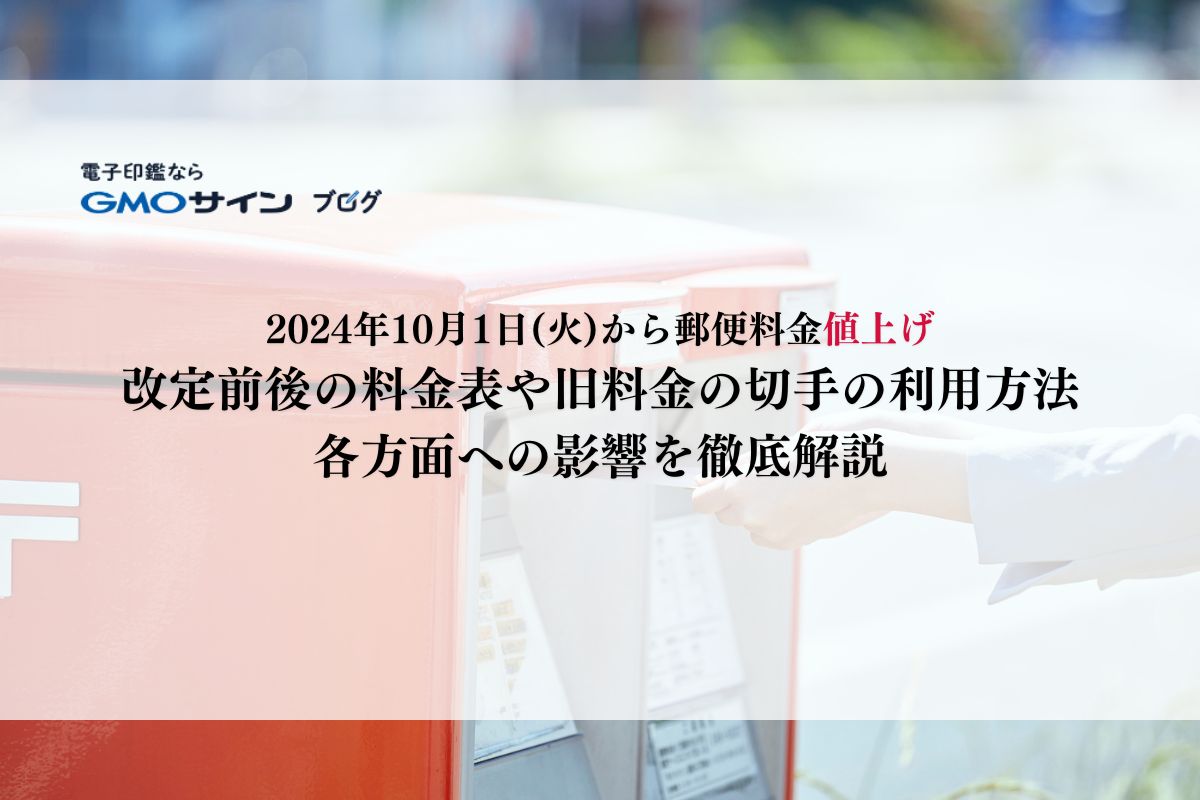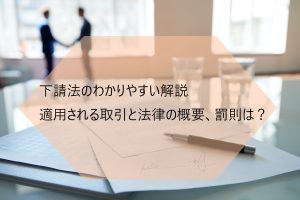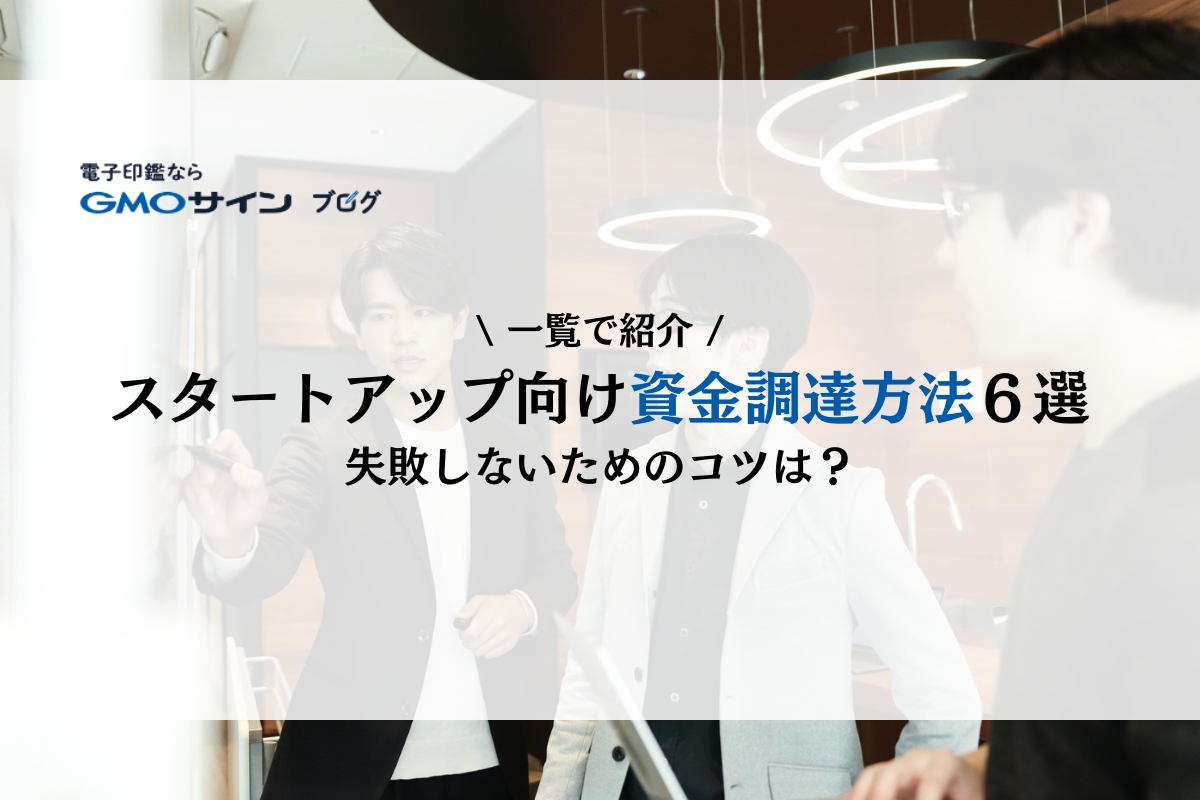所有している不動産を売却するにあたり、取引事例比較法について知りたいと考えていませんか。物件や土地の価値を見定める方法にはいくつかあるので、すべての方法を把握したうえで評価額を算出することが重要です。
この記事では、不動産鑑定評価に使われる取引事例比較法についてくわしく解説します。取引事例比較法以外の鑑定方法、計算の流れやメリット・デメリットも紹介するので、不動産を売りたい方はぜひ参考にしてください。
目次
取引事例比較法とは?
取引事例比較法とは、売りたい不動産と似た条件で売却された事例と比較することにより、不動産の評価額を算出する方法です。売りたい不動産と似た条件の物件を複数ピックアップして比較しますが、場合によっては以下の作業も追加して評価が行われます。
- 事情補正
-
取引価格に影響する何らかの理由から補正を行う
- 時点修正
-
取引する際に不動産の価格水準に変動がある場合は補正を行う
- 地域要因
-
各地域の特性を考慮したもの
- 個別的要因
-
築年数や土地の形状など不動産に関する特性
事情補正や時点修正による補正を行ったあと、地域要因や個別的要因があればそれらを含めて不動産を評価します。補正によって価格が変動するので、似た条件の事例の平均価格がそのまま評価額になるわけではありません。
取引事例比較法以外の不動産の鑑定評価方法
不動産を評価する方法は複数あるので、所有する土地や物件を売りたいと考える方は、事前に把握しておきましょう。ここでは、取引事例比較法以外の評価方法を解説します。
原価法
原価法とは、売る予定の不動産を現時点で建築する場合の再調達原価、つまりどれくらいの費用で建てられるかを計算する方法です。総面積や建築費用などを割り出した数字から、築年数に応じた価値の低下額を引くことで算出できます。
原価法を適用できるのは、建物を新しく建築する際の費用を割り出し、築年数や耐用年数に応じた価値の低下額を把握できる場合です。なお、建物のない土地でも、新しく建物を建てられる土地として数字を割り出せば、土地のみでも原価法で計算できます。
収益還元法
収益還元法とは、売る予定の不動産が将来的にどれくらいの利益を生み出すかを試算する方法です。直接還元法とDCF法があるので、それぞれの特徴を見てみましょう。
- 直接還元法
-
一定期間に得られる純収益から還元利回りを差し引いて算出する方法
- DCF法
-
不動産を保有している間に得られる純利益と不動産売却時に得られる利益を現在価格に割り戻す方法
直接還元法で出てくる還元利回りとは、不動産で得られる収益性を表す利率です。不動産の条件にもよりますが、賃貸用物件なら5~8%、事業用なら7~10%ほどが目安とされています。
たとえば、年間に200万円の収益を得られる賃貸物件を売却するとしましょう。物件を維持するためにかかる修繕費や損害保険料などが20万円、利率を6%とした場合の計算式は(200万円-20万円)÷6%=3,000万円となります。算出された金額が不動産の評価額です。
DCF法は精度が高いものの、特殊な内容で計算もより複雑になっています。不動産を証券化するときや企業価値を評価する際に使われることが多い計算方法です。
取引事例比較法で計算する流れ
不動産を取引事例比較法で評価してもらうことになったけれど、流れがわからないとお困りの方も多いでしょう。ここでは、取引事例比較法はどのような流れで進んでいくのかを紹介します。
STEP
周辺の不動産売却の情報を集める
まずは、周辺の不動産売却の事例や情報を集めます。前述したように、不動産を評価する際にはいくつかの似た事例を比較しなければならないので、最初の情報収集はとても重要です。事例や情報は以下のポイントを元に収集されます。
・半年以内の事例かどうか
・立地条件や面積、建物の規模などが似ているか
・建物の築年数が近いかどうか
・不動産の最寄り駅からの距離が同程度か
上記の条件から今回売却する不動産と似た条件のものを探し、1平方メートルあたりの面積の価格を計算します。たとえば、100平方メートルの土地が3カ月前に3,000万円で売却されていたとします。3,000万円÷100平方メートル=30万円となり、1平方メートルあたりの価格は30万円です。
STEP
採用する事例の事情補正を行う
採用する事例に何らかの事情があり、価格に影響を及ぼしている場合は事情無しの価格に計算しなおします。早く不動産を売らなければならない、借金返済のために急いで現金化する必要があるなどの事情で売却する際は、市場価格よりも安い値で取引されます。
採用する事例に何らかの事情がある場合は、事情を除いた価格を算出しなければなりません。たとえば、3,000万円の価値がある土地を急ぎで売却しなければならず、市場価格の2割引で売ったとします。
この場合は事情補正率が80%となり、計算式は「事例の単価×事情補正」となりますから3,000万円×(100÷80)=3,750万円です。2,400万円で売却されてはいるものの、事情補正をすることによって3,750万円の適正価格が算出されます。
STEP
過去の取引事例を現在の時点で計算しなおす時点修正を行う
次に、事情補正を行った数字に過去と現在の価格水準のずれを掛ける時点修正を行います。半年以内の事例であっても、状況によっては不動産の価格水準が変動していることもあります。
たとえば、売却されたときよりも価格水準が10%値下がったとしましょう。事情補正後の3,750万円に値下がった分を差し引いた90%を掛けることで、3,375万円に修正されます。
STEP
個性的な土地を鑑定する場合は標準化補正を行う
個性的な土地を売却する場合、事情補正と時点修正を行った数字に、標準化補正を行いましょう。土地の形状がいびつな土地は、使いづらい、または買い手がつきにくいなどの問題から安く取引されます。
所有する土地の形状がいびつだと判断された場合、差し引く数字をもとに補正しなければなりません。たとえば、特殊な形状であることから標準的な土地よりも10%差し引いて評価する場合、3,375万円×90%=3,037万円に補正されます。
STEP
地域要因と個別的要因を確認する
ここまで算出した数字に、地域要因と個別的要因を確認してさらに補正を行いましょう。地域要因には以下のようなものがあります。
・地域の街並み
・閑静な住宅街かどうか
・一般的・高級住宅街などの地域からの評判
住みやすく、治安のいい地域にある土地は買い手がつきやすいことから、高く評価される可能性があります。地域要因に加え、個別的要因が加われば、ここまでの評価額が高くなるかもしれません。個別的要因は以下の通りです。
・不動産から最寄り駅までの距離
・日あたりのよさ
・不動産周辺の道路の幅
・不動産周辺の店舗
・上下水道の設備
・自然災害発生時の影響
これらの要因から売却予定の不動産がプラスになるか、マイナスになるかを検討し、数字を補正します。地域要因にプラスになる要素が多く、人気の土地であれば数字が上乗せされます。
たとえば、採用した取引事例の土地よりも人気があり、10%ほどの価値の上昇が見込める場合は3,037万円×110%=3,340万円に上がるため、売る予定の方に大きなメリットがあるといえるでしょう。
STEP
補正を反映したうえで評価額を算出する
ここまでの補正を反映したうえで、不動産の評価額を算出します。これまでの例をまとめた評価額を見てみましょう。
- 近隣の不動産情報から面積を割り出す(面積100平方メートル×過去事例から割り出した1平方メートルあたりの価格30万円=3,000万円)
- 事情補正の適用(3,000万円×(100÷80)=3,750万円)
- 時点修正の適用(3,750万円×90%=3,375万円)
- 標準化補正の適用(3,375万円×90%=3,037万円)
- 地域要因と個別的要因の適用(3,037万円×110%=3,340万円)
複数の補正を適用した結果、3,340万円の評価額がつきます。さまざまな補正を適用しなければならないので、個人で正確な評価額を算出するのは難しいというのが実情でしょう。不動産を売る場合は、不動産会社に計算をお任せすることがおすすめです。
取引事例比較法のメリットとデメリットは?
不動産を評価する方法は複数あるなかで、取引事例比較法だけのメリットが知りたいと考える方も多いでしょう。ここでは、取引事例比較法で不動産を評価するメリットとデメリットを解説します。
メリット
取引事例比較法のメリットは、過去半年以内の事例を採用することで、精度の高い売却額がわかる点です。複数の事例を比較することで、売る予定の不動産の相場を把握できます。
評価額を知ってから不動産を売却するか、所持するかを判断できる点も大きなメリットです。予想以上に高値が付く場合は売却、補正によって価格が大きく下がる場合は土地の評価額が上がってから売却するなど、売るタイミングを決める判断材料になります。
デメリット
取引事例比較法のデメリットは、査定をお願いする不動産会社によって価格が左右される点、戸建ての評価額算出に向いていない点です。
取引事例比較法では、売る予定の不動産に似た事例を探さなければなりません。不動産会社のリサーチ力によっては、あまり似ていない事例を比較され、予想以上に低い評価額を提示されるかもしれません。
また、戸建ては物件別に個別的要因が大きく異なります。築年数・面積・間取り・日あたりなど、物件別に特徴が変わるため、似た事例を探すのに時間がかかるでしょう。地域によっては似た事例が見つからず、ほかの方法で評価額を算出することになります。
取引事例比較法の内容を知ったうえで不動産の評価を依頼しよう
取引事例比較法とは、売る予定の物件や土地に似た売却事例と比較し、評価額を算出する方法です。事例を採用する際は過去半年以内、立地条件や面積が類似しているかなどがチェックされるので、事例の収集に時間がかかるケースもあります。
似た事例が見つかれば、精度の高い売却額を把握することが可能です。売却額を知ることで売るタイミングを決められるので、売却を検討している方にとってメリットが大きいでしょう。情報収集力がカギとなるため、リサーチ力の高い不動産会社に評価を依頼することがおすすめします。