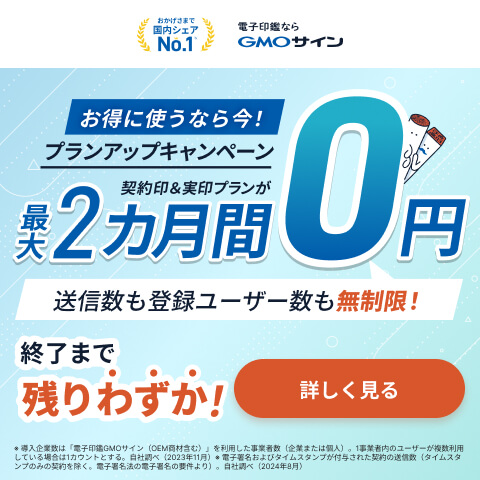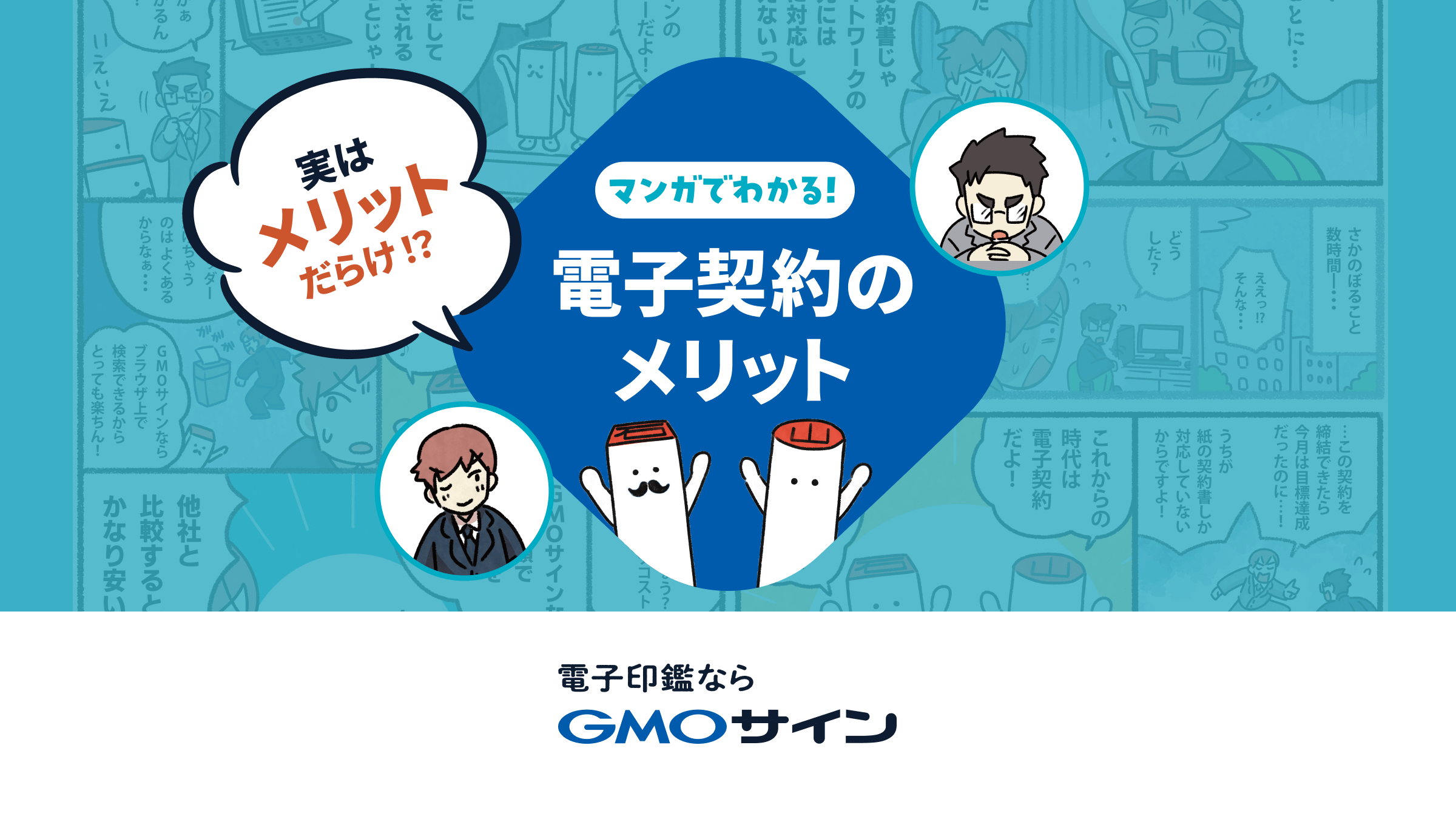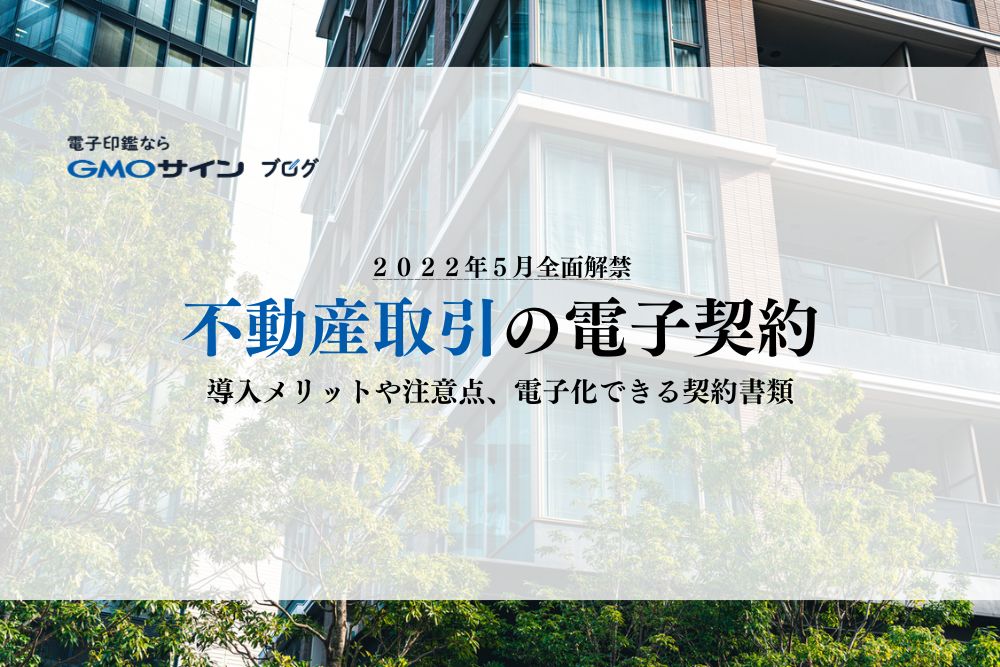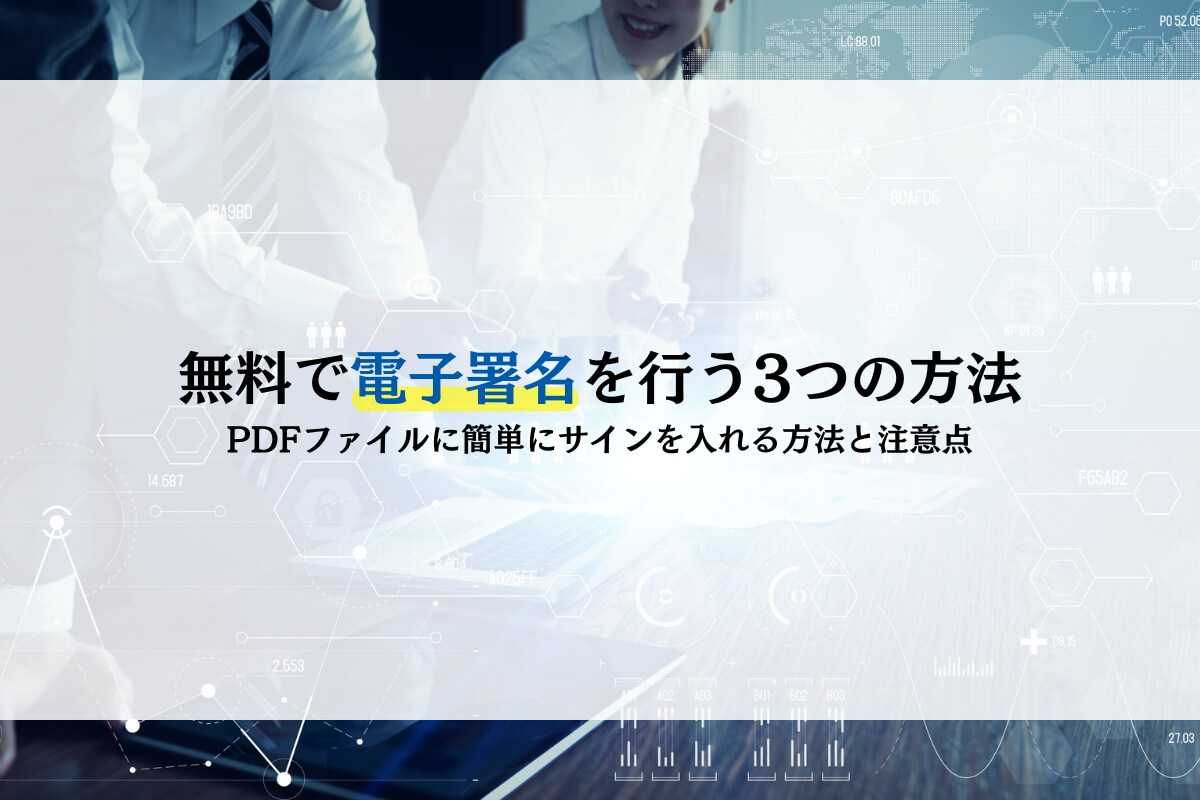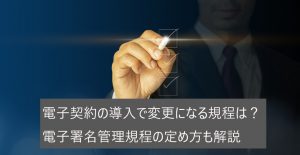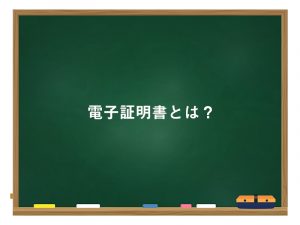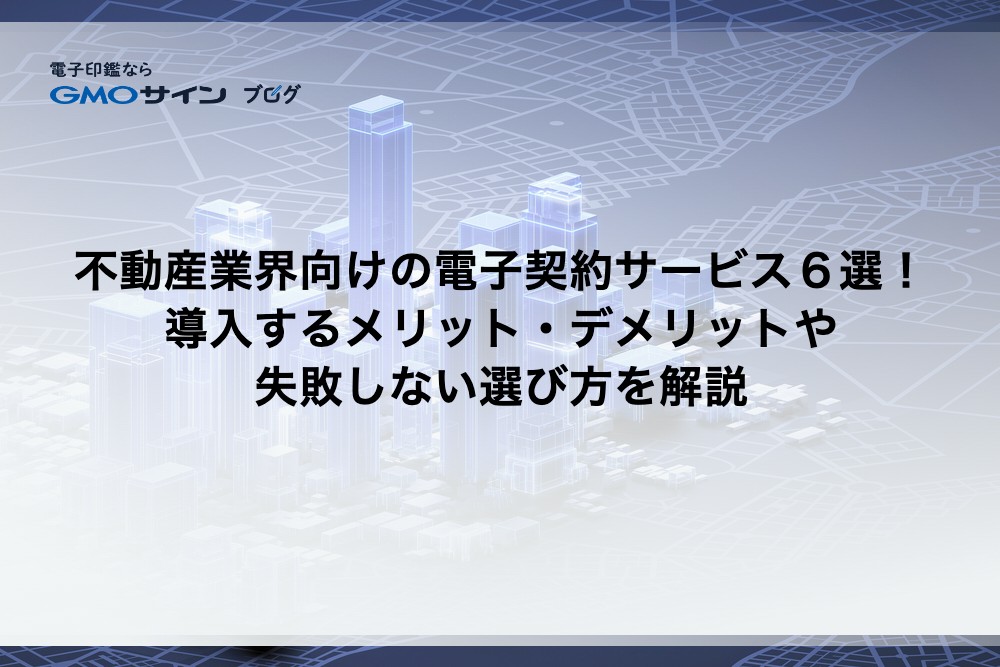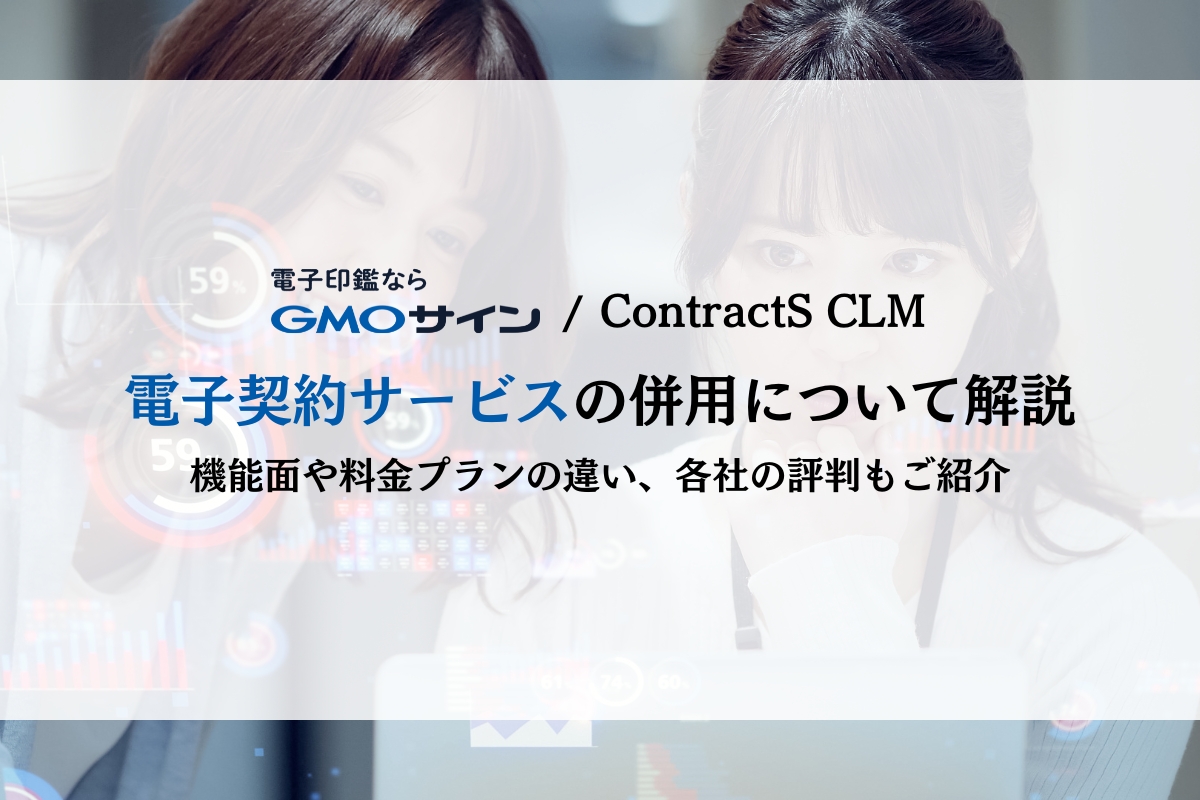【この記事で解決できるお悩み/わかること】
・電子契約書の概要
・電子契約のメリット
・電子契約を導入する際の注意点
・電子契約サービスを選ぶポイント
最近は、働き方改革やDX、ペーパーレス化の流れを受けて、企業間の取引に電子契約が増えてきました。政府もデジタル庁を創設し、書面の電子化のための法律改正も積極的に行っています。
一方で、電子契約での契約書の作り方がわからないため、導入に踏み切れていない企業や電子契約を行うためのサービスの選び方がわからないという声も少なくありません。
そこで今回は、電子契約をするメリットや電子契約をする上で注意すべき点を解説します。
あわせて読みたい
電子契約の仕組みとは?書面契約との違いやメリット、証拠力についてどこよりもわかりやすく解説!【弁...
5分でわかる「電子契約」基本講座 https://www.youtube.com/watch?v=8vkZJdLhcew 月額料金&送信料ずっと0円 GMOサイン公式サイト 新型コロナウイルス(COVID-19)に...
目次
電子契約書とは?
電子契約書とは、従来合意内容を証拠として残すため紙に印鑑で押印して取り交わされていた契約書にかわり、契約内容を記載した電子データに電子署名をすることで締結する契約です。
「書」は「書面」のこと、つまり「紙」「用紙」を指します。電子契約は「電子データ」ですので、「電子契約“書”」ではなく「電子契約」と書くのが正確です。(このため、本記事も、以下「電子契約」と記載します。)
紙の契約書も、今ではパソコンを使って作成されることがほとんどなので、契約内容を作る段階までは、紙の契約書と電子契約との作成方法に違いはありません。紙の契約書は、パソコンで作成した後、プリンターで紙に印刷。製本して、両当事者が署名または記名・押印します。
それに対して、電子契約は、プリンターで印刷することなく、相手にメールなどで契約書を送付し、内容を確認してもらい、問題がなければ、電子署名のうえ契約締結となります。
紙の契約書の場合、印刷する手間、郵送する手間、押印する手間、ファイルなどに保管する手間がかかりますが、電子契約であれば、これらの手間はかかりません。
電子契約書の作り方
電子契約の作り方は、①電子契約サービスを利用する方法と、②自社で環境を整えて作成する方法があります。ただ、セキュリティ対策やサーバーの管理など自社で環境を整えることは、相当ハードルが高いため、電子契約サービスを利用することが一般的です。
電子契約の作り方に決まりはありませんが、法定書類として認められるためには、「e-文書法」(※)の要件を満たす必要があります。
(※)e-文書法とは民間事業者等に対して法令で課せられている書面(紙)による保存等に代わり、電磁的記録による保存等を行うことを容認する法律のことです。具体的な要件は各府省により異なりますが、少なくとも①見読性、②完全性、③検索性が必要です。
見読性とは、作成した内容をディスプレイに表示し、プリンターで印刷できることです。特殊な装置がないと表示されないものや印刷ができないものは認められないということです。
完全性とは、文書が安全な状態で保存されることです。具体的にはバックアップ体制を整え、容易にデータ消失するようなことがないようにしなければなりません。また、文書の改ざんや削除などされないようにログが残るようにする必要があります。
検索性とは、電子文書を検索できるようにしておくことです。文書が大量になってくると、容易に探すことができなくなるため、検索できなければ文書がないのと同じことだからです。
もっとも、電子契約サービスを提供している会社はこれらの要件は満たしているため特に気にする必要はありません。
電子契約のメリット
電子契約には、紙の契約書にはない様々なメリットがあります。具体的に見ていきましょう。
あわせて読みたい
電子契約のメリット・デメリット|導入時に発生し得る課題への対処法
書面での契約書から解放される電子契約は、業務効率性やコストなどの面でメリットを持っています。同時に、導入に当たってはデメリットを見過ごすことなく、上手にプロ...
印紙税がかからない
印紙税法では、契約書を作成した場合には、契約の種類と金額によって、印紙税を納めなければならないことになっています。数百円の印紙であれば気にする必要はないかもしれませんが、何十万円という額になると相当な負担です。たとえば、契約金額が1億円超~5億円以下の請負契約書ともなると、10万円の印紙税がかかります。しかし電子契約は「書面」でないため、印紙税法上の文書には該当せず、印紙税がかかりません。契約書を多く作成する企業にあってはコスト削減につながります。
あわせて読みたい
電子契約で収入印紙が不要になる理由を政府見解に基づき解説
紙で契約書を交わす際に必要となる収入印紙、つまり印紙税は、電子契約では必要ありません。ここでは、その理由について、印紙税法や国税庁などの見解を踏まえて解説し...
業務効率が上がる
契約書を紙で作成する場合、契約書を印刷の上、製本し、記名・押印する必要があります。それを、封筒に入れて、宛名を書き、郵便局やポストに投函し、相手から押印した契約書を受け取ります。契約書を受け取った後も、契約書ファイルなどに綴って、台帳などに記入するなどして管理する必要があります。また、大量に契約書がある場合には保管場所の確保も必要です。
一方、電子契約であれば、契約書をメールなどで送付して、オンライン上で署名するだけで契約が締結できる、事務手続きの多くを省略できます。物理的な保管の場所も必要なく、検索も容易なので台帳などを作る必要もありません。
リモートワークが可能
すっかり定着したリモートワークですが、従業員が代表印を自宅に持ち帰るということは許されません。そのため、紙の契約書を作成するためにはわざわざ社員が出社する必要があります。
電子契約であれば、代表印を押印する必要はないため、権限さえあれば、自宅で契約締結のすべてが完結できます。
コスト削減ができる
紙の契約書の場合、紙代、トナー代、封筒代、切手代、事務作業の人件費、契約書を綴るファイル代、書棚代、書棚のスペースにかかる賃料などがかかります。
それに対し、電子契約の場合、既にパソコンとインターネット環境がある場合には、電子契約サービスの利用料以外のコストがかかりません。
電子契約を導入する際の注意点
電子契約にはメリットばかりではありません。導入にあたっては、必ず、注意点も把握しましょう。
相手の同意が必要
契約は相手があることなので、電子契約をするためには契約の相手方から電子契約利用の同意を得る必要があります。
電子契約ができない契約がある
定期借地契約、定期借家契約、任意後見契約、訪問販売等に関わる契約など、一部の契約については、法令等により、書面の交付が義務づけられているものがあります。不動産の契約等、来年にも電子化が解禁となる契約もありますが、現時点では重要書類については、書面での交付が求められているものがあります。
【参考】電子署名が利用可能な文書一覧
あわせて読みたい
【2024年最新版】不動産取引の電子契約がついに全面解禁!導入メリットや注意点、電子化できる契約書類...
日本ではかつて、不動産取引において完全な電子化が難しく、煩雑な紙の書類が多く残っていました。これは、法律上不動産取引に際して作成が義務付けられている書面があ...
インターネット障害のリスクがある
電子契約に限らず、現代社会では、パソコンやインターネットが使えなくなると、事務的業務のほとんどはできなくなります。大規模災害が発生した場合などでインターネットが長期間使えない環境となってしまうと業務が停滞してしまうリスクがあります。
電子契約サービスを選ぶポイント
電子契約サービスと一口に言っても、数多くのサービスがリリースされています。ここでは、電子契約サービスを選ぶポイントを見ていきましょう。
使いたい機能があるか
電子契約サービスに利用したい機能があるかどうかは、選択する上で重要な要素になります。たとえば、会社内部での決裁のため承認機能や契約書のテンプレートの有無などです。使いたい機能が搭載されているサービスを選びましょう。
料金が適正か
電子契約サービスは、一度導入したら長期的に利用することになるため、無理のない料金であることが必要です。月額料金制のところがほとんどなので、大きな金額ではないように思われるかもしれませんが、企業の業績には浮き沈みがあるものなので慎重に検討してください。
セキュリティ対策が十分か
契約書の内容は、機密性が高いものが多いので、その内容が外部に漏れるようなことがあってはなりません。インターネットでの取引では、常にサイバー攻撃の脅威にさらされます。セキュリティ対策がしっかりしている業者を選びましょう。
あわせて読みたい
電子契約サービス29社を徹底比較!どこを選ぶべき?特徴や料金、使いやすさなどをご紹介【2025年2月最新...
紙の契約書は、作成後に署名・押印を行い、さらに相手方にも同様の手続きをしてもらう必要があり、非常に手間がかかる業務です。しかし、電子データを用いて契約書の作...
あわせて読みたい
無料で使えるおすすめの電子契約サービス19選!失敗しない選び方も解説【2025年2月最新版/比較表付き/...
電子契約サービスの電子署名を利用すれば、書類に押印をする契約書と同等の効力を持つ契約が交わせます。雇用契約書や賃貸借契約書といった従来では電子化が難しかった...
GMOサインを無料で試してみる
機能やセキュリティ対策をしっかりと比較検討して電子契約サービスを選ぼう
電子契約における契約書の作り方、作成するメリット、注意点、サービスの選び方などについて解説しました。政府もデジタル化を進めており、官民ともにデジタル化の進展が期待されています。契約書の電子化を認める法律も多く改正されており、電子契約はこれから益々普及していくでしょう。
電子印鑑GMOサインは、トップレベルのセキュリティ対策がなされており、料金は月額費用 9,680円(税込み)とお手頃です。
さらに、「必要に応じて2種類の電子印鑑を使い分けできる」「押印ワークフローを変更せずに導入できる」というメリットもあります。くわえて、運用コンサルティング、社内向け説明会、取引先説明会の実施などの導入支援も行っています。
電子契約サービスの導入を考えている方は、電子印鑑GMOサインも検討してみてはいかがでしょうか。
\ 各種お役立ち資料が全て “無料” /
GMOサインを無料で試してみる