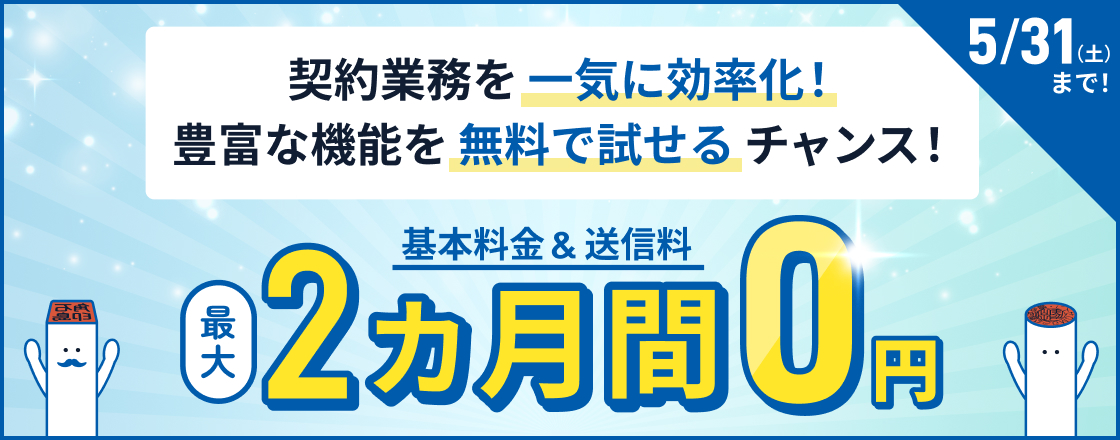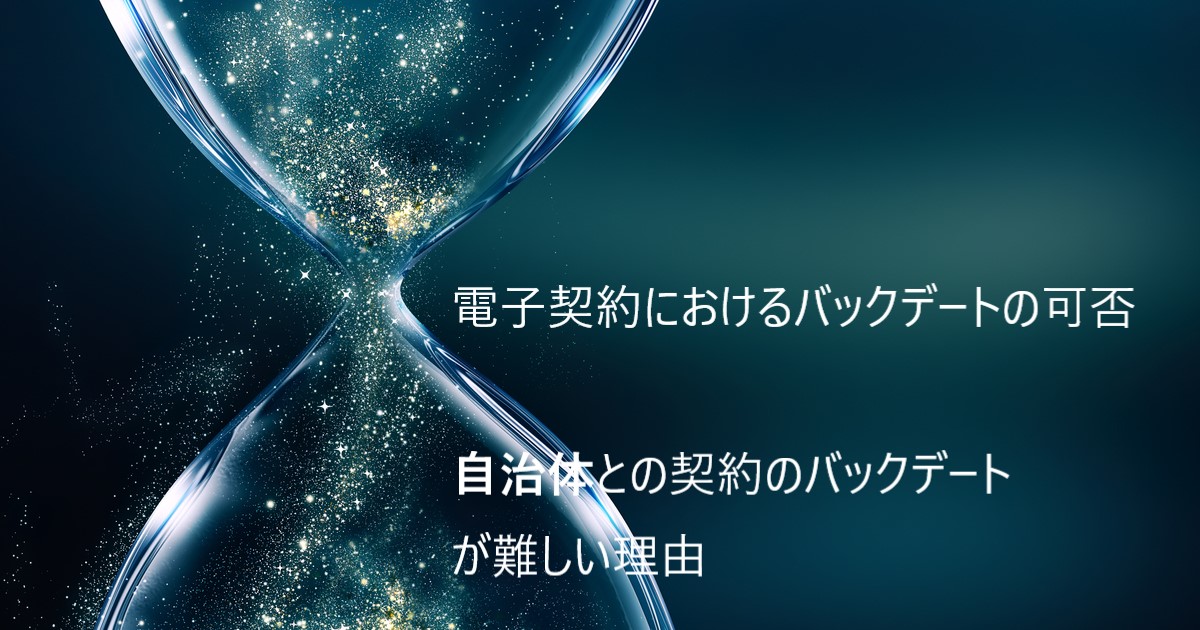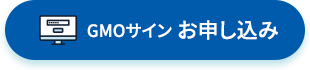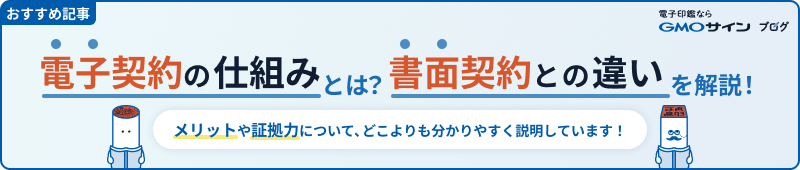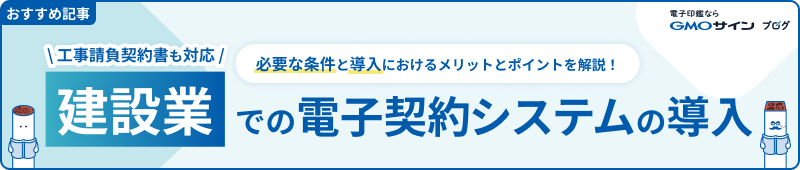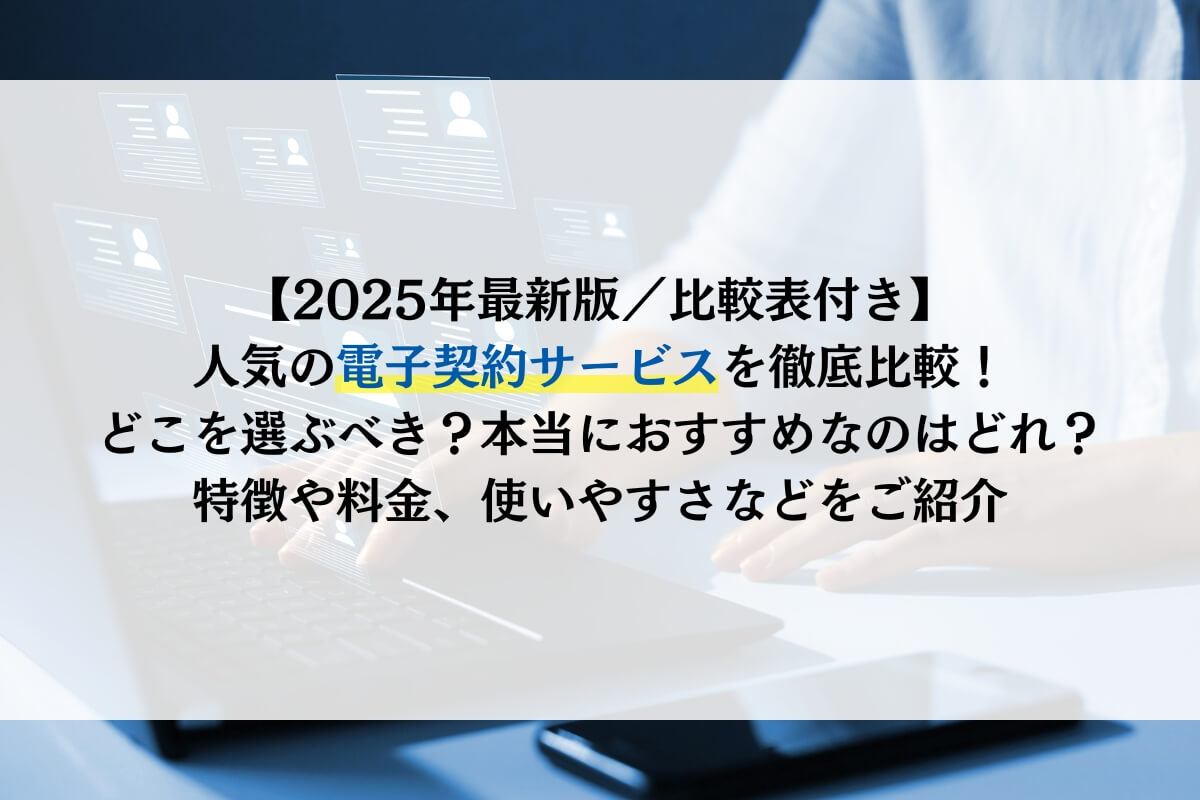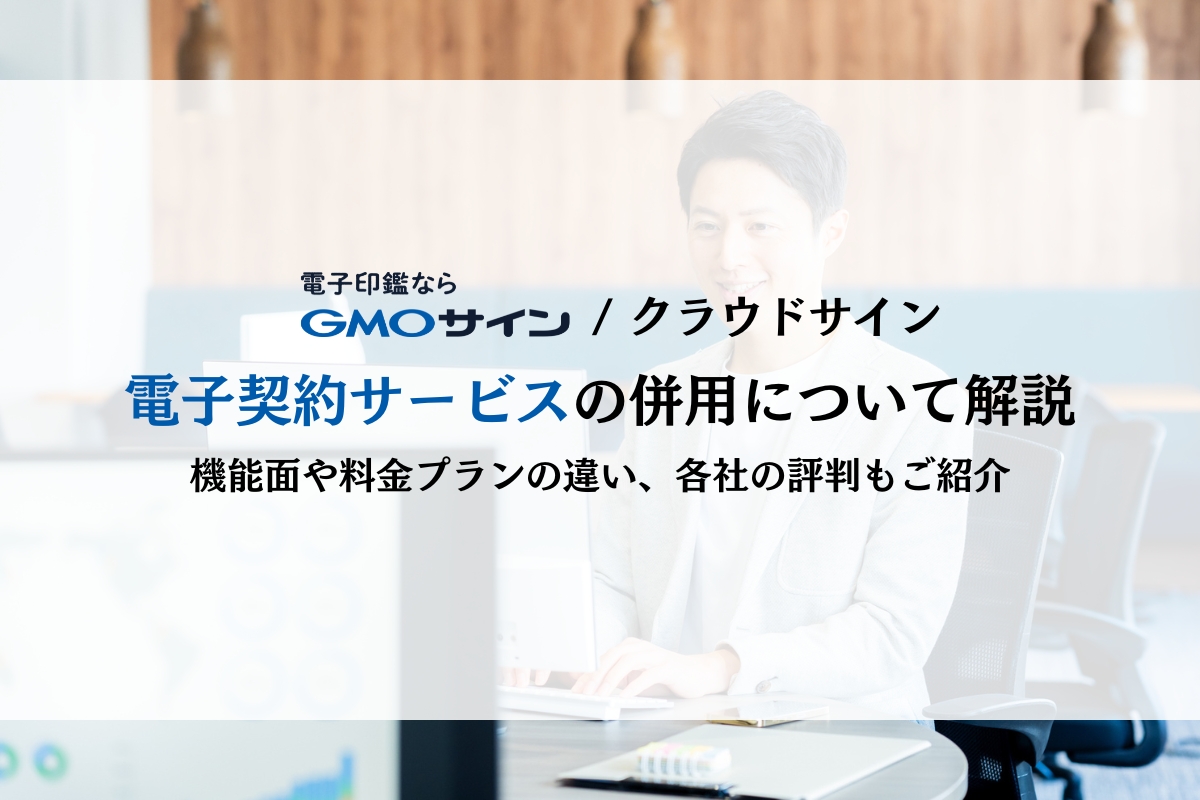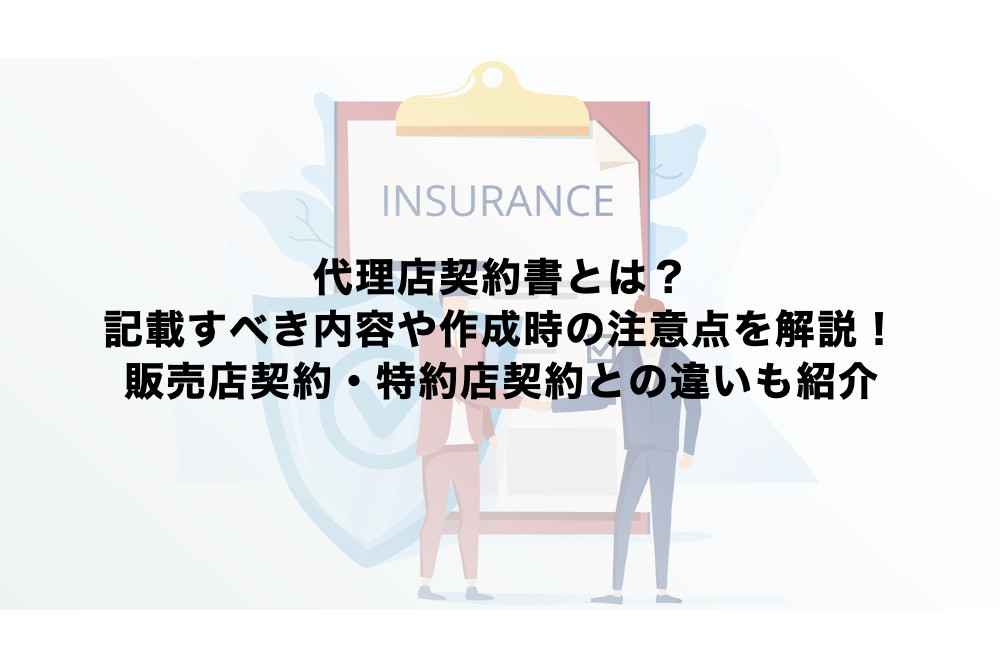契約のバックデート(backdate)とは、実際に契約が締結されたのとは異なる日時にさかのぼって契約が締結されたこととする行為のことを言います。ビジネスの世界では、半ば慣例化している現状がありますが、実は潜在的にリスクのある行為なのです。
最近では電子契約書を作成するケースも増えてきており、バックデートすること自体が難しくなってきています。また、地方自治体ではバックデートそのものが制限されています。
今回は、紙の契約書および電子契約に関するバックデートの可否、地方自治体におけるバックデートの現状について解説します。
契約の「バックデート」とは何か?
当事者間に契約に基づく債権債務の発生など法的効力が発生するのは、原則として契約について合意が成立した時です。しかし、何らかの事情によって契約書の作成日(または契約書内の「契約締結日」など)を実際の契約成立日よりも過去にさかのぼった日付を記載するケースが存在します。
このようなことが起こるのは、ビジネスの実務上、正式に契約書を取り交わす前に相手方と取引行為を行うことが決して珍しいことではなく、一般的であるという実態があります。
例えば、業務上すぐに必要である物品の購入に関して契約書面を取り交わす前に納品を受け、後から契約書を作成するようなケースです。このような場合、契約書を作成する時点(契約が成立する時点)では、すでに売買の目的物は納入されています。つまり、契約が正式に成立する前にもかかわらず、契約内容の履行がすでに終わっているという事態となるわけです。
この逆転状態を解消するため、契約書の作成日などを過去(実際に取引が行われた日)にさかのぼって記載するようなことがバックデートです。
半ば慣例化されている感のあるバックデート行為ですが、リスクをはらむ行為であり、大きな問題となることがあるので注意が必要です。
バックデートの問題点
このように業務の必要上、どうしてもバックデートする必要があるケースは多いかもしれません。通常のケースでは契約内容が滞りなく履行されることが大半であるため、大きな問題となることはまずないでしょう。
しかし、実際に契約が成立した日とは異なる日を契約書に記載する行為や契約の相手方と共謀して契約書の日付をごまかして記載する行為は不正のバックデートにあたります。厳密には虚偽の内容を記載した書類を作成したことになり、法律的に厳密に考えた場合には私文書偽造などの刑事罰(刑法第159条)となる潜在的なリスクがあるのです。また社内コンプライアンス的に考えても、好ましい行為でないことは明らかです。
また、年度や決算のタイミングで人事異動や組織改編があり、決裁者や担当役員、管轄の部署が変更となる可能性があります。自分の担当していない時期の取引の決裁をためらう新役員もいるでしょう。契約書や電子契約の作成が自社だけでなく、他社の人事異動や組織改編のタイミングに振り回される可能性があることにも注意が必要です。
バックデートを避けるための対処法
上述のような問題点があるため、バックデートは極力避けるべきです。
それでは、バックデート以外で同様の実務的要請を解決し、さらに法律的に問題のない方法はないのでしょうか?
実は、以下のような方法を用いることでバックデートと同様の効果を持ち、しかも法律的にも問題のない対応ができるのです。
バックデートせずに契約を行うためには、契約内容に遡及効(そきゅうこう)を持つ条項を加えることが有効です。遡及効とは、さかのぼって契約の効力を及ばせるという意味です。
契約書の文言に「この契約の効力は契約締結日にかかわらず、〇年〇月〇日に行われた取引行為に対しても及ぶ」などといった条項を加えましょう。契約書の条文の中に、このような遡及的に効力が及ぶこととする条項を加えることによって、バックデートと同じ効果を得ることができます。
電子契約におけるバックデートの可否
電子契約では従来の紙の契約書の作成よりも迅速にプロセスが進むため、バックデートの必要性は少なくなる可能性があります。しかしそれでも、日付を遡らせる必要性が無くなるとは言い切れません。実際、ビジネスの現場では根強い需要が残ると考えられます。
電子契約の場合には、電子ファイルを作成する際に電子署名を行うことになります。電子署名すると、その日時がタイムスタンプによって明確になるため、バックデートした場合にはデータを改ざんした形跡がハッキリと残ってしまいます。仮に従来の紙を使った契約書でバックデートする場合、契約書作成日(契約締結日)と実際の契約成立日に食い違いがあったとしても、書面上からその痕跡を見つけることは困難です。
しかし、電子契約ではバックデートした痕跡が残るため、事実と異なる書類を作成したことが簡単にばれてしまうのです。
このため電子契約では紙の契約書で行われていたようなバックデートはできない、と認識しておいたほうが良いでしょう。もし電子契約でもバックデートをするのと同じ効果を持たせたいのであれば、すでに述べたように契約条項の中に遡及効を持つ条項を設けておくことをおすすめします。そのようにすれば、法律的なトラブルを回避することができるでしょう。
地方自治体との契約に関するバックデート
一般企業において慣例上行われることの多い契約のバックデート問題ですが、地方自治体との契約ではどのように考えるべきでしょうか。
(1)バックデートは事実上できない
結論から言うと、地方自治体のバックデートは私企業における場合よりも厳しく制限されており、事実上不可能となっているといってよいでしょう。地方自治体が契約する際には、地方自治法や最高裁判例等によって、契約書の作成または電子契約の締結が義務付けられており、契約書または電子契約がなされない場合には契約の効力が法律上認められないとされています。地方自治体の契約には、このように厳しい制約が課せられているため、契約書を作成せず「とりあえず契約内容を履行する」ということが難しいのです。
(2)地方自治体の契約にはバックデート以外の制限も課せられている
このように、世間ではよく見かける「まず契約内容の履行をしてから正式に契約を締結する(契約書を作る)」ことを地方自治体が行うことは高いハードルが存在します。
これは、地方自治体の行う契約は予算の執行を伴うものであり、その予算の執行には予め議会の承認を得ておく必要があることによります。契約書の作成・電子契約の締結が効力要件となっているのも予算承認の結果があってこその取引であることを明確にするためでしょう。
このようなバックデートに対する制限を前にして、地方自治体の実務は苦慮しているようです。ある地方自治体が「遡って契約を有効にする」バックデートの逆ともいえる「来年度の予算案が議会で可決されたら契約が有効になる」という「未来の条件」を付した契約締結は可能かという問い合わせを総務省に行っていますが、総務省がNGと回答した事例が記録として残っています。年度末の時点において翌年度のための契約を一定の条件の下に認めてほしいというものでしたが、総務省は認めませんでした。
(3)契約実務を早める電子契約
上述は、地方自治体の契約実務の現場が時間的なコストに困惑していることを伺わせる好例だと思われますが、この点、電子契約サービスを活用し電子契約を行えば、契約内容の確認をデジタル上で行うことができ、契約当事者が電子署名をした日時がタイムスタンプで把握できるようになります。
また、郵送の手間や時間の縮減も見込めるでしょう。さらにあらかじめ押印権限者の設定を行ったりするなど契約締結までの準備も進めておけば決裁者が遠隔地にいてもオンラインの環境があれば素早く契約締結までのフローを進めることができます。
まとめ
契約のバックデートは半ば慣習化されているような感がありますが、法律的・コンプライアンス的な観点から見れば問題のある行為であるのは間違いありません。場合によっては、大きな問題となる可能性もありますので、業務の担当者としては、極力バックデートは避けるべきです。
そのようなリスクを負わなくても、契約内容に遡及条項を設ければバックデートと同様の効果を得ることが可能になります。今回ご紹介した知識を活用し、ビジネスに役立てていただければ幸いです。