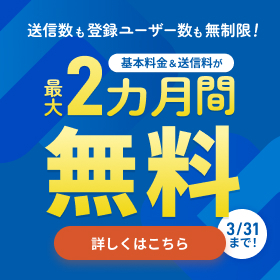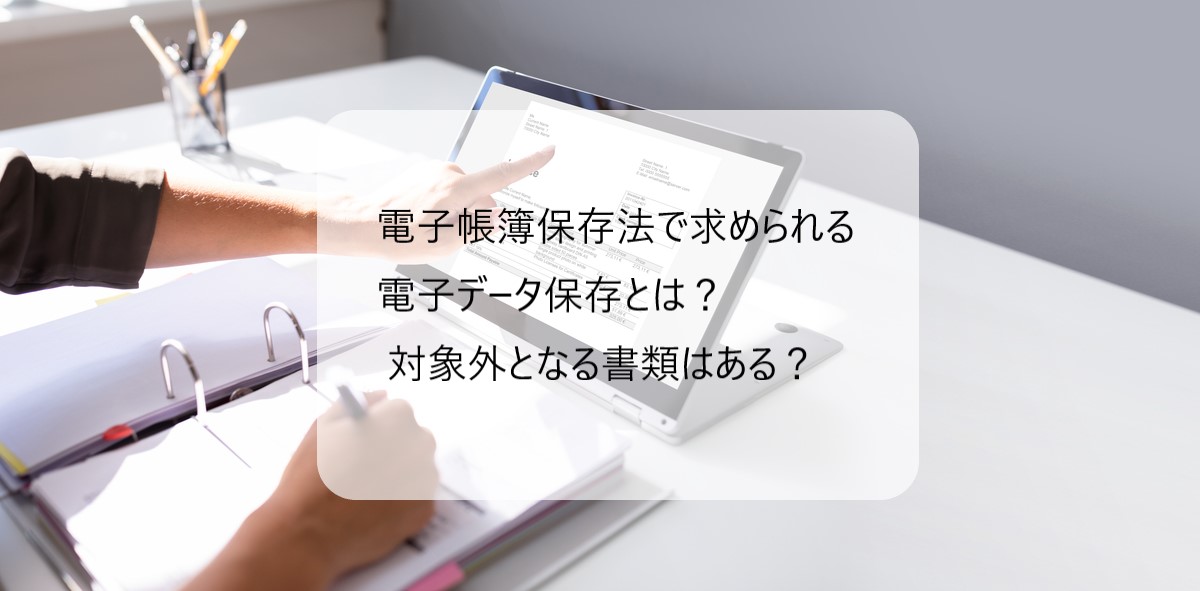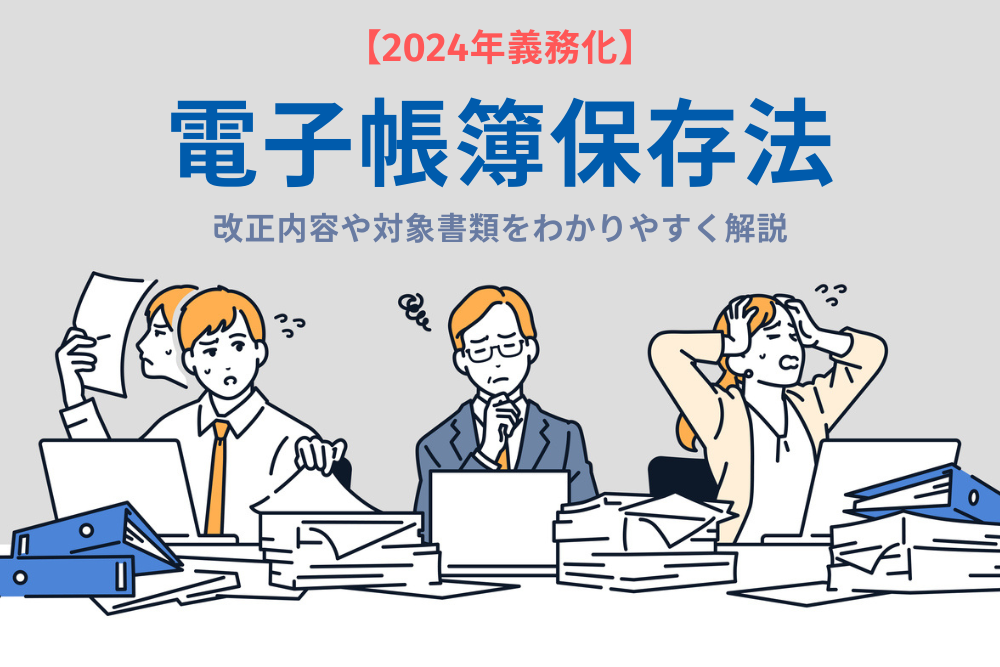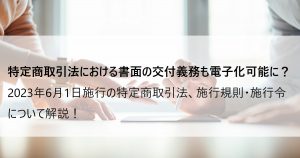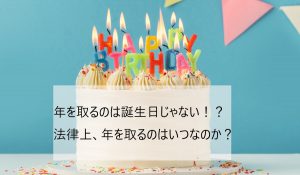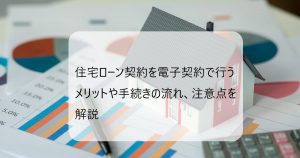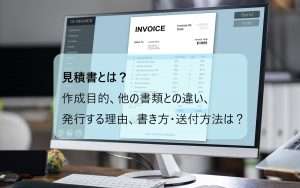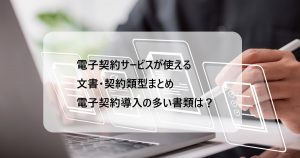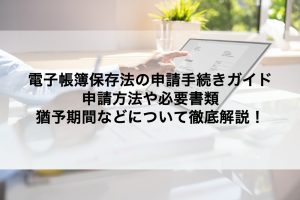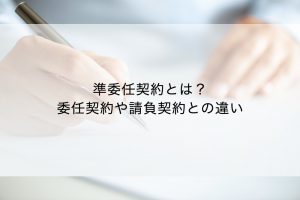2021年に電子帳簿保存法が改正され、個人事業主や企業が電子取引を行っている場合、紙ベースではなく、電子データでの保存が求められるようになります。今までとは書類の取り扱いが大きく変わる可能性がありますので、事業者はしっかりと理解し、早急に対応をしていく必要があります。そこで、電子帳簿保存法の対象となる書類と対象外となる書類を確認し、どのような扱いをしたら良いかを押さえておきましょう。

電子帳簿保存法まるわかりガイド
電子帳簿保存法について詳しく知りたい方におすすめ!
目次
電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法の改正によって、2022年以降電子取引に関するデータ保存をすることが求められています。しかし、多くの企業や個人事業主ですぐに対応することは難しいことから、2年間の猶予期間が設けられています。
最終的に、2023年12月以降は電子取引を行うすべての事業主が対応を済ませておく必要があります。その詳細をチェックしてみましょう。
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法とは、電子取引を行っている事業者に対して、税務に関係する書類を電子データとして作成、取り込みを行い、保管しておくことを求める法律です。電子取引をまったくしていない事業者は対象とはなりません。しかし、この時代にまったく電子取引をしていないという事業者は稀ですので、ほとんどの企業や個人事業主があてはまると考えて良いでしょう。
電子帳簿保存法に対応することは面倒だと感じるかもしれませんが、そもそもこの法律は、より効率的な書類の保管を目指すことを目的としています。帳簿書類は原則として紙ベースでの保管が求められていますが、電子帳簿保存法により、一定の条件をクリアすれば電子データでの保管が可能となります。これにより、紙の書類を持たずに済むので、書類の作成や管理が楽になり、保管スペースも節約することができます。
電子帳簿保存法への対応は、はじめは負担も小さくないですが、最終的には業務効率化やコスト削減を実現することができるので、前向きに切り替えを進めていくと良いでしょう。
あわせて読みたい
【2024年義務化】電子帳簿保存法の対象書類や保存要件、最新改正内容をわかりやすく解説
2023年12月31日で電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)措置が終了し、2024年1月からはついに電子帳簿保存法の本格的な運用が始まりました。たとえば、これまではメールで受...
データの作成と保存方法
電子帳簿保存法では、電子データの保存は主に3つの種類に分けられています。
①電子帳簿等保存
税務関係の帳簿や関連書類を電子的に作成、つまりソフトなどを使って作成し、そのデータを保存しておく方法があります。
②スキャナ保存
契約書や見積書、領収書など紙ベース作成したものをスキャンもしくは撮影して、そのデータを保存する方法です。ビジネスの現場ではまだまだ紙ベースの書面が多く存在するので、この保存方法は多く利用されるでしょう。
③電子取引
オンラインでの取引など、はじめから電子データでやり取りされた書類をそのまま電子データで保存する方法です。たとえば、ECサイトから備品を購入した場合、領収書がメールで送られてきたり、サイト上に表示されたりします。こうした電子データをそのままパソコン等に保存しておけば、紙で保管しなくても済みます。
電子帳簿保存法の対象書類
上記のように電子帳簿保存法の対象となる保存方法は、主に3つの種類に分かれます。それぞれの方法でどのような書類が対象となるのかを確認しておきましょう。
国税関係の書類や帳簿
国税関係の帳簿としては、以下のようなものがあります。
- 現金出納帳
- 売上台帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 固定資産台帳
- 売掛金台帳
- 買掛金台帳
これらの帳簿は、原則、紙ベースで7年間の保管が義務付けられていました。しかし、電子帳簿保存法に対応した電子データの保管を行えば、紙帳簿での保管をしなくても良いことになります。クラウド会計ソフトなどを使って会計・税務処理をしているのであれば、わざわざ印刷しなくても良くなるわけです。
国税関連書類
また、国税関連書類としては、次のような書類が対象となります。
- 賃借対照表
- 損益計算書
- 棚卸表
- 領収書
- 見積書
- 契約書
- 請求書
こうした書類も、要件をクリアした形で電子データ保存をしていれば、紙の書類の保管は不要となります。帳簿類以上に、領収書などはかなりかさばりますので、データのみの保存で済むことはメリットが大きいです。
ただし、契約書などで税務関連以外の法律により保管が義務付けられているものもありますので、注意が必要です。
領収書などは紙ベースで受領することも多く、スキャンもしくは撮影したデータを保管することになるでしょう。この際、タイムスタンプを押す必要があります。タイムスタンプは、取引から3営業日以内から2カ月+7営業日以内の期間に押さないといけません。
同時に、フォルダの中で検索しやすいように、タグもしくはタイトルを付けることも求められています。取引の年月日と取引金額、取引先ですぐに検索できるようにする必要があるのです。電子帳簿保存法への対応では一番面倒とも言えるところで、タイムスタンプを押せるシステムを導入しないといけません。
電子取引を行った書類
オンライン上やメールでの取引をした場合、電子取引に関係する書類は、そのままデータとして残しておくことが可能です。たとえば、電子契約やWEB請求書、WEB受領書、EDI取引書類などです。これらの書類は取引日時や内容などがわかるようにして、クラウドやパソコン上で保管しておくだけで十分です。

電子帳簿保存法まるわかりガイド
電子帳簿保存法について詳しく知りたい方におすすめ!
あわせて読みたい
特定商取引法における書面の交付義務も電子化可能に?2023年6月1日施行の特定商取引法、施行規則・施行...
現在、日本では日常生活における各種の場面において電子化が推進されています。また、法改正によって各種書類の電子化が可能となってきています。 この流れは特定商取引...
電子帳簿保存法の対象外となる書類
基本的にはすべての書類や帳簿は電子的に保存しなければならないのですが、一定の条件では対象外となるものもあります。これからどのような対応を取るべきかを検討する際の参考にしましょう。
手書きで作成した書類
電子帳簿保存法の対象外となる書類として、特定の書類が指定されているわけではありません。経理や国税関連の帳簿書類において、手書きで作成したものについては対象外となるというルールがあるのみです。たとえば、仕訳帳や補助簿、請求書などを手書きのみで作成していれば、それは電子データとして保管する必要はないと定められています。
もちろん、こうした帳簿でもクラウド処理に移行したり、会計ソフトに打ち込んでいたりしていれば、電子データで保存しなければなりません。あくまでも、手書き帳簿のみで処理している場合が対象外となるという意味です。また、請求書などの書類はスキャンもしくは撮影して電子データ保存も可能ですので、事業者がどちらの方式を採るかを選択する必要があります。
原本の保管が求められる
電子帳簿保存法の対象外となる手書きの書類であっても、引き続き原本の保管は義務付けられています。単に電子帳簿保存法の適用を受けないだけであって、国税関係書類などは7年間の原本保管が必要となるわけです。
電子帳簿保存法に対応しない場合
2024年1月から、電子取引を行う事業者はすべて電子帳簿保存法の対象となります。もし、規定に反して電子データでの保存をしていない場合、どのようなペナルティを科せられるのでしょうか。
青色申告が取り消される
個人事業主の場合は、青色申告の承認が取り消される可能性があります。電子帳簿保存法は、法人か個人事業主か、事業規模はどうかということに関わりなく、すべての事業者が公平に取り扱われることになります。もちろん、なんらかのミスや対応不足で要件を満たしていないからと言って、即座に青色申告が取り消されるわけではありません。悪質性があるとか、故意に対応していないケースで、こうしたペナルティを科せられることが考えられます。
青色申告ができなくなると、青色申告特別控除が受けられなくなります。最大で65万円の控除が受けられる制度ですので、これが使えなくなると大きな痛手となるでしょう。また、赤字の繰越控除など、事業を続けていくうえでのメリットもなくなってしまいます。さらに、青色申告専従者給与の経費計上も不可となります。経費に算入できる金額がかなり減ってしまうことにもつながりますので、青色申告を取り消されることがないようにしましょう。
過少申告加算税の対象となる
申告になんらかの不備がある場合、過少申告加算税の対象となることがあります。もともとこのペナルティは、申告漏れなどで本来の納税額よりも少ない場合に科せられるものです。しかし、正式な方法で申告義務を果たしていないケースでも適用されることがあります。電子帳簿保存法にしっかりと対応しないことで、追徴課税の恐れがあることも覚えておきましょう。
過料を科せられる
企業ならば、会社法の定めによって、過料が科されることも考えられます。法的に有効な手続きをしない場合、その会社に対して100万円以下の過料を求められることがあるのです。過料は刑事罰とは異なるものですが、無駄なお金を支払うことになりますし、会社の評判を下げる結果となりますので、避けたいところです。
電子帳簿保存法について正しい理解を
電子帳簿保存法では、今まで紙ベースで帳簿書類を保管していたものが、2024年1月以降は電子データでの保存を義務付けられます。電子取引がある企業、個人事業主であれば、すべて適用されますので、確実に対応しなくてはなりません。この制度の対象外となる書類は手書き作成のものだけですので、原則としてはすべての書類が対象となると考えたほうが良いでしょう。どのような保存を行ったら良いかを早めに検討し、必要なシステムを導入して、しっかりと対応しましょう。
\ 電子帳簿保存法にも対応!/