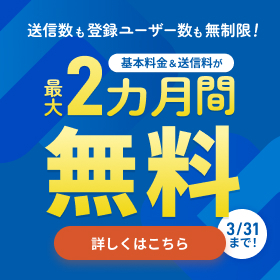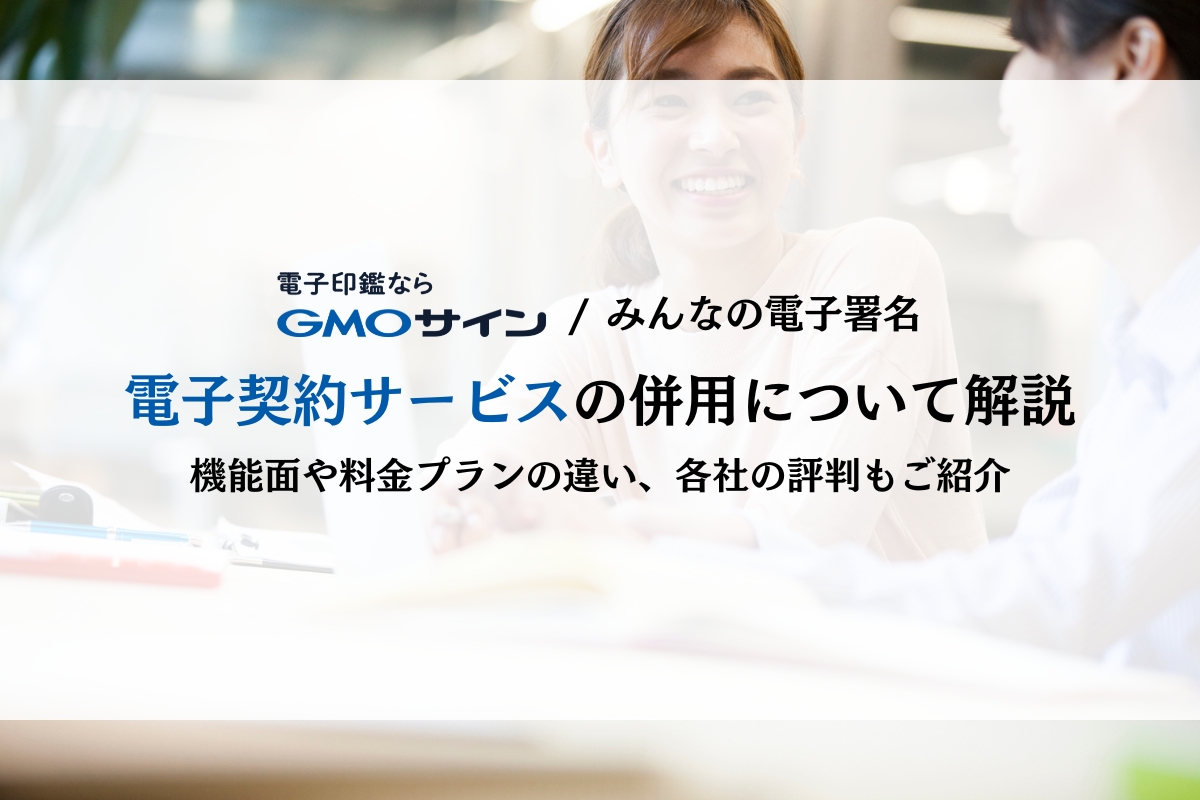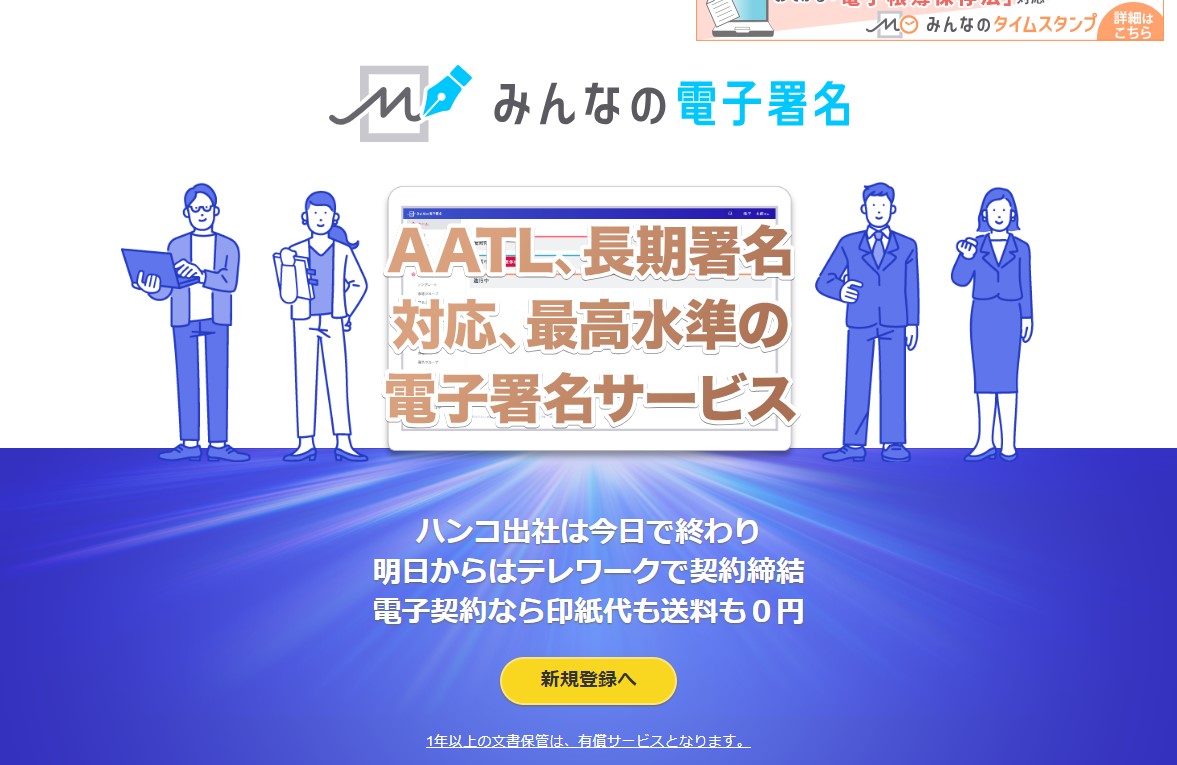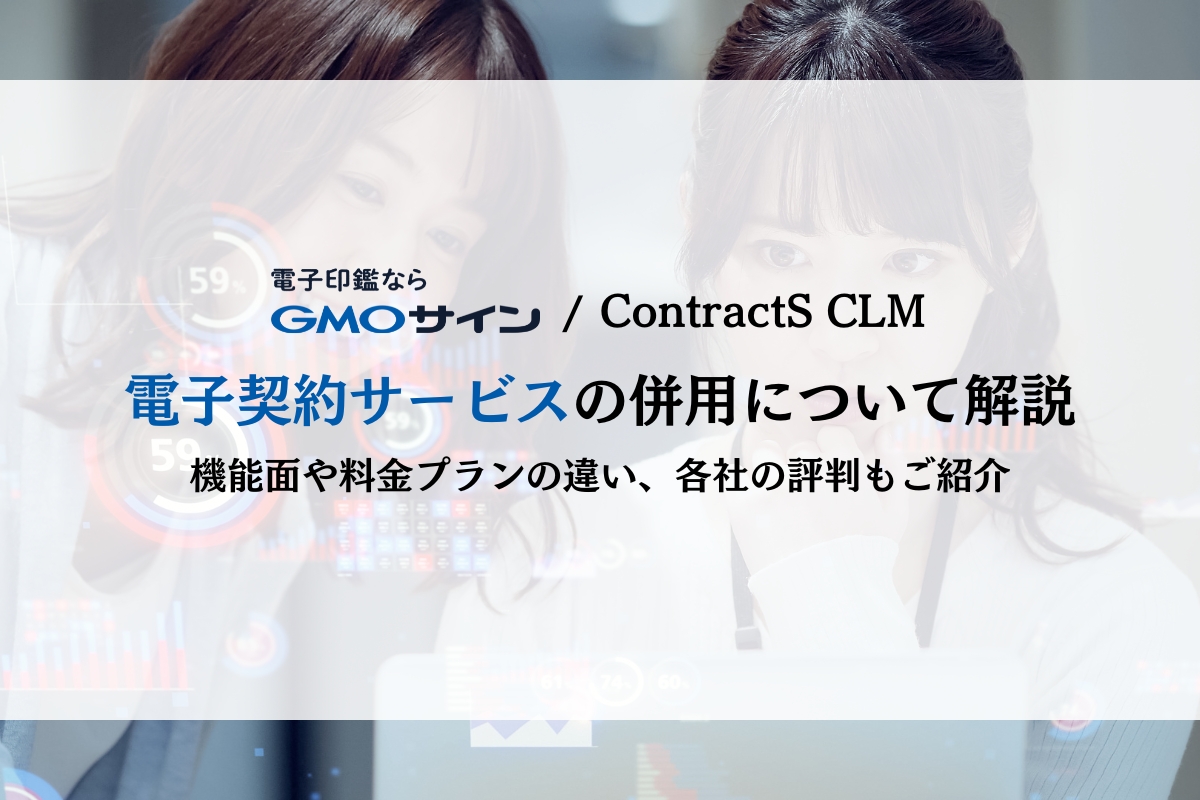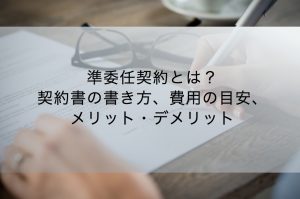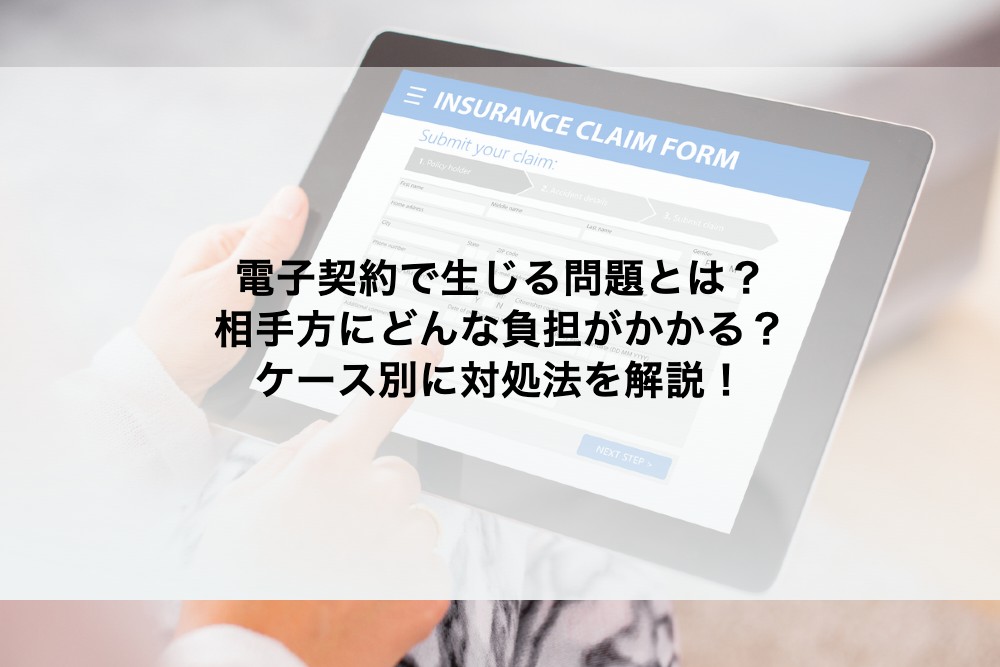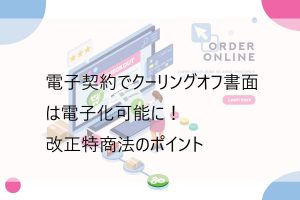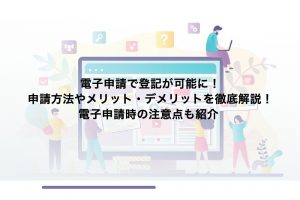掲載内容は【2024年2月】時点の情報を基に作成したものです。最新の情報は各社公式サイトにてご確認ください。
電子契約サービスの本格導入にあたり、どのサービスにすべきか迷うことが多々あります。とくに取引先が多い企業であれば契約相手方に合わせて複数の電子契約サービスを使い分けていることも多く、一本化が難しいこともあるでしょう。また、規模が大きい企業であれば、部署ごとに利用しているサービスが異なるケースもあります。
本記事では、電子印鑑GMOサインとみんなの電子署名という2つの電子契約サービスを例に挙げて、複数の電子契約サービスを使い分ける、すなわち複数サービスを併用する際の、注意点やメリットについて詳しく解説します。さらに記事後半では、複数サービスに散らばった電子文書を一つの場所にまとめて管理する具体的な方法についてもご紹介。ぜひ最後までご覧ください。
目次
電子印鑑GMOサインの基本情報

電子印鑑GMOサインはGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供している電子契約サービスです。GMOグローバルサイン・ホールディングスは、ITやインターネットの分野で高い知名度を誇るGMOインターネットグループの企業です。
GMOサインは350万社以上(※)の企業が導入しており、このことからも知名度や信頼性の高さをうかがい知ることができます。地方自治体などの公的機関での導入実績もあり、国内屈指の電子契約サービスといえるでしょう。
また、対応している書類の種類が幅広く、さまざまな業種で利用可能です。パソコンとスマートフォンの両方に対応しているため、出先でも利用できるのも便利です。
月に5件まで電子署名を利用できるお試しフリープランという無料プランもあり、実際に使用感などをチェックしてから有料プランを利用するかどうか決められます。
※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)
みんなの電子署名の基本情報
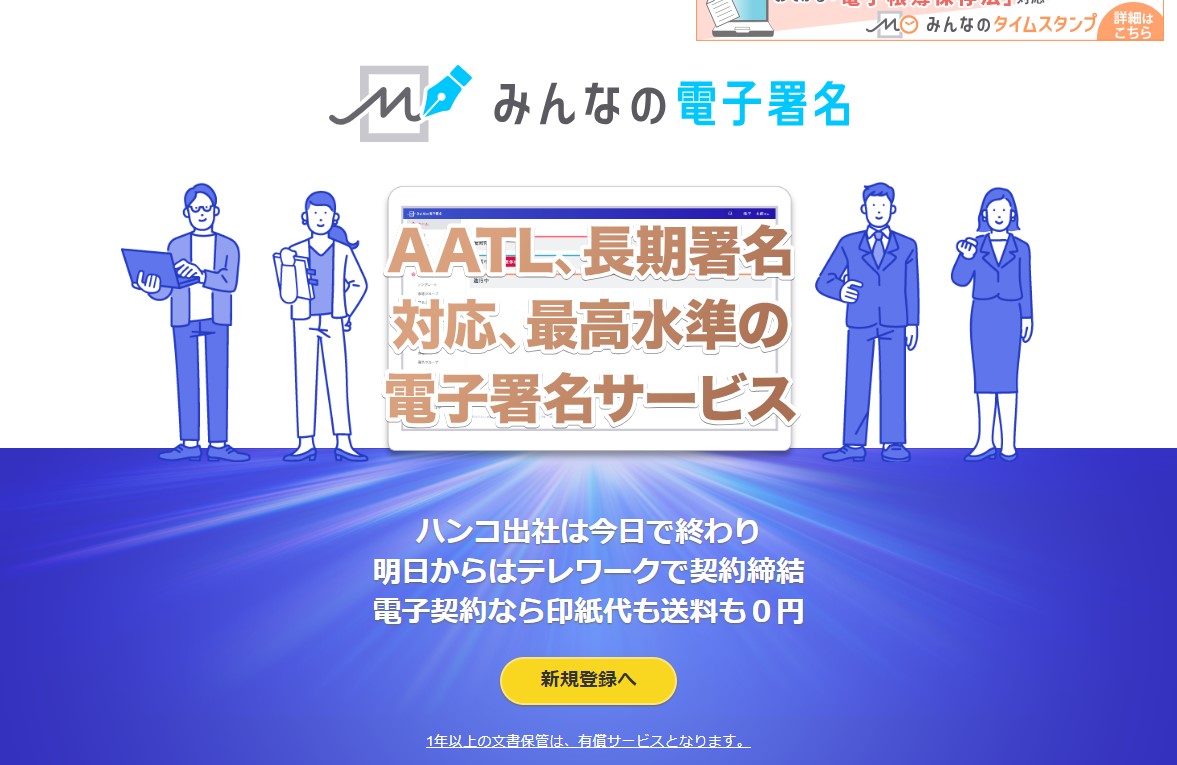 出典:https://es.vector.co.jp/
出典:https://es.vector.co.jp/
みんなの電子署名は株式会社ベクターが提供している電子署名サービスです。株式会社ベクターはPCソフトウェアの販売などを主軸としている企業で、IT関連の分野において豊富な実績があります。みんなの電子署名の特徴として、有料プランや無料プランといった括りが存在せず、月額固定料金が完全無料であることが挙げられます。
※ただし、1年以上の文書保管は、有償サービスとなります。
「みんなの電子署名」は、2024年11月末(予定)をもって、電子契約サービス「ベクターサイン」へサービスを統合されることが公式サイト上で告知されています。
>> 詳細はこちら
電子印鑑GMOサインとみんなの電子署名の料金と機能比較
GMOサインとみんなの電子署名とでは、料金体系や利用できる機能に違いがあります。ここからは、GMOサインの各プランの特徴やみんなの電子署名で利用できる機能について、詳しく紹介します。
電子印鑑GMOサインのお試しフリープランの主な機能
GMOサインのお試しフリープランでは、ユーザー数は1人のみ登録できます。送信件数は月に5件までで、送信料はかかりません。署名方法に関しては契約印タイプ(立会人型)に対応しています。また、アドレス帳や文書テンプレートを登録できる機能が備わっています。印影登録や手書きサインにも対応可能です。
ただし、お試しプランは有料プランと比べて利用可能な機能が少ないため、プラン名通りあくまでトライアル(お試し)として利用するのが良いでしょう。
スクロールできます
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | |
| 印影登録 | |
| 認定タイムスタンプ | |
| 契約締結証明書 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | |
| 署名順設定(順列/並列) | |
| アクセスコード認証 | |
| ⽂書テンプレート登録 | |
| アドレス帳 | |
| 下書き保存 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | |
| フォルダ作成 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | |
GMOサインの無料プランでできること電子印鑑GMOサインの有料プランの主な機能
GMOサインの有料プランは契約印&実印プランと呼ばれ、月額基本料金9,680円(税込)で提供されています。その名称通り、メール認証で本人性を担保する契約印タイプ(立会人型)と認証局で発行される電子証明書で本人性を担保する実印タイプ(当事者型)の両方を利用可能です。オプションを付けることでマイナンバー実印も利用できるようになっています。
業務委託契約書や秘密保持契約書など個人相手の契約であれば立会人型、大型の取引や業務提携など企業にとって重要な契約には当事者型など契約内容による使い分けが可能です。
また、登録できるユーザー数と送信件数の制限がなくなるのもお試しフリープランとの違いです。ただし、毎月の基本料金とは別に送信料がかかります。契約印タイプだと1件につき110円(税込)で、実印タイプは1件につき330円(税込)です。
権限の設定や操作ログの管理、二要素認証などセキュリティ面での機能も利用できるようになります。電話やメール、チャットなどでのサポートも充実しています。
みんなの電子署名の主な機能
みんなの電子署名では、登録できるユーザー数は無制限で、送信件数も無制限です。送信するごとに料金がかかることはありません。また、立会人型(契約印タイプ)に対応しています。サービスの運営会社である株式会社ベクターの証明書が用いられる仕組みです。
みんなの電子署名には、タイムスタンプやワークフロー設定、文書検索など基本的な機能が一通り揃っています。操作ログを取る機能やワンタイムパスワードを設定する機能などもあり、一定のセキュリティも保たれています。
また、みんなの電子署名で作成した署名にはPAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)という長期署名が添付されているのが特徴です。これにより10年間有効に機能します。
ただし、PDF形式の文書のみをサポートしており、WordやExcelなどで作成した文書には対応していません。
「みんなの電子署名」は、2024年11月末(予定)をもって、電子契約サービス「ベクターサイン」へサービスを統合されることが公式サイト上で告知されています。
>> 詳細はこちら
電子印鑑GMOサインとみんなの電子署名を併用すると料金はどのくらいかかる?
みんなの電子署名は、利用状況にかかわらず料金が発生することはありません(※ただし、1年以上の文書保管は、有償サービスとなります)。一方、GMOサインの契約印&実印プランの月額基本料金は9,680円(税込)です。
複数の電子契約サービスを利用する場合、月額基本料金が高額だと、その分コスト負担が大きくなります。しかし、固定料金が不要のみんなの電子署名とコストパフォーマンスの高さを売りにするGMOサインの併用であれば、コスト負担を最小限に抑えながら、電子契約の併用が可能です。
「みんなの電子署名」は、2024年11月末(予定)をもって、電子契約サービス「ベクターサイン」へサービスを統合されることが公式サイト上で告知されています。ベクターサインの料金体系はみんなの電子署名と異なり、月額基本料金が発生します。そのため、固定料金がかからないことを理由に現在みんなの電子署名を利用しているユーザーは注意が必要です。
>> 詳細はこちら
電子印鑑GMOサインとみんなの電子署名を併用するメリット
GMOサインとみんなの電子署名を併用することで次のようなメリットがあります。
どちらか一方が利用できなくなった場合の備えになる
電子契約サービスを含むWebサービスは、サーバーの不具合などで一時的に利用できなくなることが稀にあります。ほとんどの場合、短時間で復旧しますが、それでも今すぐに利用できないと困る場面もあるでしょう。
そのようなときに、電子契約サービスを2つ併用していると便利です。大半の電子契約サービスは月額基本料金がかかるため、不具合発生時に備えて2つ利用するのは難しいかもしれません。
その点、みんなの電子署名なら月額基本料は無料のため、併用しやすいでしょう。そのため、GMOサインをメインで使用して、サブとしてみんなの電子署名を併用するのがおすすめです。
電子契約サービスを併用する際の注意点
電子契約サービスを併用する際は、以下のポイントに注意しなければなりません。
- ランニングコストの増加
- 書類や送信先など管理業務の複雑化
- 電子帳簿保存法への対応
ここでは、デメリットについてわかりやすく解説します。
ランニングコストの増加
複数の電子契約サービスの併用には、それぞれ月額費用やオプション料金などが発生します。紙の契約書を電子化すれば大幅なコストカットが実現できますが、企業にとって余分なサービスにかける費用は削りたいはずです。そのため電子契約サービスを併用する場合は、契約内容や利用方法で無駄なコストが出ないように定期的に見直す必要があります。
書類や送信先など管理業務の複雑化
複数のサービスを導入すると、書類やアドレス帳の管理が複雑化する恐れがあるので、注意が必要です。
取引先にあわせてサービスを切り替える場合は、サービス別に対応する企業の一覧表を作っておくことがおすすめです。一覧表があれば、担当者が変わってもどちらのサービスを選べばいいかすぐにわかるため、取引先にも迷惑をかけずに済みます。
また、サービスによって操作方法が異なるので、それぞれのマニュアルを社員全員に共有することも大切です。マニュアルがあれば徐々に2つのサービスの操作に慣れていけるため、導入時に周知しておきましょう。
電子帳簿保存法への対応
2つ以上の電子契約サービスを利用する場合は、各サービスが電子帳簿保存法に対応しているかを確認しておきましょう。なお、法改正により、2024年1月から電子帳簿保存法の本格的な運用が開始しています。書類は7年間保存しなければならないので、流出しないよう、強固なセキュリティ環境に保管する必要があります。
また、電子帳簿保存法の保管要件として、すぐに書類を検索できることと、書類内容が作成時から変更されていないことを証明しなければなりません。具体的には、ファイル名に取引日や取引金額などを入力してすぐに書類を探し出せるようにする、書類にタイムスタンプを付与するなどの方法があります。
電子契約サービスの併用がおすすめできる企業
電子契約サービスの併用は次のような企業におすすめです。
小規模事業者から大きな企業まで取引がある企業
電子契約サービスは数多く提供されており、企業によって導入しているサービスが異なります。同じ電子契約サービスを使っていなくても契約はできるものの、使い慣れていないサービスを使うことでミスが起きるかもしれません。
複数の電子契約サービスを契約していれば、相手が導入しているサービスに合わせて使うサービスを切り替えられます。双方が導入しているサービスを使えば操作ミスが起きる心配もないため、滞りなく契約締結まで進めるでしょう。
電子契約のスモールスタートを希望する企業
電子契約サービスの導入を検討しているが、やはり実際に使ってみないとどのサービスが自社に合うのかわからないというケースは多々あります。そのような場合におすすめなのが、スモールスタートが可能な電子契約を併用することです。
本記事で紹介したみんなの電子署名は固定料金が無料で利用でき、GMOサインは月額基本料金9,680円という低価格で利用を開始することが可能です。さらにGMOサインは、年間契約を通常とする多くの他社サービスと異なり、1カ月単位での利用ができます。そのため、みんなの電子署名とGMOサインは、ともに電子契約のスモールスタートに最適なサービスだといえるでしょう。
複数の電子契約サービスで作成した契約書類を一本化する方法
現在、電子契約サービスは数多く存在します。そのため、契約相手の利用サービスに合わせて複数のサービスを使い分けている方も多いのではないでしょうか。相手方に合わせることでスムーズな取引が行えるメリットはありますが、保存書類が分散されることで、文書の検索性が落ちるなどのデメリットも存在します。
そのような方におすすめなのが、GMOサインの署名互換機能(※)です。他社サービスにて署名済みの文書をGMOサイン内でまとめて管理ができます。
※「署名互換機能」対象のサービスはこちらからご確認ください。
「相手方とどの電子契約サービスで署名するか調整しなくてはならない」「署名したサービスごとに契約文書がバラバラに保管される」といった悩みをお持ち方でも、今後はGMOサインでまとめて署名・保管することが可能です。
>> 署名互換機能について詳しく見る
まとめ
GMOサインは国内の電子契約サービスの中でも知名度が高く導入実績も多いサービスです。大企業や官公庁などでも導入実績があります。みんなの電子署名は、知名度や導入実績ではGMOサインに及びませんが、料金面での魅力が大きいサービスです。フリーランスや小規模事業者に人気があります。
これら2つの電子契約サービスは、メインとなる利用者層が異なります。取引先が多いと、GMOサインを利用しているところもあれば、みんなの電子署名を利用しているところもあるでしょう。そのような場合には、GMOサインとみんなの電子署名の併用を検討してみましょう。2種類のサービスを併用していれば、万が一どちらか一方で不具合が生じたときの備えにもなります。
ただし、2024年11月にみんなの電子署名はサービス終了予定ですので、あくまでそれ以前の併用を前提とすることになるでしょう。
「みんなの電子署名」は、2024年11月末(予定)をもって、電子契約サービス「ベクターサイン」へサービスを統合されることが公式サイト上で告知されています。
>> 詳細はこちら
掲載内容は【2024年2月】時点の情報を基に作成したものです。最新の情報は各社公式サイトにてご確認ください。
あわせて読みたい
電子契約サービス29社を徹底比較!どこを選ぶべき?特徴や料金、使いやすさなどをご紹介【2025年3月最新...
紙の契約書は、作成後に署名・押印を行い、さらに相手方にも同様の手続きをしてもらう必要があり、非常に手間がかかる業務です。しかし、電子データを用いて契約書の作...