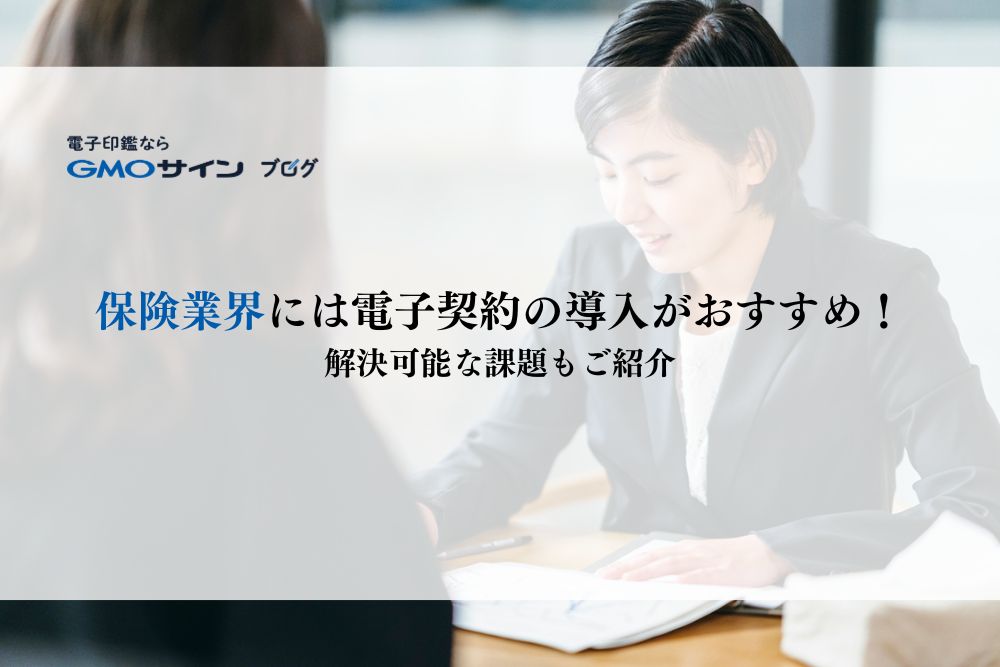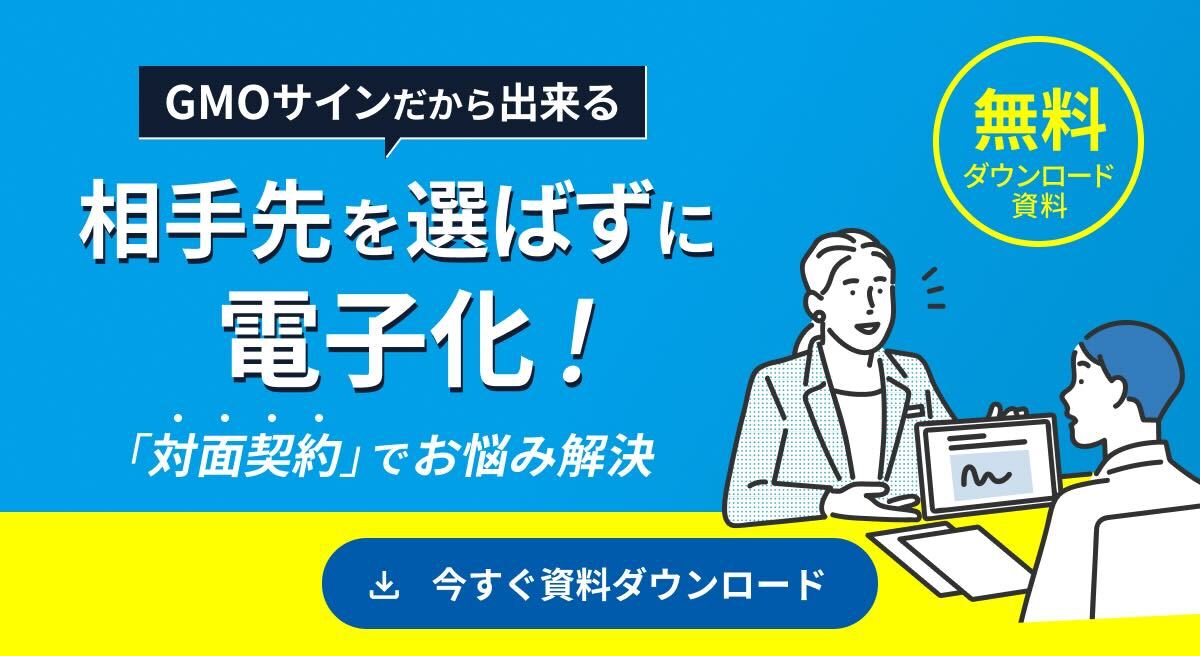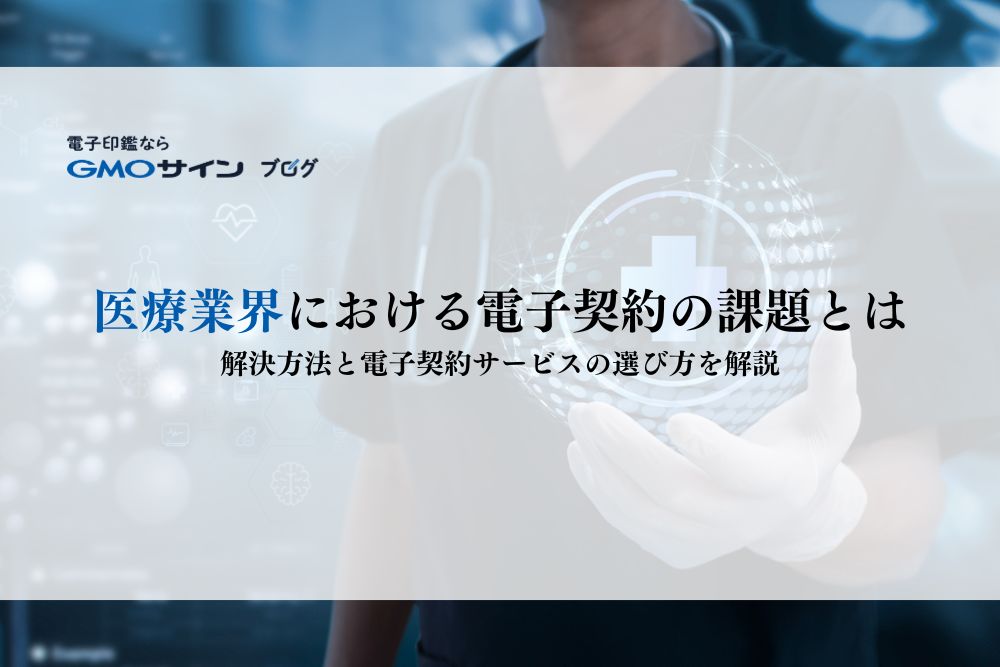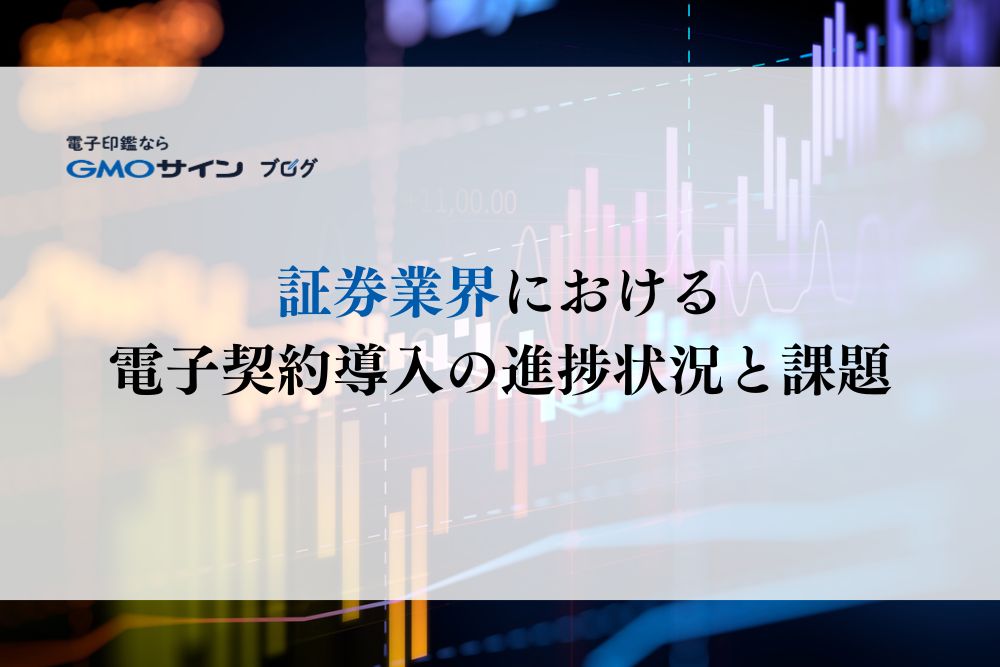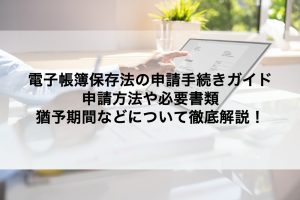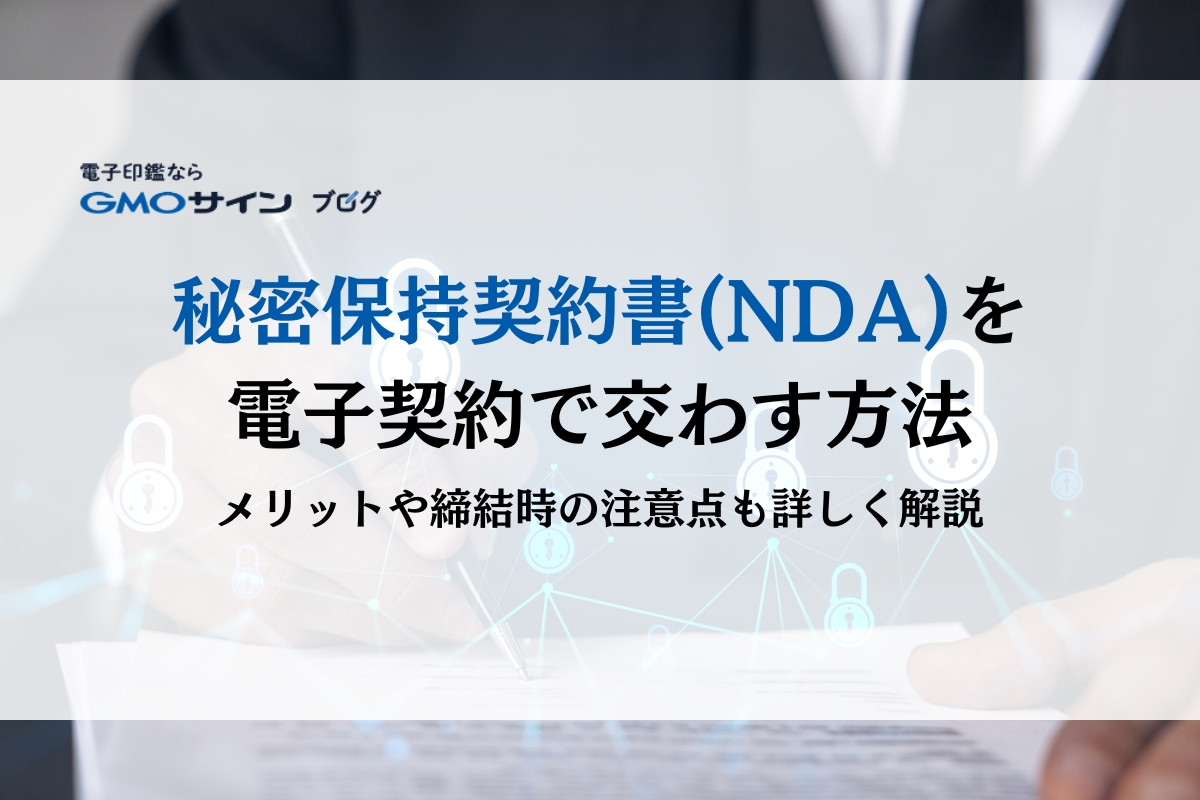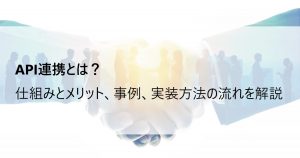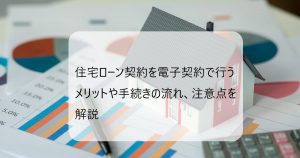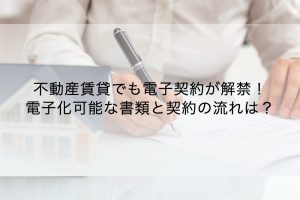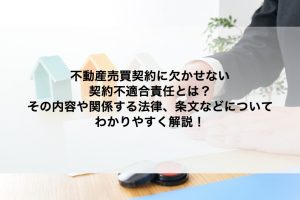保険業界を取り巻く環境は大きく変化しており、これまで通りのやり方では立ち行かなくなってくる可能性があります。早めに課題を洗い出して、解決のための対策を講じることが重要です。
このような変化に伴う課題の解決方法のひとつとして、電子契約の導入が考えられます。本記事では、保険業界が抱えている課題やその対策としての電子契約の導入が解決につながる理由などを解説していきます。
目次
保険会社の種類
保険業界といった場合には、保険会社やその代理店を指しますが、保険会社は大きく次の2種類に分けられます。
生命保険会社
生命保険会社は被保険者の死亡に備える内容の保険商品を中心に取り扱っている保険会社です。主に終身保険や定期保険、養老保険などが該当します。個人年金保険も生命保険会社で扱う保険商品です。また、生命保険会社で扱う保険商品は、保険業界の中で第一分野と呼ばれることもあります。
生命保険会社では、保険業務のほかに金融業務も行っています。顧客から預かった保険料を運用して増やすのが目的です。金融業務により、将来の保険料支払いに備えることができます。
損害保険会社
損害保険会社は、災害や不慮の事故に備える内容の保険商品を中心に取り扱っている保険会社です。損害賠償保険や自動車保険、火災保険などが該当します。生命保険が第一分野と呼ばれるのに対して、損害保険は第二分野です。
損害保険会社では、事故や災害が発生したときの問い合わせへの対応や保険金請求に伴う調査なども行います。
また、医療保険やがん保険に関しては、生命保険会社と損害保険会社のどちらでも取り扱い可能です。第三分野と呼ばれることもあります。
現在の保険業界を取り巻く環境
現在の保険業界は次のような環境に置かれています。
高齢化社会・人口減少社会
日本の人口は2008年にピークを迎え、その後は減少に転じています。とくにここ数年の減少率は大きく、人口減少に歯止めがかからない状況です。人口が減るということは、保険会社にとっては少ない顧客を奪い合うことになり、競争が激化します。
また、高齢化も急速に進行している状況です。保険商品に関しても、これまで通りの内容では対応が難しくなることもあるかもしれません。高齢化社会に合わせた対応が求められます。
2024年6月5日に厚労省が公表した2023年の人口動態統計の概数によると、日本国内において1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる「合計特殊出生率」は1.20で、過去最低にだったとのことです。東京都においては0.99と1を下回る結果となっています。
低金利環境
現在の日本の政策金利は0%程度で国債の利回りも非常に低いのが実情です。生命保険会社では、主に債券で資産運用をしているため、なかなか資産を増やせません。そのため、生命保険会社の金融業務は芳しくない状況が続いています。
外資系保険会社の本格参入
2000年代から外資系保険会社が国内に参入してきました。国内の保険会社と比べて保険料の安いところも多いため、国内の保険会社は外資系保険会社に顧客を奪われないように対策を講じなければなりません。
生命保険に関しては、2022年3月末時点での保有契約年換算保険料ベースのシェアにおいて、外資系が23%(※)を占めています。
※出典:金融庁「2023年保険モニタリングレポート」
保険業界が現在抱えている課題
多くの保険会社では次のような課題を抱えています。
契約者以外の関係者の情報把握
一般的に契約は当事者間において権利や義務が発生します。大半の契約において、当事者以外の人とはとくに関わりはありません。しかし、保険契約においては、当事者以外の人と関わりを持つことが多いのが特徴です。
たとえば、契約者以外の人が被保険者になることがあり、受取人も存在するため、関係が複雑になります。契約者に関しては契約時に説明をしたり契約書を交わしたりして接点を持っているでしょう。しかし、契約者以外の関係者とは、保険金の支払いまで接点を持たないことも多いのです。
そのため、関係者の情報を十分に把握できていないこともあります。契約時に契約者から情報提供を受けていても、保険契約は長期にわたります。契約時から保険金支払い時まで状況が変化することもあるでしょう。
保険会社の方で最新の情報を把握しておけるような体制を整えるのが課題の1つです。
診断書などの管理
生命保険では、自社で作成する契約書だけでなく医師が作成する診断書などが必要になることもあります。そのため、管理が複雑になる傾向にあります。医師の診断書は紙で作成されることが多く、その管理が課題です。
コールセンターの待ち時間短縮
大きな災害が発生すると、保険会社への問い合わせが増加します。近年では新型コロナウイルスの影響や能登半島地震で大きな被害が発生しました。問い合わせが増加すると、保険会社のコールセンターでは、待ち時間が長くなる傾向にあります。電話がつながりにくくなることもあり、顧客満足度が低下する原因になってしまいます。
そのため、コールセンターでの待ち時間を短縮することも保険会社が抱える重要な課題です。
また、損害保険会社においては、問い合わせだけでなくその後の調査にも時間がかかっており、対応の迅速化が求められています。
営業以外の販売チャネルの拡充
保険の加入チャネルに関して、営業職員の割合は年々減少傾向にありますが、依然として高い割合を占めています。生命保険の場合には、2021年度で55.9%(※)と半分を超える水準です。
※出典:金融庁「2023年保険モニタリングレポート」
しかし、少子高齢化・人口減少が進む中で、今後は十分な営業職員の確保が難しくなるでしょう。そのため、インターネットなど営業職員以外のチャネルの拡充に力を入れなければなりません。
課題解決のためには電子契約の導入が効果的
上述のような課題を抱える保険業界ですが、電子契約を導入することでその多くを解決できるかもしれません。その理由について見ていきましょう。
非対面での契約が可能
電子契約を導入すると、顧客はインターネットから保険契約を申し込んで、対面でのやり取りなしで完結できます。営業職員の人数は少なくて済むため、これからの人口減少社会にも対応でき、新たな販売チャネルを拡大できるため、契約者の増加にもつながります。
また非対面であれば、顧客から営業所などに出向いてもらう必要もありません。時間のあるときに必要事項を入力してもらうだけで済むため、顧客にとって利便性も向上するでしょう。
業務効率化を実現
電子契約では、紙の契約書を作成する場合と比べて手間を減らせるのもメリットです。大半の手続きをオンラインで済ませることができるため、書類を郵送する必要がありません。印刷をしたり封筒を用意して投函したりする時間を削減できるでしょう。
さらに、相手に書類が届くまで日数を要することもありません。電子契約なら瞬時に相手に届き、手続きを短時間で進められるようになります。
また、紙の書類の電子化も可能です。医師の診断書も電子化した上で保管すれば、管理が楽になります。契約者以外の被保険者や受取人などに関するデータの一元管理も可能です。
コストカットを実現
電子契約は紙の契約書を交わす場合と比べて、少ないコストで行えるのもメリットです。ペーパーレスのため用紙代や印刷代はかかりません。封筒代も切手代も削減できます。さらに紙の契約書を交わす際には、収入印紙も貼付しなければなりませんが、電子契約では収入印紙不要です。
あわせて読みたい
電子契約で収入印紙が不要になる理由を政府見解に基づき解説
紙で契約書を交わす際に必要となる収入印紙、つまり印紙税は、電子契約では必要ありません。ここでは、その理由について、印紙税法や国税庁などの見解を踏まえて解説し...
コストカットを実現できれば、コールセンターのスタッフ増員などに予算を割けるようになるでしょう。
【対面契約とは?3つの特徴】
①紙の契約書と同様に、その場でサインが可能。メールアドレスが不要に!
②タブレットを使い目の前で契約を締結するため、契約相手先の準備がいらない
③フリーメールアドレスよりも本人性担保が高い状態で締結!
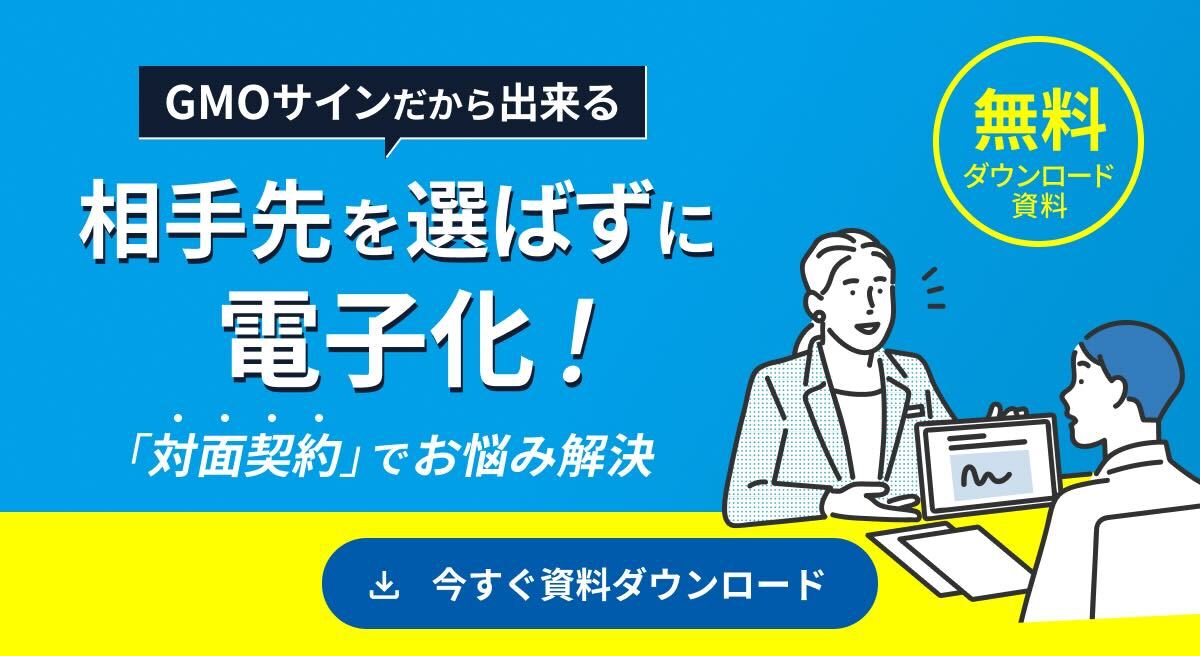
GMOサイン対面契約なら、
相手方のご状況に依存せず様々なシーンで電子契約が可能になります。
保険業界で使われることが多い契約書の種類
保険業界では主に次のような契約書類が利用されていますが、いずれも電子化が可能です。
保険証券
保険証券とは、保険契約締結後に契約者に対して交付する書類です。保険の対象や期間、保険料、保険金の金額などが記載されています。保険に加入していることと、その内容を証明できるため重要度の高い書類です。
重要事項説明書
重要事項説明書は、契約概要や注意喚起情報などについて記載されている書類です。保険会社では、契約者に対して重要事項説明を行うとともに、重要事項説明書を交付しなければなりません。非対面で契約を締結する際には、重要事項説明書も電子化したものを交付します。
代理委託契約書
代理委託契約書は、保険会社が代理店に保険商品の販売を委託する際に交わす契約書です。電子化すれば郵送の必要がなくなるため、スムーズに業務を進めることができます。
まとめ:電子契約の導入で状況の改善を図ろう
保険業界は、人口減少や低金利、外資系保険会社の参入など厳しい環境に置かれています。また、保険契約の特性上、契約者以外の関係者の把握や診断書の管理など多くの課題も抱えています。このような状況下で課題解決するためには、電子契約の導入がおすすめです。コストダウンや業務効率化を図れるため、契約者の増加や収益のアップにも期待が持てるでしょう。
現在、保険業界で使用される契約書類の大半は電子化が可能です。保険業界においていまだ電子契約を導入していない企業は、導入を前向きに検討してみましょう。