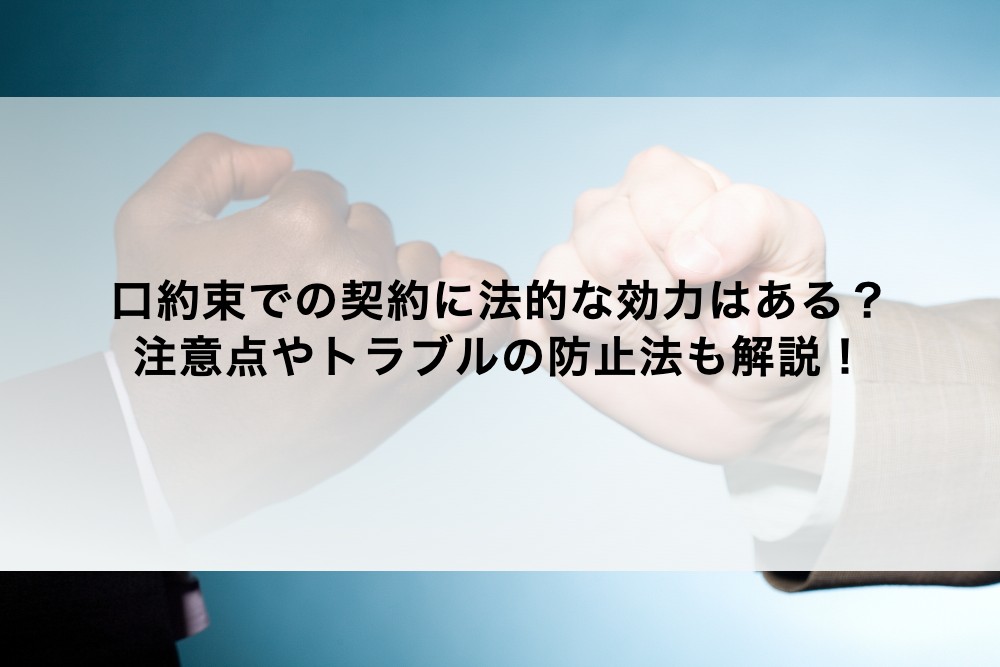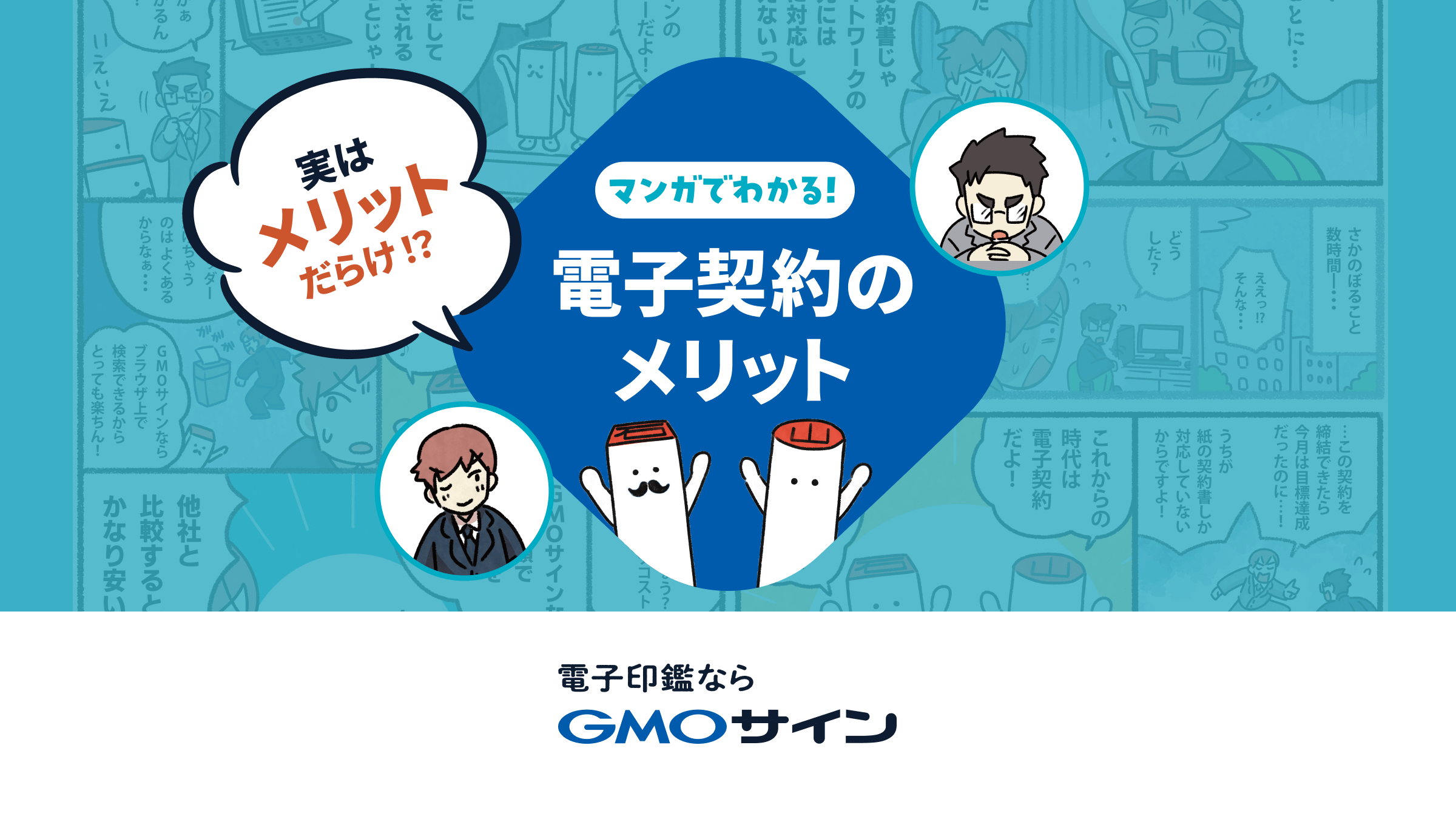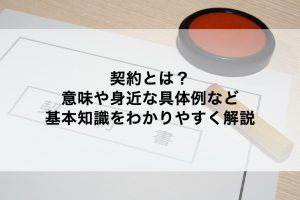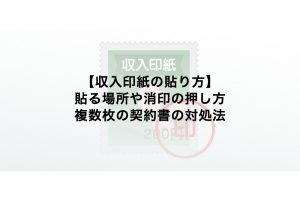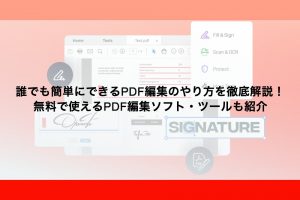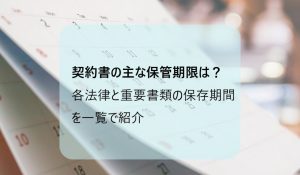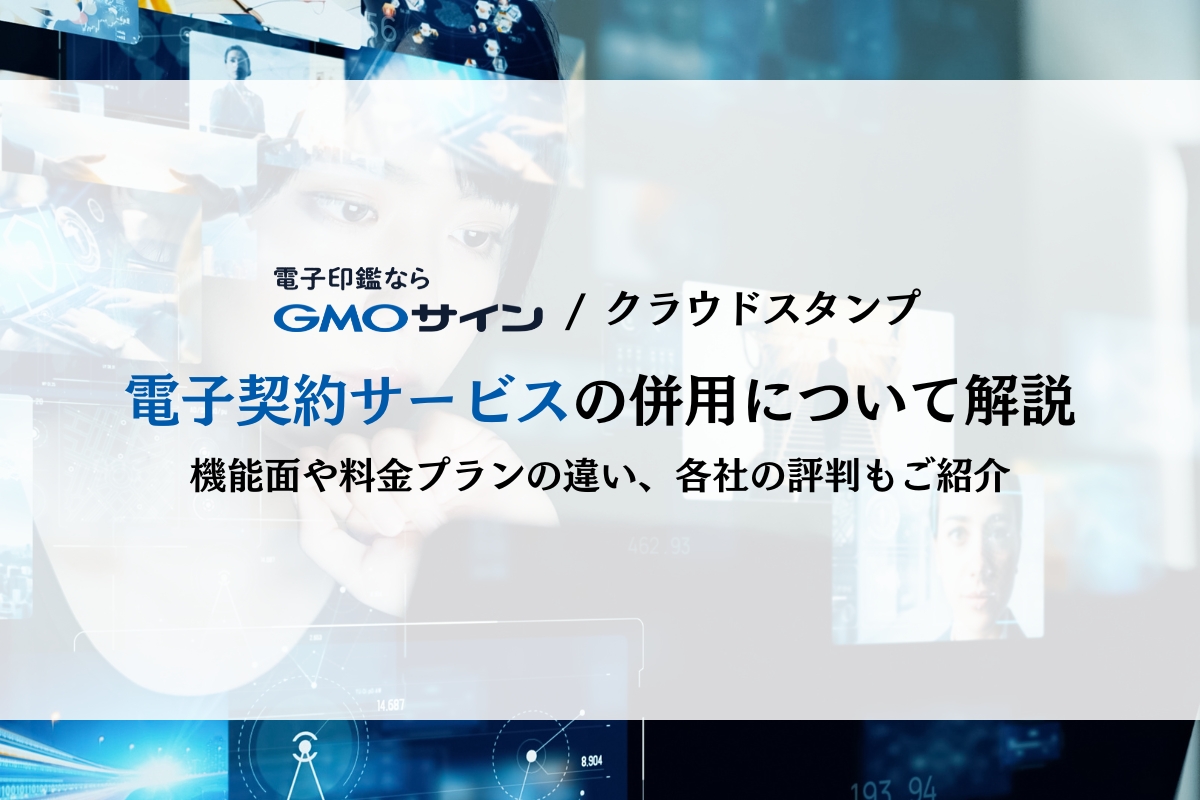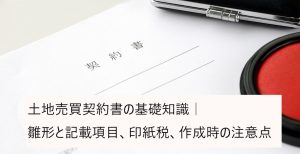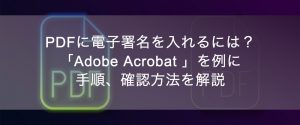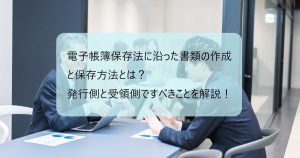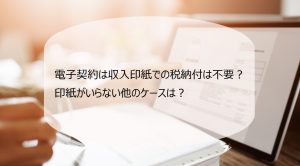仕事上だけでなく、生活を送るうえで「口約束」を交わすことは多いかと思います。ですが「所詮口約束だから」、「契約書があるわけじゃないから」と軽く考えてはいませんか?
実は口約束のルールをよく知っておかないと、後に大きなトラブルに発展することも。そこでこの記事では、口約束での契約に法的な効力はあるのか、また口約束の注意点やトラブルの防止法などを解説していきます。
「口約束の効力について詳しく知りたい」ときは、ぜひ最後までご覧ください。
目次
口約束での契約に法的な効力はある?
まずは、口約束での契約の法的な効力の有無や法的根拠を解説します。
口約束とは?法的な効力はある?
口約束とは、契約書などの書面を用いず、言葉だけの「口頭」で行われる約束のことです。仕事上・私生活における会話や電話でのやり取りによる「決めごと」が、口約束になります。
そして、口約束にも法的な効力はあります。民法において、契約は「当事者の意思表示の合致」があれば、書面がなくても成立すると定めているためです。
「口約束も契約である」ことを忘れず、特に仕事上では不用意な口約束を交わすことは控えましょう。
口約束の効力の法的根拠
「口約束での契約に法的な効力がある」という法的な根拠は、民法の第522条です。
民法第522条(契約の成立と方式)
1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
出典:e-Gov法令検索
つまり契約は、
- 申込みに相手方が承諾すること(当事者の意思表示の合致)で成立する
- 原則として書面を必要としない
ということで、口約束でも効力は発生するのです。
「書面による契約」と「口約束による契約」は、原則として法的な効力に変わりはありません。よくある「契約書がなければ契約は成立しない」という考え方は間違いですので、注意しましょう。
そもそも契約とは?
契約とは、法的には「一方当事者の申込みの意思表示(考えを表すこと)に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為」のことを言います。簡単にいうと「法的な責任が生じる約束」のこと。
当事者の一方からの「申込み」と、相手方の「承諾」という「意思表示の合致」があったときに、契約が成立します。
「契約」については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
口約束はいつまで有効?(口約束の効力の時効)
口約束の効力の時効は「5年間」です。決めたことを5年間行なわない場合には、その約束ごとがなくなります。
5年という期間は、民法で「債権の消滅時効」として以下の通り定められています。
民法第166条(契約の成立と方式)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
出典:e-Gov法令検索
ちなみに、以前は「債権の種類」で時効の期間は違いましたが、2020年4月の民法改正によって、時効期間が5年に統一されました。
口約束による契約の変更と解除
ここでは、口約束による契約の変更と解除について解説します。
当事者同士の合意があれば口頭で変更可能
口約束は「当事者同士の合意」があれば、口頭で変更が可能です。話し合って、お互いが「こう変えよう」と納得すれば、口約束の内容が変更されたことになります。
そもそも口約束はあくまでも「契約」ですから、一方の当事者による勝手な変更は行えません。一方的な変更が行われても、当事者の合意がないため新たな契約は成立せず、元の口約束が有効となります。
口約束による契約の解除
契約の解除とは、その契約を「最初からなかった状態」にすることです。
口約束の場合、契約の解除には大きく次の3つの方法があります。
①法定解除
成立した契約に次のような解除原因があるときに、契約がなかった状態となる。
- 当事者の一方が契約を守らない
- 契約の目的物の種類や数量が契約内容と異なる
②約定解除
契約で定めていた理由が発生したときに、契約がなかった状態となる。
③合意解除
当事者同士の合意で、契約をなかった状態とする。
口約束についての注意点
次に、口約束についての注意点をご紹介します。
【注意点1】口約束では効力を持たない契約がある
契約のなかには、口約束では効力を持たない次のような契約があります。
| ①保証契約 |
債務者が債務を履行しない場合に、代わっての弁済を約束する契約
(民法で「書面による契約」が義務付け) |
| ②定期建物賃貸借契約 |
定めた期間が満了することで、更新されずに確定的に賃貸借が終了する賃貸借契約
(借地借家法で「書面による契約」が義務付け) |
| ③建設工事の請負契約 |
当事者の一方がある仕事を完成し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払う契約
(建設業法で「書面による契約」が義務付け) |
| ④警備業に係る契約 |
警備業者と依頼者との間で交わす契約
(警備業法で「契約締結前」と「契約締結時」の2回、依頼者に対して書面の交付が義務付け) |
| ⑤使用貸借契約 |
当事者の一方が、相手方から受け取った物について使用後に無償で返還する契約 |
| ⑥寄託契約 |
当事者の一方が、相手方のある物を保管する契約 |
上記①~④については法律で「書面の作成」が、⑤~⑥は「物の受け渡し」が必要(要物契約)と定められています。
すべての契約が、口約束で効力をもつわけではないことを知っておきましょう。
【注意点2】口約束ではトラブルが起きやすい
口約束では、その内容を証明するのは「当事者の記憶」のみ。そのため、次のような「言った、言わない」 というトラブルが起きやすくなります。
- 聞き間違いによる契約内容の齟齬
- 勘違いによる契約内容の齟齬
- 口約束の有無(約束した、していない)
当事者だけで解決しないケースでは裁判で争うこともありますが、裁判では「口約束の存在」の証明が必要です。立証できなければ、相手方が悪い場合でも裁判に負けることも有り得ます。
できるだけ次項で解説する方法を実行して、トラブルを防ぐようにしましょう。
口約束のトラブルを防ぐ方法
ここでは、口約束のトラブルを防ぐ方法を解説します。
【トラブル防止法1】契約書を作成して契約内容を証明する
口約束に法的な効力があるとはいえ、トラブル防止の観点からは「契約書を作成して契約内容を証明する」ことが重要です。
契約書を作成することで、例えば次のような取り決めを証明できます。
特に小規模な企業では、「昔からの付き合いだから」と、契約書無しで取り引きすることも多いようですが、これでは「約束どおりに取り引きされない」ことがいつ発生してもおかしくありません。
以前からの慣習であっても、業務上重要なケースや金額が大きい取り引きでは、できるだけ契約書を締結しましょう。
【トラブル防止法2】やりとりの証拠を残す
状況によっては、どうしても契約書を取り交わせないケースも発生します。
契約書を締結できないときは、できるだけ次のような「やりとりの証拠」を残しましょう。
- 話し合いの内容のメモ
- 契約内容についてやり取りしたメール
- 打ち合わせを行った際の議事録
- 口約束をした際の会話の録音
証拠があれば、のちにトラブルになった場合でも、裁判が少しでも有利に進みます。
【トラブル防止法3】不用意な口約束を行わない
不要なトラブルを避けるために、特に業務上においては「不用意な口約束を行わない」ことをおすすめします。
中には「口約束には効力がないだろう」と考え、取引先と不用意な口約束を交わしてトラブルになることも多いようです。さらに現代では、悪い評判はあっという間に拡散され、企業イメージの低下につながることも。
取引先に信頼されるために、もともと遂行するもりがない事柄を、口頭であっても伝えるのはやめておきましょう。
口約束の効力についてのQ&A
最後に、口約束の効力についての疑問にお答えします。
電話での口約束にも法的な効力はある?
電話での口約束にも法的な効力はあります。これは、前述のとおり民法第522条で「書面がなくとも、当事者の意思表示の合致があれば契約が成立する」と規定されているためです。
例えば「ピザのデリバリー」が、電話での口約束にあたります。電話で注文することが民法における“申込み”、ピザ店が注文を受ければ“承諾”として売買契約が成立します。
口約束で法的な効力が発生しているため、注文者がお金を払わなければ「債務不履行」となるわけです。
口約束だけの示談にも効力はある?
口約束だけの示談にも効力はあります。
例えば交通事故を起こして、その場で「私が費用をすべて弁償します」と口約束した場合、当事者同士が合意していれば、この示談にも効力が発生します。その後に「やはり過失割合に応じた支払いを…」と言っても、最初に成立した示談を取り消すことは原則としてできません。
交通事故の現場など、冷静になれない状況で「その場での示談」に応じることはやめましょう。
口約束での婚約にも効力はある?
口約束での婚約にも効力はあります。
判例上でも、「たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納をかわし、もしくは同棲していなくても、相手方は、慰藉料の請求をすることができる。」(最一小判 昭38.9.5民集17巻8号942頁)とあり、「慣習的な儀式や同棲などをせずとも婚約は成立する」としています。
そのため口約束であっても、お互いが本心から「結婚したい」と言えば婚約が成立します。その後に、正当な理由がなく婚約破棄となった場合には、相手に慰謝料を請求できます。
まとめ:口約束でも効力があることを知ってトラブル防止を!
この記事では、口約束での契約に法的な効力はあるのか、また口約束の注意点やトラブルの防止法などを解説しました。口約束でも法的な効力はあり、口約束ならではのトラブルも発生します。
ぜひ記事の内容を参考に、契約書や証拠を残すなどして、口約束でのトラブルを防ぎましょう。