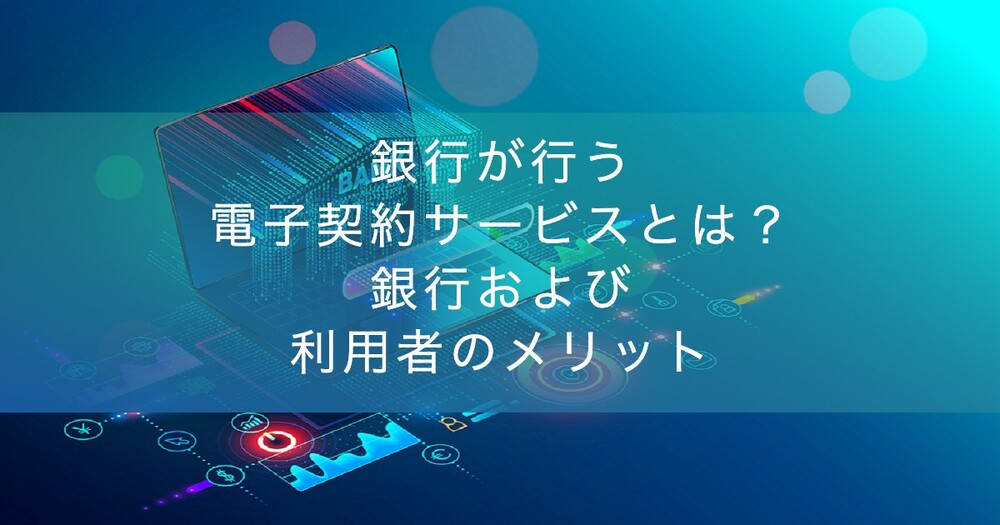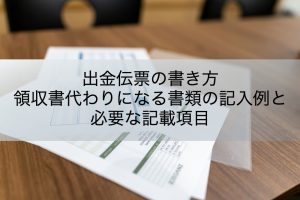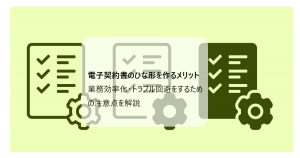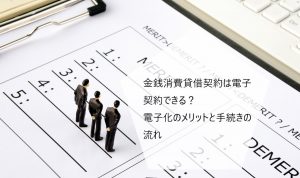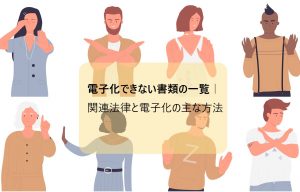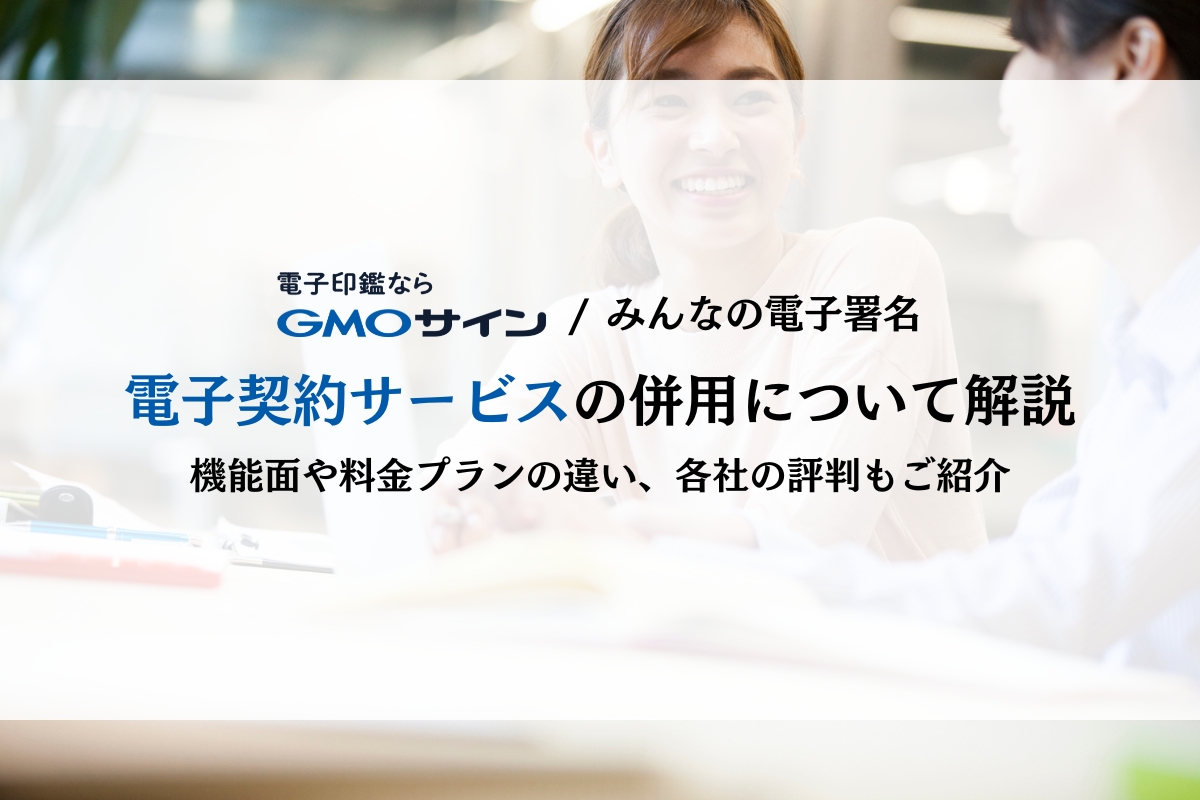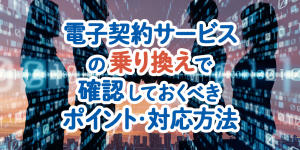デジタル社会の進展によって、契約書もデジタル化が進んでいます。これまで、紙で契約書を作る場合、契約書の印刷、製本、印紙の貼付、押印が必要でした。それを、直接持参あるいは郵送する必要があったので、処理をするのに最低でも1週間程度はかかりました。
しかし、電子契約は、申し込みをして了承を得られれば、すぐに契約を締結できます。融資を受ける場合、審査にはある程度の時間がかかりますが、契約の締結自体は1日どころか数分で完了します。
銀行での取引でも電子契約が導入されはじめており、今後ますます増えていくことが予想されます。そこで、銀行が行う電子契約サービスの状況と利用者のメリットを解説します。
電子契約とは?
電子契約とは、従来の書面契約に代わり、申し込みと承諾をインターネット上で行い、契約内容を紙ではなく、電子署名を施した電子データの形で保存する契約形態です。紙ベースの契約ではないため、印鑑を押印することはできず、電子サインを行うことで申し込みと承諾が行われます。
もともと、契約の成立には書面の作成は必要ないことから、ほとんどの契約は電子契約で締結することが可能です。また、適切な電子サインがなされていれば電子契約も裁判で証拠能力が認められます。
銀行が行う電子契約サービスの概要
電子契約サービスとは、紙の契約書に代わりWeb上またはPDFファイルに電子署名を行うことで契約を締結できるサービスのことです。
対象となる取引は、銀行によって異なりますが、銀行取引約定書、証書貸付、当座貸越、保証などが一般的です。住宅ローンの申し込みをWebで完結できる銀行も少なくありません。
大手銀行はもちろん、地方銀行でも電子契約を導入しているところが増えてきています。電子契約にすることで紙代や印刷代の削減になりますし、印紙代も不要になります。
ただ、電子契約手数料を取る銀行もあるので注意が必要です。電子契約の手数料は、無料の銀行がある一方で、10,000円ほどが必要な銀行もあります。コストを掛けたくないという方は、手数料が無料の銀行を選びましょう。
銀行側の電子契約のメリット
銀行が電子契約を行うことのメリットは、融資などの申し込み手続きを非対面でできる点です。窓口の負担が減ることと、顧客が融資の申し込みがしやすくなることで、融資申し込みの件数が増えることも期待できるでしょう。
また、非対面にすることで、コロナなどの感染症から行員を守れます。さらに、非対面で融資を申し込めることは、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
申し込み内容がデジタル化されるので、手書きに比べ管理がしやすくなり、記入ミスなども減ることも期待できます。
利用者側の電子契約のメリット
利用者側の電子契約のメリットは、融資などを気軽に申し込める点です。融資の申し込みをするということは、審査を受けるということで、窓口に行くのは緊張するものです。しかし、電子契約であれば非対面で融資の申し込みができることになるため、窓口に出向く必要はありません。
また、コロナ禍では、多くの人が集まる銀行には行きたくないという利用者も多いと思います。非対面で融資の申し込みができることは、利用者の安全面でもメリットがあります。手書きの負担が減ることも、利用者のメリットでしょう。
利用者が銀行の電子契約サービスを利用するまでの流れ
電子契約サービスを利用するまでの流れは、銀行により異なりますが、おおむね次のような流れで行われるのが一般的です。
①申込書の記入
電子契約のための所定の申込書に必要事項を記入し、取引をする銀行の担当者に提出します。この時、本人確認書類の提示が必要になります。
②ユーザー登録
IDや仮パスワードが銀行から発行されるので、利用者は、専用のURLにアクセスして、ユーザー登録をします。
③電子証明書の発行
次に、電子契約用PINコードが発行されます。IDとパスワードでログインし、電子契約用PINコードを入力することで、署名手続きが完了します。
④サービスの実行
融資の申し込みの場合、電子契約が署名により締結すれば、融資が実行されます。
これからますます増えていく電子契約の導入を検討してみては?
銀行が行う電子契約について見てきました。これまで、銀行から融資を受ける場合、相談、融資の申し込み、面談、契約書の提出と何度も銀行に足を運ばなければなりませんでした。
それが、電子契約の導入によって、Webから融資を申し込み、非対面で契約締結まで完結できるようになりました。特にコロナ禍ということもあって、電子契約は無くてはならないものになりつつあります。
これからの時代、銀行に限らず電子契約は増えていくことは間違いありません。銀行への融資申し込み以外の取引についても電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
「電子印鑑GMOサイン」は、導入企業数260万社の実績があります。気軽にできる契約印タイプ(立会人型)と電⼦認証局によって本人性が担保された実印タイプ(当事者型)を選択でき、契約の内容に応じて使い分けることができます。高いセキュリティ体制も整っているので安心して利用できるでしょう。
詳しくはこちら