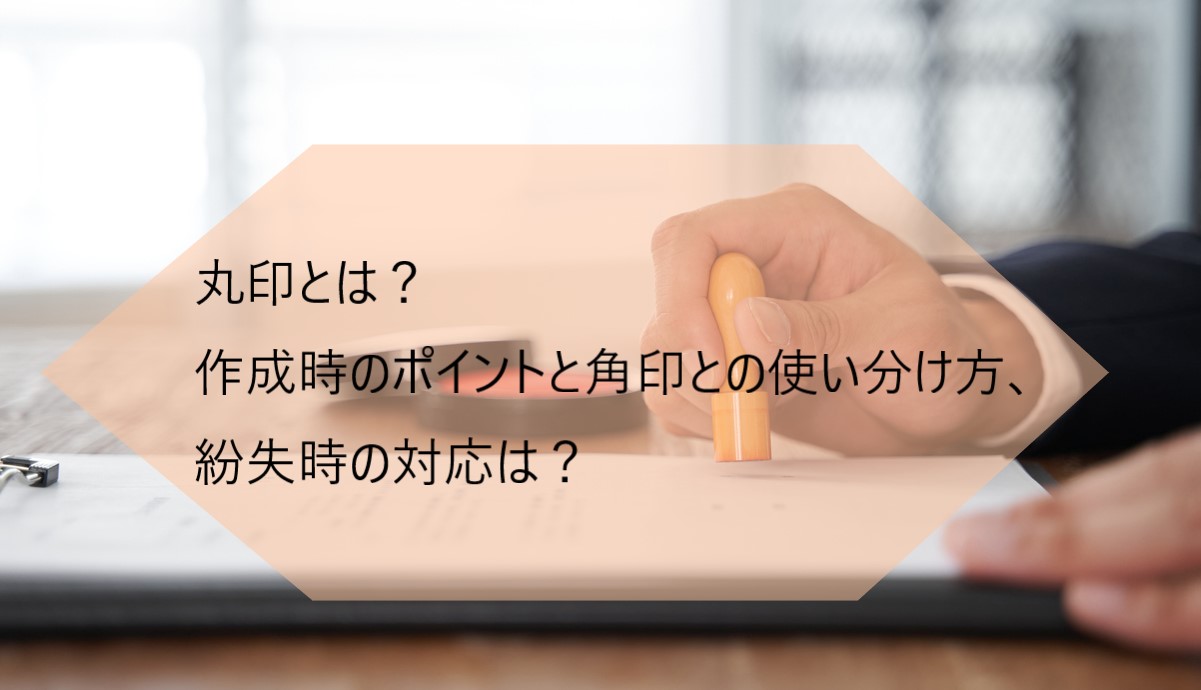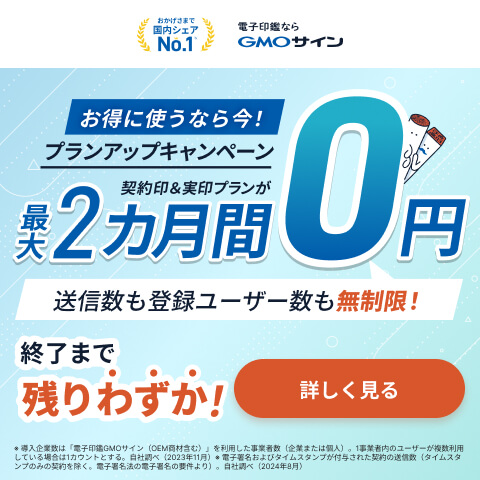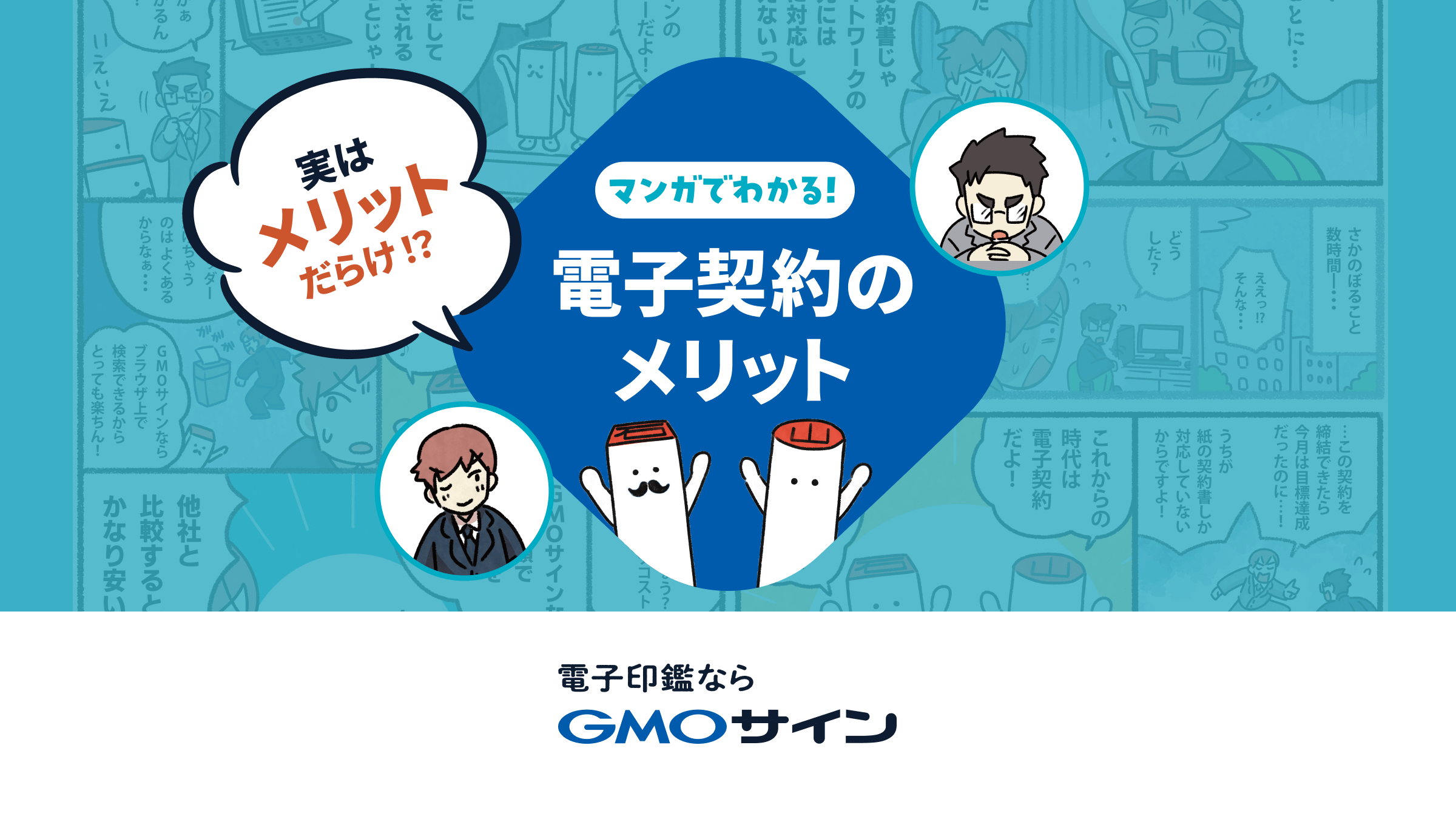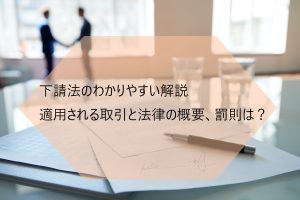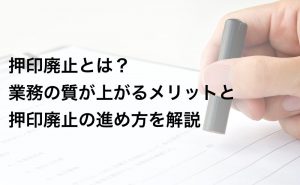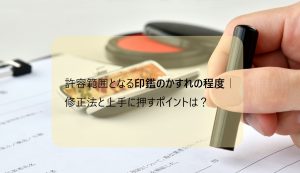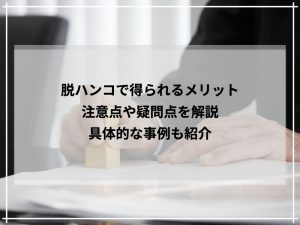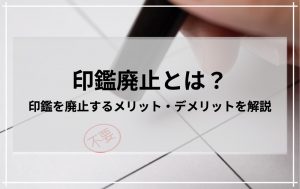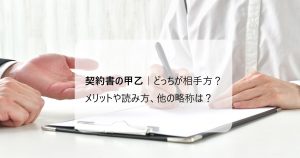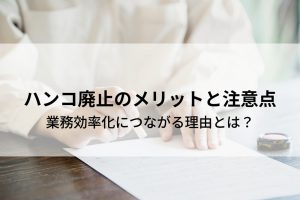「丸印ってなんだろう?」「作り方は普通の印鑑と同じ?」などの疑問を抱いていませんか?
本記事では、丸印について重要な点を知りたい方向けに、概要や作成時のポイントなどを解説しています。最後まで読むことで紛失時の対応や電子印鑑への対応方法への理解も深まります。
角印との使い分け方も解説しているため、角印との違いに悩んでいる方は、参考にしてみてください。
目次
丸印(代表社印・会社実印)とは?
丸印とは、会社を設立時に法人登記する際、市役所や区役所へ登録する印鑑のことです。印鑑登録証明書に用いられる印鑑であり、会社を代表する印鑑になります。
会社の意思表示を示す印鑑であるため、契約の締結や行政への提出書類など、企業間取引や行政との間で使用されるケースが多いです。丸印の持つ責任は重いことから、社長や部長など経営陣が保管・使用することが大半です。
丸印と合わせて使われる印鑑に角印がありますが、役割や用途、刻印内容など、異なる点がいくつもあります。書類や取引の内容に適した印鑑を使用するためにも、丸印と角印の違いを押さえておきましょう。
丸印と角印の違い、使い分け方は?
丸印と角印の大きな違いは、次の表のとおりです。
| |
丸印 |
角印 |
| 役割 |
契約の締結や買収など、会社の意思表示を示す役割 |
確認の意思を示す法人の認印の役割 |
| 別名 |
代表社印、会社実印 |
会社印、社印 |
| 用途 |
契約書、行政への申請書類など |
見積書、請求書など |
| 形状 |
丸い |
四角い |
| サイズの規定の有無 |
規定あり |
規定なし |
| サイズ |
10mm〜30mmを超えない正方形におさまるサイズ |
一般的に20mm~30mm程度のサイズ |
| 印面の内容 |
二重の円で以下の刻印が一般的
外側の円は、法人名
内側の円は、役職名と法人名
|
法人名 |
| 法務局への登録の要否 |
必要 |
不要 |
丸印の用途は限定的で企業間の契約書への押印や官公庁への入札といった、重要なケースに用いられることが一般的です。法務局への登録が必要な印鑑であり、印鑑のサイズは法律で定められています。
【参考】商業登記規則第9条3項目
一方で、角印に関しては、見積書や請求書、領収書など自社で作成する書類に用いられることが一般的です。認印の役割として角印を使用している企業が多く、法務局への登録は必要ありません。丸印のようにサイズに決められたルールはありませんが、20mm〜30mmのサイズが広く普及しています。
丸印の正しい押し方・位置
丸印を押す位置は、氏名や法人名に被らないような空白なスペースです。文字に被らないよう押印するのは、印鑑登録証明書に登録されている印影と照らし合わせるためです。
契約書や法的手続きなど重要な場面では、なりすましや改ざんを防止するため、印鑑登録証明との照合が行われます。丸印は代表者の意思決定を示す役割があるため、セキュリティの観点から、文字と被らないような位置に押印します。
一方で角印の場合は、印鑑登録証明書を発行できないため、社の印の真上や法人名に被るよう押印します。書類の改ざんや印影の複製などを防止するためです。第三者が照合するための証明がないため、文字に被せて押印します。
丸印を作成する際のポイント
丸印を作成する際、次の5つのポイントがあります。
サイズにあっては、法律(商業登記規則第9条3項目)で定められています。ルール化されている項目もあるため、作成の前に必ず確認しておきましょう。
書体(文字)
代表的な書体は、次の3つです。
- 吉相体(きっそうたい)
- 篆書体(てんしょたい)
- 古印体(こいんたい)
それぞれの書体には、次のような特徴があります。
| 書体 |
吉相体
(きっそうたい) |
篆書体
(てんしょたい) |
古印体
(こいんたい) |
| 読みやすさ |
× |
〇 |
◎ |
悪用リスク
(改ざん・複製など) |
低 |
中 |
高 |
| 特長 |
ほとんど読めないため、改ざんや複製のリスクは低い |
ある程度文字を読めるため、吉相体に比べ悪用されるリスクは増す |
読みやすい反面、他の書体に比べ悪用されるリスクは増す |
書体の特徴を考慮したうえで、書体を選ぶ ことをおすすめします。
サイズ
丸印のサイズは、商業登記規則で次のように定められています。
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
引用:商業登記規則第9条3項目
丸印を作成時は、10mm〜30mmの正方形に収まるサイズかどうかを必ず確認しましょう。
規定を満たさない丸印は、効力が無く認められない可能性があります。
電子契約サービスを利用する流れで丸印を電子印鑑で作成する際は、十分注意しましょう。
形状
丸印の形状は、主に次の2種類があります。
それぞれの形状には、次の特徴があります。
| 形状 |
天丸タイプ |
寸胴タイプ |
| 特徴 |
・持ちやすく押印しやすい加工がされている
・印面を保護する保護キャップがある |
何も加工されていない一般的な形状 |
| 価格 |
比較的高い(天丸>寸胴) |
比較的安い |
| 価格が違う理由 |
加工に手間がかかる |
加工がない |
天丸タイプは、持ち手が握りやすい形に加工され、印面の向きが真上にくるよう目印が付いています。付属品として印面を保護する保護キャップがあり、使いやすさや耐久性を求める方に適している印鑑です。
寸胴タイプは、一般的な印鑑の形状で何も加工されていません。加工がないため天丸タイプより価格が安く、印鑑にこだわりを持たない方に向いています。
印影(刻印内容)
丸印の印影は、法人名と役職名を刻印するのが一般的で、二重の円の外側と内側に刻印します。法人と個人事業主で刻印内容が異なるため、次の表を参考にしてください。
| |
法人 |
個人事業主 |
| 刻印の内容 |
法人名+役職名 |
屋号+役職名 |
| 外側の円の刻印例 |
株式会社〇〇 |
屋号 |
| 内側の円の刻印例 |
代表取締役印 |
代表者印 |
素材
丸印は、長期的に使用される印鑑です。個人の認印のように、紛失や破損したら直ぐに買い替えられる印鑑ではありません。そのため、作成時には次の2つのポイントを押さえる必要があります。
・落とした衝撃に耐えられる素材か?
・長期的に使用しても劣化しない素材か?
素材の代表的な例として、チタンや黒水牛が挙げられます。長期的に使用できるため、多くの方に選ばれている素材です。
丸印に関するよくある疑問
丸印に関して、次のような疑問を抱いていませんか?
- どうやって保管すればよいの?
- 紛失した場合はどう行動すればよいの?
- 電子契約にはどうやって使うの?
これらの疑問は、丸印を使用するうえで大切です。第三者に悪用されるリスクを抑えるために、よくある疑問について解説します。
適切な管理方法は?
法人の場合は、社長や部長など上職の限られた人が保持・保管することが一般的です。盗難防止として、ロック付きの引き出しに保管する、保管場所に南京錠をかけるなどが対策として考えられます。
個人で丸印と印鑑登録証明書を合わせて管理している場合は、別々に保管するのが望ましいです。両方とも盗難されると、盗難者に悪用される可能性が高まるためです。身分証明を提示できる書類やカードと一緒に管理することも、可能な限り避けましょう。
紛失したらどうする?

丸印を紛失した場合は、すぐに管轄の法務局(登記所)へ届け出ます。法務局へ届け出ることで、紛失した丸印の効力を 失わせることができます。失効となれば悪用されるリスクがないため、被害を抑えられます。
法務局へ届け出る際、次の書類が必要です。
- 代表者個人の実印
- 代表者個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 公的な身分証明書
印鑑証明書を発行する際、印鑑登録カード(印鑑登録証)が必要になるため、予め用意しておくと円滑に対応できます。
丸印と角印を兼用できる?
丸印と角印の兼用はできません。角印は印鑑登録証明書の発行ができないため、契約の締結時に印鑑登録証明書の提出を求められても対応できないためです。
丸印だけを作成し、角印の役割を担わせることは可能ですが、印影が複製されるリスクが高まります。領収書や請求書など、社内で発行する全ての書類も丸印だけで処理するのは、セキュリティ面で望ましくありません。
電子化した書類にはどう対応する?
電子証明書を発行できる電子印鑑を活用することで、丸印と同様に、契約書や合意書など企業間取引で重要な書類に対応できます。
電子証明書を発行できるかが重要なポイントになるため、電子印鑑を作成する時は、電子証明書の発行の有無を確認しておきましょう。
まとめ:丸印は重要書類に押印する印鑑
本記事では、丸印の役割や作成のポイントなど、丸印に関わる情報を解説してきました。改めて重要な点を振り返りましょう。
- 丸印は会社を代表する印鑑であり、個人の実印と同様に使用には社会的責任を伴う
- 企業間取引や行政手続きなど、重要な書類に用いられる
- 丸印を押印する位置は、文字と被らない空白のスペースにする
数多くある印鑑の1つにすぎませんが、会社の意思表示を表すツールであるため、使用用途や保管の際は十分注意が必要です。紛失や盗難により第三者に使用されるリスクを回避したい方は、丸印と同程度の効力を持つ電子印鑑を作成することをおすすめします。
書類の電子化が主流になりつつあり、見積書や請求書、契約書まで電子契約ツールを使って対応する企業が増えています。電子契約ツールを導入すると、ハンコの用意や紙を印刷する作業が不要になり、業務を効率化できます。
数ある電子契約サービスのなかでも、特に電子印鑑GMOサインがおすすめです。官公庁や大手企業の多くがGMOサインを使用しており、セキュリティ精度や利便性に高い信頼性があります。電子契約サービスの利用が初めての方は、まずお試しフリープランから取り組むことがおすすめです。
「電子印鑑GMOサイン」サービスサイト