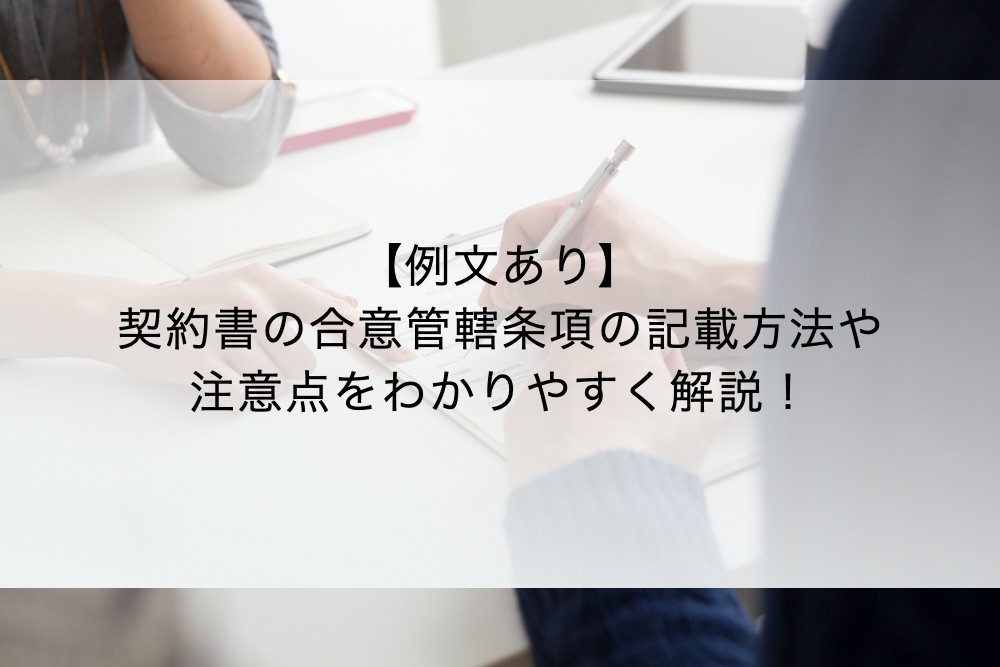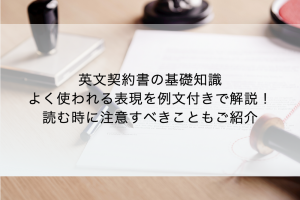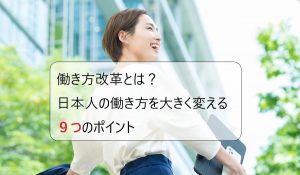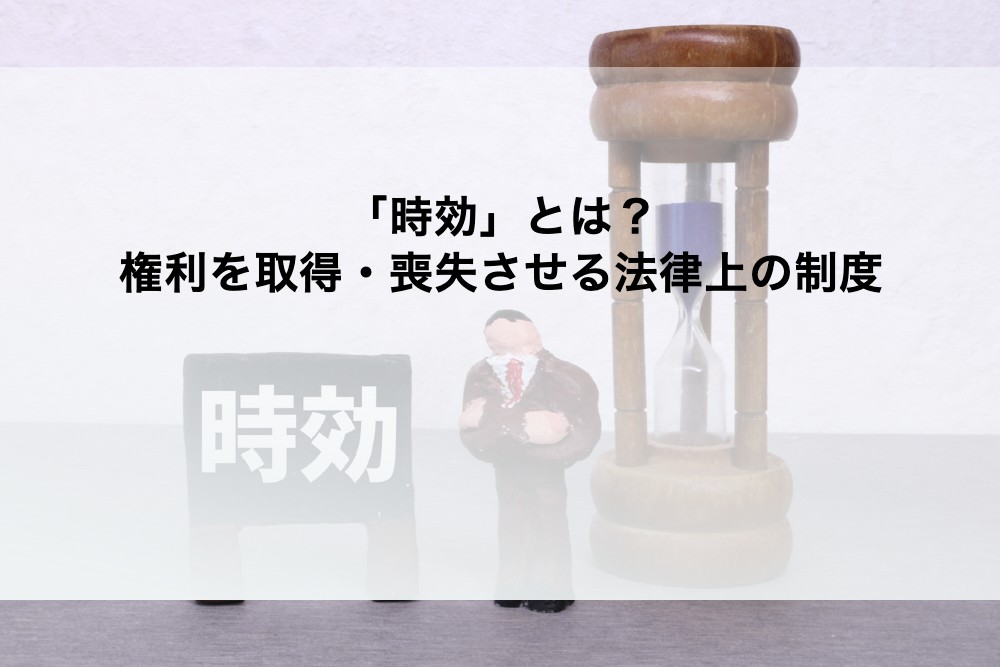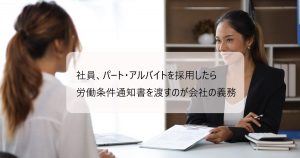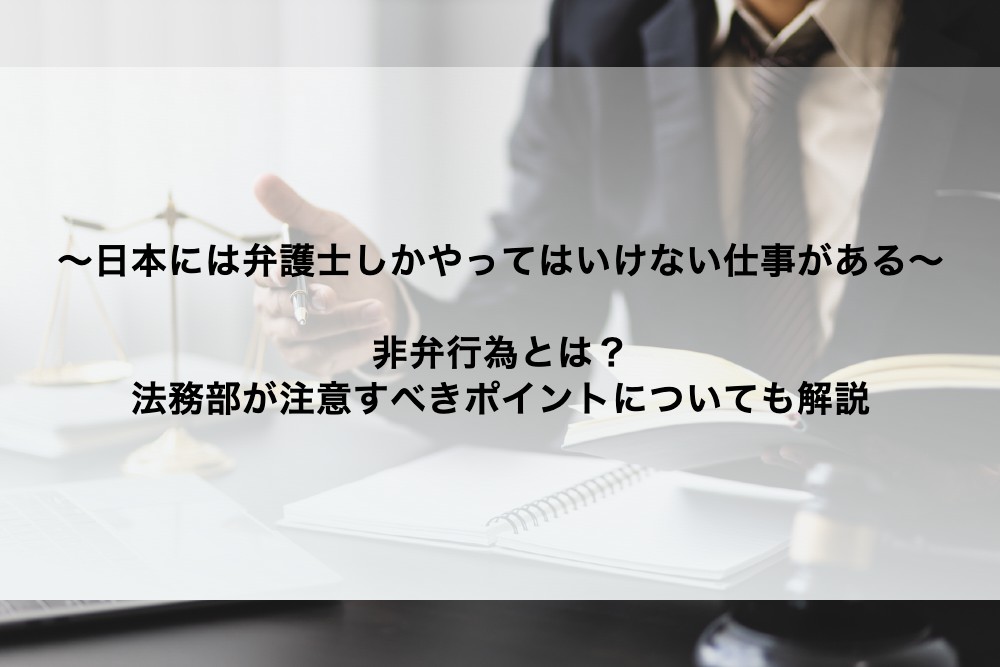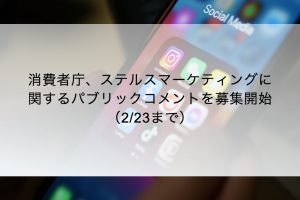契約書の後ろのほうでよく見かける合意管轄(ごういかんかつ)の条項について、きちんと理解していますか?
合意管轄は、契約の相手方と裁判を行うことになった際の費用や手間に影響し、場合によっては自社に高額な出費や業務負荷を発生させることになります。
今回は、合意管轄の意味とその重要性について説明するとともに、実際に契約案を作成する際の注意点についても説明します。
目次
合意管轄とは?
合意管轄とは何かを説明する前に、まず「管轄」についてご説明します。
(例)第XX条(合意管轄)
「本契約に関連して甲乙間に生じた一切の訴訟については、○○裁判所のみを専属的合意管轄裁判所とする。」
管轄とは、裁判(事件)をどの裁判所で処理するかを決める基準のことをいいます。管轄にはさまざまな種類がありますが、具体的なものとして、第一審の訴訟を地方裁判所と簡易裁判所のどちらで行うかの定めや、地方裁判所の中でもどこの地方裁判所で訴訟を行うかの定めが挙げられます。
法律では、裁判(事件)の性質や各裁判所の役割だけでなく、当事者間の公平や便宜を考慮して各裁判所に配分する原則を定めていますが(法定管轄)、契約に関する訴訟のような民事訴訟においては当事者間の合意によってどこの裁判所で訴訟を行うかを決めることも認められています。これが、合意管轄です。
民事訴訟法第11条
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
契約書内で合意管轄を定める重要性
では、当事者間で管轄裁判所を決め、その旨を契約書に記載することが、実際の契約にどのように影響するのでしょうか。
特に当事者間の所在地が離れている場合に、管轄裁判所を定めておくことが極めて重要です。なぜなら、合意管轄条項を契約で定めない場合、自社が無駄な出費や手間を負う場合が想定されるからです。
たとえば、東京都に本社を置く契約の相手方企業が、鹿児島県に本社を置く自社に対して、契約不履行を理由に訴えを起こしたとします。契約に合意管轄に関する定めがないと、相手方企業は自らの本社が近い東京地方裁判所で裁判を起こすことができます。
東京地方裁判所で裁判となると、自社の代表者や証人、訴訟代理人となる弁護士が鹿児島県から東京都まで出向くことになりますが、弁護士費用だけでなく往復の交通費や宿泊費などの費用も発生することになります。また、裁判が始まると1~2カ月に1回程度は裁判所に出頭することになります。さらに場合によっては訴訟が終結するまで1~2年かかることもあります。裁判にかかる費用の方が請求額よりも高くなってしまう場合には、自社は請求を断念することも検討することになりかねません。
つまり、合意管轄はただ定めるだけでなく、自社に有利な合意管轄を定めることが重要となります。そうすれば、裁判にかかる出費と労力を最小限に抑えることができ、請求額が少額であっても訴えやすくなるでしょう。契約の案は、なるべく自社で作成し先方に自社から渡すことが望ましいと言われるのもこういったメリットがあるからです。
合意管轄条項の記載方法と注意点
では、具体的な契約案作成の場面で、どのように合意管轄条項を記載すればよいでしょうか。ここでは合意管轄条項の記載のポイントを説明します。
専属的合意管轄にする
契約書に合意管轄条項を記載する際、「専属的合意管轄」であることを明記しましょう。専属的合意管轄とは、管轄裁判所を一つに限定し、その他の裁判所に提訴することを認めないとするものです。ちなみに「付加的合意管轄」というものもあります。これは、合意管轄条項で記載した裁判所に加えて、民事訴訟法に基づいて決められる裁判所への提訴も認めるという定めです。東京地方裁判所で裁判を行うことを契約の当事者間で合意した場合は「東京地方裁判所のみを専属的合意管轄裁判所とする」と記載しましょう。
合意管轄条項で指定できるのは第一審のみ
民事訴訟法第11条1項は、「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」としています。第一審に不服がある場合、当事者は控訴して第二審を行い、それにも不服がある場合、上告して第三審まで行うことができますが、当事者同士で合意して裁判地を決めることができるのは、初めに提訴したときの第一審のみであることに注意しましょう。第二審は第一審の、第三審は第二審の上級裁判所で行われるため、第一審をどこの裁判所で行うかが重要となります。
合意管轄条項の対象を明記する
民事訴訟法第11条第2項は、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」(第3項で電磁的記録も認められています)としています。「前項の合意」とは、当事者間で行った合意管轄のことをいい、「一定の法律関係」とはどのようなトラブルが発生したときに合意管轄条項を適用するかを明記する必要があります。
というのも、「調停」が起こされた場合には、「訴訟」についての合意管轄条項を記載していても、合意管轄条項が適用されないとした判例があるからです(調停は勝ち負けと決めるものではなく、和解の成立に向けたお互いの話し合いの制度であり、訴訟とは異なる別の制度です。)
トラブルが起こってから訴訟と調停のどちらにするかを決めることもあるので、そのどちらでも合意管轄条項が適用できるように「本契約に関する一切の紛争(調停による裁判手続きを含む)は、XX裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。」と記載することも可能です。
合意管轄の裁判所を記載する
合意管轄として定める裁判所を記載しましょう。合意管轄条項の「XX裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする」という文言の「XX裁判所」の部分です。この条項のうちでどの場所にするかを決める、最も重要な部分です。簡易裁判所と地方裁判所のどちらにするのか、どこにある裁判所なのか、明確にしたうえで記載しましょう。
なお、裁判期日に裁判所に出廷するのは、当事者ではなく訴訟代理人である弁護士である場合がほとんどです。もし会社の所在地と弁護士・弁護士事務所の所在地が都道府県をまたいで離れているような場合は、誰にとって利便性が高い裁判所を合意管轄に設定するかも検討しましょう。
合意管轄の記載例
契約の条項は、基本的に自社に有利であることが理想です。以下、自社の本社が東京都にあるケースでいくつか記載例をご紹介します。
例①
第XX条 合意管轄
甲及び乙は、本契約における一切の紛争(調停による裁判手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
つぎに、自社の本社を移転する予定がある場合には、訴訟提起時の本社の所在地の近くで訴訟を行えるよう、以下のように規定しましょう。
例②
第XX条 合意管轄
甲及び乙は、本契約における一切の紛争(調停による裁判手続きを含む)は、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とすることに合意する
自社が契約相手から業務を受託する側で契約を交わす上で相手よりも弱い立場にある場合、自社に有利な合意管轄条項は、相手方の了承を得られない可能性があります。そこで、契約相手との公平性を図るために、訴えた側(原告)が訴えられた側(被告)の裁判所に出向くと定めることもできます。
例③
第XX条 合意管轄
甲及び乙は、本契約における一切の紛争(調停による裁判手続きを含む)は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属的合意管轄とすることに合意する。
また、以上の例は地方裁判所に限定して合意管轄裁判所を規定していますが、地方裁判所だけでなく、簡易裁判所においても訴訟を提起することが可能です。民事事件において、地方裁判所が第一審を包括的に担当するのに対し、簡易裁判所は、請求額が少額で一定金額以下である軽微な訴訟を担当する裁判所です。請求額によっては簡易裁判所を合意管轄とするのも良いでしょう。
例④
第XX条 合意管轄
甲及び乙は、本契約における一切の紛争(調停による裁判手続きを含む)は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
合意管轄について理解し、自社に有利な契約の締結を心がけましょう。
以上、契約における合意管轄条項についてご説明しました。
合意管轄をきちんと理解し、自社に有利になるように合意管轄条項を契約書に記載すれば、万一裁判になったときにも自社のコストを抑えることができるでしょう。また、可能な限り契約案を自社で作成し、相手方に自社から渡すようにして契約交渉自体をうまく進めていくことを心がけましょう。
なお、民事訴訟法第11条第3項には、電磁的記録(電子ファイル)を用いた契約(電子契約)についても書面と同じ法的効力を持つことが書かれています。
最近ではリモートワークを行う企業が増え、電子契約を導入する企業も増えています。電子契約で契約を行うと、パソコン上で契約データを送信するので郵送を行う必要がなく、相手に届くまでのタイムラグもありません。また、電子契約は書面でないので印紙税もかからず保管用の書棚も不要です。電子契約を利用すればさらなる費用や業務時間の削減が見込めるでしょう。
「電子印鑑GMOサイン」は、法的効力を持つ電子契約が可能なクラウドサービスで当事者型(実印タイプ)と立会人型(契約印タイプ)の2タイプを使うことができます。電子契約も併せて検討してみてください。
\ 月に5件まで電子契約を無料で利用可能 /