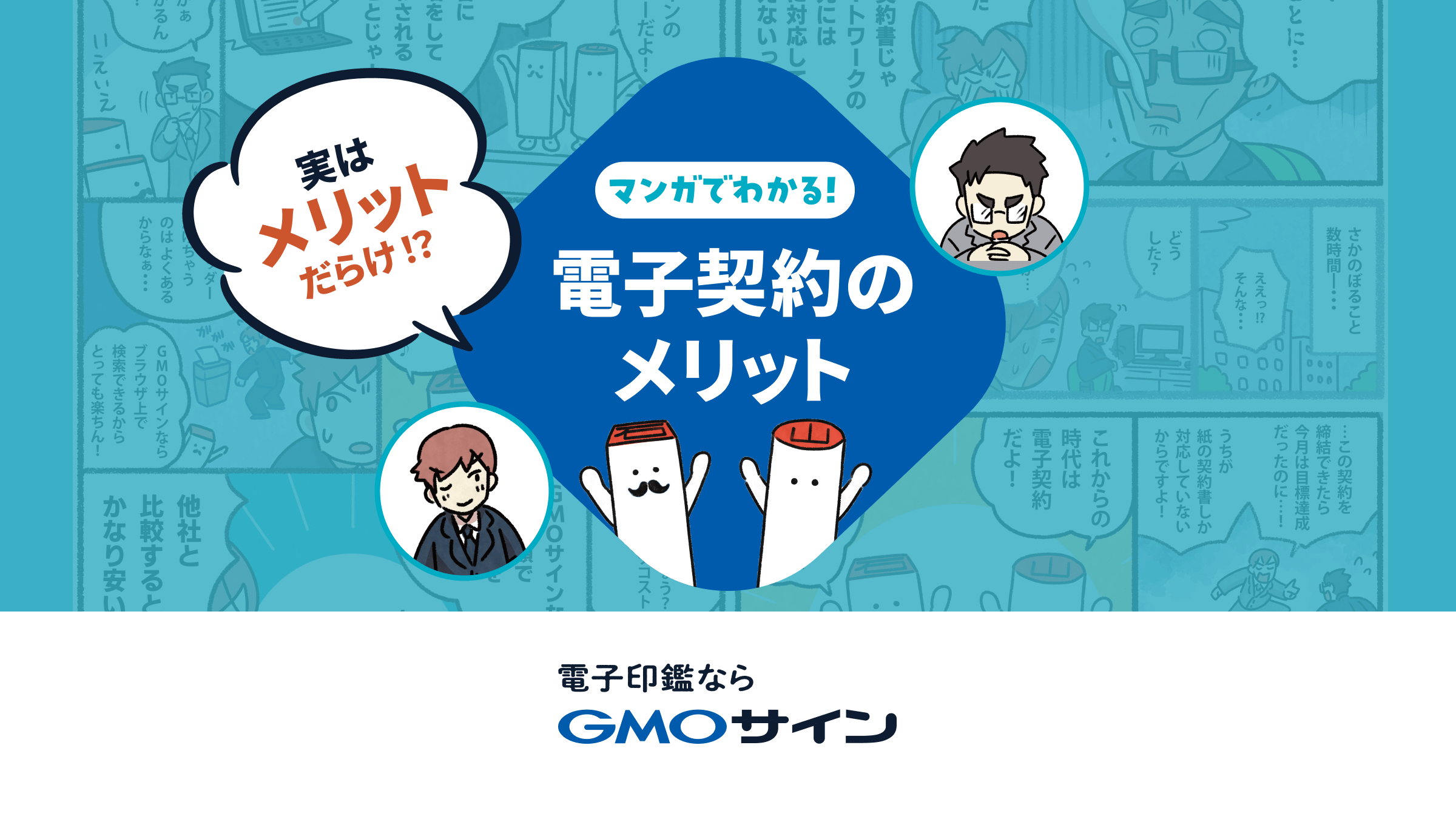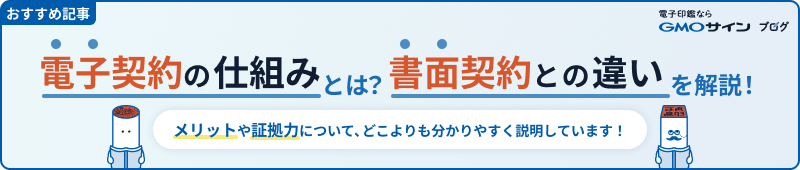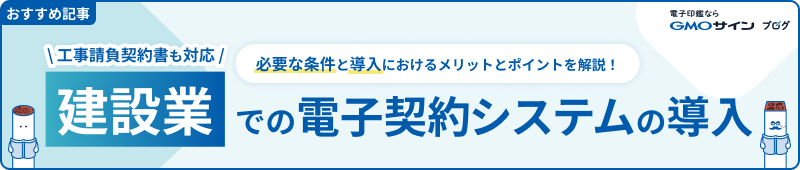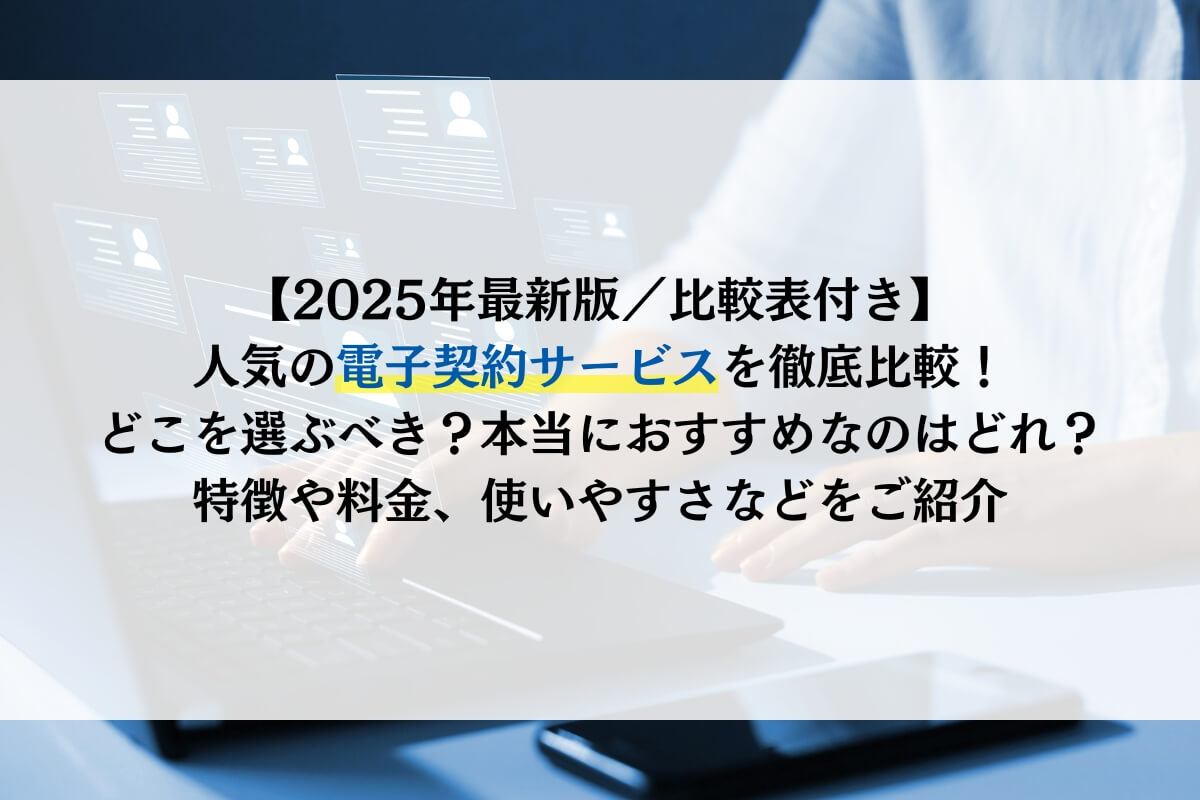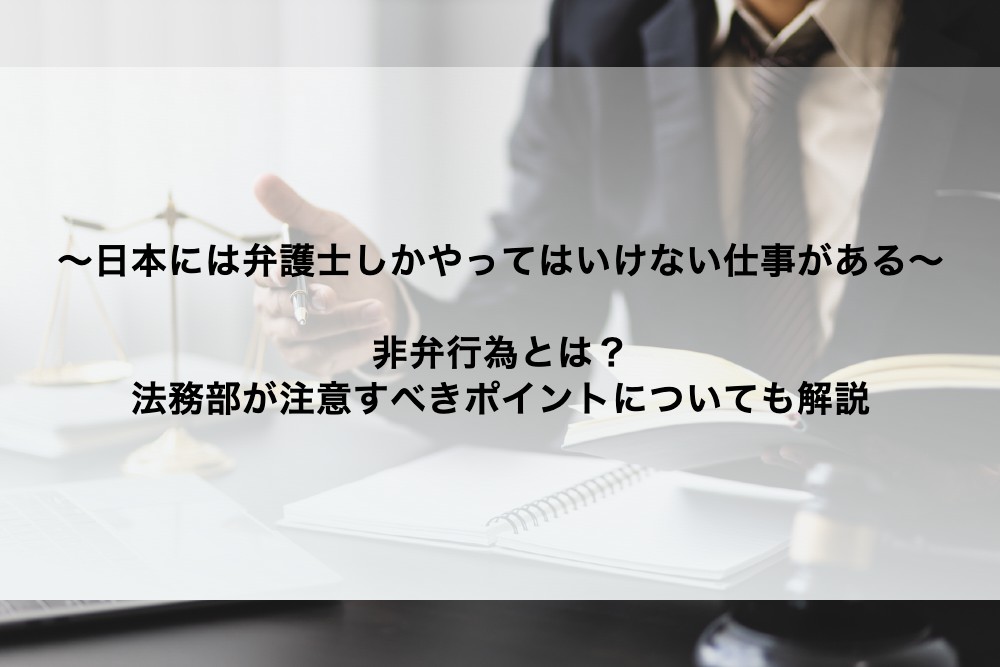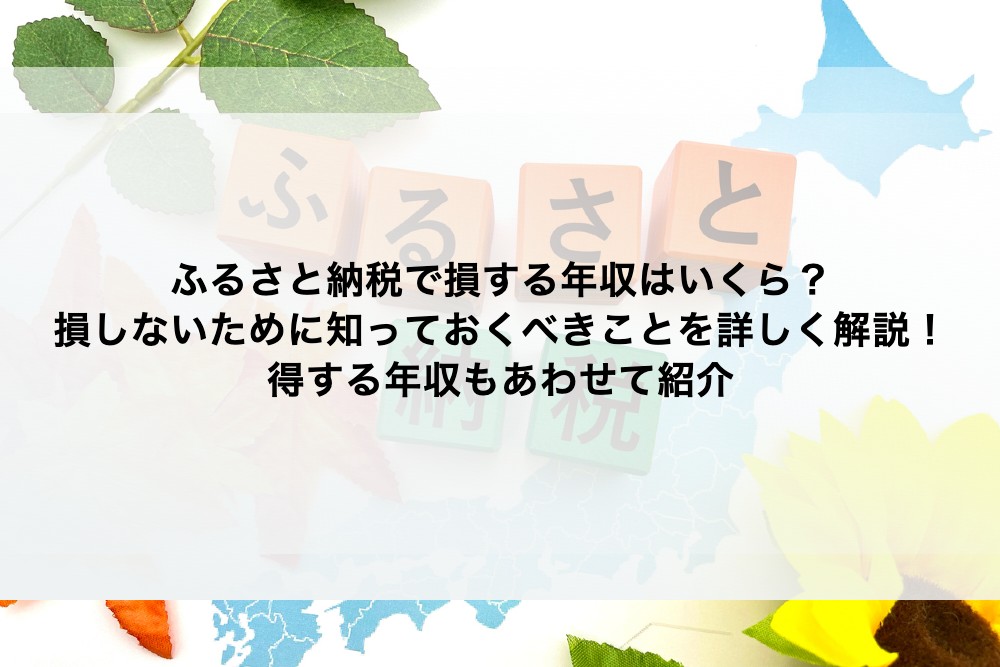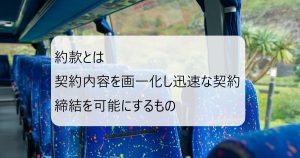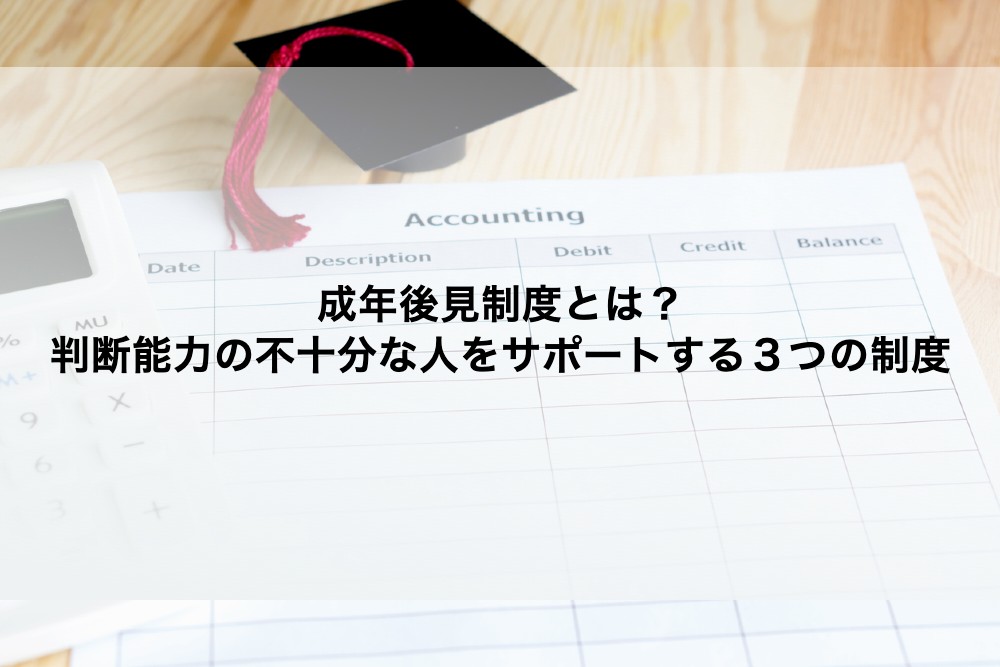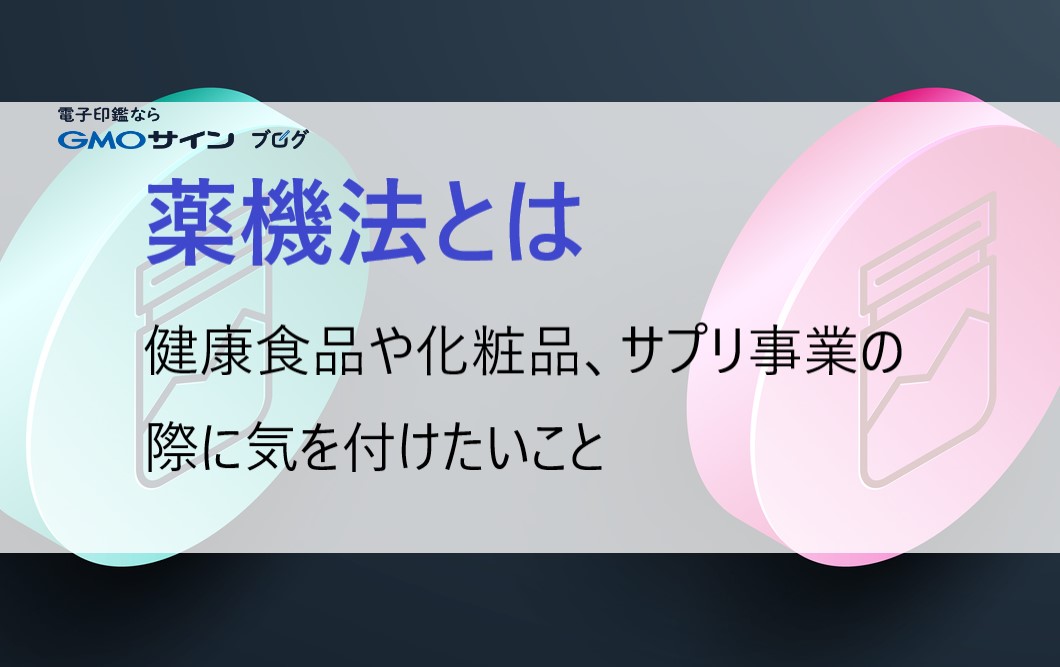「時効」という言葉を聞くと、刑事ドラマなどで犯人の罪を問えなくなる期限のことをイメージする方も多いのではないでしょうか?
ある犯罪に関して時効が成立すると、真犯人が判明したとしても法律上の罪を問うことができなくなってしまうということは、皆さんもご存じのことでしょう。しかし、法律上における「時効」は、上記のような刑事事件に関するものだけではありません。
民事上の法律問題(権利の消滅や取得など)に関しても時効が存在するのです。民法上の時効が成立した場合には、その対象となる権利を取得したり、持っていた権利を失ったりするなど法律上の効果が発生します。
今回は、この「時効」について、特に民法上の時効制度に焦点を当てて解説いたします。
目次
時効とは
時効とは、長期間継続している事実状態を尊重し、事実状態に即した権利関係を確定することで、事実状態を法的に保護することを目的としています。「時効」と聞くと刑事ドラマのようなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、時効制度は、刑事上だけでなく民事上でも定められています。
刑事上、時効が成立した場合には、その犯罪を行った人間(犯人)は刑罰を逃れることになります。これに対して、民事上で時効が成立した場合には、その対象となる権利などを取得したり喪失したりするという法律上の効果が発生することになります。なお、民法上の時効制度は、2020年に行われた大改正の際に大幅に変更されたので注意が必要です。
時効制度の目的
法律で時効という制度が定められているのはなぜでしょうか?
刑法上の時効・民法上の時効ともに、長い時間が経過することによって証拠が散逸してしまい事実関係等の立証が困難になることが大きな理由の一つとされています。
他方、刑法においては処罰すべき必要性が希薄であり、民法においては永続化している現状を保護する必要があることに意義があるとされています。
時効の種類|刑事上の時効と民事上の時効
上記のとおり、一般的にはひとくちに「時効」と言いますが、厳密には「刑事上の時効」と「民事上の時効」の2種類に分類することができます。
それぞれについて順次、見ていくことにしましょう。
刑事上の時効|「公訴時効」と「刑の時効」
現在、殺人罪など重大な犯罪に関しては時効が撤廃されており、犯行時からいくら時間が経過しようとも時効は完成せず、犯人を逮捕し裁判にかけることが可能となっています。
しかし、それ以外の(比較的軽微な)犯罪に関しては、刑法上も時効が定められています。そのため、その犯罪ごとに定められている時効期間内に犯人が逮捕されることなく経過した場合には、法律上その罪を問われることがなくなるのです。
刑事上の時効に関しては、さらに「公訴時効」と「刑の時効」という2つの制度が定められています。
(1)「公訴時効」とは
「公訴」とは、犯罪者を裁判にかけて、それ相当の刑罰を科すために検察官が裁判を起こす(提起する)ことを言います(「起訴」とも言います)。日本において公訴は検察官にのみ認められた権利であり、これを「公訴権」といいます。
犯罪が行われたにもかかわらず公訴が行われないまま一定の期間が経過した場合、一定の犯罪に関しては公訴時効が成立し、国は犯罪者を処罰する権限を失います。つまり、裁判を起こすこと自体ができなくなります。捜査や起訴にはタイムリミットがあるということです。
公訴時効が設けられている理由としては、時の経過によって、証拠が散逸したり目撃者の記憶もあいまいになったりすること、事件によっては犯人への処罰感情も薄れるものもあることなどが挙げられています。
公訴時効の期間は犯罪の種類によって異なりますが、現在の法律では最長で30年です。ただし、殺人罪のように人を死亡させた罪で、法定刑の最高が死刑に当たるものについて公訴時効は刑事訴訟法の改正(2010年)により廃止されており、犯罪が行われてからどれだけ時間が経過していたとしても犯人が判明した場合には公訴を提起することが可能となっています。
最近では2023年6月23日に性犯罪の公訴時効が5年延長されたこともニュースになりました。
(2)「刑の時効」とは
刑事裁判を経て有罪となったにもかかわらず、その刑の執行(刑務所への収監など)を受けずに一定期間が経過した場合には、刑罰の執行が免除される制度を「刑の時効」といいます。
通常のケースであれば、有罪判決後に一定期間以上刑罰の執行を受けない状態は考えられませんが、法律上ではこのような制度も設けられているのです。
民事上の時効|「取得時効」と「消滅時効」
民法では、時効制度のなかでも「取得時効」と「消滅時効」の2種類が定められています。ビジネスでもとても重要ですので、それぞれについて、確認していくことにしましょう。
(1)取得時効
時効が完成することによって一定の権利を取得することができることとなる制度です。
自分の物でなかったとしても、それを①所有の意思を持ちながら、②平穏かつ公然に、③一定期間(10年または20年)④占有し続けることで、その物の所有権を取得することが認められるのです(民法第162条)。①~④のすべてを充足することで、取得時効の要件を満たすことになります。
たとえば、他人の土地であっても、自分が所有する意思を持ちながら、暴行脅迫等の行為を用いず、また真の所有者にことさら隠ぺいすることなく、10年または20年占有し続けた場合、その土地に関する所有権を取得することが認められることになります。
(2)消滅時効
時効の完成によって一定の権利が消滅する(権利を失う)という効果が発生する制度です。
①権利を行使できる状態になり②一定期間を経過し、③時効を援用する意思表示をした場合には、その権利は消滅します(民法第166条)。
いかに正式に取得した権利であったとしても、一定期間その権利を行使しなかった場合には消滅時効が成立し、権利を失ってしまうことがあるのです。
たとえば、誰かから借金をした場合、借りた側はその借金を返済しなければならないという義務(債務)を負います。逆に貸した側は相手に対して借金の返済を求める権利(債権)を取得します。この債権は、一定期間返済を受けなかったりするなど消滅時効の条件を満たした場合には時効によって消滅することになるので注意が必要です。
なお、本記事では消滅時効期間に関して改正民法の規定によって記載していますが、2020年4月1日の改正民放施行前に成立した債権の消滅時効に関しては、改正前の規定が適用されますのでご注意ください。
短期消滅時効について
旧民法第169条~174条では、債権の種類によって消滅時効期間を5年・3年・2年・1年など細かく規定していました。
たとえば、「旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権」は、旧民法第174条4項で「1年間」という短期で消滅時効が完成するとされていました。驚かれる方も多いかもしれませんが民法には「ツケ払いの踏み倒し」に関する記載があり、1年間支払わなければツケを踏み倒すことも不可能ではなかったのです。
しかし、これらの規定は債権の回収を妨げる・合理的でないなどの理由によって改正民法では完全に撤廃されるに至っています。このため現在では、ツケの踏み倒しは非常に難しい状態となっています。
消滅時効が成立する期間
民法第166条1項では、一般的な債権に関する消滅時効期間を原則として以下のように定めています。
・債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
上記期間のうち、どちらか早く期間が満了した時点で消滅時効が成立することになります。つまり、自分に権利があり、それを行使できることを知っている場合には、わずか5年間で消滅時効が完成することになります。権利がある状態にもかかわらずそれを放置する人は守ってあげない、ということです。
通常の債権に関する消滅時効期間は上記のとおりですが、不法行為に基づく損害賠償請求権など一定の債権に関しては、これとは異なった消滅時効期間が定められています(同166条2項他)。
なお、所有権に関しては、どれだけ権利の行使をしなかったとしても消滅時効が成立することはありません。たとえば、自分の所有している土地をずっと放置していたとしても消滅時効によって所有権を失うことはありません。ただし、他人に取得時効が成立することによって所有権を失うことはあり得ます。
なお、消滅時効の成立を阻止したい場合には、以下に述べるように「時効の更新」あるいは「時効の完成猶予」に該当する行為を行う必要があります。
「時効の更新」とは
「時効の更新」とは、時効の進行中に後述の事由が発生した場合、時効の進行がふりだしに戻る効果を発生させるものです。
以前は「時効の中断」と呼ばれていたものですが、民法の改正によって「時効の更新」と呼び方が変更されました。民法上、時効の更新は主として以下のような事由が発生した場合に認められます。
①裁判上の請求等(民法第147条)
②強制執行等(同148条)
③権利の承認(同152条)
裁判上の請求とは、お金を貸した側(債権者)がお金を借りた側(債務者)に対して裁判を起こすような場合です。権利の承認とは、債務者が債権者に権利の存在を認めることです。「確かに私はあなたに100万円を借りています。返済期限が過ぎて申し訳ありません。必ず返します。」と債務者が債権者に言ったときにわざわざ時効の制度を発動させる必要はないというわけです。これらは時効の更新事由であると同時に、以下に述べる「時効の完成猶予」事由でもあります。
「時効の完成猶予」とは
時効の完成猶予とは、時効の完成を一定期間猶予するものです。具体的には、時効の完成猶予事由に該当する事実等があった場合には、時効の完成が6か月間猶予されることになります。具体的には、以下のような事由が該当します。
①仮差押え等(民法第149条)
②催告(同150条)
③協議を行う旨の合意(同151条)
なお、上記「時効の更新事由」は、すべて時効の完成猶予事由ともなっています。
「時効の援用」(えんよう)とは
民法上の時効は、その期間が満了し時効が完成したからと言って当然に権利の消滅(消滅時効の場合)または権利の取得(取得時効の場合)などの効果が発生するわけではありません。法律上、時効による権利の得喪という効果が確定するためには「時効の援用」が必要とされています(民法第145条)。
時効の援用とは、権利の得喪という法律上の効果を受ける意思表示であり、この意思表示があることを条件に時効によって正式に権利が消滅または取得されることになります。
具体的には、借金の消滅時効が完成した場合では、8で100万円借りていた債務者が「時効が完成したので借金はもう払うつもりがない」などと主張することによって債務(借金を支払う義務)が法律上消滅することになります。
援用権の喪失
消滅時効が完成したにもかかわらず、時効によって消滅したはずの債務について、その存在を承認などした場合、時効の援用をすることが法律上認められなくなることがあります。これを「援用権の喪失」といいます。
積極的に債務が存在することを認めるケースだけではなく、ごくわずかな金額でも支払った場合なども債務の承認に該当し援用権を喪失する可能性があるので注意が必要です。
まとめ
刑法上および民法上における時効制度について解説いたしました。
民法上では、一定の要件を満たした場合、時効が成立し権利を取得したり、逆に権利を失ったりするような効果を生み出します。現在権利を持っていたとしても、それを一定期間行使しない場合には、それを失うことがあるので注意が必要です。契約書の期限管理などを怠ってうっかり時効が到来していた、ということも十分ありうる話なのです。自分の大切な権利を失わないためにも、時効制度について覚えておけば、ビジネスのいざというとき強い味方になってくれるかもしれません。
「電子印鑑GMOサイン」は、契約の期限管理機能や通知・リマインド機能など、便利な機能を数多く搭載した電子契約サービスです。この機会にぜひご活用ください。