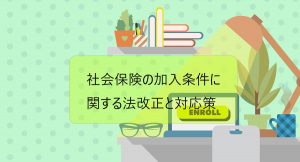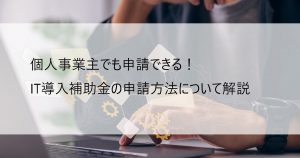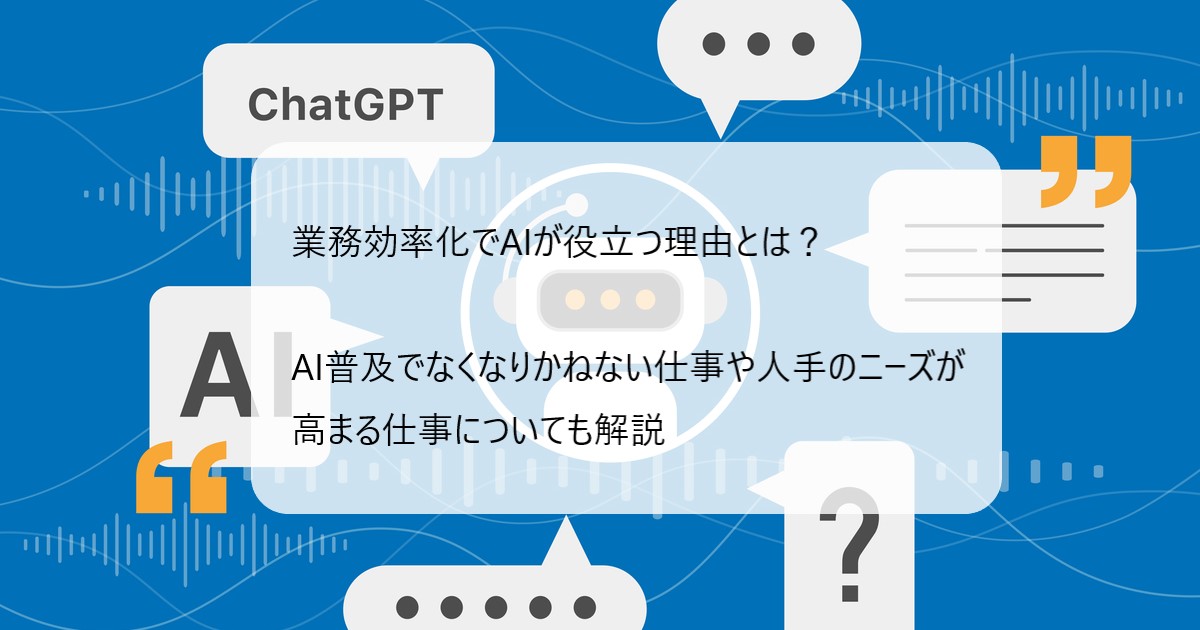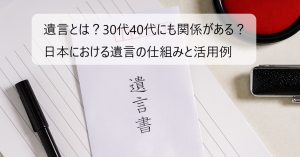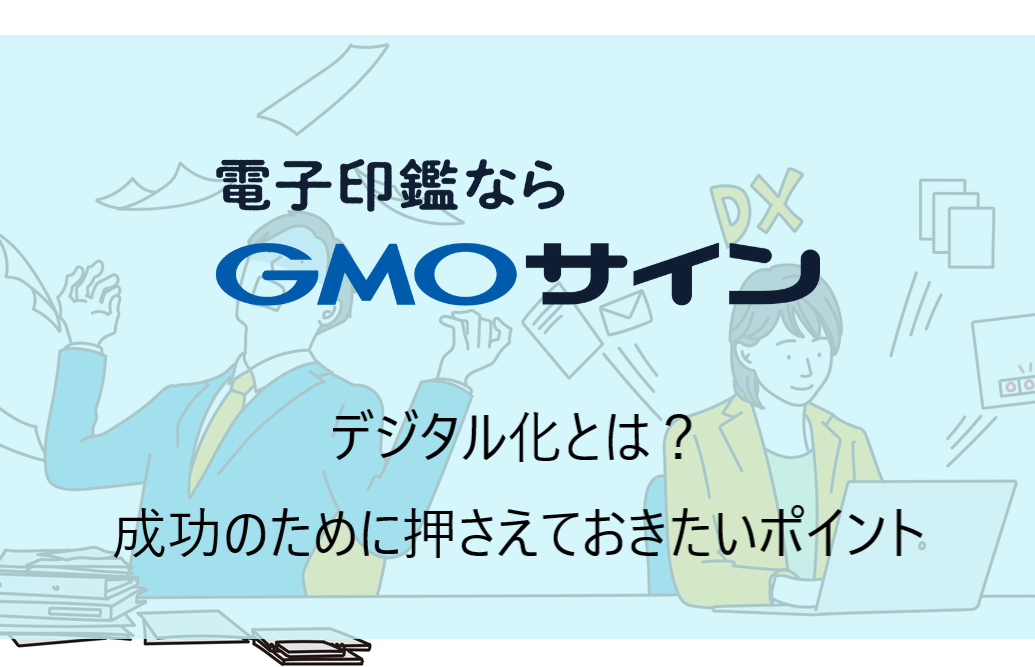従業員数の少ない事業者が販路開拓や生産性向上などの新たな取り組みを始める場合、「持続化補助金」の利用がおすすめです。近年は、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、より大きな補助金を交付する枠も設けられています。
ここではこの「持続化補助金」がどのような制度なのか説明した上で、補助対象や対象事業、申請方法やスケジュールに関することまでまとめています。なお、当該補助金は「電子申請」もポイントになってきますので、この点も解説します。
目次
持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)とは?
持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)とは、「小規模事業者」に「販路開拓・生産性向上を目指した取り組みに要する経費」を一部支援する制度です。
商工会、商工会議所などのサポートを受けつつ経営計画書や補助事業計画書を作成し、審査の結果、採択が決定されれば所定の補助が受けられるというものです。
この持続化補助金は「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の2種類に分けられます。
「低感染リスク型ビジネス枠」は特にポストコロナを踏まえた内容となっており、感染症対策に配慮した新規⽣産プロセスやサービスに取り組む事業者へ補助が行われます。
※新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ちた企業が対象になるわけではないため注意
持続化補助金の対象者と補助額
持続化補助金の対象となるための条件・補助額等に関して、下表で「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」それぞれを確認しましょう。
|
一般型 |
低感染リスク型ビジネス枠 |
| 対象者 |
常時雇用の従業員20人以下の法人・個人事業主
※宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業では5人以下 |
同左 |
| 補助率 |
2/3 |
3/4 |
| 補助上限額 |
単独申請:50万円 |
100万円
※感染防止対策にかかる経費は上限25万円だが、緊急事態措置に伴う措置の場合には50万円まで上限を引き上げ |
共同申請:500万円
※1事業者あたり上限50万円
※最大10者 |
| 取り組み例 |
Webサイト作成、店舗改装、商談会への参加など、販路拡大に繋がる様々な取り組み |
予約システムの導入、テイクアウトを可能にする商品開発など、販路拡大のうち特に感染リスクを下げる取り組み |
| 実施機関 |
全国商工会連合会、日本商工会議所 |
中小企業基盤整備機構 |
持続化補助金では、常時雇用の従業員が20人以下と、かなり規模の小さな事業者が対象とされています。なお「事業者」であればよいため、法人であることは条件とされていません。個人事業主でも補助対象となり得ます。
また、「一般型」は比較的幅広い取り組みが対象になる点で特徴的です。これに対し「低感染リスク型ビジネス枠」では上限額が高く設定されているものの、対象となる取り組みは限定的です。当然、新型コロナウイルス感染症にかこつけただけの、実質単なる広報にあたるような取り組みは審査で落とされてしまいます。
持続化補助金の申請方法
申請方法に関しても「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」では違いがあります。特に電子申請かどうか、という点がポイントです。
まずは「一般型」における申請の流れから見ていきましょう。
基本的には以下の手順で進めていきます。
- 「経営計画書」と「補助事業計画書」の作成
- 「経営計画書」と「補助事業計画書」の写し等を、商工会議所窓口に提出し、「事業支援計画書」の交付を依頼
- 商工会議所が発行する「事業支援計画書」を受け取る
- 受付締切までに、必要な書類を補助金事務局に提出
※単独申請であれば電子申請による提出が可能
電子申請を行う場合は、Jグランツ(補助金申請システム)を利用します。利用にあたってはアカウントが必要ですが、その取得に数週間ほど要するとされていますので注意が必要です。
「一般型」に応募する場合の主な必要書類は以下のとおりです。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)
※電子申請の場合は不要
- 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
- 補助事業計画書②(様式3-1)
- 事業支援計画書(様式4)
※地域の商工会議所が発行する
- 補助金交付申請書(様式5)
- 電子媒体(CD-R・USBメモリ等)
※ここに「事業支援計画書」以外のデータを入れる
※電子申請の場合は不要
ただ、共同申請の場合には上記書類の様式が変わるため要注意です。また、法人か個人事業主かによっても変わってくるものがありますので、詳細は各自チェックする必要があるでしょう。
続いて「低感染リスク型ビジネス枠」における申請方法ですが、こちらはJグランツによる電子申請でしか受け付けていません。同システム内で指定の手続きを行いましょう。なお、「低感染リスク型ビジネス枠」ではアカウント取得にかかる期間が補助金活用の障壁とならないよう、早期発行が可能な「暫定gBizIDプライムアカウント」の運用が実施されています。
全事業者に必須となる書類は以下のとおりです。
- 経営計画および補助事業計画
※WordまたはPDFで作成
- 代表者が自署した宣誓・同意書
※緊急事態措置に伴う特別措置を適用する場合、専用の宣誓・同意書を提出
「一般型」同様、法人か個人事業主かで変わってくる書類もありますので、そちらもチェックする必要があるでしょう。例えば、法人なら直近1期分の貸借対照表および損益計算書、個人事業主なら直近の確定申告書が必要です。
持続化補助金のスケジュール【2021年~2022年】
持続化補助金は「第〇回受付締切」といった形で、1年間に何度か申し込みの機会が設けられています。当記事作成時点での最新情報に基づいて、スケジュールを下表にまとめていますが、翌年度以降に関しては現段階で公表されていませんので、公式サイトにて追記がないか確認をする必要があります。
| 一般型スケジュール(第11版:2021年6月8日) |
| 申請受付開始 |
2020年3月13日(金) |
| 受付締切 |
第6回受付締切 |
2021年10月1日(金)
締切日当日消印有効 |
| 第7回受付締切 |
2022年2月4日(金)
締切日当日消印有効 |
今年度は、10月と翌年2月の2回分です。申請を考えている方は遅れないように手続を行いましょう。
| 低感染リスク型ビジネス枠スケジュール(第6版:2021年6月4日) |
| 申請受付開始 |
2021年5月12日(水) |
| 受付締切 |
第2回受付締切 |
2021年7月7日(水) |
| 第3回受付締切 |
2021年9月8日(水) |
| 第4回受付締切 |
2021年11月10日(水) |
| 第5回受付締切 |
2022年1月12日(水) |
| 第6回受付締切 |
2022年3月9日(水) |
こちらはおよそ2ヶ月に1回のペースと、比較的多く実施されています。
持続化補助金についてのよくある疑問
持続化補助金に関して、多くの方が疑問に思う事柄をいくつかピックアップしました。
「持続化補助金はほかの補助金と併用できる?」
持続化補助金以外にも補助金が受けられる制度は存在しますが、それらとの併用が可能なのかどうか、疑問に思う方も多いでしょう。
持続化補助金に関しては、
「同一事業者が同一の内容について、国が実施する助成制度を併用することはできない」
とされています。
そのため中小企業での活用例が多い「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」といった補助金との併用はできません。
「補助金はいつ交付される?」
交付される時期に関しては明確な交付時期を示すことはできませんが、締切日から交付決定まで少なくとも1、2ヶ月程度は要すると考えておくべきでしょう。
また、申請後、審査に通ったとしてもすぐに交付されるわけではなく「採択通知書」を受け取った後、補助事業を実施し、事業終了後に実績報告書などを提出する必要があります。これら一定の過程を経てからでなければ振り込まれませんので、少しでも早く交付を受けたい場合、申請のみならず採択後のアクションも迅速に行うことが重要です。
なお、「低感染リスク型ビジネス枠」については
「申請受付締切後、採択結果を公表するまでの間、審査に数か月要する場合があります。」
と明記されており、数週間程度の短い期間で結果が判明するようなことはないと考えられます。実際、2021年5月12日締切分に関する採択案件の公表は2021年7月上旬とされています。
「審査では何を評価される?」
どのように審査が行われるのか、どこに着目して評価されるのかについては、
必要書類が提出されていることなど、形式的な要件はもちろんですが、応募要項(「一般型」)では以下の事項を評価する、とあります。
- 補助対象となる取り組みを遂行するのに必要な能力の有無
- 事業者が主体となった活動か
- 事業者の技術・ノウハウ等を基にした取り組みか
- 自社製品またはサービスの強みを適切に把握しているか
- 対象になる市場の特性を捉えているか
- 計画の実現可能性の高さ
- 小規模事業者ならではの創意工夫の有無
- ITを有効に活用しているか
- 事業費の計上・積算が正確かつ明確であり、内容が適切か
- 電子申請を行ったか
①~③が基礎審査、④~⑩が加点審査です。
審査は経営計画書、補助事業計画書を用いて行われます。「低感染リスク型ビジネス枠」では電子申請が必須のため加点対象ではありませんが、「一般型」では、電子申請をすれば政策的観点から加点を行う旨明記されています。そのため積極的に電子申請を活用すべきでしょう。
持続化補助金の取得に向けて早期着手しよう
持続化補助金には「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の2種類があり、それぞれに対象となる取り組みや補助額、スケジュールなども異なっています。そのため、当該制度を利用しようと考えている方は早めに具体的な検討を始め、締切に間に合うように準備することが大切です。
電子申請が必須ではない「一般型」でも審査の加点要素であるため、どちらの枠組みで申請する場合でも、電子申請はできるようにしておくべきです。ただ、アカウント取得には期間を要しますので、やはり早期着手が欠かせません。
【参考】
小規模事業者持続化補助金メニュー(日本商工会議所)
https://jizokukahojokin.info/
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>(全国商工会連合会)
https://www.jizokuka-post-corona.jp/
Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
gビズID(gBizID)(デジタル庁)
https://gbiz-id.go.jp/top/