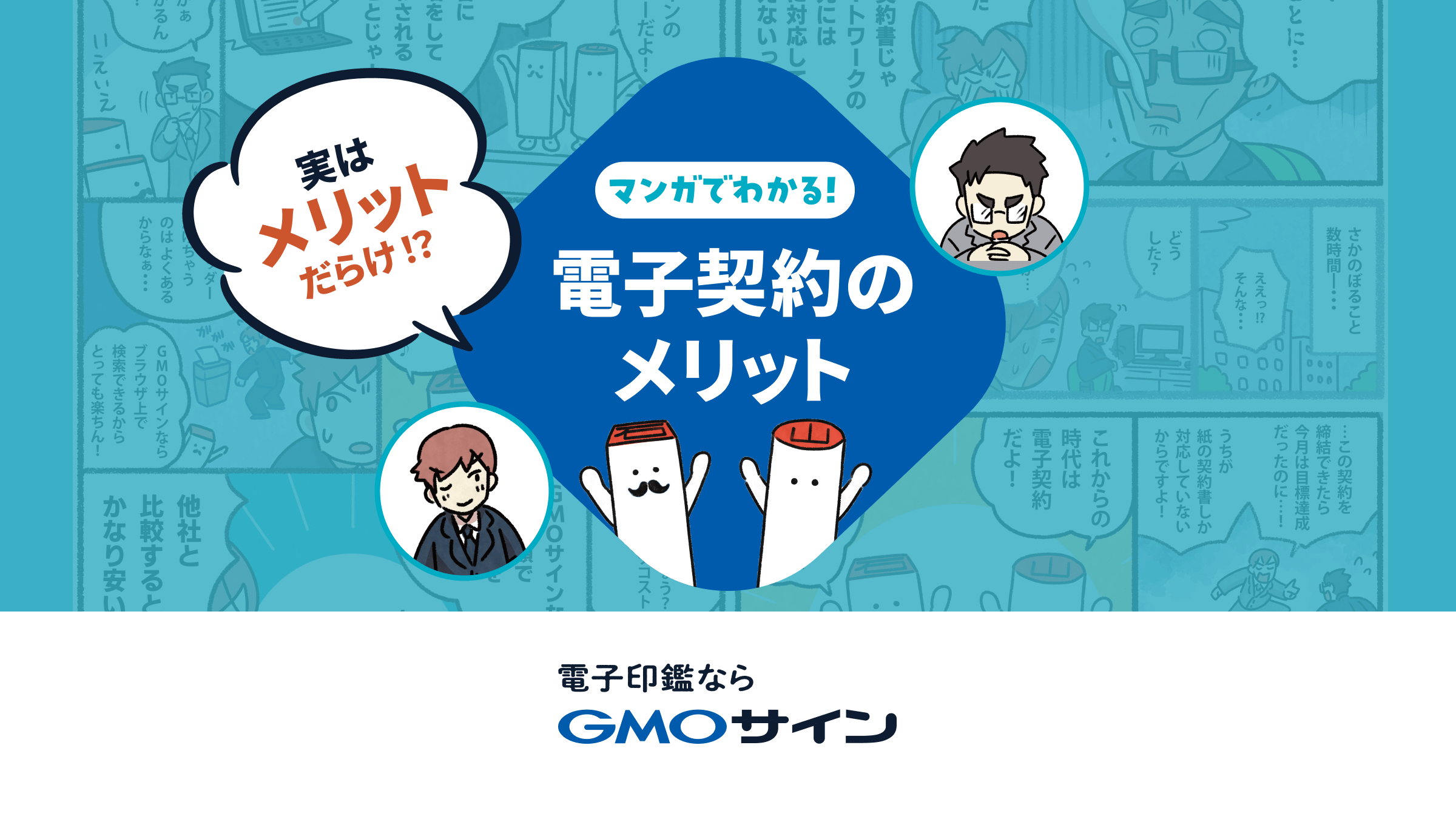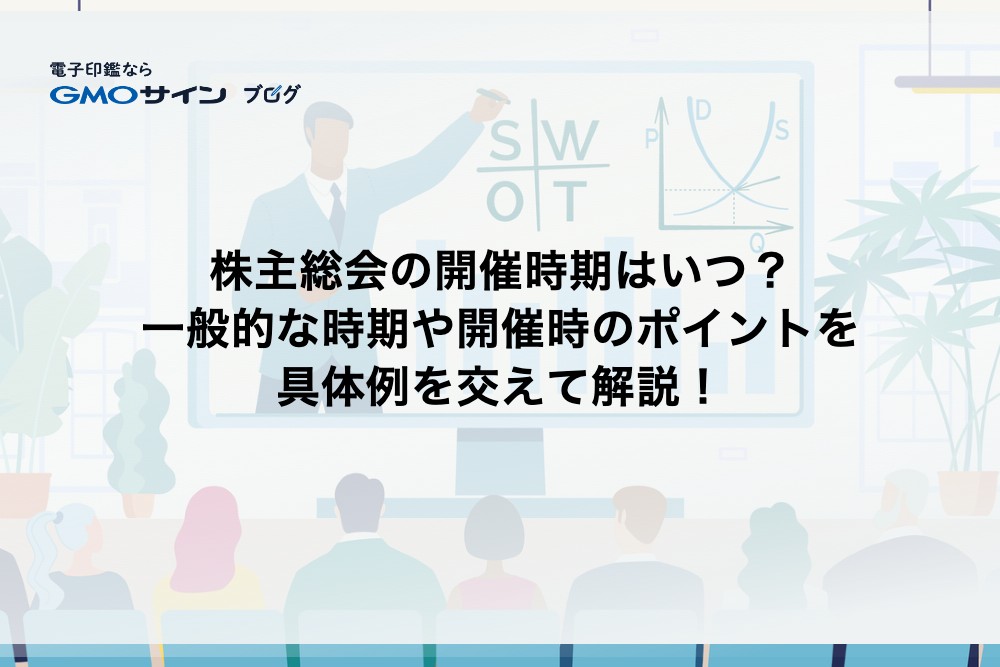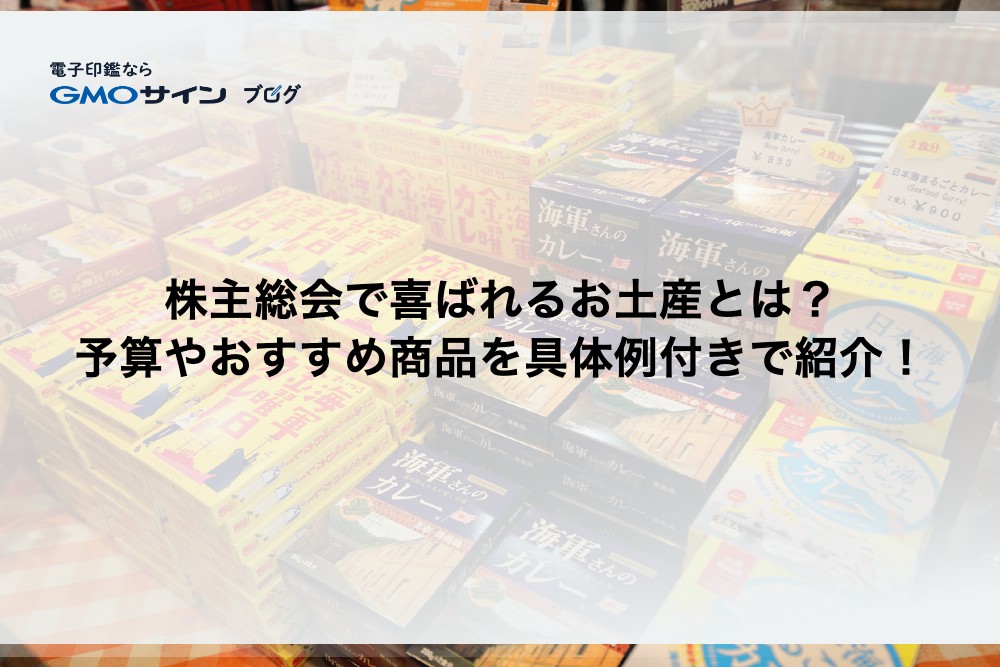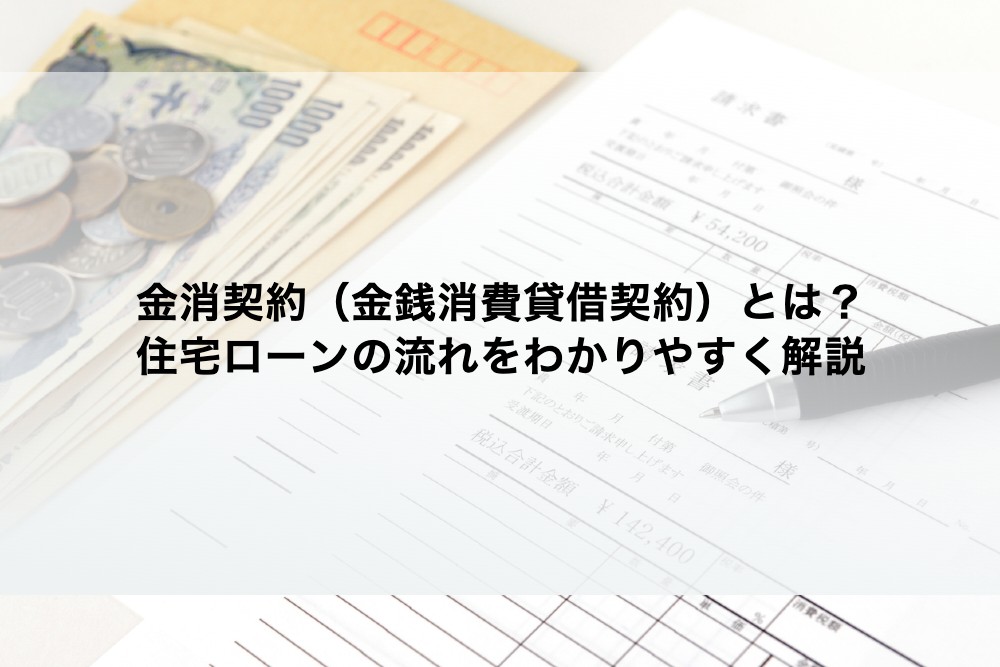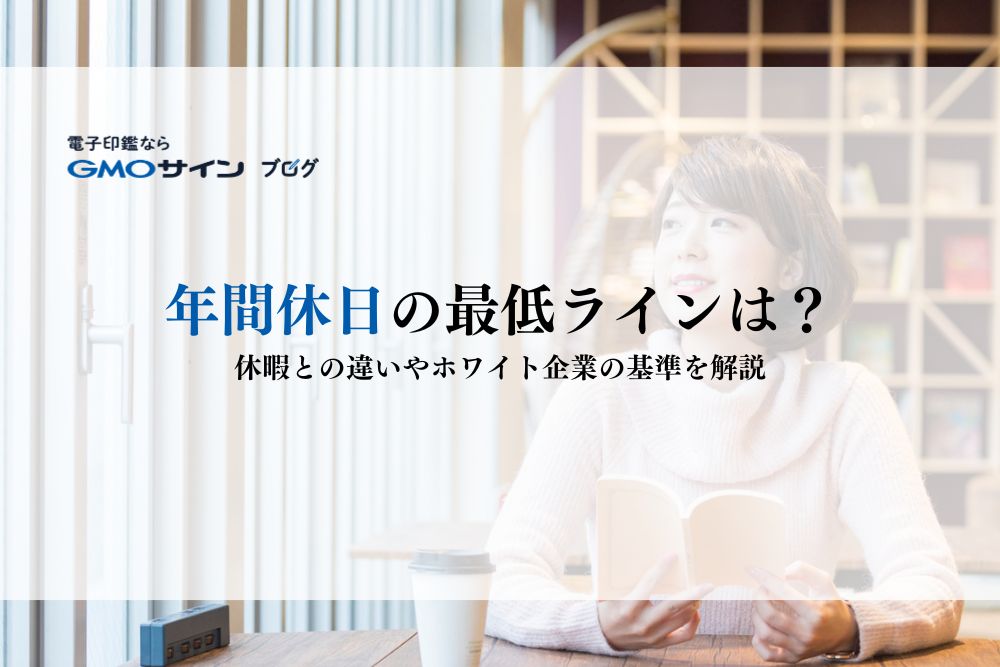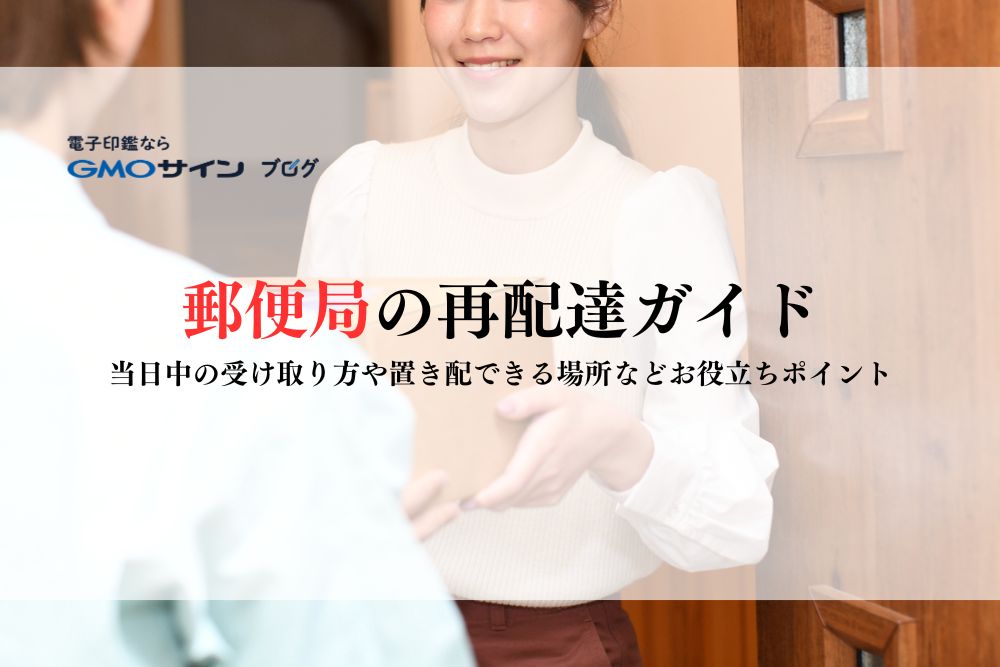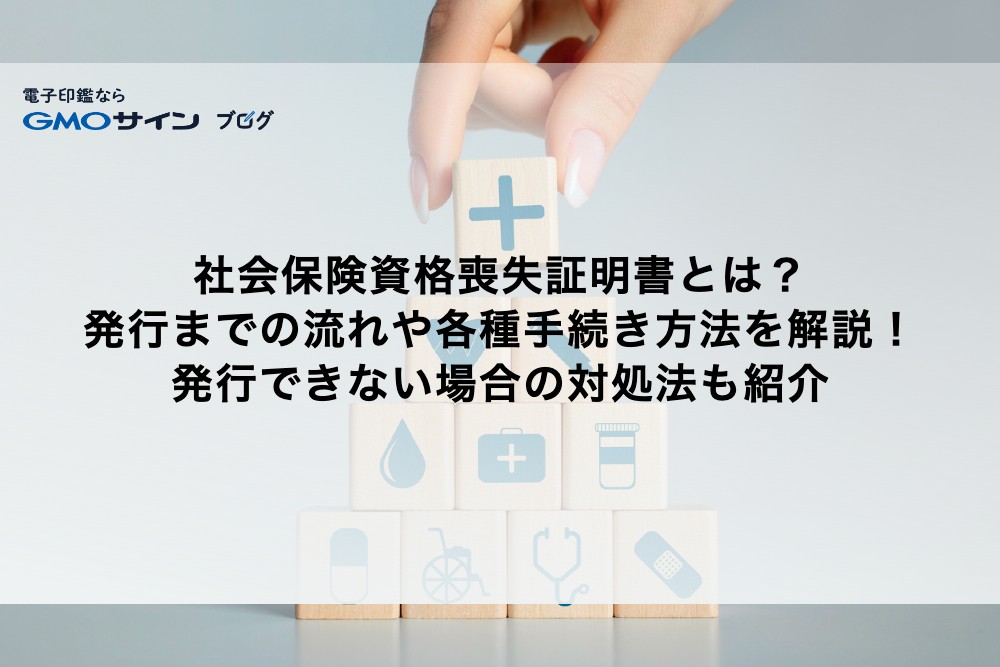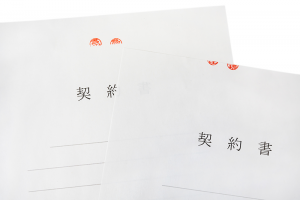複数店舗を展開し事業を拡大すれば、大きな利益が見込めます。しかし、リスクも伴うため、新規店舗の出店には慎重になる経営者の方も多いでしょう。できるだけリスクを抑えた上で効果的に事業拡大を図りたいところです。
事業拡大のための戦略として「ドミナント戦略」というものがあります。これから事業拡大を図りたいのであれば、選択肢のひとつとして検討してみるといいかもしれません。有名チェーン店の中にも、ドミナント戦略で事業を拡大してきた企業があります。
本記事ではドミナント戦略について、メリットやデメリットなどを中心に全般的に解説します。
目次
ドミナント戦略とは
最初にドミナント戦略がどのようなものを指すのかかんたんに見ていきましょう。
特定のエリアに絞って出店する
ドミナント(dominant)とは「支配的な」や「優位な」という意味の英単語です。ドミナント戦略は、特定のエリアに絞って集中的に出店することで、そのエリアで支配的な地位を確立する戦略を指します。特定のエリアに同じチェーン店が多く出店すれば、チェーン全体で見た場合のシェアは高くなるでしょう。競合他社に対して、優位な立場になれます。
出店する方法に関しては、直営店だけとは限りません。フランチャイズで出店する方法を採るケースもあります。
ランチェスター戦略との違い
ドミナント戦略とよく似ているものとして、ランチェスター戦略というのがあります。ドミナント戦略は特定のエリアに特化しますが、ランチェスター戦略は特定の分野に特化するのが大きな違いです。主に中小企業がニッチな分野で大企業に勝つことを目指して行われます。
ドミナント戦略のメリット
ドミナント戦略を行うことで得られるメリットについて見ていきましょう。
対象にしたエリアで認知度を向上させられる
ドミナント戦略を採ると、全国各地に出店するよりも、出店の対象にしたエリアでは、多くの人の目に留まるようになります。たとえば、47都道府県に1店舗ずつ出店しても、各都道府県では、あまり大きなインパクトはありません。これに対して、同じ都市内に47店舗出店すれば、その都市内の至るところで目に付きます。その都市に住む人なら誰でも知っている店舗になれるでしょう。
対象にしたエリアに特化したマーケティングを実施できる
エリアが違えば消費者の動向にも違いが出ることがあります。エリアにより売れる商品が異なることも多いでしょう。文化や気候などの影響も大きいです。全国展開している店舗だと、エリアごとの細かな違いを考慮してマーケティングをするのは難しいのが現実です。
これに対して、ドミナント戦略なら、対象にしたエリアに特化したマーケティングができます。地域に根ざしたチェーン店として、ブランディングを確立できるのです。
競合他社が参入しにくくなる
すでに大きなシェアを占めている店舗やブランディングを確立している店舗があるエリアは、あまり他社が参入したがりません。他社にとっては成功の難易度が他のエリアよりも高く、リスクを考慮すると割に合わないためです。そのため、ドミナント戦略が成功すれば、長期間にわたって、そのエリアで優位な地位に立つことができます。
配送業務を効率化できる
チェーン店が特定のエリアに集中していれば、店舗間の距離が短いため、配送を効率的に行えます。全国各地に配送する場合と比べて、コストが抑えられるでしょう。配送にかかる時間も短縮できます。食品を扱う店舗なら、新鮮な状態で届けられるのもメリットです。
経営資源を効率的に活用できる
チェーン店間の距離が短いと、人員配置もやりやすくなります。一時的に人員の足りなくなった店舗があれば、他のチェーン店のスタッフからヘルプに来てもらうことも可能です。また、ひとつの倉庫を複数店舗で共有することもできます。
ドミナント戦略のデメリット
ドミナント戦略はメリットばかりではありません。実際に行う際には、次のようなデメリットも認識しておく必要があります。
自然災害に弱い
大きな地震や台風などの自然災害が発生した場合には、特定のエリアに被害が集中します。全国各地に少しずつ出店していれば被害が集中したエリア以外の店舗は無事で済むでしょう。しかし、ドミナント戦略を採っていると、すべての店舗が被害を受けてしまう可能性があります。
そうなると、被害を受けていない店舗の売上で会社全体の業績をカバーすることができません。復旧費用がかかる上に、営業を再開できず売上がゼロの状態が長期間続くことになります。状況によっては事業の継続が困難になることもあるでしょう。
地域的な環境変化の影響を受けやすい
出店中の店舗が特定のエリアに偏っていることで、自然災害と同様に地域的な環境変化の影響も強く受けます。たとえば、同じエリア内に大型店舗が出店すると、顧客を一気に奪われてしまうリスクがあります。
人口の増減などによる地域的な需要の変化が起こったときにも影響を受けやすいです。
カニバリゼーションのリスクが高まる
カニバリゼーション(cannibalization)というのは共食いを意味する英単語です。マーケティングにおいては、同一企業での顧客の奪い合いを指します。
ドミナント戦略を採っている場合には、基本的に店舗間の距離はあまり離れていません。店舗間を徒歩で行き来できるところもあります。そのため、エリア内に住む人にとっては、生活圏内に複数の店舗があるという状況になりやすいです。同じ企業のチェーン店同士で、顧客を奪い合う構図ができてしまいます。
他のエリアへの進出が難しい
店舗の経営では、地域の事情や環境を把握しておくことが重要です。ある地域でうまくいくやり方が、他の地域でもうまくいくとは限りません。
一方、ドミナント戦略を採っている企業では、対象にしているエリア以外はあまり詳しい情報を把握していないことが多いです。そのため、他のエリアへの進出を試みても、あまりうまくいかない可能性があります。
ドミナント戦略で成功するために必要なこと
ドミナント戦略で成功するためには、次のようなことが必要です。
出店エリアの市場調査
ドミナント戦略は特定のエリアに特化した戦略であるため、出店エリアの市場調査は非常に重要です。まず、現在の人口やこれまでの増減の推移をチェックしておきましょう。人口減少が続いているエリアでは、長期的に売上を伸ばしていくのは困難です。昼間人口と夜間人口の差や年齢別の人口構成などもチェックしておく必要があります。
さらに、最寄り駅までの距離やバス路線などの交通事情も確認しておきましょう。集客が見込めるかどうかを判断する上で重要な要素です。マイカーでの来客を想定する場合には、道路の混雑具合などもチェックしておく必要があります。
競合他社との差別化
出店予定エリアですでに一定の実績や知名度のある企業について、詳しく調査しておきましょう。その上で、出店後に勝てるようにするための戦略を練ります。
エリア内に住んでいる人にとっては、すでに競合他社を定番の店舗として認識しているケースが多々あります。その中で勝たなければなりません。同じようなサービスではなく、自社ならではの魅力をアピールし、独自のサービスを提供するのが効果的となるでしょう。全国チェーン展開している店舗が競合なら、地域に即したサービスを提供することで差別化を図れます。
また、新しいサービスも積極的に取り入れましょう。会員制のサービスや契約が必要なサービスなら、電子契約を導入するのも効果的です。
電子契約サービス国内シェアNo.1(※)の電子印鑑GMOサインでは、対面契約のオプションも提供しています。タブレット端末に手書きサインをして、電子契約できるため、非常にスムーズです。画像添付やSMSなどでの本人確認ができる機能も備わっています。
申込みや契約手続きが必要な業種で出店する際には、ぜひ電子印鑑GMOサインの対面契約をご利用ください。
※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)
BCPの策定
BCPとは、自然災害発生時の事業継続計画のことです。自然災害が発生すると、打撃を被ることを想定した上で、それでも復旧できる体制をあらかじめ整えておきます。具体的にどのような行動を取るのかなども、あらかじめ策定しておくため、迅速な対応が可能です。
ドミナント戦略の事例
有名企業でもドミナント戦略で成功した事例がいくつかあります。代表的ドミナント戦略の事例を見ていきましょう。
セブン-イレブン
セブン-イレブンは全国展開しているコンビニチェーンですが、実はドミナント戦略により成長してきました。セブン-イレブンの1号店がオープンしたのは1974年のことです。その後は東京都江東区内に絞って集中的に出店を進めました。
その後も、他のエリアへ進出する際にも特定のエリアに集中的に出店を続けます。さらに、出店エリアの周辺に惣菜などを作る工場を設置しました。地域単位のドミナント戦略で少しずつエリアを拡大し、現在ではローソンやファミリーマートを上回り、全国最多の店舗数を誇る規模に至っています。
参考:セブン&アイ・ホールディングス「今、さらなる「近くて便利」へ。進化の原動力を読み解く5つの視点。(2018年6月)」
スターバックスコーヒー
スターバックスコーヒーもドミナント戦略で成長してきた企業です。創業間もない頃は、アメリカのシアトル市にある小さなカフェでした。その後、シアトル市内でドミナント戦略により店舗を増やし、他のエリアへ進出する際にも、特定のエリアに集中的に出店する方法を採っています。
日本への進出もドミナント戦略で行われました。港区と渋谷区、新宿区のエリアにスターバックスコーヒーの店舗が集中しています。
参考:ライブドアニュース「新宿にスタバが約30店舗もあるのはなぜ?“ドミナント戦略”という儲け方」
アパホテル
アパホテルは、2010年から東京の都心部に絞ってホテル建設を進め、シェアを伸ばしました。現在では全国各地に出店していますが、東京都での出店件数が突出して多いのが特徴です。
東京都以外のエリアでも出店数を増やす際には、ドミナント戦略を採っています。たとえば、福岡県では博多駅周辺に集中して展開しています。
参考:月間ホテレス「トップインタビュー アパグループ社長 兼 最高経営責任者(CEO)元谷 一志 氏」
まとめ:事業拡大を目指すならドミナント戦略を検討してみよう
ドミナント戦略は特定のエリアにチェーン店を集中して出店し、そのエリアでの優位性を確保する戦略です。経営資源を効率的に活用できて、競合他社が参入しづらい状況を作れます。対象にしたエリアの地域的な特徴をよく理解した上で店舗経営を行えば、急成長も見込めるでしょう。セブン-イレブンやスターバックスコーヒーのような有名チェーン店でも行われてきました。
ただし、自然災害や地域の環境変化に対して弱いのがデメリットです。ドミナント戦略を採る際には、あらかじめ十分な市場調査を行い、BCPを策定しておく必要があります。デメリットを理解し対策を講じた上で行えば、有用な戦略です。