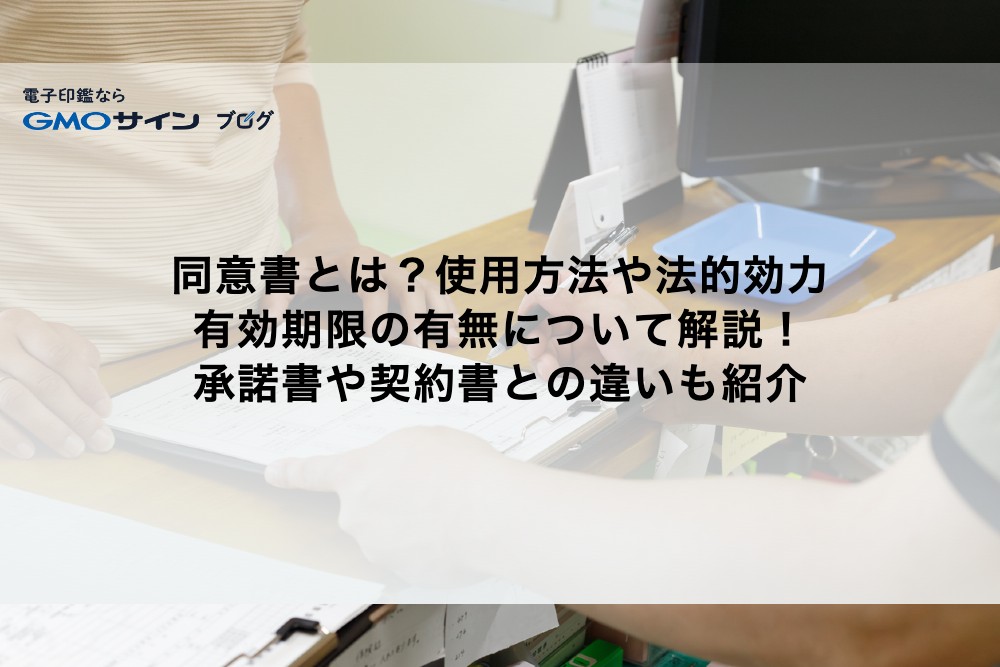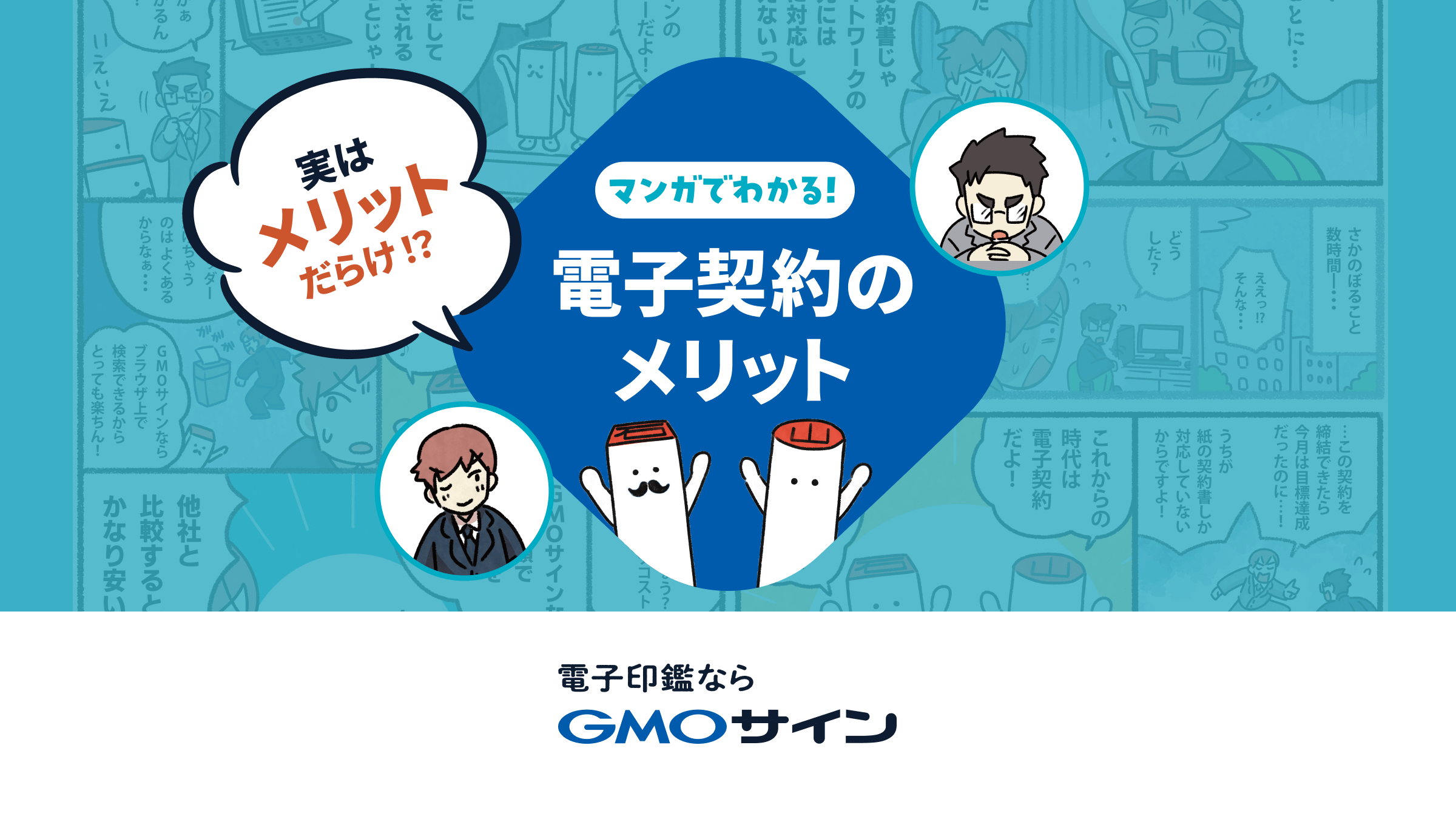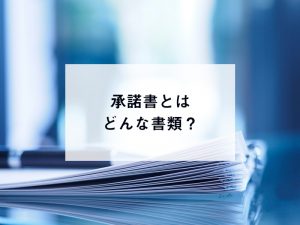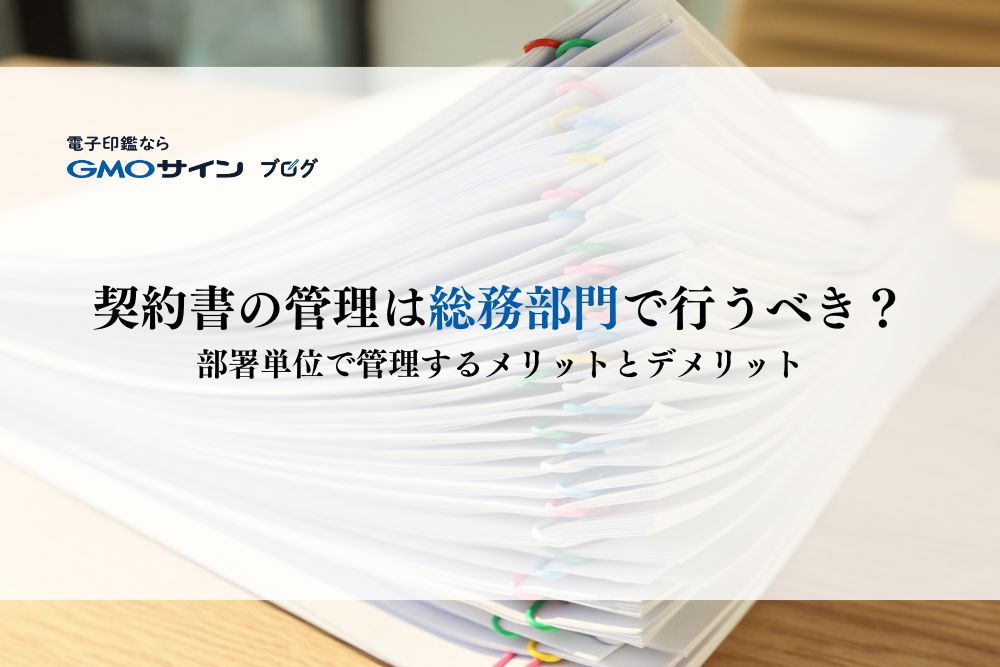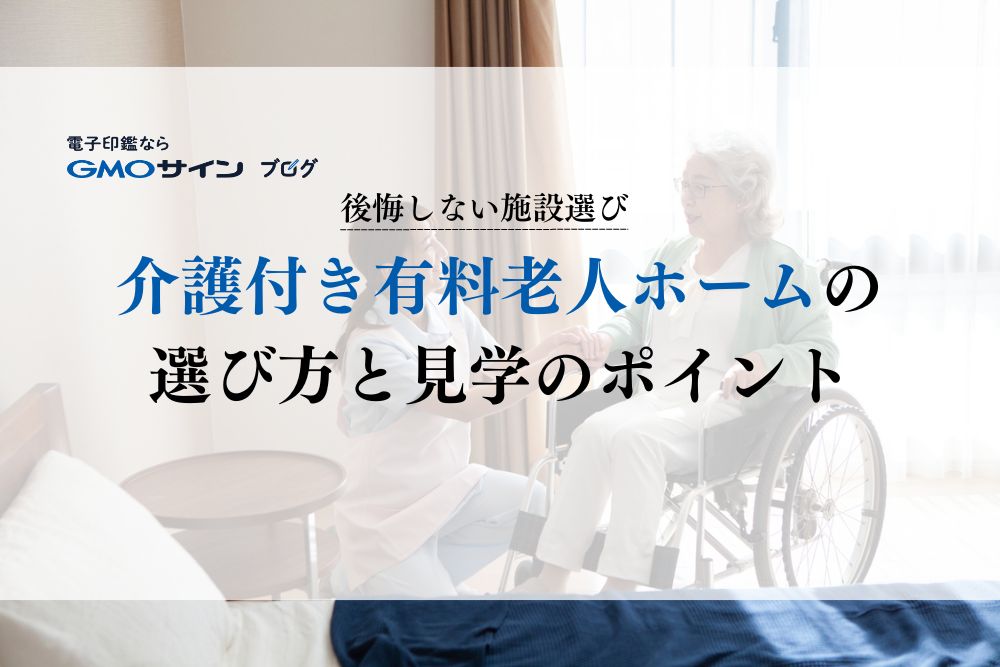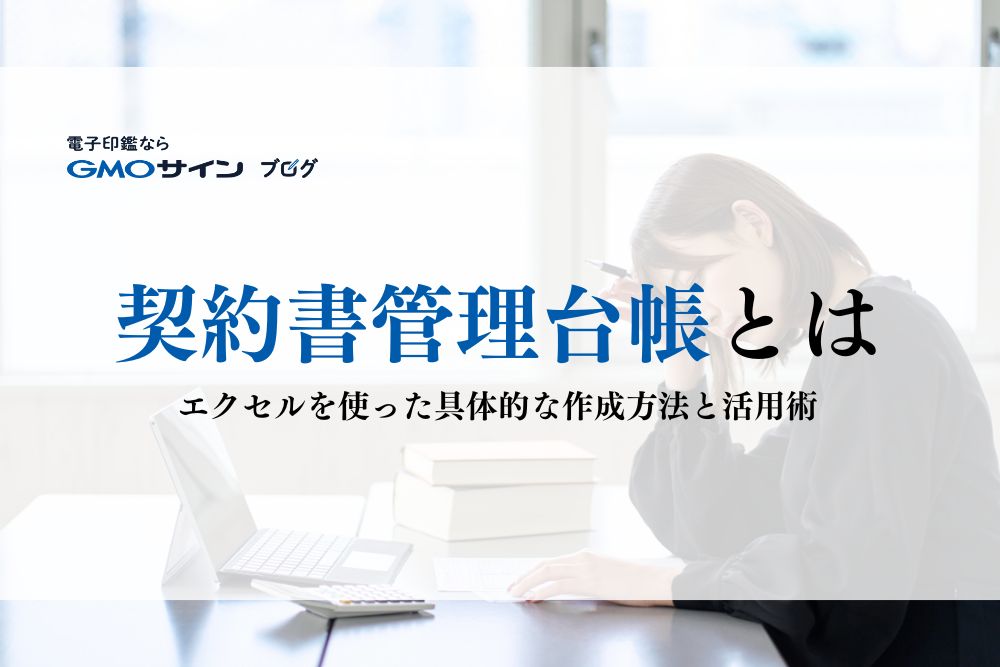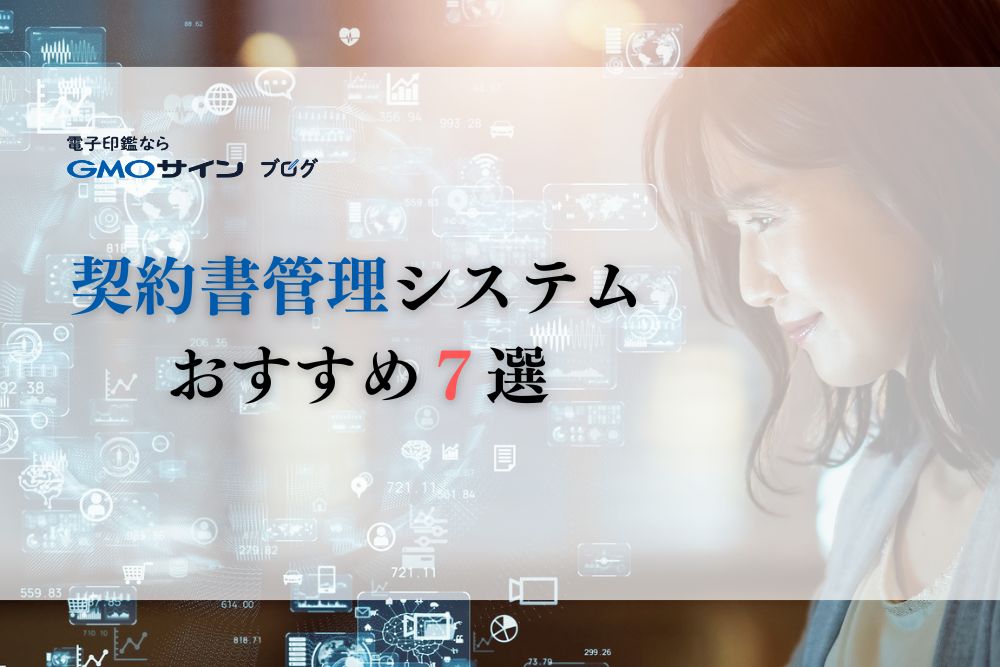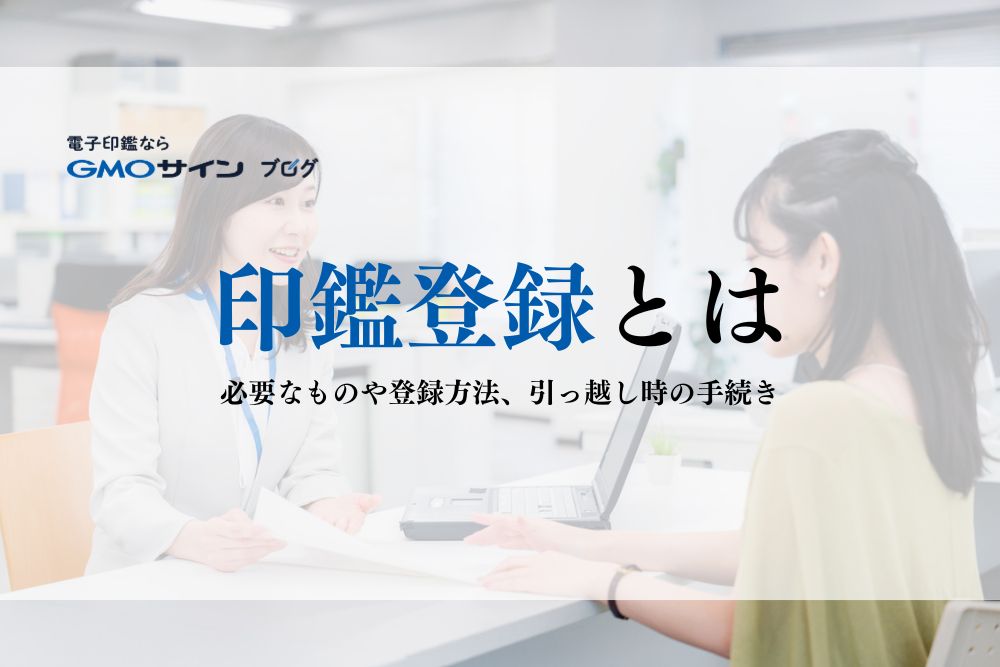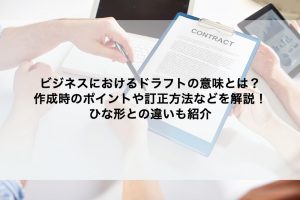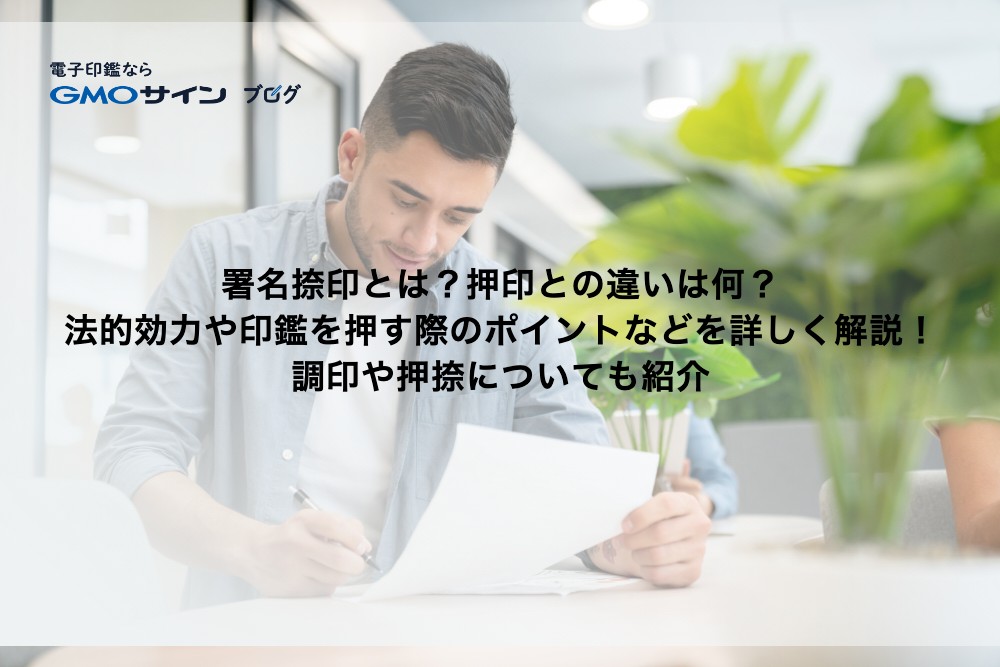目次
同意書について
同意書とはどのような目的で作成するものなのか、そしてどのような法的効力があるのかを知っておくと、必要な場面でより効果的に利用することができます。
同意書を作成する目的
同意書とは、今後起こりそうな事柄に対して、同意する意思を表すための書類です。
この書類を作成することの目的は、契約締結の際などに、相手へ同意書の内容の確認と署名・捺印をしてもらうことで、「本人の同意を得ている」という証拠を残すことにあります。
これによって、もし締結後に「このような条件は聞いていない」など主張されても、この同意書を証拠としてはねのけることができるのです。
どのような法的効力があるのか
同意書には、同意の内容によって次のような法的効力があります。
まず1つめは、契約締結の際に「契約内容について説明義務を十分に果たしたという証明になること」です。例えば事業者と消費者が契約を結ぶ場合、契約内容を説明し消費者が一方的に不利益を被らないようにしなければなりません。同意書を作成することによって、「説明されていない」など主張されてしまうようなトラブルの防止になります。
2つめは、未成年者などとの契約締結の際に「親権者に同意を得たことで、不完全な法律行為を補完し有効化したという証明になること」です。未成年者に限らず、病気などで判断能力が衰えている人は、多くの場合、その人単独で契約を結ぶことはできません。そのため、法定代理人や後見人などから同意を取得する必要があるのです。
そして3つめは、「事前に本人の同意を得ることで、提供の条件(同意の取得)を得た証明になること」です。これは業種によって必要なもので、例えば個人情報は個人情報保護法により守られており、通常は第三者が自由に利用することはできません。しかし、事業者が個人情報について「利用目的」「第三者への提供の有無」「個人情報開示請求」などの項目が書かれた同意書を作成し、消費者が署名捺印することによって、事業者は個人情報を取り扱うことができるようになるのです。
ただし、いくら同意書に署名・捺印をもらったとしても、その内容に法律や公序良俗に違反する内容があると、無効となります。
有効期限はあるのか
同意書は、原則的にお互いが同意している間は有効となるため、期限はありません。
同意書に、「○○年○○月○○日まで」と有効期限について定める一文を加えた場合は、その日までが有効期限となります。
同意書とその他の書類の違いについて
同意書と似た役割を持つ「承諾書」「契約書」について、それぞれの違いをまとめると以下のとおりです。
承諾書との違い
同意書と承諾書は、名前が違うだけでその用途も効力もほぼ同じです。
「同意」には「賛成」という意味があり、「承諾」には「受け入れる」という意味があるため、それに合わせて書類の内容で使い分けされています。
あわせて読みたい
承諾書とはどんな書類?同意書との違いと必要項目、作成時のポイント
内定承諾書など、「承諾書」と呼ばれる書類はどのようなものなのでしょうか。また、「承諾書」は「同意書」と混同されることもありますが、両者は性質の異なる書類です...
契約書との違い
同意書は、「今後起こりそうな事柄に対して了承した」ことを表す書類で、基本的に1通だけ用意するものです。しかし契約書は、「自分と相手の双方が、書類に書かれた権利と義務について合意し契約締結をした」ことを表す書類なので、自分だけではなく相手の分も用意し、双方が署名・捺印した上で1通ずつ保管することになります。
同意書を必要とする場面とは
同意書の作成は、ビジネスだけではなく日常のさまざまな場面で必要となりえます。例として次のようなケースがあります。
個人情報の提供
例えば、クレジットカードの作成やローンの申し込みを受けた事業者は、申込書に記入された個人情報の照会を行います。このケースでは、事前に、事業者が個人情報保護法に基づき個人情報を業務や利用目的の達成のために必要な範囲で利用することに同意することを示すため、同意書に署名・捺印することになります。
医療行為の提供
手術などリスクを伴う医療行為を行うときにも、同意書は大切な役割を果たします。医師や看護師が患者やその家族に対し、これから行う医療行為について危険性も含めて十分な説明を行い、しっかりと理解した上で同意書に署名・捺印をしてもらうことが重要です。
未成年者などの契約時
未成年者や病気で判断能力が衰えている人が契約を行うときは、本人だけでは不完全な法律行為となり契約として成立しないことがあります。この場合、親権者などの法定代理人が、同意書に署名・捺印をして同意することによって、初めて認められることになります。また、不完全な法律行為で締結された契約は、本人や法定代理人などの申し出で取り消しが行えます。
給与明細の電子化
所得税法によって義務付けられている給与明細の交付は、従業員の承諾を得ることによって電磁的方法で行えるようになります。紙での交付では、印刷に伴うコストや誤配などのリスクを伴いますが、電子化することによってそのようなデメリットは解消されます。
同意書の使用方法
同意書に必要な項目
同意書には、次の5つの必要項目があります。それは、「表題」「同意した内容」「同意した日付」「同意した本人の住所氏名」「同意した本人の捺印」です。
この5つの要素を満たしていれば、特に形式に決まりはありません。
送付する際の注意点と送付方法
同意書を送付する際には、ビジネスマナーとして送付状を添付するとよいでしょう。
送付状とは、契約書などの書類に同封する書面のことを指し、挨拶や用件の通知などの役割を果たします。
そのためマナーとしても大切な役割を果たしていますが、受け取った側が書類の内容を把握しやすくなるという役割もあります。
郵送する場合には、「書留」の利用がおすすめです。書留は郵便局の窓口へ出した時から配達が完了するまでの記録が残り、配達状況の確認もできるほか、万が一紛失などの事故が起こった場合には損害賠償サービスが受けられます。ただし、同意書は信書扱いなので、ゆうメールや宅配便など利用できないサービスもある点に注意しましょう。
あわせて読みたい
簡易書留の出し方と手順を解説!活用シーンや出す時の注意点、メリット・デメリットなども紹介
簡易書留は、大切な郵便物や物品を確実に郵送するための郵便サービスです。しかし、初めて利用する人にとっては、手続きや出し方がわからず、不安を感じることもあるか...
郵送以外の方法では、PDFファイルへ電子化し、データとして送信する方法もよいでしょう。プリントアウトや郵便ポストへの投函などといった手間の省略や、郵送代のコスト削減にも繋がります。
同意書作成時に注意すべきこと
同意書を作成し、署名・捺印を相手に求める場合には、以下の点に注意が必要です。
まず、書面にまとめた同意内容について、漏れがないかを確認しましょう。同意してもらいたい内容に漏れがあると、後々トラブル発生の原因となってしまいます。また、他にも同意書として必要な項目が抜けていないか、しっかりと確認することも大切です。
次に、相手から署名・捺印された同意書について、必要なことが全て記入されているかを確認しましょう。特に、「同意した日付」は念入りに確認し、もし漏れがあれば連絡して再度記入してもらいましょう。もし日付が未記入の場合、いつから同意したのかが分からなくなるため、最悪の場合同意が無効となることがあります。