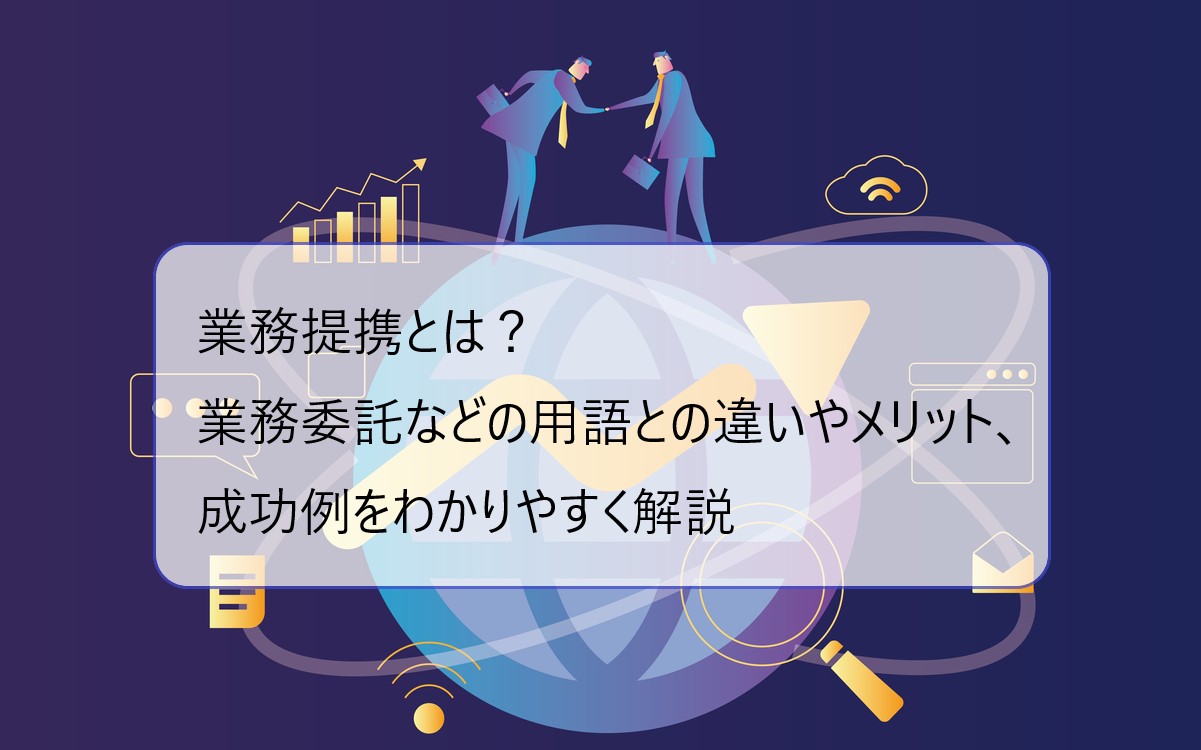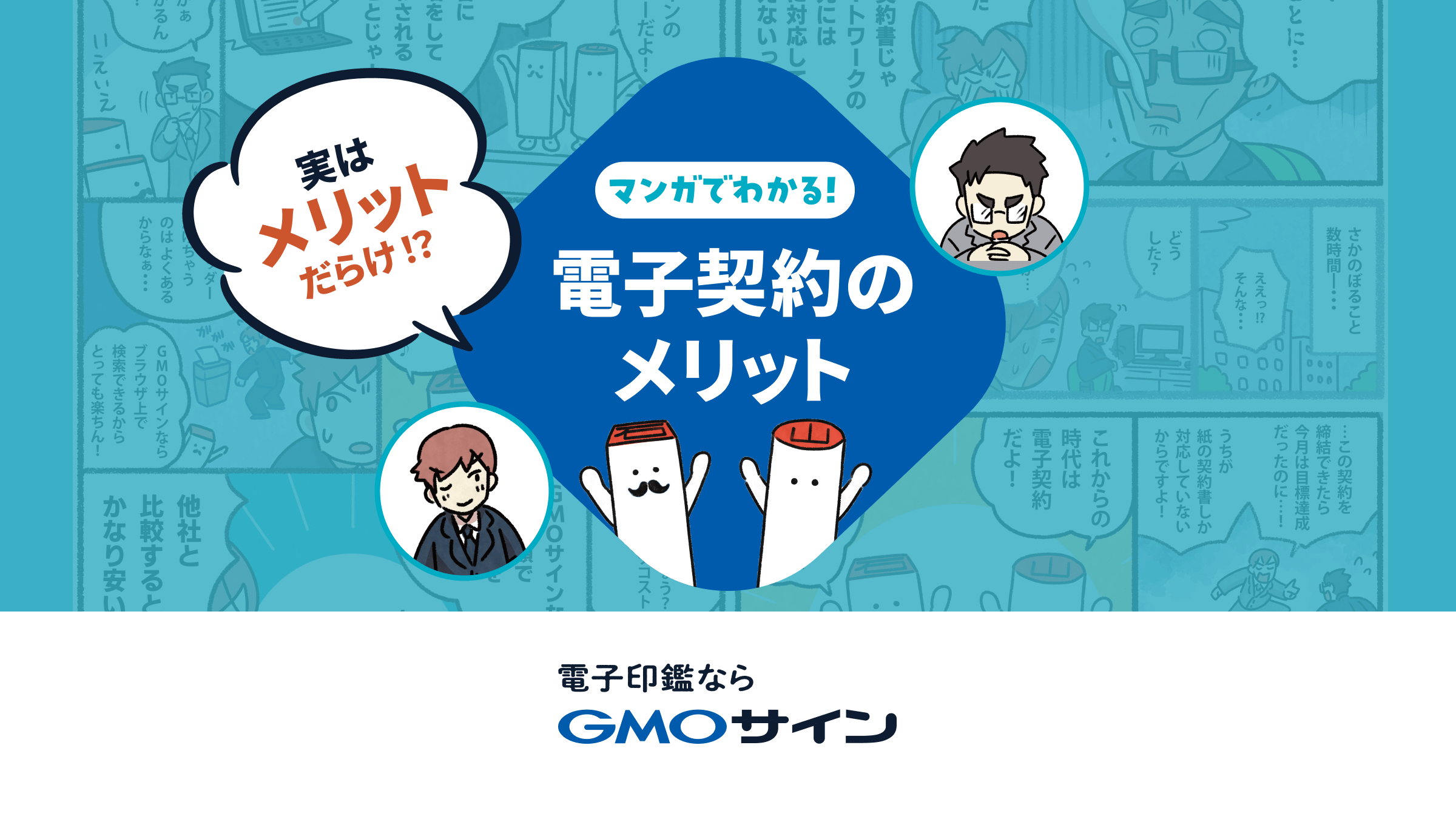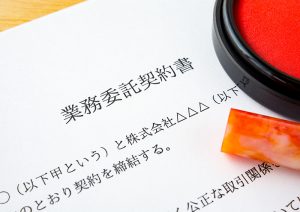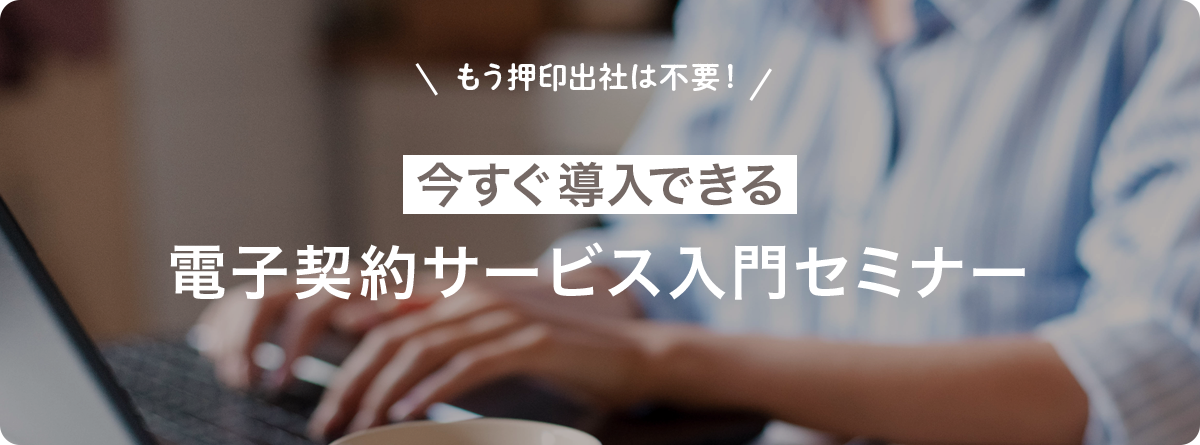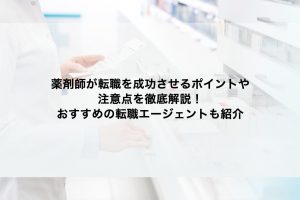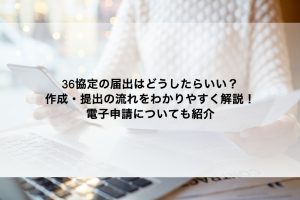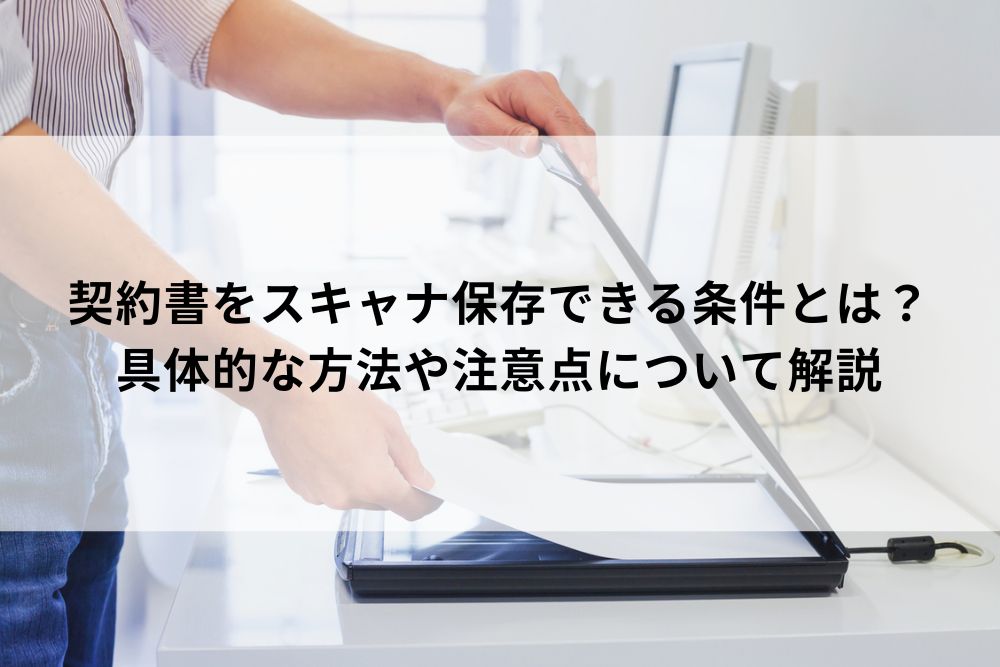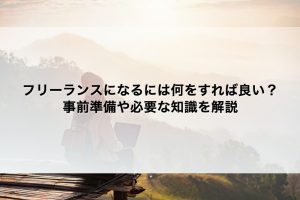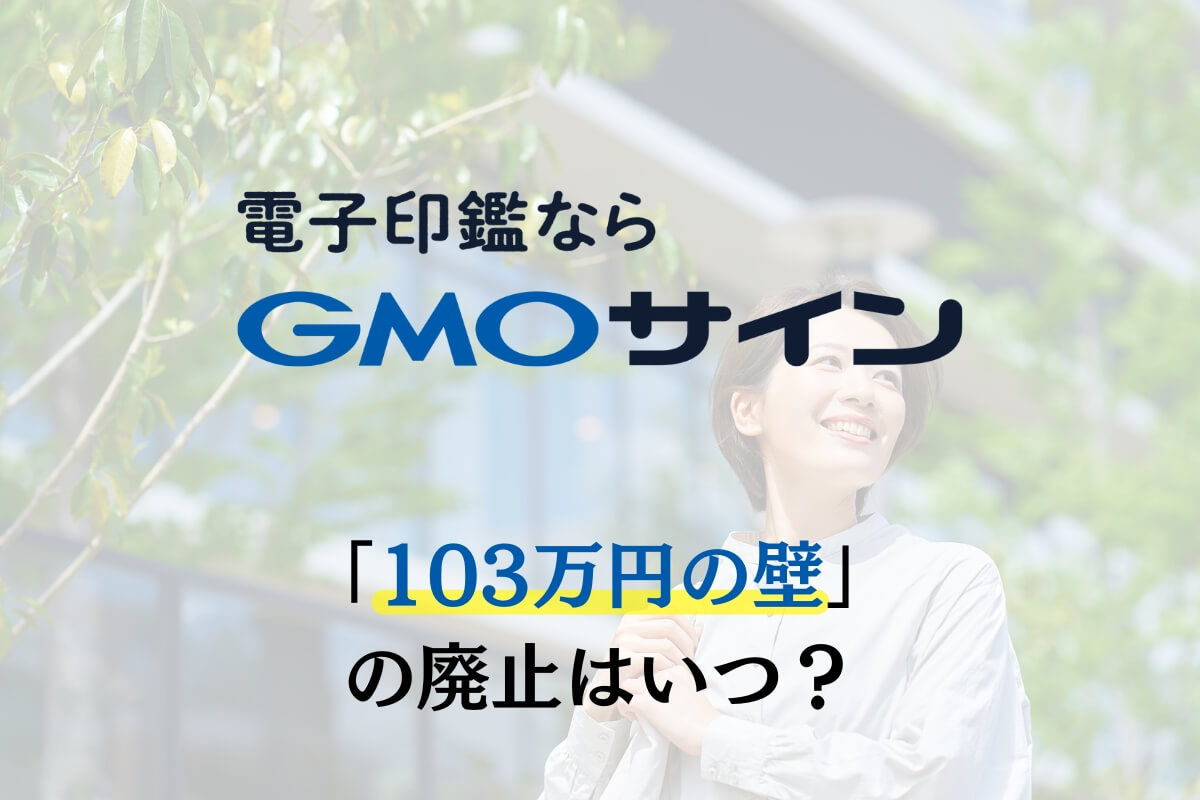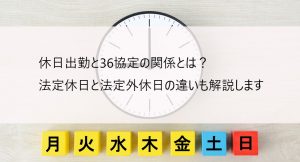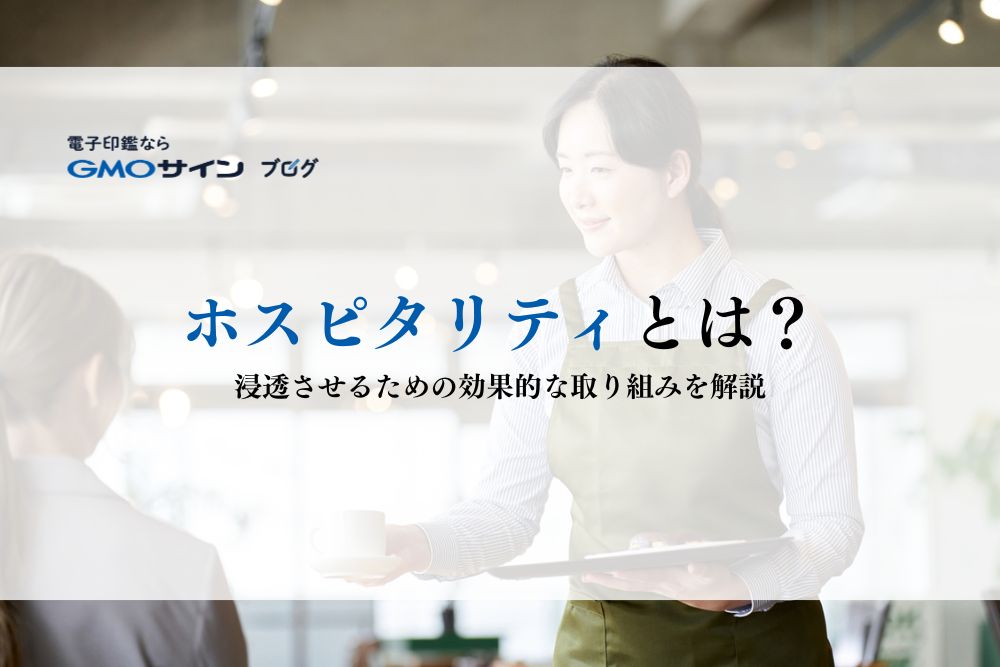日本のビジネスでは資本主義による競争原理によって、企業は良い製品を生み出したり生産性を向上させたりしています。しかし、自社が持つ技術や人材などのリソースだけでは十分な発展が望めないケースも存在します。
そこで注目されている方法が業務提携であり、それぞれの企業が持つ利点を活用しながらより一層のビジネス的発展を目指すために使われています。そこで本記事では、業務提携の概要や業務委託などの用語との違い、メリットやデメリットなどについてわかりやすく解説します。
目次
業務提携とは?
業務提携とは、異なる企業間で協力し合う取り組みを指します。それぞれの企業が持つ技術・資源・知識を活用し、共同で事業に取り組むことで単独では達成できない目標の達成を目指します。
業務提携では、情報や技術、リソースを共有してそれぞれの企業が得意な分野で協力することでシナジー効果を生み出します。このシナジー効果によって、企業はより大きな目標達成や新たなビジネスチャンスの創出を図れるようになるのです。
業務提携と業務委託の違い
業務提携と業務委託の大きな違いは、パートナー企業との関係性や目指す成果など
業務提携と業務委託は、いずれも企業間で行われる方法ですが、その内容や意図は大きく異なります。それぞれの特徴を理解することで、企業が適切なビジネス戦略を立てる際の参考になるでしょう。
業務提携と業務委託の大きな違いは、パートナー企業との関係性や目指す成果などの点です。
業務提携では、それぞれの企業がパートナーとして協力し、新しい価値を創造していく関係が構築されます。
一方、業務委託では業務を依頼する側と受ける側の間に発注者と受注者という関係が構築されるため、明確な上下関係が存在します。また発注者の業務を受注者が完遂することが目的であり、それ以上の成果は期待されません。
あわせて読みたい
業務委託契約書とは?収入印紙は必要なの?記載すべき内容や作成時の注意点を解説!よくある質問もご紹介
ビジネスでよく目にする契約書のひとつに「業務委託契約書」があります。この契約書は、仕事を依頼する、または請け負う場合に取り交わすものです。ただし、記載される...
業務提携と資本提携、M&Aの違い
業務提携と資本提携、M&Aは経営独立性の視点で区別できる
業務提携と資本提携、M&Aはどれも企業間のパートナーシップの関係を意味しますが、これらの用語は経営独立性の視点で区別できます。
業務提携は企業間の協力を表す用語で、それぞれの企業は経営独立性を維持します。
一方資本提携では、お互いの企業がある程度経営に対する影響力を獲得しますが、経営が完全に統合されるケースは該当しません。
またM&Aでは、買収される企業で経営独立性が失われるため、一般的に一つの企業として完全に統合されます。
業務提携の種類について
業務提携には様々な種類がありますので、それぞれの特徴について詳しく解説します。
販売提携
販売提携とは、企業間での商品やサービスの販売に関する業務提携です。一般的には、他の企業の製品やサービスを自社の販売チャネルを通じて販売する方法で行われます。そのため、それぞれの企業は売上の増加や新たな市場への開拓を期待できるのです。
技術提携
技術提携とは、一方の企業が他方の企業に自社の技術を提供し、共同で製品開発やサービスの改善などを行う業務提携です。双方の企業は新しい技術や知識を得られますので、製品の品質向上やビジネスの効率化が期待できます。
生産提携
生産提携とは、複数の企業が共同で生産活動を行う業務提携を指します。主に自社製品の製造過程の一部を他社に委託して、製造能力を補強する目的で行われます。
その他の提携
業務提携には他にも多くの形式があり、ご紹介した方法以外にも様々な種類があります。
例えば、以下のような種類があります。
調達提携
製品や原材料の調達に関する活動を共同で行う業務提携
流通提携
企業が製品やサービスの販売・配送など、流通に関する業務を共同で行う業務提携
包括提携
複数の業務領域にわたる提携であり、企業間で多面的に協力して効率的な業務運営と利益最大化を目指す業務提携
業務提携のメリット
業務提携には、主に以下のメリットが挙げられます。
スクロールできます
| リソースの共有 | 業務提携によって知識・技術・人材など企業が持っている資源を共有することで、自社だけでは獲得が難しいリソースを活用できるようになります |
| リスク分散 | 新規事業の展開や技術開発といったリスクを伴う活動を行う際に、提携すればリスクを分散できます |
| 市場進出の加速 | 提携先がすでに展開している市場や顧客ネットワークを共有することで、新規市場への進出をスムーズに行えるようになります |
| 競争力の強化 | 提携企業との協力によって、より効率的な業務運営や製品開発・サービス改善などを行って競争力を強化します |
| コスト削減 | 設備などを共同で利用することで、コストを削減できます |
業務提携のデメリット
業務提携には多くのメリットがありますが、注意すべきデメリットも存在します。業務提携がうまく機能しないと、企業にとって大きな損失となりかねませんので、以下のようなデメリットに注意しましょう。
スクロールできます
| 情報流出のリスク | 提携により相手方と情報を共有することで、自社の知識や技術が第三者に漏れる恐れがあります |
| 目標の不一致 | 提携企業間でビジネスの目標や価値観が一致しない場合、業務提携はうまく進行しなくなるでしょう |
| コミュニケーションの問題 | 企業間で文化や組織体制の違いなどによるコミュニケーションの問題が発生すると、逆に業務提携がマイナスに作用する恐れがあります |
業務提携契約の進め方
一般的に、業務提携は以下の手順で進めます。
STEP
提携パートナーの選定
まず提携する企業を選定する際には、共有する目標・価値観・事業展望などが一致しているかどうかを慎重に評価することが大切です
STEP
提携内容の議論・決定
提携によるメリット・提供するリソース・役割分担など詳細な事項について、共通の理解を得ることが重要です。もし提携によるビジョンが一致していないと、失敗で終わる可能性が高くなってしまいます
STEP
契約書の作成
契約書では、業務提携の目的・期間・役割分担・財務条件・機密保持・契約終了時の手続きなど、具体的な取り決めを明記します
STEP
リーガルチェック
法律の専門家によるチェックによって、法的な問題や不明確な点をクリアします
STEP
契約締結
契約書に双方の代表者が署名・押印すれば、正式に業務提携がスタートします
業務提携契約時の注意点
業務提携契約書を締結には、提携の内容を明確に記載することが大切です。具体的には、「業務提携の目的は何か」「どんな役割をどのように分けるのか」「収益や費用をどう分配するのか」「作った商品や知識をどう使うのか」などをできる限り詳細に記載しましょう。また、より法的な安全性を担保するために、契約書の内容を弁護士などの法律の専門家にリーガルチェックを行ってもらうことをおすすめします。
業務提携の成功事例
業務提携の成功事例として、2022年に実施されたリコーとサイボウズの業務提携をご紹介します。リコーとサイボウズは国内外での伴走型サポートによるDX加速を目的として、デジタルサービス事業に関する業務提携を締結しました。
この業務提携によって、「kintone」をベースにリコーとサイボウズが共同開発した「RICOH kintone plus」を国内市場向けに2022年10月から提供しています。またグローバルでの展開も見据えていると考えられますので、より広がっていくことが期待されています。
本件事例は、リコーが持つ日本や海外における顧客基盤とサイボウズのローコード・ノーコードの開発力を組み合わせて成功した業務提携といえます。
【参考】サイボウズ株式会社「リコー、サイボウズと資本提携契約を締結」
業務提携をうまく利用して、ビジネスの発展につなげましょう!
業務提携を利用すれば、それぞれの企業が持つ強みを合わせてシナジー効果による効率的なビジネス的成長が期待できます。しかし、情報流出のリスクや目標の不一致といったデメリットもある点には気をつけましょう。
また契約書を作成する際には、業務提携の目的から契約終了時の手続きまで記載しなければなりません。業務提携は終了後まで見据えておかないと、トラブルに発展する恐れがあります。
そのため、不明な点がある場合は弁護士などの法律の専門家に相談しましょう。できれば提携する業務に詳しい専門家にリーガルチェックしてもらえば、より確実性が高いのでおすすめです。