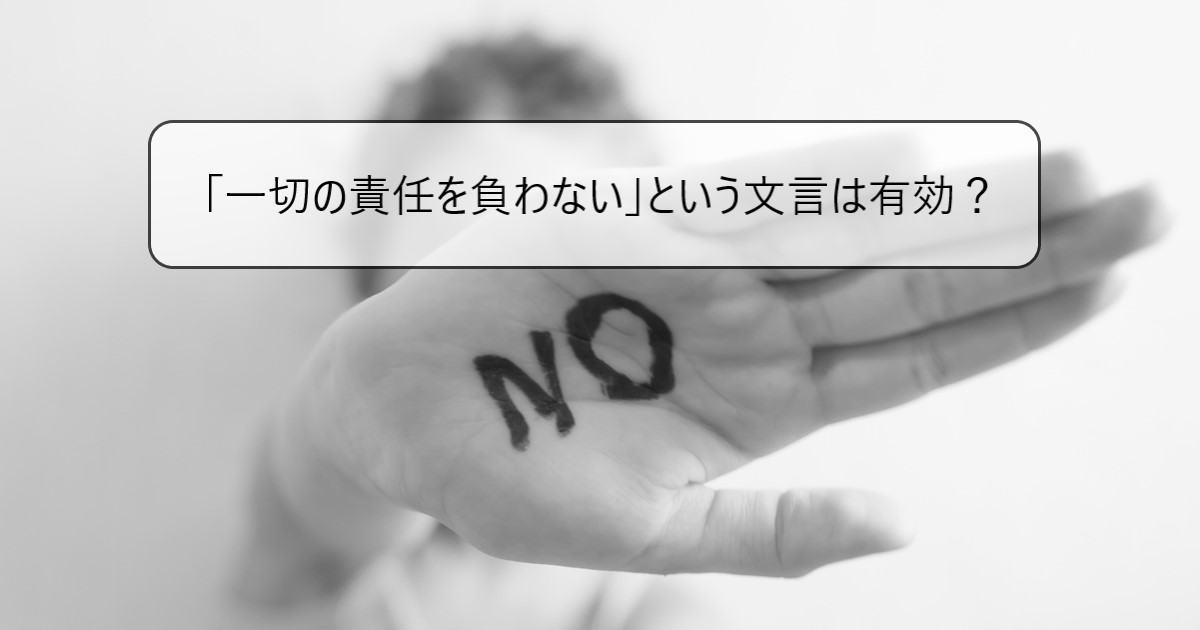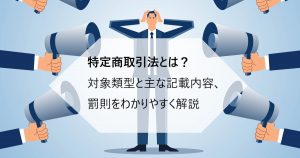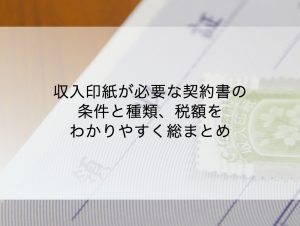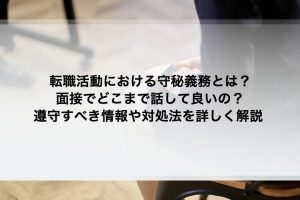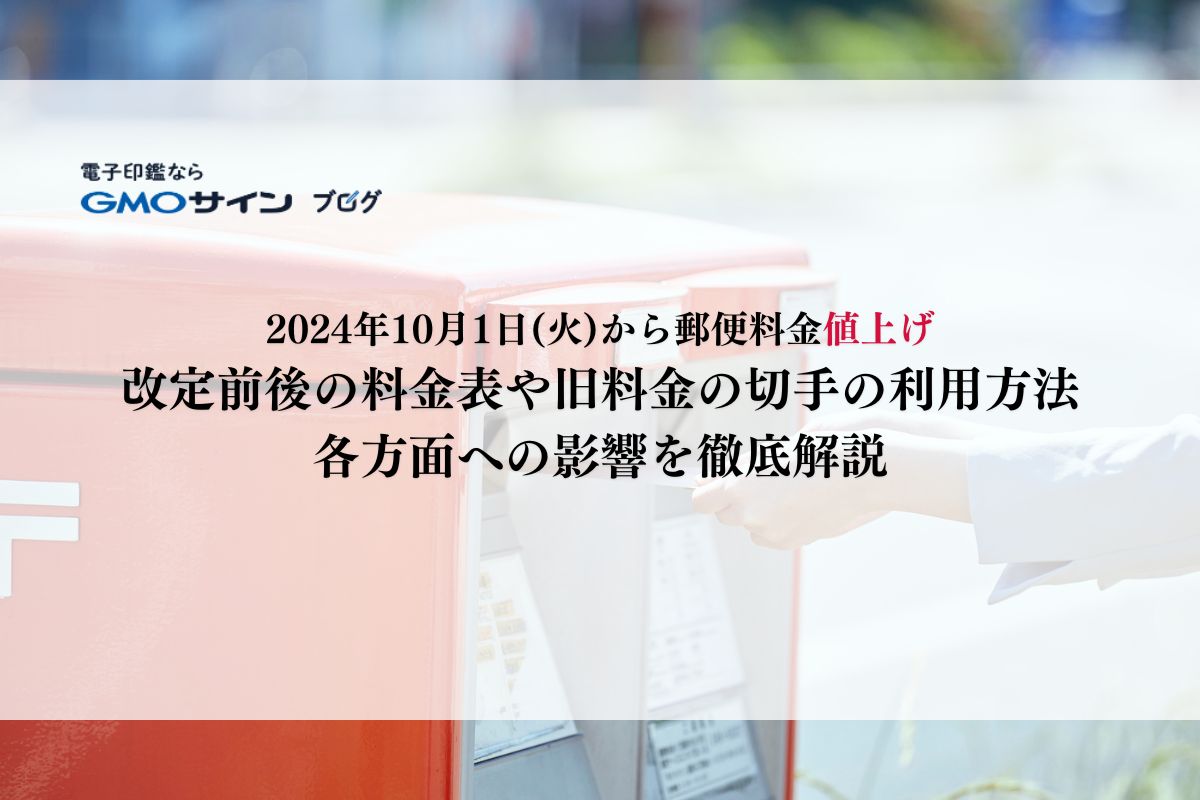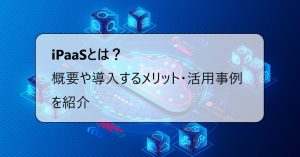「一切の責任を負わない」という文言を見かけたことがある人も多いのではないでしょう。このような文言は、利用規約などに記載する免責事項に該当します。
しかし、免責事項を記載さえしていれば、事業者はすべてのトラブルの責任を回避できるのでしょうか。そこで本記事では、免責事項を記載する上で注意すべき点や適切な免責事項の例文について詳しく解説します。
目次
「一切の責任を負わない」という文言の効力について
公共施設や駐車場等の利用規約や看板で、「一切責任を負いません」「一切の責任を負いかねます」といった文言を見かけたことがある人も多いでしょう。しかし、このような事業者の責任を認めない文言は有効なのでしょうか?
結論からお伝えしますと、あらゆるトラブルにおいて事業者はすべての責任を負わない利用規約などにおける文言は無効です。なぜなら、利用者に落ち度がないにも関わらず、事業者の過失で重大な事故や損害が発生した場合でも、一方的に利用者側が不利益を被る恐れがあるためです。
なぜ責任を負わない利用規約が一般的に使われているのか?
しかし、なぜそのような文言が記載された利用規約がよく使われているのでしょうか。その理由は万が一トラブルが発生した際に、事業者が必要以上の賠償責任を負う事態を回避するためだと考えられます。
また利用規約に記載しておけば、善管注意義務などに配慮している事業者は責任を負わずにすむ可能性があり、さらに利用者に対する注意喚起としての役割も果たします。
免責事項を用いる際の注意点
「一切の責任を負わない」という免責事項を利用規約などに記載するメリットはありますが、注意すべき点も存在します。具体的な内容をご紹介しましょう。
規定自体が無効になるケースがある
利用規約などの規定に「一切の責任を負わない」旨の免責事項が記載されている場合、規程自体が無効になるケースがあります。利用規約への同意は、事業者と利用者との「消費者契約」に該当します。
そのため、消費者が一方的に不利になるような契約は消費者契約法で保護されている消費者の権利を害する恐れがあるため、このような規定は無効となりうるのです。
適格消費者団体とのやり取りが公開される
次に無効となった場合の当該事業者の取り扱いについて見ていきましょう。具体的には、適格消費者団体(不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人)が、事業者に対して差止請求を行います。
また企業名と実際に企業側に発せられた請求文書をインターネット上に公開され、消費者被害の防止の観点から情報提供措置が実施されます。SNSが普及している現代では、事業者の社会的信用に関わりかねないため、注意が必要と言えるでしょう。
消費者保護に関わる法令について
基本的には事業者よりも消費者を保護する法令が多く施行されています。そこで代表的な法令を2つお伝えします。
消費者契約法
消費者契約法とは、事業者と消費者間の契約において事業者より知識や経験が劣る消費者が不利な契約を締結しない、あるいは締結してしまった後に取り消しや無効にできるよう定められた消費者を守るための法律です。消費者の権利を幅広く保護している内容のため、汎用性が高い点が特徴です。
民法における「定型約款」
定型約款とは、令和2年4月1日の民法改正において規定された利用者を保護するための新しい制度です。具体的には、以下のように定義されています。
① ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、
② 内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの
を「定型取引」と定義した上、この定型取引において、
③ 契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体
【参考】約款(定型約款)に関する規定の新設
一般的に鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款が該当し、インターネットサイトの利用規約も定型約款に当てはまります。定型約款の規制には、「利用者側の利益を一方的に害する契約内容に関しては合意したとみなされない」といった内容が含まれています。
そのため、定型約款に該当する利用規約において不当な免責事項が使われている場合は、無効と扱われるのです。
適切な免責事項の例文
 Contract Signing Concept, closeup
Contract Signing Concept, closeup
現代の法律は消費者保護の傾向にあるため、有効となる事業者の免責事項を作成するのは難しいでしょう。そこで、適切な免責事項の具体的な例文をご紹介します。
消費者に対して直接商品やサービスを提供している場合
事業者が消費者に対して直接商品やサービスを提供するケースでは、以下のポイントが重要です。
・事業者に故意または重過失がない
・善管注意義務に対して十分に配慮している
具体的には、以下のような免責事項の例文が考えられます。
『当社は、施設内で発生した事故について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。』
消費者契約法では、事業者の故意または重大な過失によって消費者に損害が発生した場合、事業者の責任(の一部)を免除する条項は無効になると定めています(8条1項)。そのため、事業者に故意または重過失がないことを定める点が重要と言えます。
また免責事項には記載しませんが、事業者は普段からトラブルが起こらないように十分な対策を講じている点も必要です。免責事項を定めていても、善管注意義務を果たしていなければ損害賠償請求が成立する可能性が高いので、事業を行っている場所をきちんと管理しておく必要があります。
事業者が利用者に直接関わらない場合
web上で利用者同士が使うサービスを提供している事業者では、問い合わせなどを除いて利用者に直接関わらないケースが一般的です。そのような場合には、以下のような免責事項の例文が考えられます。
『本サービスの利用によって、お客様及び第三者に生じた損害においては、当社の故意又は過失に起因する場合を除き、当社は責任を負わないものとします。』
また古い情報が残っている場合もあるので、情報の正確性を保証しない条項を付け加えておくことをおすすめします。
法律に違反しない免責事項を作成しましょう
本記事では、「一切の責任を負わない」免責事項に関して、注意点や例文などを解説しました。トラブルを未然に防ぐためには、消費者契約法や民法の定型約款の内容を正しく理解して、事業者と消費者どちらにも不利益とならないようバランスのとれた免責事項を作成しましょう。
電子契約なら「電子印鑑GMOサイン」が便利!
免責事項を盛り込んだ契約書を作成する際は、難しい手続き不要でスムーズに契約が締結できる電子契約がおすすめ。課税文書に必要な印紙が不要でコストも削減でき、すべてインターネット上で契約が完結できます。
詳しくは、「3分で分かるGMOサイン」という資料をご用意しておりますので、ダウンロードしてみてください。