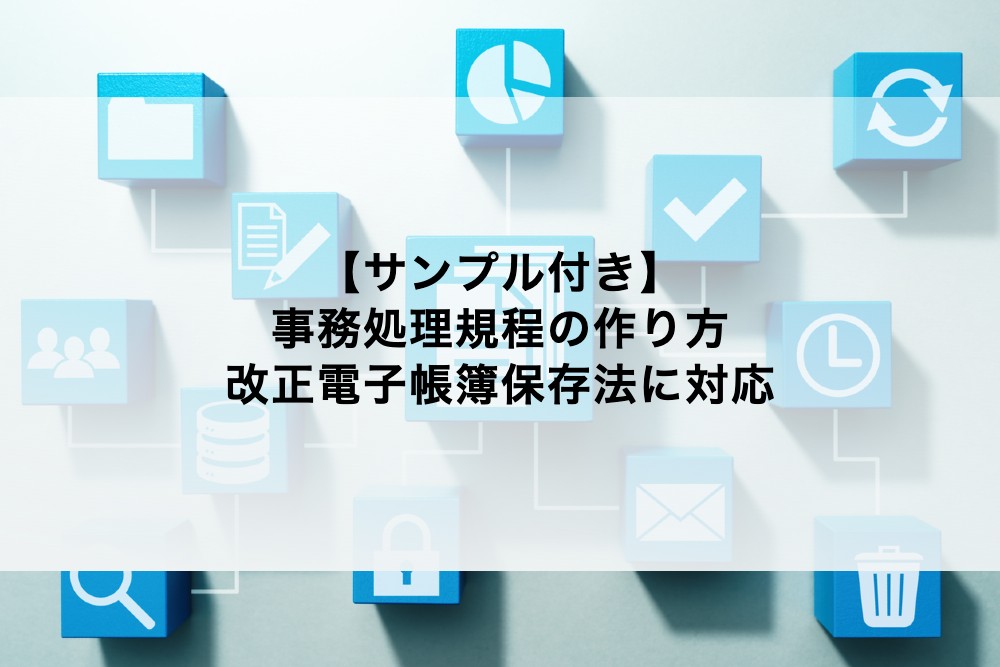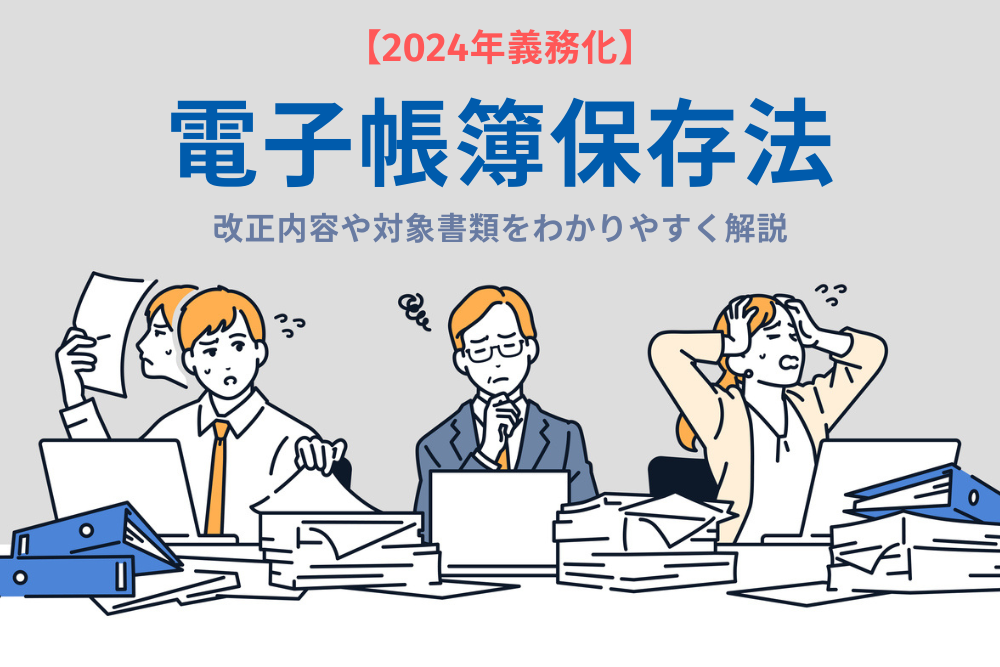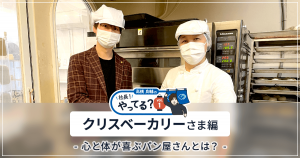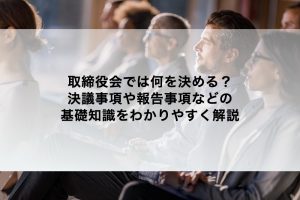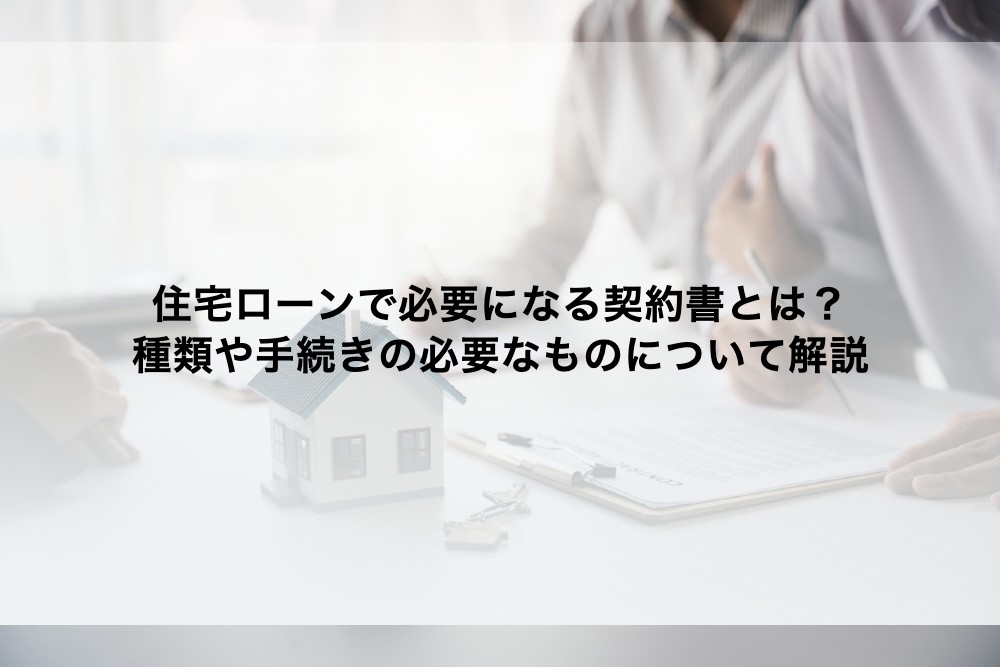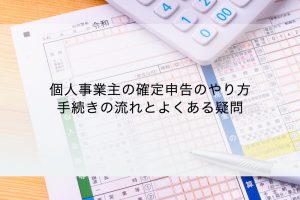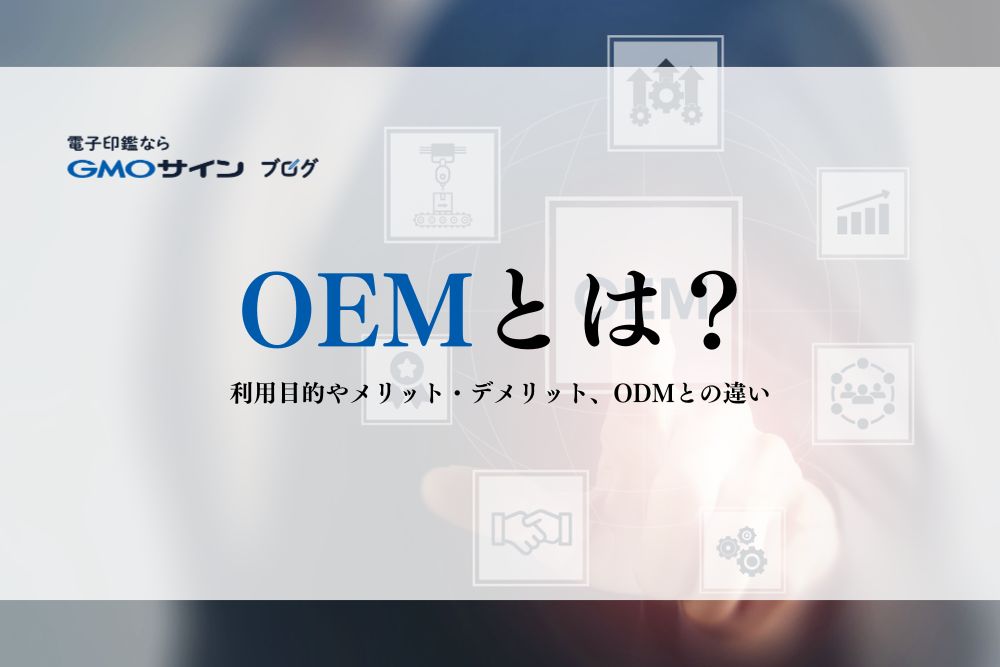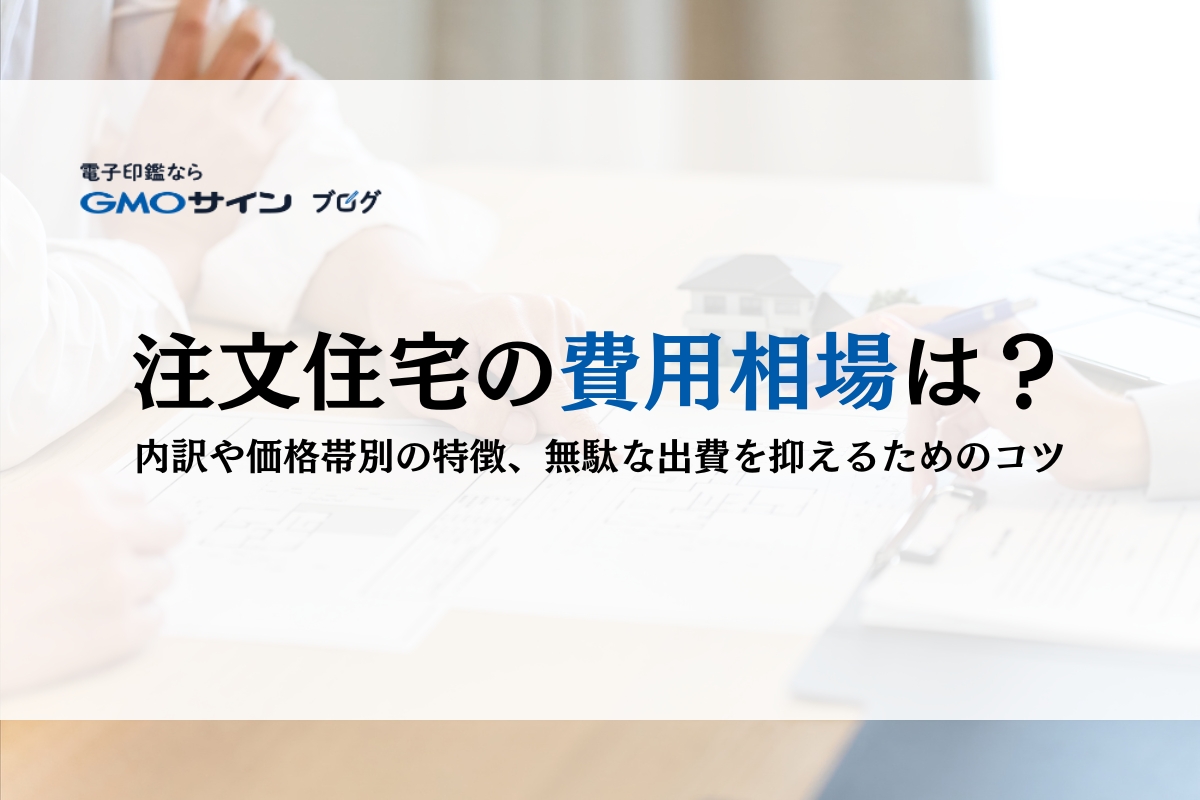事務処理規程とは、電子取引データや電子帳簿、スキャナ保存したデータなどを電子帳簿保存法に則って保存するために企業が定める規程を指します。
本記事では、事務処理規程の概要や作成するメリット、具体的な作り方などを紹介します。事務処理規程を作成しておけば、電子取引データなどの保存ができるだけでなく、業務効率化などにもつなげられます。事務処理規程の作成を検討している企業の担当者はぜひ参考にしてください。

電子帳簿保存法まるわかりガイド
電子帳簿保存法について詳しく知りたい方におすすめ!
目次
事務処理規程とは?
事務処理規程とは、電子取引データや電子帳簿、スキャナを使って保存したデータなどを電子帳簿保存法に則って保存するために企業で定める規程を指します。
全ての企業で必要であるわけではありませんが、条件次第では作成が求められるため、どのようなものなのか理解しておくことが大切です。また電子データの意図的な訂正や削除を防ぐためにも、社内で規程を遵守することが求められます。
事務処理規程を作成するメリット
事務処理規程の作成には、企業にとってさまざまなメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。
業務効率化につながる
事務処理規程を作成しておけば、電子データ化する際の責任者と保存対象となるデータが明確になります。そのため万が一トラブルが発生したとしても、誰が責任者でどのデータがトラブルの原因になっているのかといったことがすぐにわかるため、スムーズに対応できて業務効率化につながります。
また保存対象となるデータが明確化されていれば、対象外のデータを電子化してしまうといったミスも防止できます。
判断の指針になる
事務処理規程は、電子データを保存する際に企業が遵守すべきルールであるため、データを扱う際の判断基準にもなります。電子帳簿保存法では、国税関係帳簿や国税関係書類といった国税関係帳簿書類のほか、電子取引データが法律の対象となりますが、中には対象なのかどうか判断に迷ってしまうものもあります。
そのような場合に事務処理規程があれば、規程に沿って作業を行えるため迷う場面も少なくなるでしょう。また業務マニュアルを事務処理規程にあわせて記載しておけば、さらに業務を進めやすくなります。
ルールが明確化される
事務処理規程があればルールが明確化されるため、業務の手順やノウハウなども伝えやすくなります。企業では、異動に伴い人材が入れ替わる時期や新入社員が入社してくる時期には、業務手順やノウハウを説明する必要があります。
そのような時に事務処理規程を作成しておけば、手順やノウハウをスムーズに伝えられるでしょう。また事務処理規程に基づいて業務を進めていれば、業務の属人化を防ぐこともできます。
あわせて読みたい
【2024年義務化】電子帳簿保存法の対象書類や保存要件、最新改正内容をわかりやすく解説
2023年12月31日で電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)措置が終了し、2024年1月からはついに電子帳簿保存法の本格的な運用が始まりました。たとえば、これまではメールで受...
事務処理規程の作り方
次に事務処理規程の作り方を解説します。テンプレートを活用すれば比較的簡単に作成できるため、ぜひ参考にしてください。
事務処理規程のテンプレートを参考にする
事務処理規程に関しては、国税庁が「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」としてテンプレートを公開しています。
以下のリンクから法人のテンプレートと個人事業主のテンプレートをダウンロードできますので、必要な場合はぜひご利用ください。
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁
事務処理規程に記載すべき内容を確認する
国税庁が公開している事務処理規程のテンプレートは、企業によってはそのまま自社の規程として使えないケースもあります。そのため内容をチェックして、適宜自社にあった修正を行いましょう。
事務処理規程作成時のポイント
事務処理規程を作成する際には、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。そこで具体的なポイントを紹介します。
タイトル
国税庁が公開しているテンプレートでは、タイトルが「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」となっていますが、この通りでなければならないわけではありません。お勤めの企業でタイトルの付け方にルールやマナーなどがある場合は、それらに沿ってタイトルを変更しても問題ありません。
電子取引の範囲
事務処理規程を作成する際は、電子取引の範囲を過不足なく明確にしておきましょう。国税庁のテンプレートにも電子取引の範囲は記載されていますが、あくまでもテンプレートであるため最小限の範囲で記載されています。そのため自社の実態に応じて電子取引の範囲を全て洗い出し、記載するようにしましょう。
近年であれば、特に以下のようなケースがよく見られるため参考にしてください。
- ECサイトで商品を購入した際の明細や領収書などの受領
- 出張・外出の際に利用した交通機関・宿泊費などの明細や領収書の受領
- クレジットカード決済時の明細の授受
- ICカード決済時の明細の授受
- Webやアプリなどの決済サービスで決済した際の明細の授受
取引データの保存期間
取引データの保存期間も明確にしておく必要があります。基本的には紙の文書の保存期間に合わせて設定するのが一般的であり、7~10年に定めている企業が多いです。
なお、個人事業主の場合には保存期間が5年の文書もあり、また白色申告と青色申告で保存期間が異なるため注意しましょう。
対象となるデータ
規程の対象となるデータを特定しておく必要もあります。国税庁のテンプレートにもいくつかの例が記載されていますが、自社にあわせて修正しましょう。企業によっては、請求情報や検収情報などが必要になる場合もあります。
改正電子帳簿保存法で事務処理規程が必要になるケース
2022年1月に改正された電子帳簿保存法によって、これまで事務処理規程が必要なかった書類でも新しく規程が必要になるケースが出てきています。そこで具体的にどのような書類が対象になるのか解説します。
あわせて読みたい
【2024年義務化】電子帳簿保存法の対象書類や保存要件、最新改正内容をわかりやすく解説
2023年12月31日で電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)措置が終了し、2024年1月からはついに電子帳簿保存法の本格的な運用が始まりました。たとえば、これまではメールで受...
2022年1月1日以前の書類のスキャナ保存
2022年1月1日より前に作成された書類をスキャンして電子データとして保存する場合、事務処理規程が必要です。ただし、2022年1月1日以降に作成された書類をスキャナ保存する場合、事務処理規程は不要となります。
スキャナ保存できる書類には領収書や納品書など、普段の業務で使用する頻度の高い書類も含まれるため、保存する際には抜け漏れがないか入念に確認しておきましょう。
真実性の要件を満たさない場合の電子データ保存
2024年1月からは電子取引の電子保存が義務化されます。そのため、保存に当たっては以下の要件をそれぞれ満たしておく必要があります。
可視性の要件とは、取引年月日や勘定科目、取引金額といった記録項目を検索できるようになっている状態であることです。具体的には以下の条件を満たす必要があります。
- 電子データの保存場所に出力機器とマニュアルを備え付けて、明瞭な形式で出力できるようにしておくこと
- 電子計算システムの概要を備え付けていること
- 検索機能を確保しておくこと
また真実性の要件とは、電子取引の情報に訂正や削除といった加工を加えていない、もしくは加えた時に記録が残るようにしている状態であることです。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- タイムスタンプが付けられた後に取引情報の授受を行う
- 取引情報を授受した後に速やかにタイムスタンプを付けて保存する
- データの訂正削除が不可もしくは訂正削除の履歴が残るシステムを使って、データの授受・保存を行う
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程を作成して規程に沿った運用を行う
可視性の要件については全ての条件を満たしておく必要がありますが、真実性の要件ではいずれかの条件を1つ以上満たしておけば問題ありません。
電子取引データの保存には事務処理規程を用意
本記事では事務処理規程の概要やメリット、作り方などを紹介しました。事務処理規程は、電子取引データや電子帳簿などを電子帳簿保存法に則って保存するために企業で定める規程です。事務処理規程を作成すれば、業務効率化やルールの明確化などにつながるな、企業にとってのメリットは少なくありません。また国税庁がテンプレートを公開しているため、テンプレートを利用すれば作りやすいでしょう。
電子取引データなどの保存には、事務処理規程の作成だけでなく、電子契約サービスの利用もおすすめです。電子印鑑GMOサインは、クラウド型の電子契約サービスであり、電子帳簿保存法にも対応しています。250万以上の企業で導入されており、豊富な実績があります。無料トライアルもお使いいただけるため、スムーズな電子取引データの保存に興味のある担当者はぜひ一度お問い合わせくさい。

電子帳簿保存法まるわかりガイド
電子帳簿保存法について詳しく知りたい方におすすめ!