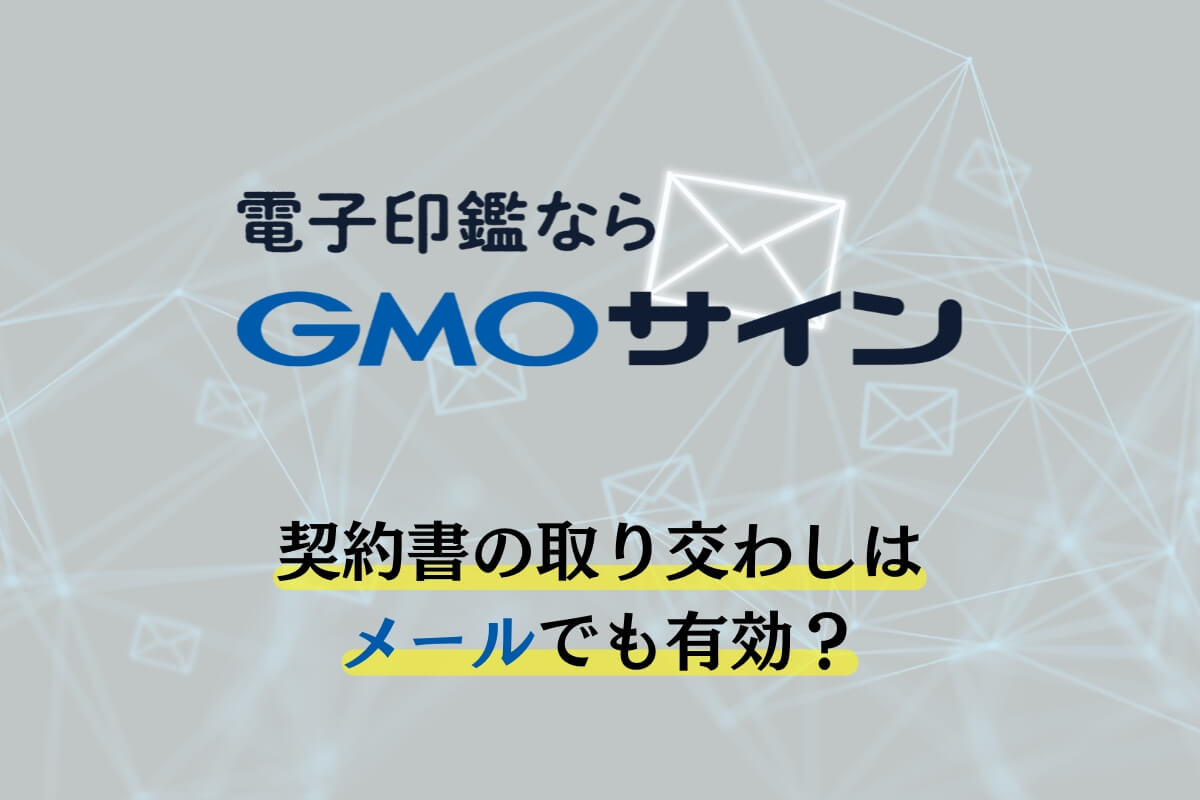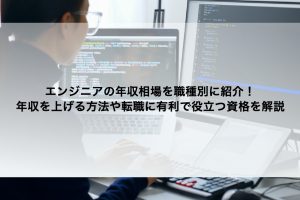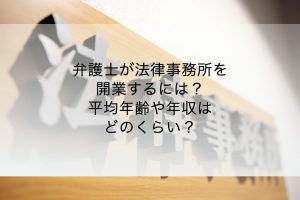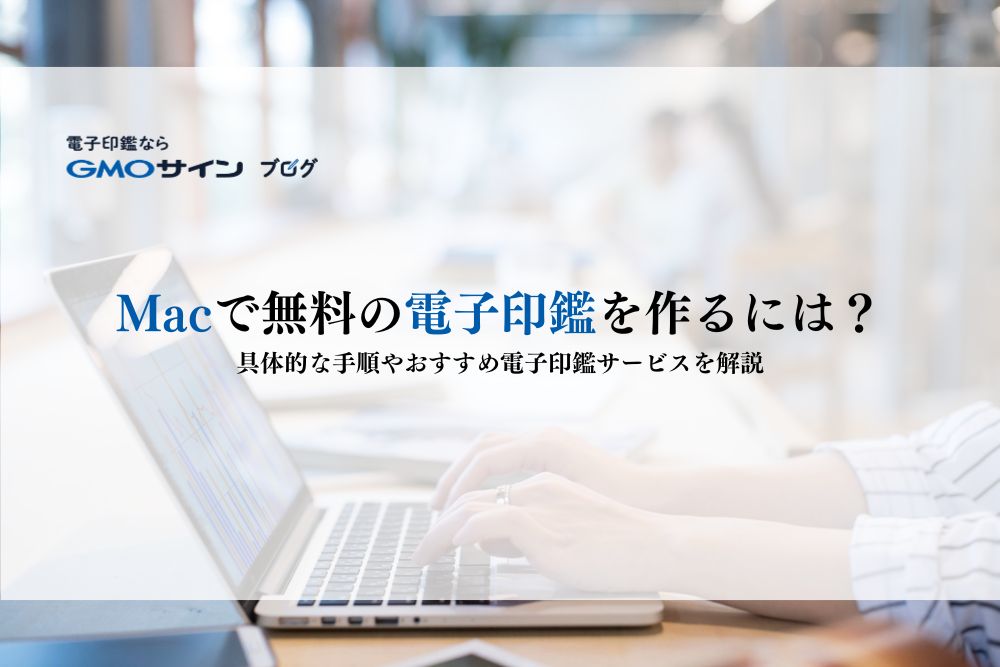賃貸契約する際に不動産会社から案内される火災保険への加入は、借主にとって義務ではありません。
しかし、火災保険への加入を必須とする賃貸物件が多いので、結果的に加入することがほとんどです。また、法律的に加入が任意だからといって、大家さんが費用を支払うことはなく、自分で支払う必要があります。
そのためよく検討せずに火災保険に加入すると、無駄な料金を支払うことになってしまうケースも。
賃貸物件向けの火災保険を安く済ませるためには、自分に必要な補償を理解しておくことが大切です。
本記事では、火災保険の基礎知識から料金相場、選び方などを解説します。
目次
火災保険とは
火災保険とは、生活基盤である「建物」と「家財」に損害が生じた場合のリスクに備えるための保険です。火災保険といいますが、多くの場合、火災のほかに落雷や破裂・爆発などの被害もカバーします。
一方で、地震、噴火、津波を起因とした損害は補償されず、これらのリスクに備えるには別途、地震保険へ加入することが必要です。
具体的な補償内容は保険会社によって異なり、風災や雪災、水災、盗難を補償するものもあります。また、火災保険は賃貸物件向けや一軒家向けなど、住まいによってそれぞれ用意されています。
賃貸物件向けの火災保険の種類
火災保険には基本的に3つの種類があり、それぞれ補償範囲が異なります。まずは、火災保険の種類とその補償内容について確認していきましょう。
住宅火災保険
1つ目にご紹介する賃貸の火災保険は、住宅火災保険です。火災保険のなかで最も基本的な保険である住宅火災保険の具体的な補償の範囲は以下の通りです。
・過失による火事
・もらい火
・ガスの爆発
・落雷
・雪崩やひょうなどの雪災
・台風や竜巻
一方で、水漏れや洪水、盗難などの被害への補償はありません。住宅火災保険は、主に火災と天災を対象とした保険といえます。
住宅総合火災保険
2つ目にご紹介する賃貸物件向け火災保険は住宅総合火災保険です。前述の住宅火災保険と混同されやすいですが、補償の範囲がより広いのが住宅総合火災保険となります。
前述の住宅火災保険の補償内容に加え、以下の補償が可能です。
・洪水
・高潮
・土砂崩れ
・航空機の墜落
・自動車の衝突
・ボールや石の投げ込み
・水道管の水漏れ
・盗難
・デモなどによる破壊行動
上記の通り、住宅総合火災保険はより充実した補償内容となっています。
住宅総合保険ワイド保険
賃貸物件向けの火災保険3つ目は、住宅総合保険ワイドです。火災保険の中でも最上位クラスとして位置付けられ、住宅火災保険や住宅総合火災保険ではカバーしきれないさまざまなリスクに備えるための保険です。
その内容は保険会社によって異なり、保証が従実している分、料金も高額になります。
補償内容の一例は以下の通りです。
・家財や住宅設備の修理費用
・家主や第三者に対する損害賠償
・入居者が亡くなった際の遺品整理や清掃費用
もちろん、火災や天災、水漏れ、破壊行為による破損などは補償の範囲内となります。
賃貸の借主が負う2つの義務とは?
賃貸住宅の借主には、善管注意義務と原状回復義務という2つの義務があります。
火災保険への加入は義務ではありませんが、これら2つの義務を理解することで、火災保険の重要性が理解できます。
善管注意義務
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」の略称であり、民法第400条に規定された義務のことです。
同法では、賃貸借契約の借主は賃貸借契約終了後に賃貸物件を返還しなければならない義務を負っており、引き渡しが完了するまで善良な管理者として適切な注意を払って物件を管理することが規定されています。
つまり、借りていた物件が通常の使用よりも消耗や損傷が激しいときには、借主は善管注意義務に違反したとみなされ、損害を発生させたことになり、修理費用やその他の損害賠償を負担することになります。
原状回復義務
原状回復義務とは、賃貸借契約時点の状態に物件を回復させる義務のこと。善管注意義務と同様、民法621条に明記された義務です。
物件を元の状態に戻すとはいえ、生活していれば使用による傷や汚れは生じます。原状回復義務を負うケースは、故意や不注意、手入れの不足による汚したりした場合です。
家具を設置したことによるカーペットのへこみや家具の後ろの黒ずみなどは、通常消耗や経年変化とみなされ、原状回復義務は負いませんが、タバコによるヤニやカーペットへ飲み物をこぼし、その後放置したことによってカビが発生した場合などは、原状回復義務を負うこととなります。
火災保険の相場は?
火災保険の料金は、補償内容のほか、家屋の評価額や所在地、建物の構造や築年数によって変動します。例えば、東京都の鉄筋コンクリート構造の賃貸マンションの場合、年間で約4,000円〜10,000円の保険料となります。
補償内容は基本的な住宅火災保険と大きく変わりませんが、保険会社によって水まわりやガスのトラブル対応や弁護士相談費用、臨時宿泊費用が保証されるものもあります。事件・事故を引き起こしたり、巻き込まれたりした際に手厚いサポオートが受けたいという方は、付帯サービスについても確認するのがおすすめです。
賃貸の火災保険の補償範囲
賃貸の火災保険保証範囲は、大きく3つに分けられます。ここからは、火災保険を選ぶ際に知っておきたい保証範囲を表す3つの用語について解説していきます。
家財補償
火災保険の家財補償とは、電化製品や家具、衣類、食器類などの動かすことができる家財を補償するもの。
補償の対象となるもの
・電化製品や家具、衣類、食器類
・1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董等
補償の対象外となるもの
・トイレや浴槽、洗面器などの建物に付属しているもの
・自動車、バイク
・動物、植物
・現金・小切手・クレジットカード、電子マネー
・パソコン内のデータ
・仕事で扱う備品
なお、注意が必要なのが貴金属や宝石などの高額品です。
30万円を超える高額品については、補償を受けるために明記物件の申告が必要になるケースが多いです。補償の金額は保険会社によってさまざまなので、あらかじめ確認しておきましょう。
借家人賠償責任保険
借家人賠償責任保険とは、賃貸物件で事故が発生したときに、貸主である大家さんに対する損害を賠償するというもの。補償範囲は火災、破裂・爆発、水濡れを起こした場合のみです。
具体的には、タバコの火の消し忘れによる火災や、浴槽の蛇口を閉め忘れて水浸しになった場合に保証されます。一方で、自然災害や故意の損害は補償の対象外となります。例えば、フローリングにこぼした飲料を掃除せずに放置していたらカビが生えてしまった場合などに、故意と認められると補償の対象外となります。
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険とは、日常生活の中で他人に対して怪我を負わせたり、所有物を破損させたりした場合の損害を補償するものです。
賃貸物件の中で起きる事故のみならず、外出先などの広い範囲での事故を補償します。
例えば、自転車で他人に怪我をさせたり、飼い犬が他人に噛み付いてしまったりした場合など、身近な事故に対する保険です。火災保険に特約として追加することができるオプションです。すでに自動車保険や自転車保険などと一緒に契約している方も多いため、火災保険にオプションとして追加するかはよく確認しましょう。
賃貸で火災保険に加入しないとどうなる?
もし火災保険に入らないという選択をした場合には、以下のようなリスクが考えられます。
・退去時の原状回復は自己負担になる
・万が一のとき家財の損害は自己負担になる
・漏水での隣人への被害を負担する必要がある
・もらい火の損害が自己負担となる場合がある
このようなリスクがあると考えると、年間10,000円ほどで入れる賃貸住宅向けの火災保険は加入しておくべきでしょう。事件事故がなく、生活したとしても、退去時に原状回復の費用が請求され、大家さんとトラブルとなるケースも多くあります。
火災保険は、生活におけるさまざまなリスクに備えることができる保険なので、加入しておくのがおすすめです。
賃貸の火災保険を選ぶ際のポイント
賃貸住宅では必須となる火災保険選びに失敗は避けたいもの。しかし、火災保険は種類も多く、保険会社選びから一苦労を感じる方も多いのではないでしょうか。火災保険を選ぶ際のポイントをまとめました。
火災保険の補償範囲はどこも変わらない
火災保険の補償内容には、実は大きな差はありません。
そのため、火災保険を選ぶときには、補償内容よりも料金に注意するのがおすすめです。当然、料金が高くなれば、補償の範囲は広がりますが、その補償が本当に必要かどうかは確認したいところ。
例えば、川の近くに住む場合には、川の氾濫にも対応した補償を選ぶ必要がありますし、山間部に住むなら土砂崩れのリスクにも備えておきたいところです。自身が住むエリアがどのような災害リスクがあるかを調べるには、災害マップを活用するのがおすすめです。
万が一のときのサポート体制のチェック
火災保険を選ぶ際に注目したいのが、万が一のときのサポート体制です。火災保険では、保険会社によって弁護士相談費用のサポートや水道やガスのトラブルの対応などの付帯サービスの充実度が異なります。一方で、賃貸住宅の火災保険の場合は、弁護士費用や水道やガスのトラブルに対する補償が加わっても年間10,000円ほどで済むケースが多いです。
そのため、万が一のサービスを充実させたい方は、付帯サービスの充実度に注目して火災保険を選ぶのがおすすめです。
火災保険の契約期間は賃貸契約期間に合わせる
賃貸の火災保険の契約期間は1年から最長5年まで選択することが可能です。
火災保険料は契約期間が長くなるほど安く抑えられます。
契約期間は賃貸物件の契約期間に合わせて決めるのが基本です。また、長期契約後に途中解約した場合は、残りの補償期間に応じて解約返戻金が戻ってきます。解約返戻金の計算方法は契約によって変わり、日割りや月割り、短期率などと呼ばれる計算方法がありますので、保険契約時には、払い戻し返戻金についてもチェックしましょう。
地震保険への加入を検討する
火災保険で必ず注意しておきたいのが、地震保険への加入です。
火災保険では、地震による損壊や津波、火災に対する補償が適用されません。日本は地震が多い国なので、万が一に備えて地震保険への加入を検討するのがおすすめです。また、地震保険は火災保険に付帯するもので、地震保険単体で加入することはできない点は注意しましょう。
なお、火災保険にすでに加入している方も、後から地震保険を追加することができます。賃貸の火災保険を見直している方は、地震保険にも加入しておくのがおすすめです。
火災保険に加入する前に知っておくべきこと
最後に、火災保険に入る前に知っておきたいことについて解説します。
火災保険は不動産屋を経由して入る必要はない
まず、火災保険は不動産屋で賃貸住宅の契約時に加入する必要はありません。賃貸物件を借りる場合、不動産会社から火災保険を案内されることが一般的ですが、自分で探しても大丈夫です。しかし、火災保険は料金も補償内容も大きな差はないため、特別な理由がなければ不動産会社からの紹介による加入で問題ないでしょう。
住む地域のハザードマップを確認する
災害が多い日本ですが、住む地域によって発生リスクが異なります。国土交通省 国土地理院の「ハザードマップポータルサイト」を利用することで、賃貸物件を借りる予定の地域での災害リスクを把握することが可能です。河川の氾濫や大雨による水害の少ない地域であれば、水災補償を外すことで保険料金を安く抑えることもできます。
賃貸住宅の火災保険は加入しよう!補償内容や料金はそれほど変わらない
今回は、賃貸住宅の火災保険について解説しました。
火災保険への加入は義務ではないものの、万が一のために加入を必須としている賃貸物件がほとんどです。火災保険はさまざまな種類があり、一見複雑そうですが、補償内容はどの保険会社も似たり寄ったりといったところ。
料金は高くて年間10,000円が相場となっており、家計への負担も少ないといえます。また、30万円を超える貴金属などの高額品に対する明記物件の申告は忘れずに行いましょう。
大切な資産を守るためにも、火災保険への加入をしておくことをおすすめします。