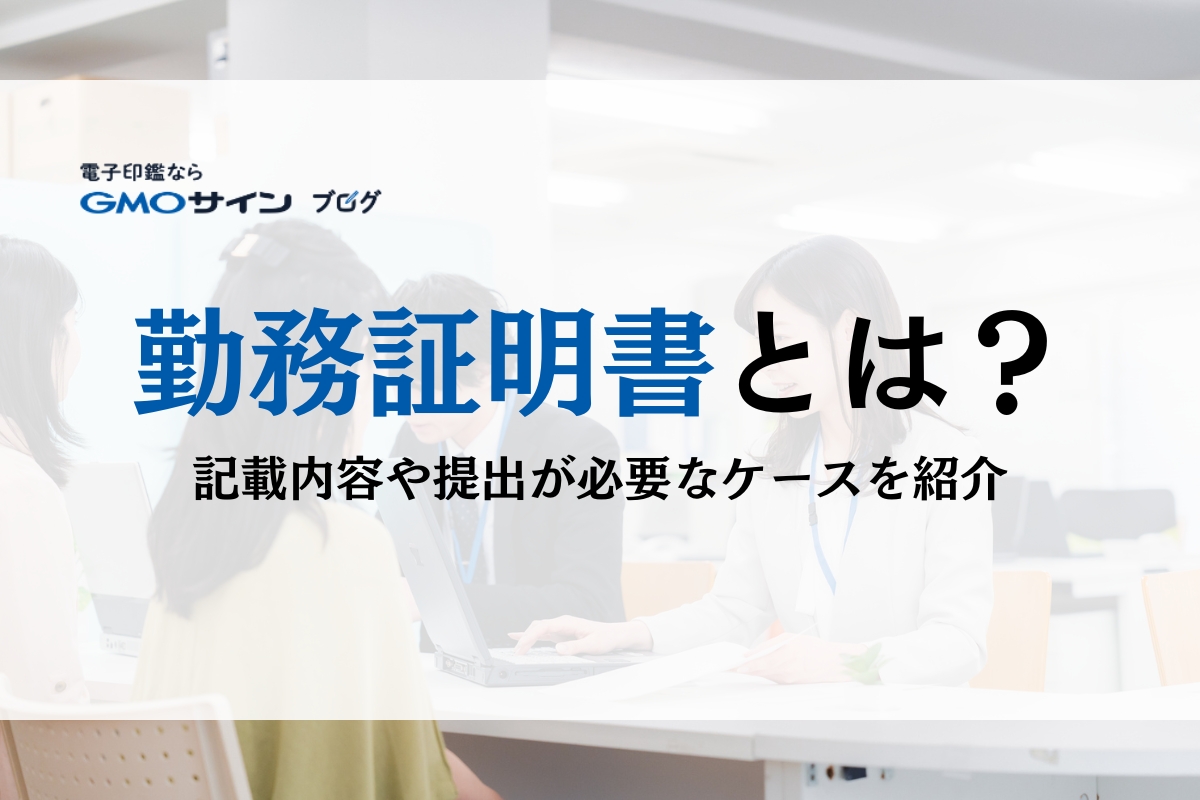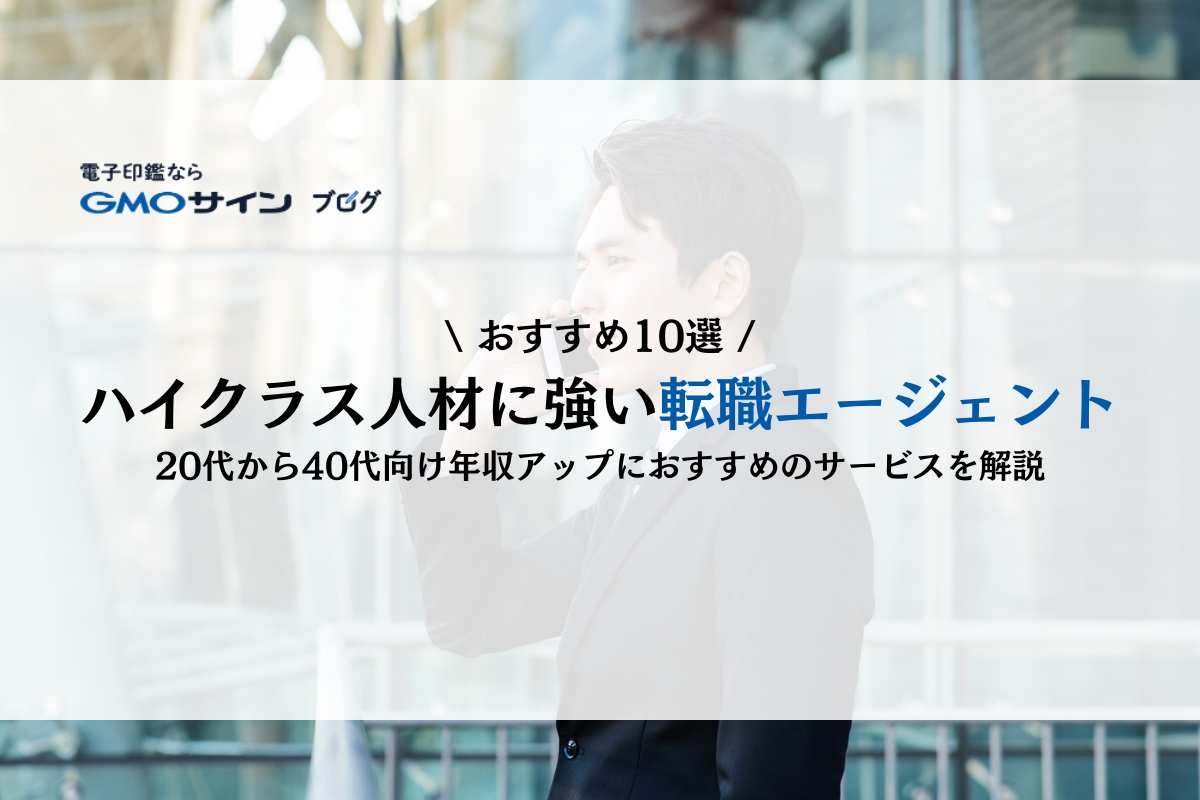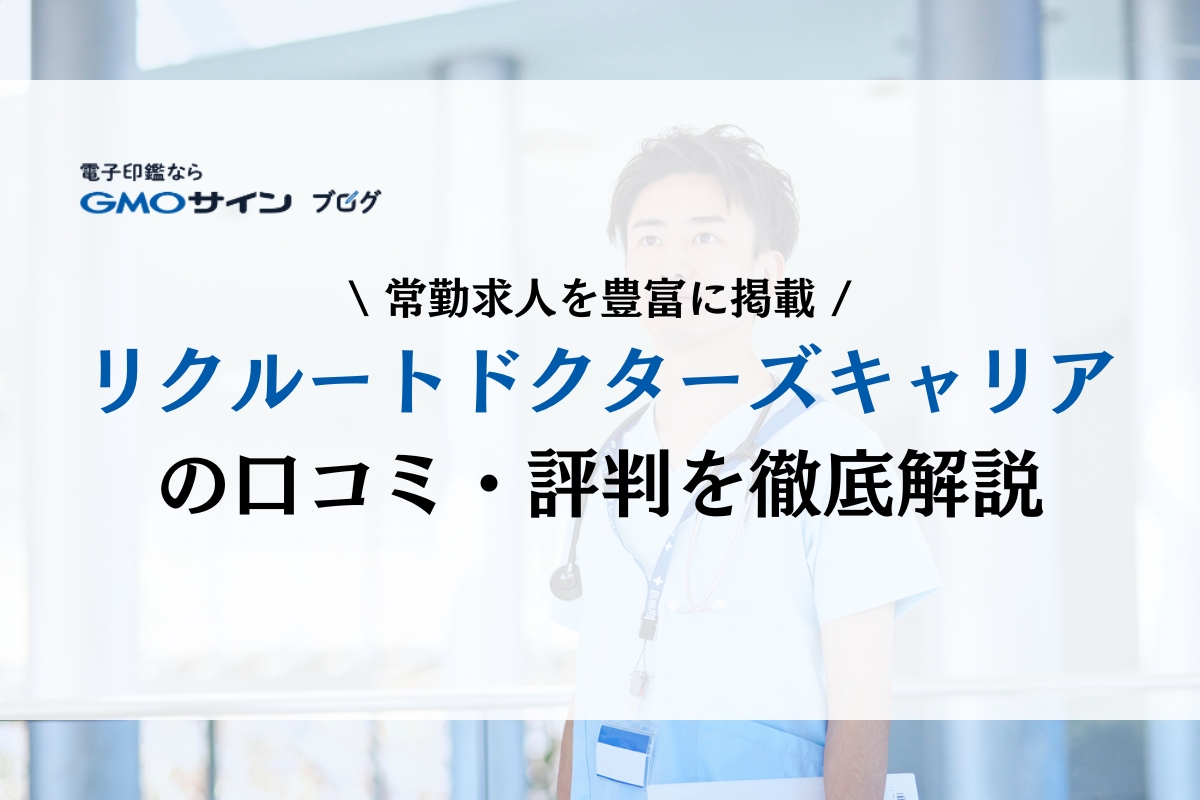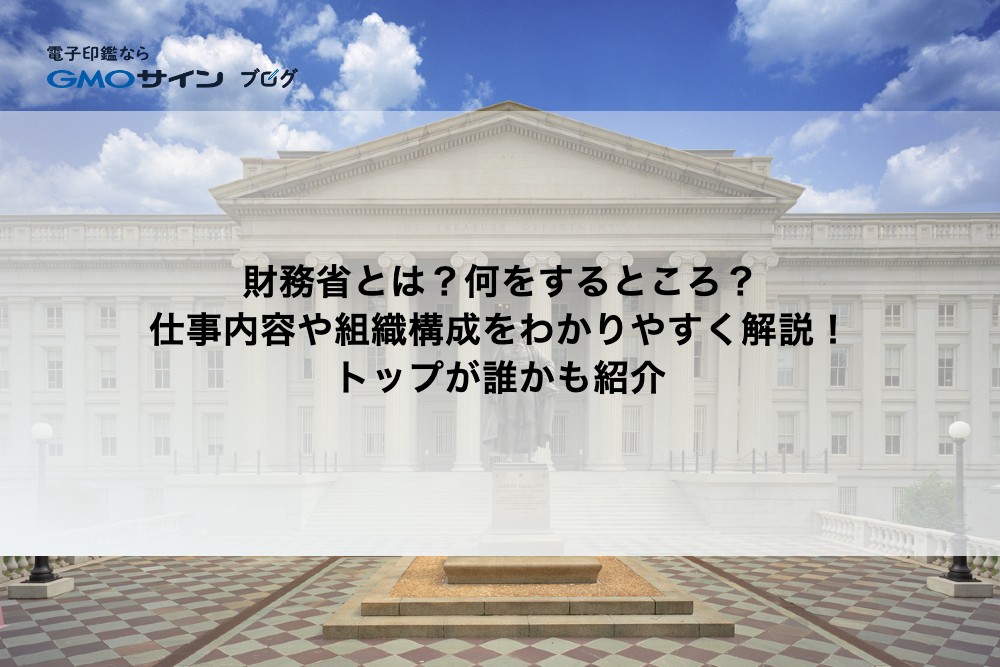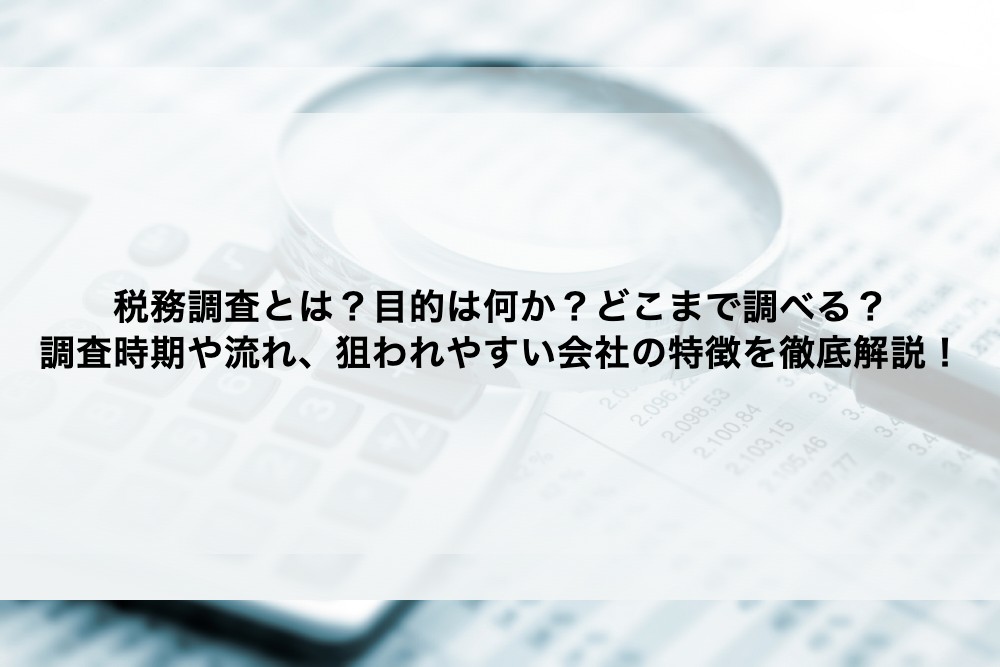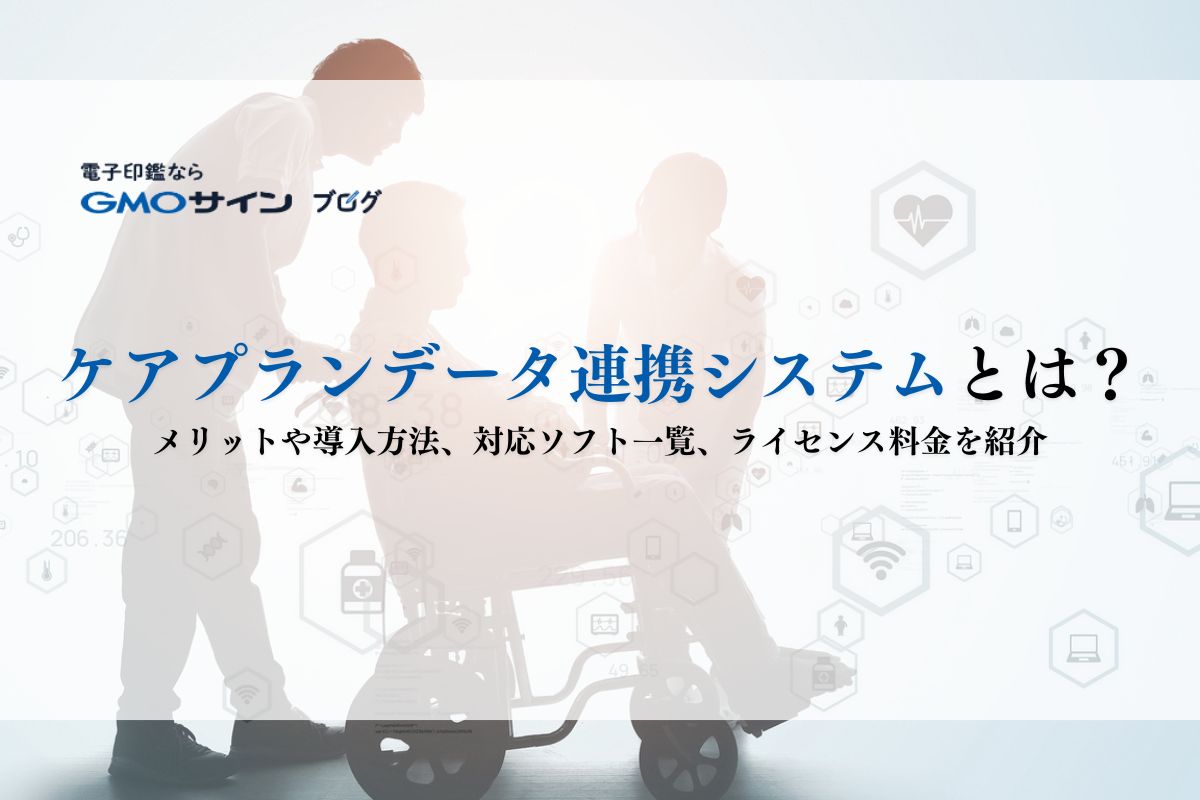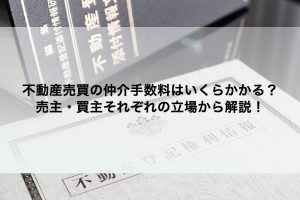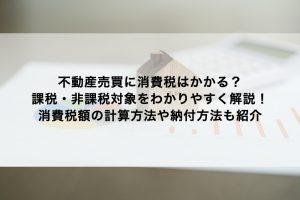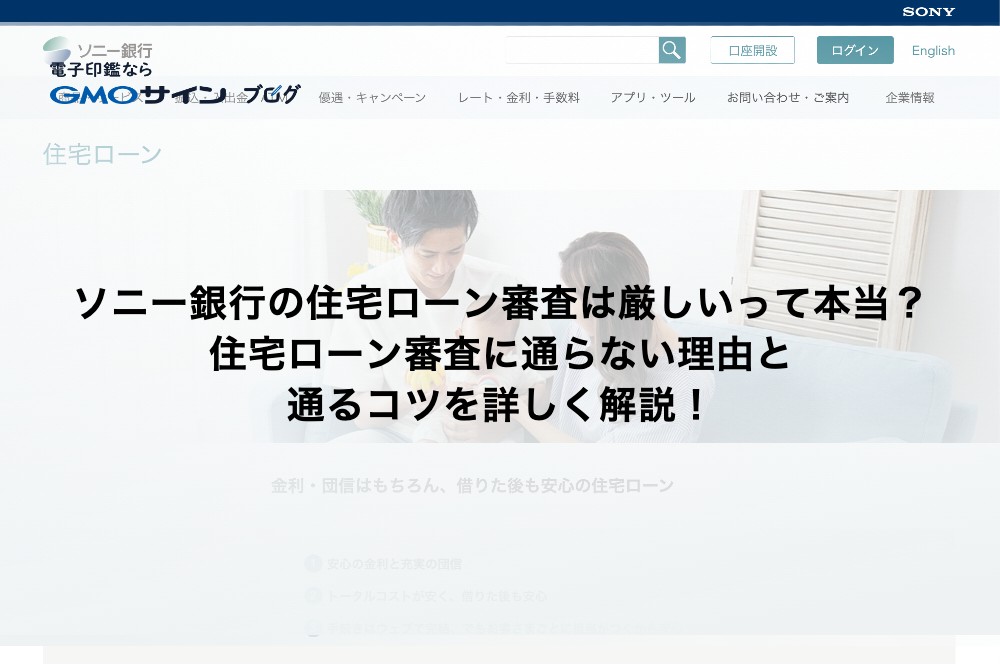勤務証明書は、従業員が会社に在籍し、勤務の実績があることを証明するための書類です。普段、業務を行う上で必要な書類ではありません。しかし、従業員の子どもが保育園に入園する、住宅を購入するときなどに作成を求められるため、スムーズな対応が必要です。
本記事では、勤務証明書の概要、どういったときに必要になるのかを見た上で、適切な作成方法についてお伝えします。また、個人事業主の方が勤務証明書の提出を求められた際の対応も解説しますので、法人、個人問わず勤務証明書の作成をスムーズに行うためにもぜひ、参考にしてください。
目次
勤務証明書とは?
勤務証明書とは、従業員が自社に在籍していること、勤務の実績があることを証明するための書類で、労務部や総務部が作成するのが一般的です。勤務証明書以外に就労証明書、在籍証明書、就業証明書、雇用証明書などと呼ばれる場合もあるものの、すべて勤務証明書と同じ書類を指します。
勤務証明書の作成に法的義務はないため、呼び方も会社によりさまざまです。勤務証明書がもっとも一般的な呼称というわけでもありません。そのため、従業員から「就労証明書が欲しい」「保育園から雇用証明書の提出を求められている」といった形で問い合わせが入るケースも十分に考えられます。
ただ、どれも同じものであるため、労務や総務担当者の方は迷うことなく、スムーズな対応を心がけましょう。
勤務証明書の作成が求められるケース
勤務証明書の作成が求められるのは主に次のような場合です。
従業員の子どもが保育園や学童に入る場合
保育園や学童に入るには、保護者が就労していて自宅で子どもの世話をできないことが重要な判断材料の一つであり、その際、求められるのが勤務証明書です。
勤務証明書は、入園する保育園や学童がある地域の自治体からフォーマットをダウンロードして作成するケースが多いようです。また、保育園や学童によっては、すでにフォーマットが用意されていて、会社側は会社名と住所、社判を押印するだけでOKなケースもあります。
住宅ローン申請・賃貸契約・ローン申請を行う場合
住宅ローンやアパート、マンションなどの賃貸契約、ローン申請を行う際にも、安定した仕事、収入を得ているのかの確認で勤務証明書の提出が求められることがあります。
特に住宅ローン申請時は、在籍証明や年収のほか、勤続年数なども細かくチェックされるケースが多いようです。逆にローン申請は借りる額にもよるものの、電話での在籍確認のみといったケースも多く、勤務証明書までは求められない場合もあります。
転職をする場合
従業員が転職する際、転職先からこれまで働いていた会社の勤務証明書が必要になることがあります。転職先の会社が、提出された履歴書の職務経歴に間違いがないかを確認するのが主な理由となります。
ただし、会社によっては勤務証明書ではなく、退職証明書を求められるケースもあるため、会社としてはどちらにも対応できるようにしておくようにしましょう。
社内に外国人の従業員がいて、就労ビザの申請・更新をする場合
外国人が日本国内で働く場合、就労ビザの取得が必須です。そして、就労ビザの申請や更新をする際に勤務証明書が必要になります。
もし外国人を雇用する際には、必ず就労ビザの取得有無を確認し、取得していないようであれば勤務証明書のほかに必要な書類を揃えて入国管理局へ提出してください。
特別な事情で中学・高校に入学する場合
従業員の子どもが中学や高校に入学する際にも勤務証明書が必要になる場合があります。主なケースは次のとおりです。
- 区域外の学校に入学する場合
-
従業員が働く会社の近く、または実家の近くにある学校に子どもを通わせたいものの、従業員を含む家族は別の区域に住んでいる場合、勤務証明書が必要です。ただし、両親が共働きもしくは母(父)子家庭で就労していることが求められます。
- 介護目的で父母のどちらか一方だけが転居する場合
-
従業員の夫もしくは妻が介護目的で転居し、子どもを転居先にある学校に転学・編入させる場合、転居しない従業員の勤務証明書を提出しなければなりません。
これらのケースは各自治体によって異なる場合もあるため、必ず入学する学校がある地域の自治体や教育委員会のWebサイトを確認してください。
一般的な勤務証明書の記載項目
勤務証明書の作成には法的義務はありません。しかし、前述したようにさまざまな場面で勤務証明書の提出を求められるため、従業員から求められた際にはスムーズに作成できるようにしておきましょう。
従業員側から勤務証明書を渡された場合は、そのフォーマットに沿って記載すればよいものの、自社で1から作成する際には、主に次の項目を記載します。
従業員の氏名・住所・生年月日
勤務証明書の作成を依頼してきた従業員の氏名・住所・生年月日を記載します
業種・役職・雇用形態
自社の業種、従業員の役職を記載します。また、安定雇用かどうかを確認する上で、正社員、契約社員、アルバイト、パートなど、従業員の雇用形態の記載を求められるケースも少なくありません。
従業員の入社年月日
住宅ローン審査や転職時など勤続年数が重視されるケースがあるため、従業員が入社した年月日を記載します。
収入
住宅ローン審査や転職時のほか、保育園や学童の入所手続きでは現勤務先での収入を求められる場合もあります。その際、基本的には勤務証明書ではなく収入証明書を別途貼付するようにしましょう。
ただし、依頼する側が用意した勤務証明書に収入を記載する欄があれば、そこに記載します。なお、収入は直近3カ月の収入を記載するのが一般的です。
勤務時間・就業日数
保育園や学童への入所、小中学校に入学する際には勤務時間が重要な判断材料です。そのため、単純に勤務時間を記載するのではなく、10時~19時、13時~21時など何時から何時まで働いているかを記載する必要があります。
なお、勤務時間と就業日数については現在の就労実績を見る上で、収入と同様に直近3カ月での1カ月あたりで見るのが一般的です。
日付け・会社情報
最後に勤務証明書を作成した日付け、会社の名称、住所、代表者名を記載し、社判を押印すれば完了です。
個人事業主が勤務証明書を作成する際のポイント
会社に勤めている場合、勤務証明書は労務もしくは総務に作成を依頼します。しかし個人事業主の場合、自分一人しかいないため依頼する相手がいません。では勤務証明書は作成できないかといえばそういったことはなく、自身で作成したものでも勤務証明書として利用可能です。
基本的な記載項目は通常の勤務証明書と同じ
個人事業主だからといって勤務証明書が特別な仕様になっているわけではありません。基本的にはここまで説明した勤務証明書と同様のフォーマット、記載項目で作成可能です。
ただし、異なる点もいくつかあります。そのなかでも重要なポイントとなるのが勤務時間です。個人事業主は労働基準法第32条で定められた勤務時間の縛りはありません。
(労働時間)
第三十二条使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
そのため、業務内容によっては日によって勤務時間が大きく異なるケースもあり、明確に記載できない場合があります。特に保育園や学童の入所手続き時は勤務時間が重要な意味を持つため、どう記載すべきかで悩まれるかもしれません。
そうした場合、直近3カ月でもっとも多い勤務時間を記載するのがよいでしょう。もし複数ある場合は、説明を入れた上で2~3つ程度であれば、複数の勤務時間を記載しても構いません。
また、もう一点、気になるのが収入です。個人事業主の場合、固定給ではないため、月により収入がバラバラといったケースも珍しくないでしょう。この場合もやはり直近3カ月~6カ月程度の収入の平均を記載すれば問題ありません。
勤務証明書だけでは受理されない場合の対応方法
日によって勤務時間がバラバラ、収入も月により大きく異なる場合、勤務証明書だけでは勤務状況の把握ができないと判断されてしまうケースがあります。その場合、次のような書類を別途、貼付することで受理してもらえる可能性が高まります。
就労状況報告書
就労状況報告書とは、個人事業主や自営業の方が利用するもので、特に業務内容を詳細に記載できる要にした書類です。主な記載項目は次のようになっています。
- 事業形態
-
経営者が本人か、配偶者か、親族かを記載します。また、本人が経営者の場合、営業許可書や開業届、役職がわかるもののコピーも貼付して提出します
- 業種や仕事の内容
-
どのような業種に属しているのか、どのような仕事内容なのかを具体的に記載します
- 仕事に関する資格
-
業務を行う上で必要な資格があれば資格証のコピーを貼付した上で記載します
- 事業規模
-
個人事業主でも雇用している従業員がいればその人数を記載し、雇用保険に加入していれば、番号も記載します
- 職場と住居の状況
-
職場は住居と同じなのか、同じ建物内で明確に分割されているか、職場と住居がまったく異なる場所にあるかなどを記載します
- 所得税の申告
-
確定申告・源泉徴収・青色専従者など所得税の申告方法を記載します
- 一週間の就労状況
-
一週間の平均的な就労状況について、曜日ごとに時間を区切り詳細に記載します。具体的には10時就労開始、就労時間10時~13時、13時~13時30分休憩、13時30分~19時といった形です。提出先にもよるものの、細かい勤務内容までは記載しなくても構いません。どのようなスケジュールで勤務しているかがわかれば十分です。
開業届
個人事業主として開業する際に税務署へ提出する書類で、多くの場合、就労状況申告書と併せてコピーを提出します。
所得税関連の申告書類
勤務証明書や就労状況申告書を提出する際に確定申告書や青色申告決算書のコピーを併せて提出することで、間違いなく収入を得ていることを証明します。
請求書や納品書
個人事業主を始めたばかりで確定申告をしていない場合、請求書や納品書のコピーを提出すれば、たしかに業務を行っていることを示すことが可能です。また入金がわかる預金通帳のコピー、取引先との業務委託契約書などでも構いません。
勤務証明書を作成する際の注意点
最後に企業として勤務証明書を作成する際の注意点について解説します。
個人情報保護に留意する
勤務証明書に記載する事項は基本的に従業員の個人情報です。住所や雇用形態、収入などについて記載するため、情報漏洩しないよう十分な配慮が欠かせません。つくりかけで放置する、複数人でたらい回しにするといった雑な扱いは厳禁です。
保存期間を守る
勤務証明書の作成自体には法的義務はないものの、一旦、作成したら労働関係の書類ということで、労働基準法109条により5年間は保存の義務があります。作成に法的義務がないからといって、作成してすぐに廃棄しないよう注意が必要です。
(記録の保存)
第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
勤務証明書の概要を理解し、スムーズな対応を実現させよう
勤務証明書とは、従業員が会社に在籍し、勤務の実績があることを証明するための書類です。会社組織の場合は通常、労務部や総務部が作成しますが、個人事業主の場合は本人による作成でも問題ありません。
特に決まったフォーマットはないものの、提出先により必要な項目も変わってきます。提出先別でフォーマットを変えるのは手間がかかり担当者の負担となるため、自社で作成する場合はすべての項目を網羅するようにしましょう。
多くの場合、勤務証明書は1~3日以内に提出しなければならないケースがほとんどです。そのため、従業員から依頼があった際にはすぐに対応できるよう、担当部署の従業員は誰であっても勤務証明書の作成方法をしっかりと把握しておくことが重要です。