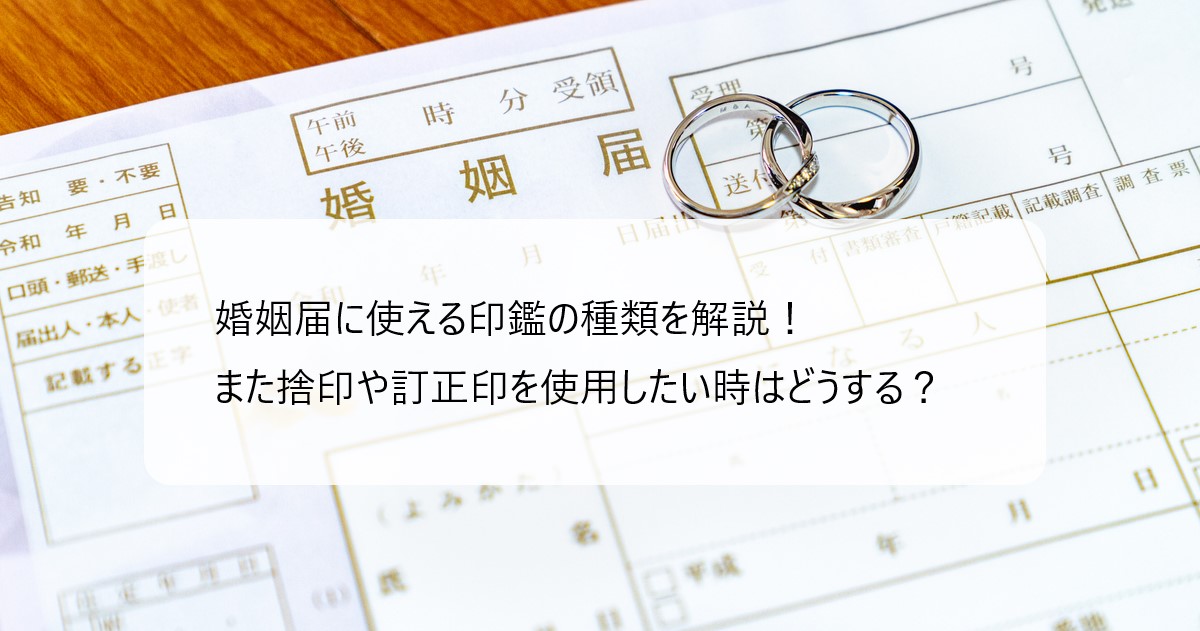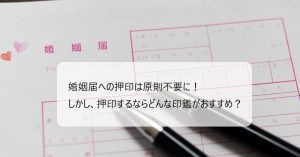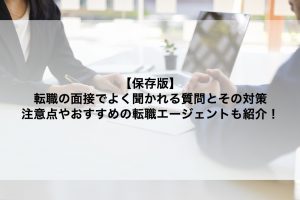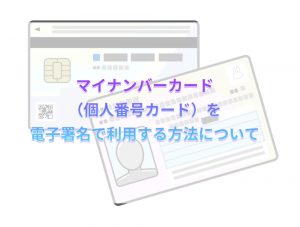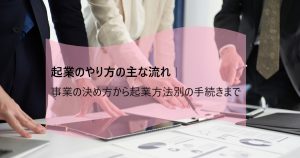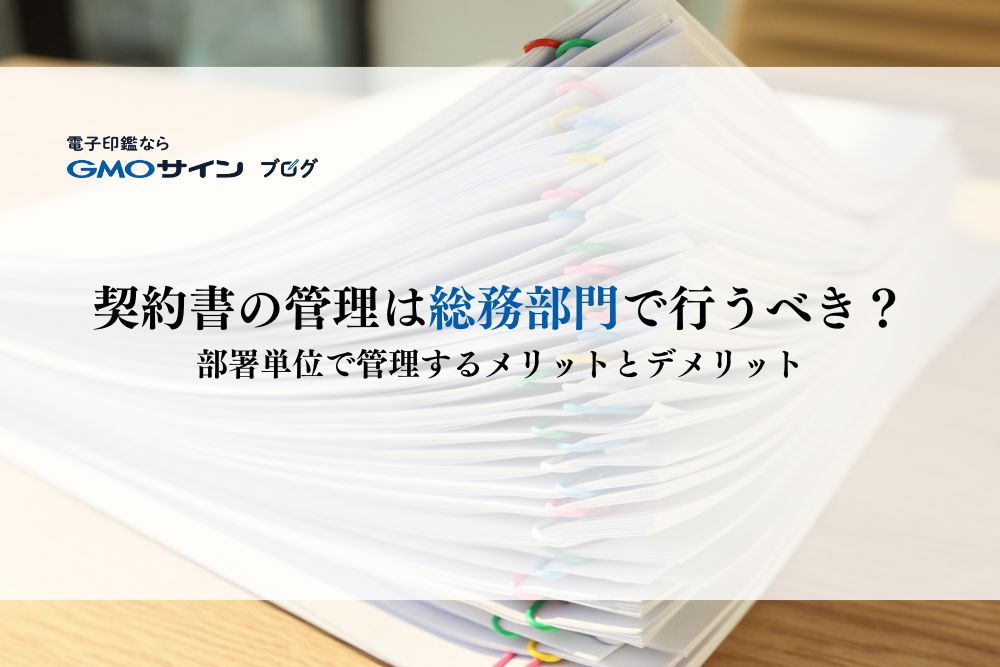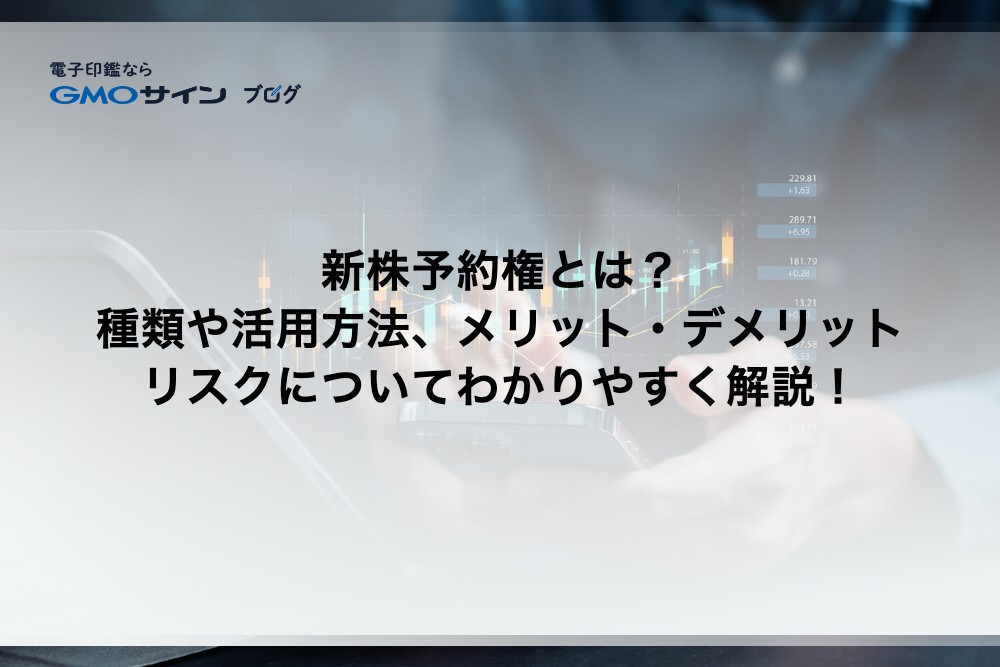婚姻届は人生の一大イベントである結婚に必要な重要な書類です。しかし、令和3年9月に行われた戸籍法の改正などによって、印鑑の扱いに変更がありました。
そこで本記事では、新しい印鑑の扱いや訂正が生じた場合の訂正印、捨印の使用法について詳しく解説します
目次
省令施行によって押印義務が廃止
デジタル社会を推進するために、令和3年9月に戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が施行されました。そのなかでも注目すべき点は、書類の押印義務の廃止です。
| 手続名 | 婚姻届 |
| 手続根拠 | 民法第739条,戸籍法第74条 |
| 手続対象者 | 婚姻をしようとする者 |
| 提出時期 | 随時 |
| 手数料 | 手数料はかかりません。 |
| 添付書類・部数 | 婚姻届書には,成年の証人2名の署名(※押印は任意)が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
| 申請書様式 | 届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
【引用】https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.html
あわせて読みたい
婚姻届への押印は原則不要に!しかし、押印するならどんな印鑑がおすすめ?使えるはんこの種類や任意に...
令和3年の戸籍法改正によって、婚姻届の押印は原則不要になりました。しかし、婚姻は人生における重大なイベントであるため、印鑑を選んで押印するケースも多く見られま...
婚姻届でも押印義務が実質廃止
この流れから戸籍法も改正されて、婚姻届でも新郎新婦および証人の押印義務が廃止されました。
そのため本来印鑑を押す必要はないのですが、重要な書類には実印などの大事な印鑑で押印する慣習や人生で重要なイベントである結婚に必要な婚姻届には押印したいなどの意見を受けて、婚姻届は任意で押印できるようになっています。
婚姻届に使える印鑑の種類
婚姻届では印鑑を用いる場合には、使える種類が限られるため作成時には注意が必要です。
そこで有効な印鑑の種類について詳しく解説します。
実印
結婚などの重要なイベントでは、実印が用いられるケースが多いです。他にも不動産の購入や賃貸借契約、自動車の購入など多額の契約や住む場所に関する契約では一般的に使われています。
銀行印
口座開設で銀行に届け出た銀行印も使えます。主に銀行の窓口で現金を引き出す際に用いられますが、公的文書にも利用できます。
認印
文房具店などで市販されている量産タイプの認印も使用可能です。ただし証人やパートナーに同じ名字の方がいる場合には、なりすましなどのトラブルを防ぐために異なる印影での押印が求められますので注意しましょう。
使えない印鑑の種類
次に、婚姻届で使えない印鑑の種類をご紹介します。他の行政への書類でも使えないケースが多いので、プライベートでの使用に留めておきましょう。
インク浸透印
シャチハタなどのインク浸透印は、印面がゴム製で経年劣化しやすくなっています。そのためインクが薄れやすいので、婚姻届などの公文書では使用できません。
ゴム印
ゴム印も経年劣化が発生しやすい印鑑です。また、押し方の力加減で印影が歪む可能性もあるため使えません。
デザイン印鑑
イラストなどのデザインがセットされた印鑑もありますが、行政に届け出る書類では基本的に使えません。そのため、プライベートな場面で使うようにしましょう。
婚姻届の訂正方法
婚姻届で誤字などの理由から訂正が必要となった場合に備えて、訂正方法をご紹介します。
1. 文字の訂正
文字や記載事項に誤りがあった場合は、その部分に二重線を引きます。二重線を引いた部分の余白に正しい記載をしてください。婚姻届では二重線の上への押印は不要ですが、もし押印してしまった場合でも提出できます。
2. 訂正文字数の添書
文字を訂正する際には、自治体によっては 訂正文字に関する添書を求めるところがあります。その場合には、「○字訂正、○字加入、○字削除」といった形で記載を行います。
たとえば、「次女→二女」と訂正を行った場合、「次」の文字に二重線を引き、「二」を書き加えて訂正をします。そして欄外に「1字訂正、1字加入、1字削除」と記載し、訂正箇所があることを示します。
この場合には、欄外に署名欄に押印したものと同じ印鑑を訂正箇所に押印します。証人欄の書き損じに関しても同様です。ただし、新郎新婦や証人側の署名欄、新しい本籍欄の訂正となる場合はその箇所に訂正印を押す必要があります。
なお、このように自治体によって訂正ルールが異なる場合がありますので、婚姻届を提出する前に担当者に確認しておきましょう。
<参考>
婚姻届などの書き損じの訂正方法について。
【回答】
誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。
届出人欄と同じ印を、届書の左側欄外に押してください(訂正した箇所への押印は不要です)。
欄外に訂正印を押すための枠がある場合は枠内に、ない場合は中段にお願いします。
※修正液・修正テープ等は使用しないでください。
■証人欄の訂正について
誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。
証人欄と同じ印を、届書の右側欄外余白に押してください(訂正した箇所への押印は不要です)。
※ただし、署名欄や新本籍欄の訂正であれば訂正箇所への訂正印も必要です。
【引用】https://www.city.seki.lg.jp/faq/
文字訂正の注意点
訂正によって婚姻届が不受理となるケースもありますので、訂正時に注意すべき点について詳しく解説します。
修正用品はNG
婚姻届などの行政への書類では、修正ペンや修正テープの使用は一切できません。もし使ってしまった場合には、書き直しになるのでご注意ください。
印鑑の取り扱い
訂正後に押印する際には、署名欄に記載した印鑑と同じものを使いましょう。事務用訂正印などの製品も存在しますが、婚姻届での使用は認められていません。二重線の上に押印する場合は、訂正を行った本人の印鑑を使用します。
届け出は平日の日中がおすすめ
婚姻届の提出時には、書き方や必要書類の不備などで受理してもらえないケースがあります。婚姻届は休日や閉庁時間でも提出できますが、訂正に手間取ってしまう事態が考えられますので、できる限り慣れている職員がいる平日に提出することをおすすめします。
事前確認を利用しましょう
事前確認とは、書類を自治体の担当者に確認してもらうことです。事前確認によって訂正箇所が正確に分かるので、時間がある休日などに婚姻届を提出したい方に便利な方法と言えるでしょう。
<参考>
藤枝市「婚姻届など戸籍の届出は事前確認をお勧めします」
字体や住居表示を確認しましょう
文字に間違いがなくても、訂正が必要になるケースがあります。よくあるのは、戸籍上の表記が旧字体や異字体で登録されている場合や住所が正しく記載されていない場合です。
婚姻届は、戸籍上の表記で提出します。そのため戸籍における氏名が旧字体などで届出されているならば、婚姻届には正当な字体で記載しなければなりません。
住所に関しても同様で、「5-77-3」などの表記だと訂正を求められるケースがあります。正しくは、「5丁目77番3号」のように表記される場合が多いです。
そのため氏名や住所の表記に不安がある場合は、住民票を取り寄せて確認しておきましょう。
訂正時に役立つ2つの印鑑
最後に、訂正時に役立つ印鑑についてご紹介します。婚姻届以外の書類でも使えますので、ぜひチェックしてください。
訂正印
訂正印とは、文字や文章の内容を訂正する際に使用する印鑑を指します。訂正印を押すことで、誰が訂正を行ったのか、削除や文字の加筆を行ったのかを明確にする意味があります。婚姻届のような重要な書類の場合では、署名欄などに使用した印鑑と同じもので訂正を行いましょう。
捨印
捨印とは、書類の余白部分への押印を指します。捨印を押しておけば、その書類の内容に訂正の必要が生じた時に訂正印として使うことができます。そのため自治体などに書類を提出した後に訂正する場面が生じても、捨印があれば「書類の提出先に訂正を委任した」と見なされるため、担当者が訂正を代行してくれます。
捨印は、書類の欄外に押印するのが一般的です。契約書などには捨印の押印欄がありますが、押印欄がない場合は書面の左上側の空欄に押します。また、捨印は書面に記載する当事者全員分の押印が必要であり、署名欄に押した印鑑と同じもので押印しましょう。
婚姻届をスムーズに作成しましょう
本記事では婚姻届に使える印鑑の種類について詳しく解説しました。訂正方法などもご紹介しましたが、婚姻届は自治体で長く保管されるためなるべく美しく作っておきたいものでしょう。
そのためには、事前確認や住民票の取り寄せなどのテクニックを使ってミスがないように気をつけてください。また自治体ごとのルールがある場合もあるので、担当者に確認しておく方法もおすすめです。