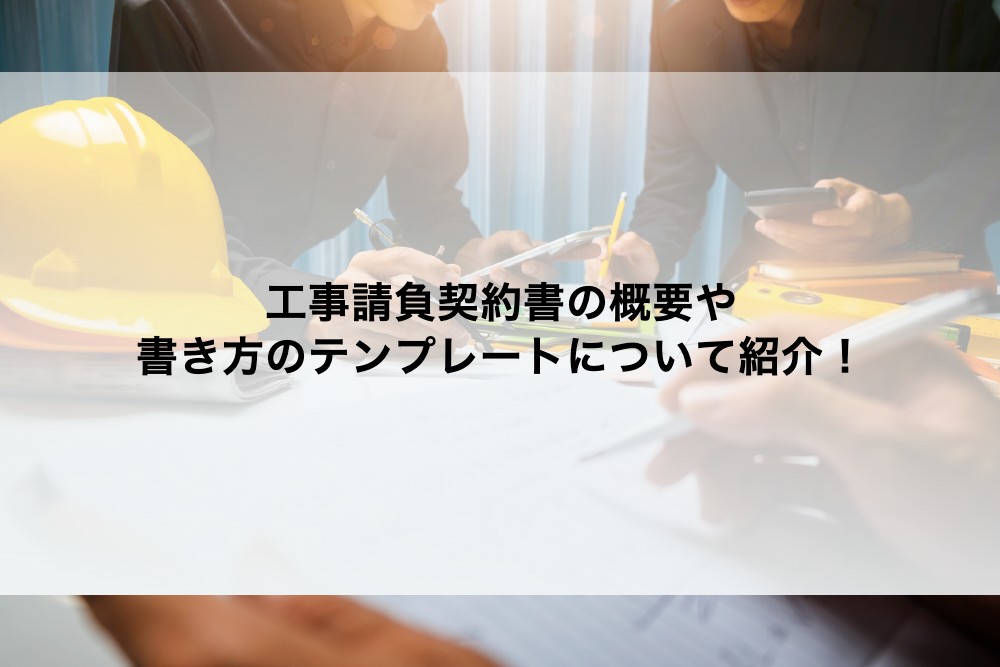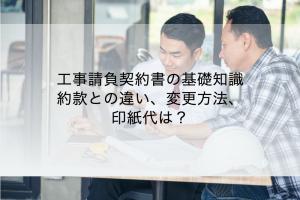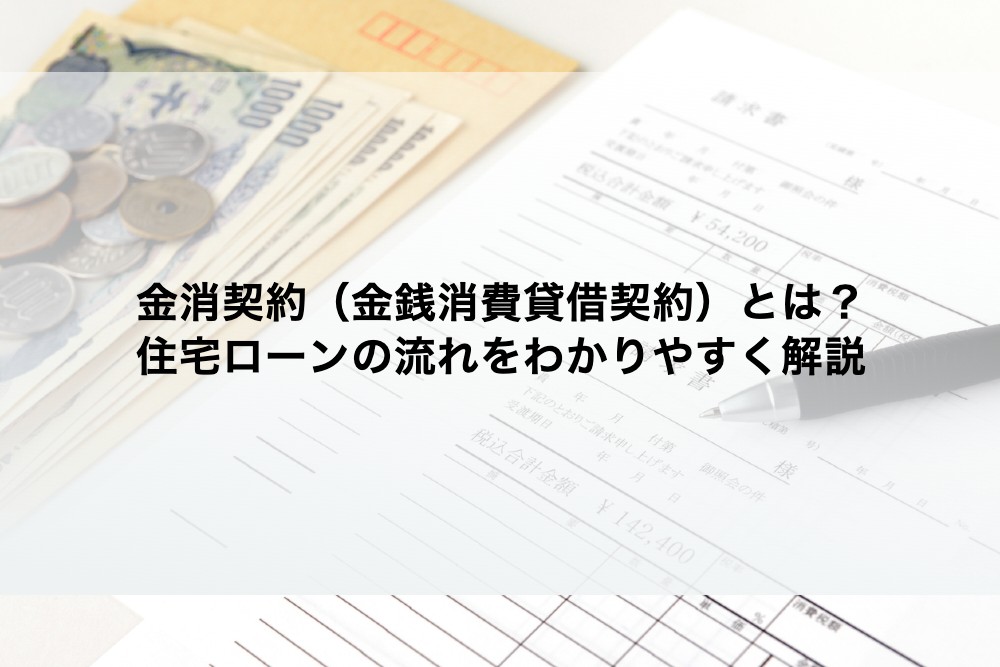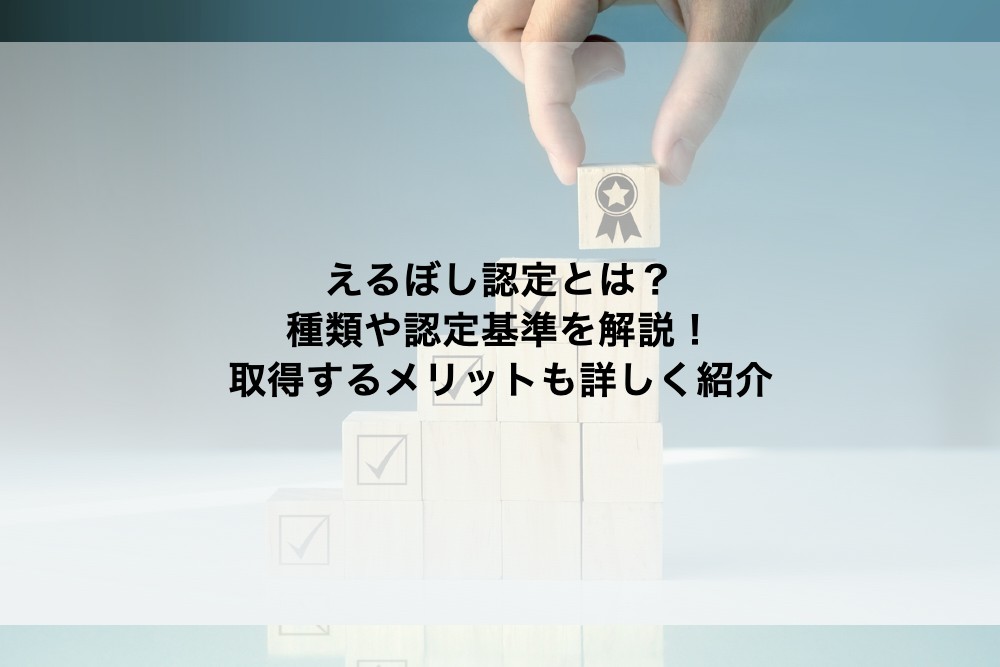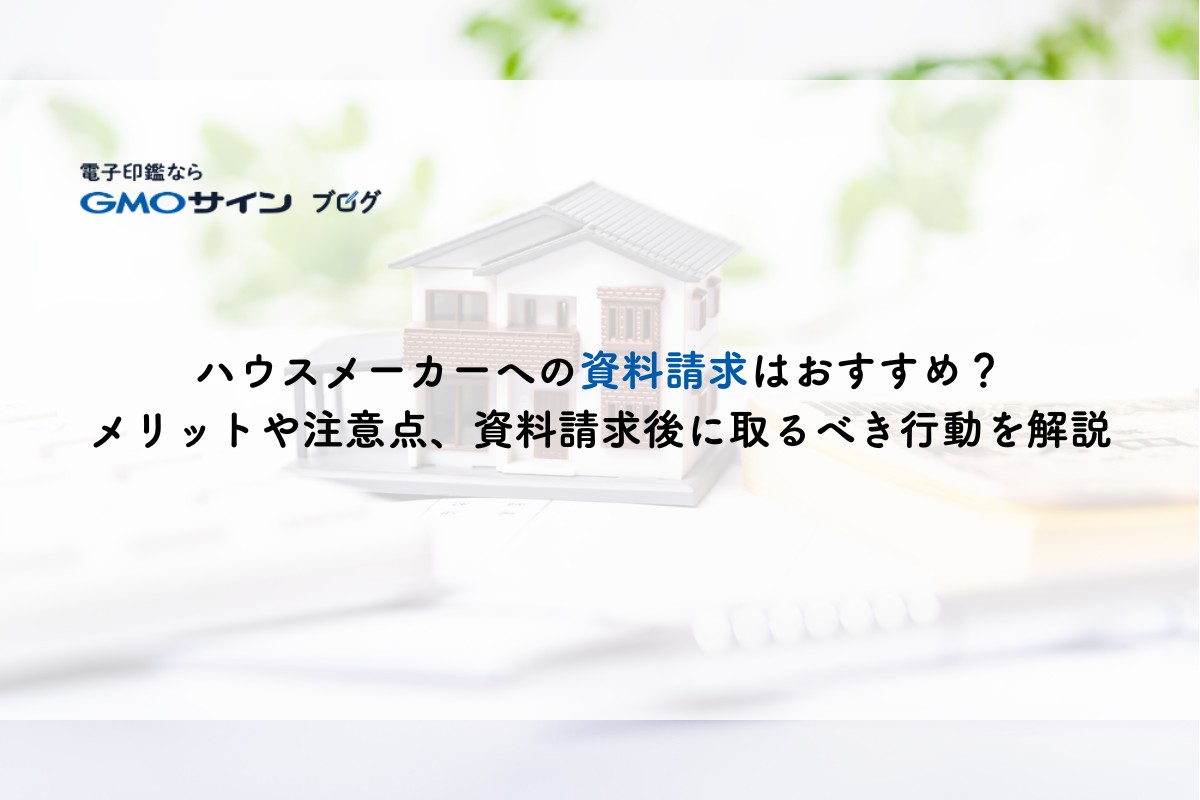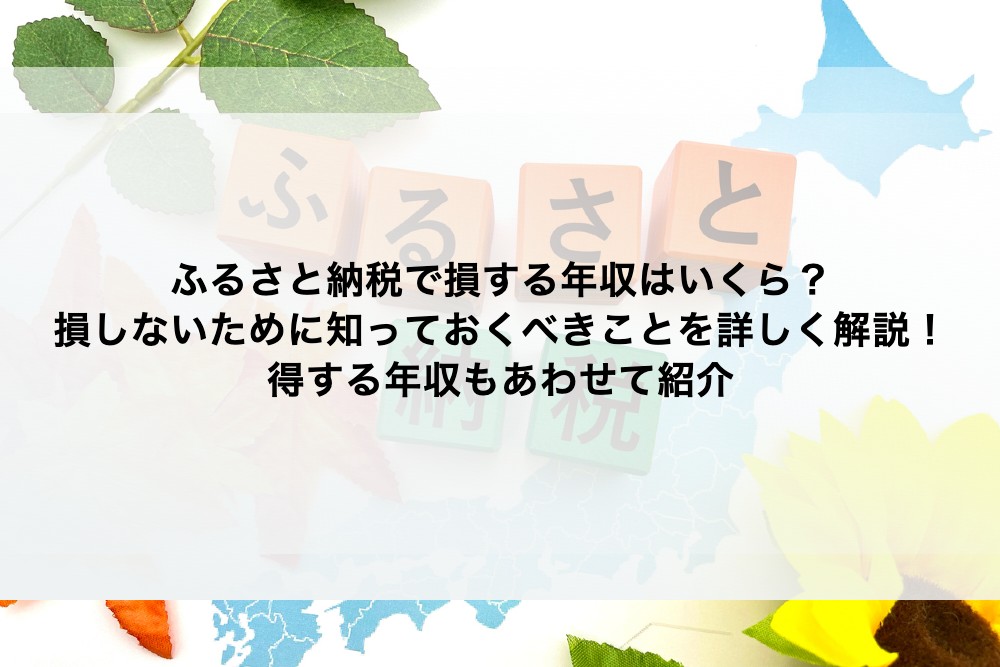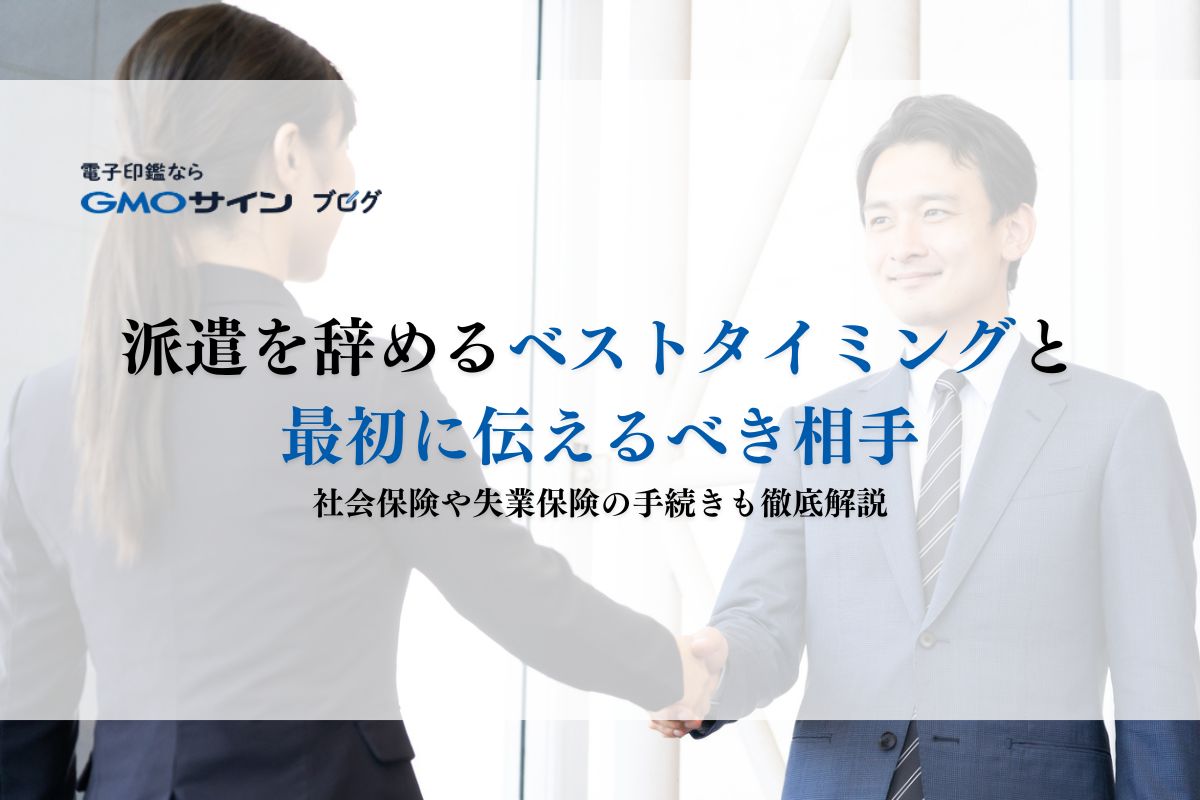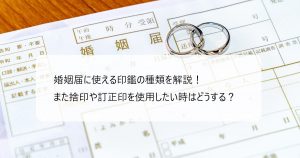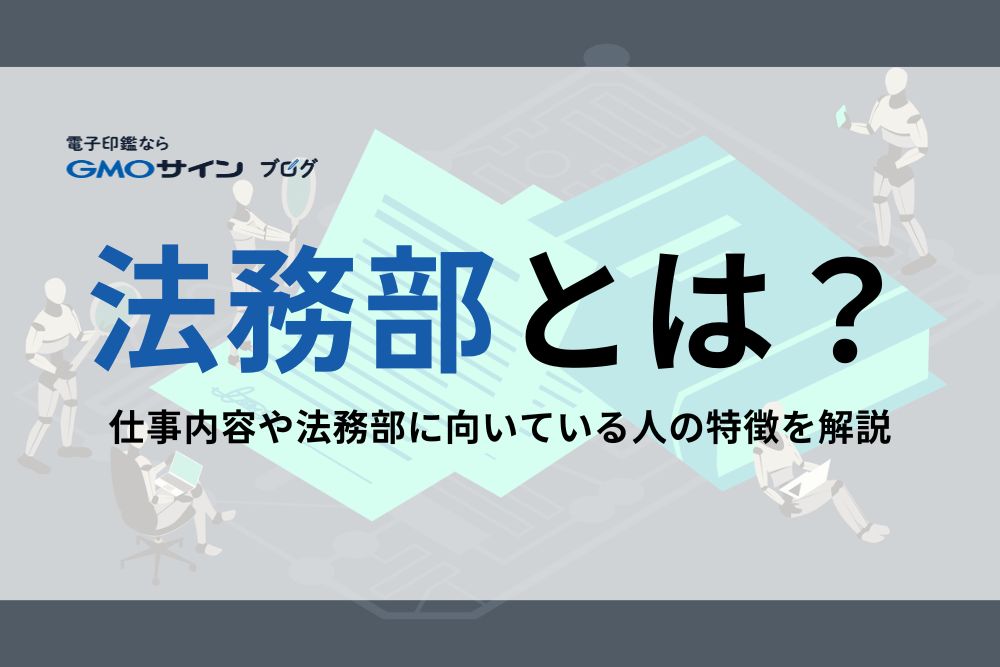工事請負契約書は、大規模な作業である工事の詳細を定める非常に重要な書類です。そのため契約書を作成して確認するには、契約内容に関する知識が欠かせません。
そこで本記事では、工事請負契約書の概要や書き方のテンプレートについて詳しく解説します。また工事請負契約書に必要な印紙税についても触れますので、ぜひご覧ください。
目次
工事請負契約書とは
工事請負契約書とは、工事を行う場合に発注者が建設業者に対して工事を依頼する際に交わされる契約書を指します。工事請負契約書が締結されれば、受注側は工事完成を約束したことになり、発注側は工事の完成に対して契約書で定めた報酬を支払う取り決めが成立します。
契約内容通りに工事が完成していない、納期を過ぎてしまったといった場合は報酬を受け取れないはずですので、工事請負契約書を交わす場合は双方の認識にずれがないことを明確に確認しなければ、トラブルに発展しかねません。そのため、認識を合わせて正しい工事請負契約書が作成しておくことが重要です。
あわせて読みたい
工事請負契約書の基礎知識|約款との違い、変更方法、印紙代は?
工事の受発注における「工事請負契約書」の作成はマストです。2001年4月、改正建設業法の施行に伴い、建設業法第19条に規定されている契約書の書面化義務が廃止になり...
工事請負契約書のテンプレートの内容
工事請負契約書は、トラブルを避けるために記載事項について詳細に検討しなければなりません。テンプレートの内容はおおむね定まっていますが、以下に挙げる項目は入っていることが望ましいです。
・工事名称
・工事場所
・工事期間
・請負金額
・追加工事発生時の費用
・注文者・請負者の情報
・支払い方法
・支払い金額
・違約金
それぞれ詳しく解説します。
工事名称
その工事に付けられる名称を記載します。
工事場所
工事を行う場所の住所を記載します。
工事期間
工事がいつから着工して、いつまでに完成するか期間を記載します。工期については、2020年10月の改正建設業法の施行によって「著しく短い工期の禁止」が定められました。その背景には、工期の短さを優先するあまり従業員達に過酷な長時間労働や休日出勤の強制を避けることが挙げられます。
工期が短いかどうかは、同じ種類・規模の工事にかかった時間や中央建設業審議会の基準にもとづいて判断されます。設定した工期が短いと判断された場合は、発注者側が勧告を受けるため注意しましょう。
請負金額
請負金額がいくらになるのかを明記します。金額は最終的な契約時に双方が合意したものとみなされるため、誤りのない適切な金額を記入しましょう。
追加工事発生時の費用
実際に工事が始まると、契約時に決まった内容にくわえて追加工事を行わなければならないケースも多いです。こうした場合に大幅な追加費用が発生するようならば、事前にその事態を想定して費用を算出して記載することが望ましいです。場合によってはこの追加分を請求する旨の合意を契約の段階から相手側から得ておきましょう。
注文者・請負者の情報
注文者と請負者、つまり発注者と受注者の情報を記入します。工事の状況によっては、実際に工事をする人と入金をする人が異なるケースがあります。その場合にトラブルが起こらないように、誰が注文者なのか契約書で明確にしておきましょう。
支払い方法
請負金額をいつ、どのような方法で支払うのかを明記します。支払いの方法やタイミングは工事の規模や会社方針によって異なり、着工時や引き渡し時、小規模ならば一括支払いなど様々です。支払い方法は契約を交わす段階で明確にしておかなければ、トラブルになかねないため注意が必要です。
支払い金額
工事によっては、タイミングごとに一定の金額をそれぞれ支払う形式もあります。たとえば契約締結時、着手開始時、建築物の基本構造の完成時、工事完了後のそれぞれのタイミングで支払うケースが多いです。
しかし、会社によって支払い方法は異なるため、契約時点で一括支払いを要求されるケースもあります。長期間にわたる工事の場合、請負側の会社が倒産したり、契約解除による施行が中止されたりするリスクもあるため、工事の進捗に応じて支払う形式がベターでしょう。金額だけでなく、支払うタイミングも明記しておきましょう。
違約金
工事が予定よりも遅れて設定した期限に間に合わない場合や、請負側の不備やトラブルによって工事の継続が困難となった場合などで発生する違約金についても明記することが必要です。また工事請負契約を発注側の都合で解除する場合などでも、発注先に生じた損害を賠償しなければならないことが民法に記載されています。
それぞれの場合の違約金についてあらかじめ定めておけば、原則その条項に応じて違約金が決定されます。契約時に違約金についてまとめていない場合、トラブル発生時に損害賠償請求で裁判沙汰にまで発展するケースもあるため気をつけましょう。
さらに、近隣住民からのクレームによって工事が遅延する可能性もあります。クレームによる工事遅延は違約金の対象としない場合は、その旨について記載しておきましょう。
添付書類も用意
準備した工事請負契約書のテンプレートによっては、詳細な工事内容が記載できないケースもあります。その場合は具体的な工事内容を示す仕様書や見積書、設計書等を添付書類として契約書類の一部にしておけば、双方が添付書類も含めて詳細に認識を合わせられるでしょう。
工事請負契約書作成時の注意点
工事請負契約書を作成する場合には、以下の注意点に気をつけましょう。
・遅延・延期時の違約金を設定する
・工期の延長規定を明確にする
・クレーム発生時の対応を明記する
・想定外の費用発生時の対応を明確にする
それぞれ詳しく解説します。
遅延・延期時の違約金を設定する
工事が遅延・延期する場合の違約金条項は、必ず盛り込んでおきましょう。工事は規模が大きいほど遅延・延期しやすく、また損害も大きくなりやすいです。そのため、違約金に関する条項は非常に重要です。
工期の延長規定を明確にする
契約書を作成する場合には、工期の延長規定を明確化しておくことも重要です。工事が進んでから延期について協議することになると、話がまとまらずトラブルに発展する可能性があります。天候不順や自然災害などやむを得ない事情に対しては、発注者側の承諾を得なくても工期が延長できるような規定を定めておきましょう。
クレーム発生時の対応を明記する
近隣住民からクレームが発生した場合、対応内容を明記しておきます。クレームの規模によっては、工事が中断や延期、中止になってしまうケースがあり得ます。見過ごしがちな条項ですが、必ず記載しておきましょう。
想定外の費用発生時の対応を明確にする
契約時に想定していない費用が発生するケースも多いです。たとえば、工事現場で埋蔵文化財が発見されたり、土壌汚染が発覚して工事ができなくなったりする場合などが挙げられます。そのため、受注側はその場合の費用を追加で請求できるように契約書に明記する必要があります。
工事請負契約書は印紙税の課税対象
工事請負契約書には、印紙税が必要です。印紙税とは契約書や領収書、手形など経済的な取引で作成が必要な文書にかかる税金を指します。納税方法は、該当書類に対して指定の金額に見合う収入印紙を購入・貼付すれば、納税は完了します。
もし未納が発覚した場合は、過怠税として本来かかる印紙税代にくわえて2倍の印紙税代を追加徴税されます。つまり、従来の3倍の印紙税を支払わなければならなくなります。
契約にかかる印紙税額
請負契約時にかかる印紙税額は、その仕事の契約金額によって異なります。契約金額に応じた印紙税額は、以下の通りです。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
| 300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
契約金額が1万円未満のものは、印紙税が非課税になります。契約金額が1万円以上、または契約金額の記載がない場合は印紙税が発生するため、税額に応じた収入印紙を購入して忘れずに貼付を行いましょう。
1億円を超える規模の契約になると印紙税もかなり高くなるため、過怠税を課されると大きな痛手となってしまいます。印紙税を節税するために、場合によっては契約書を1つにまとめたり分割したりするといった工夫がおすすめです。
建設工事請負契約書の場合は印紙税の軽減措置あり
契約書の中でも建設工事請負契約書は、平成26年4月1日~令和6年3月31日の間に作成されて、かつ契約金額が100万円を超える場合は印紙税の軽減措置があります。
契約金額ごとの軽減税率は、以下の通りです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|
| 100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 200万円を超え 300万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 300万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
また、契約時に作成した請負契約書以外でも、途中に金額変更や工事内容追加等で作成する変更契約書と補充契約書も軽減措置の対象です。条件を満たす建設工事では、軽減税率に応じた収入印紙を購入して貼り付けるようにしましょう。
電子契約なら印紙税が不要
数多くの工事を請ける場合、印紙税の金額も積み重なってしまいます。そのため節税がポイントになりますが、そこでおすすめの方法が電子契約です。契約書を電子化すれば、契約金額に関わらず印紙税は非課税となります。
そこでおすすなのが、「電子印鑑GMOサイン」の電子契約サービスです。
印紙税を全額カットできるので、工事請負契約を多く受注している企業には非常に役立ちます。また、収入印紙を用意する手間や貼り間違いなどのトラブルも省けるので、ぜひご利用ください。
工事請負契約書を適切に作成して、工事を円滑に進めましょう
工事請負契約書を正確に作成することは、工事を円滑に進めるために重要です。そのため、工事の期間や考えられるコストなどを明確に記載して、双方の合意を契約締結の段階で確実に取りつけておきましょう。
また工事請負契約書の作成には印紙税も大きな負担となるので、「電子印鑑GMOサイン」を導入してコストカットや収入印紙の貼り間違いなどのトラブル防止に役立ててください。