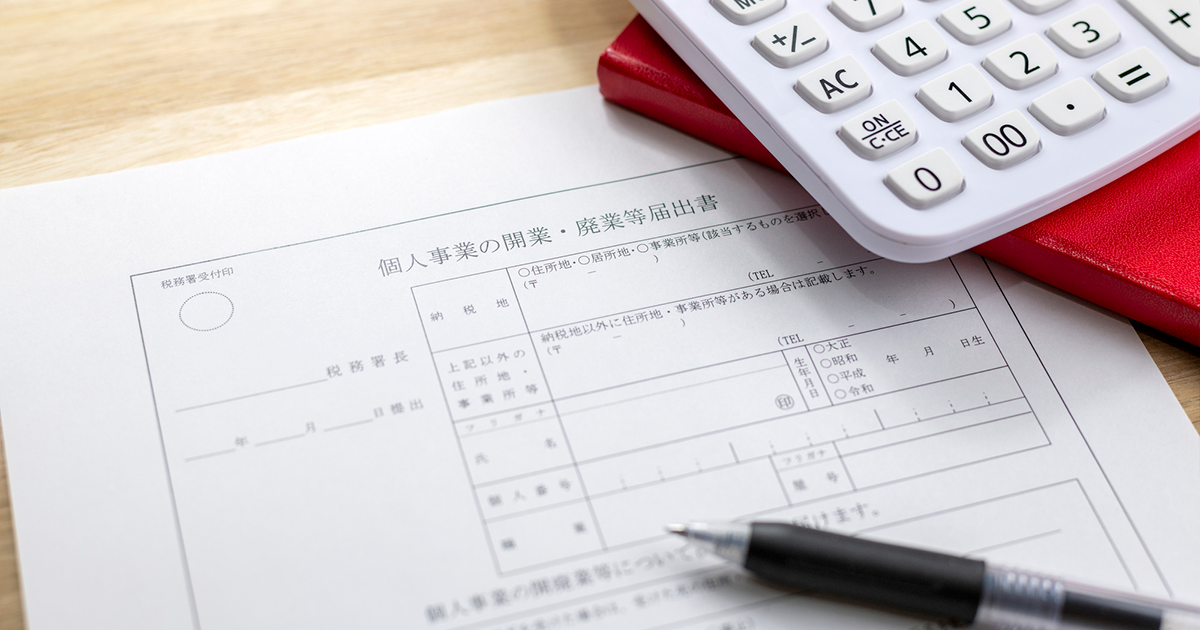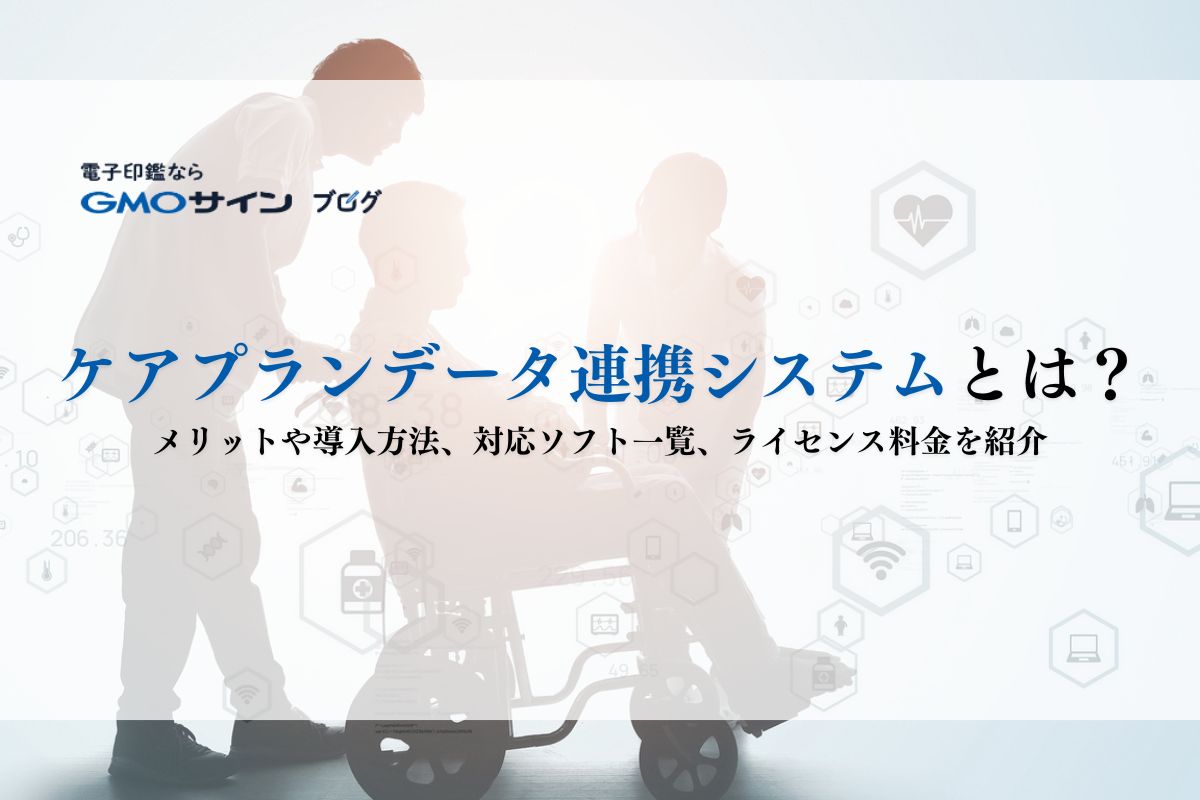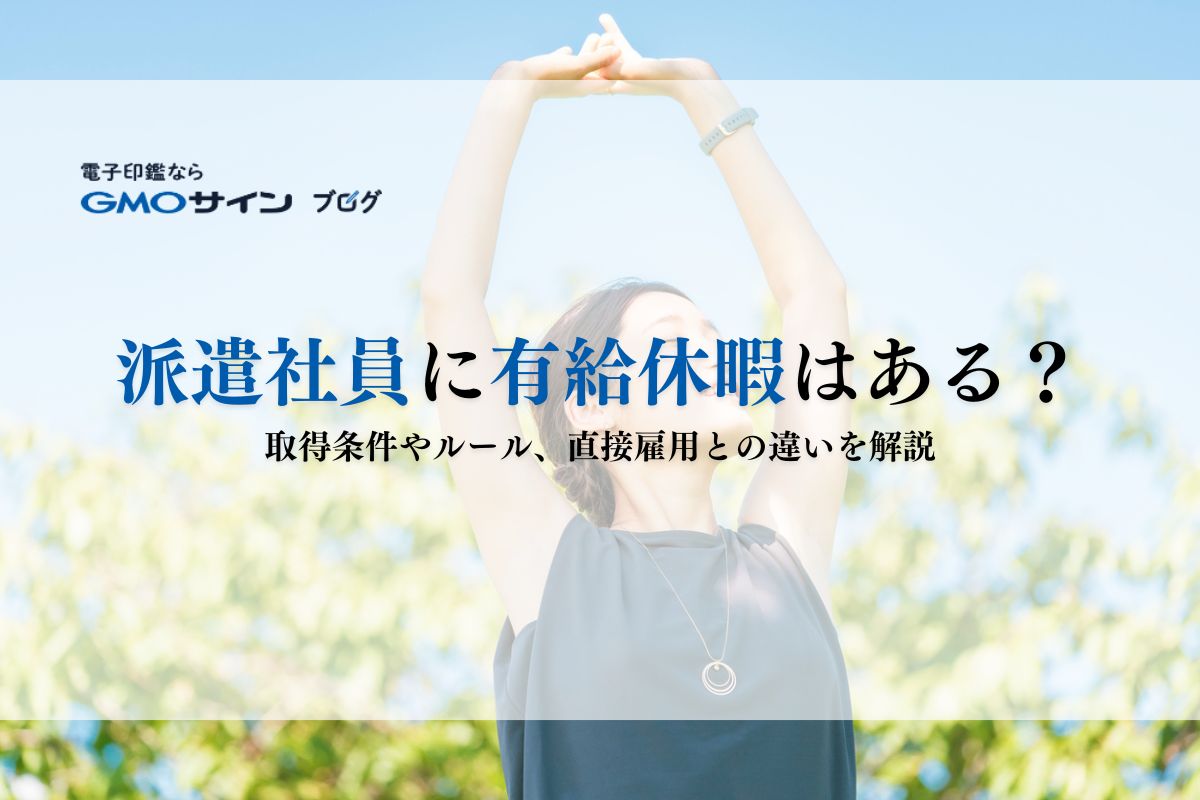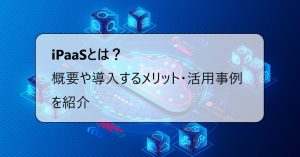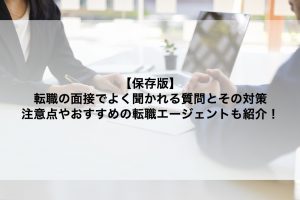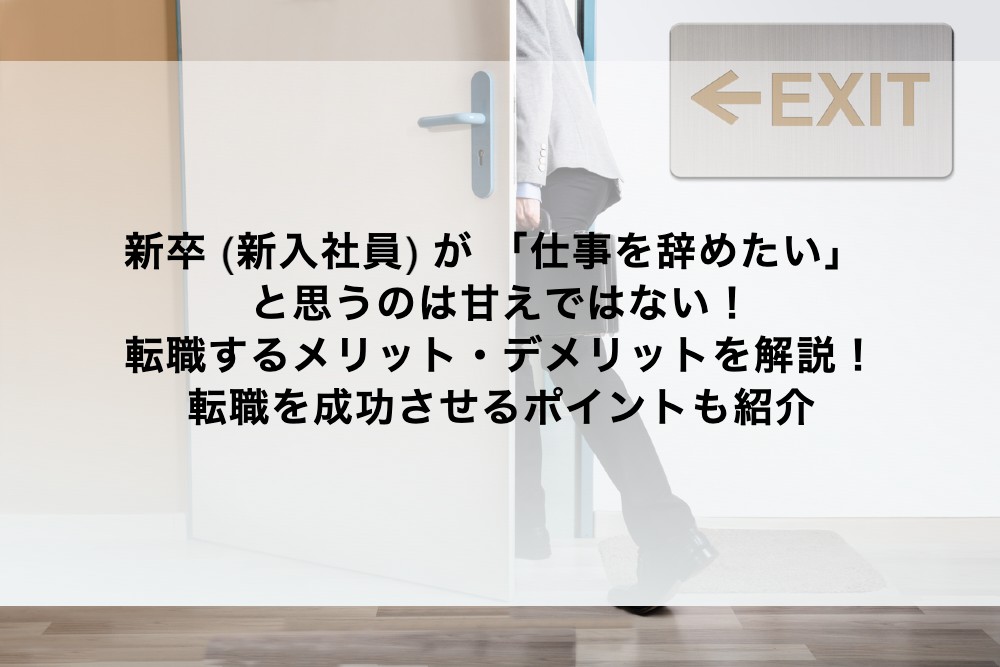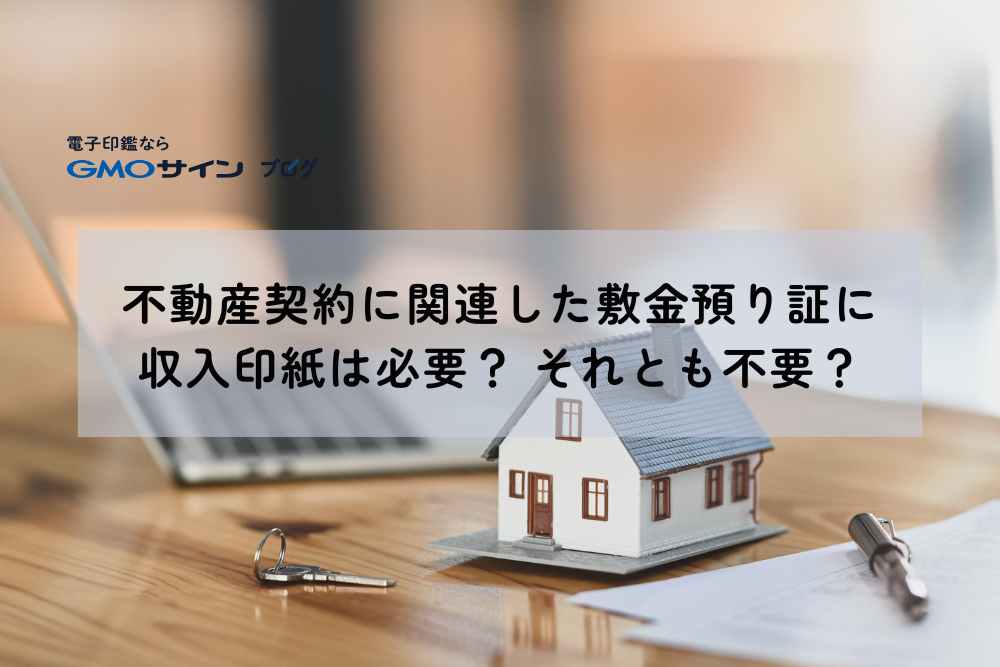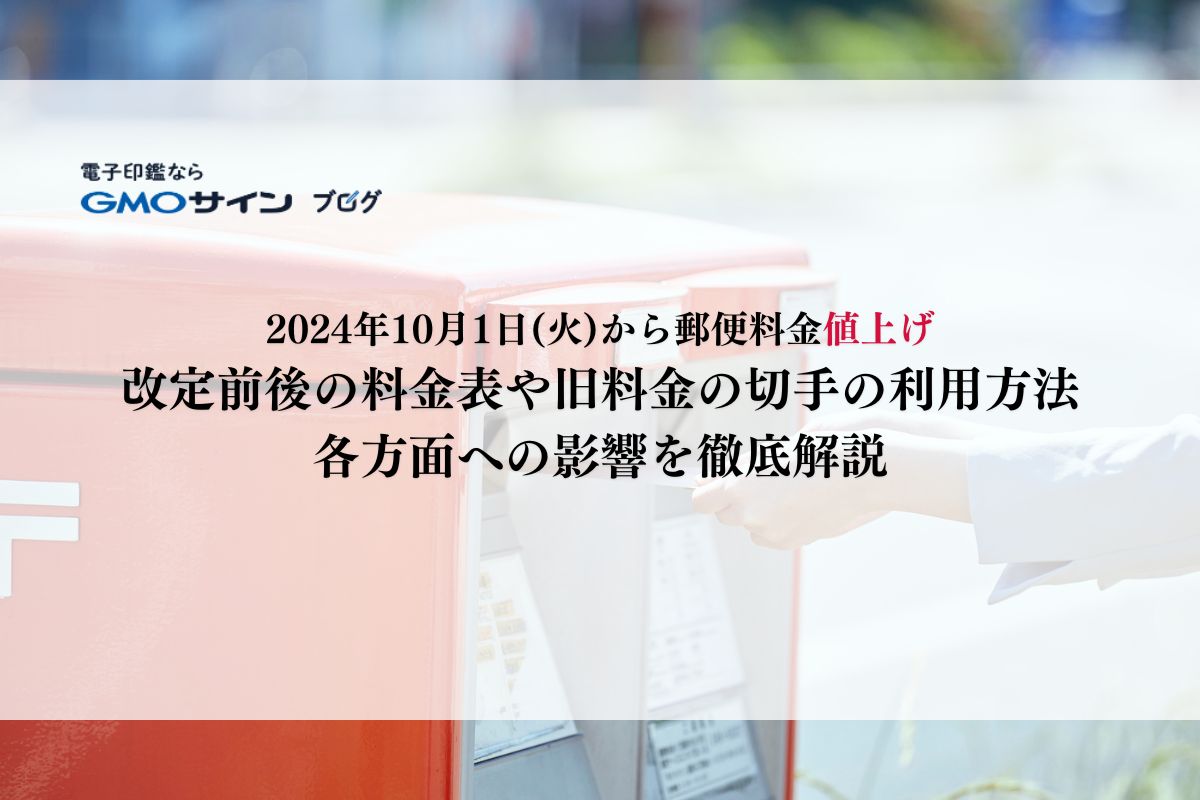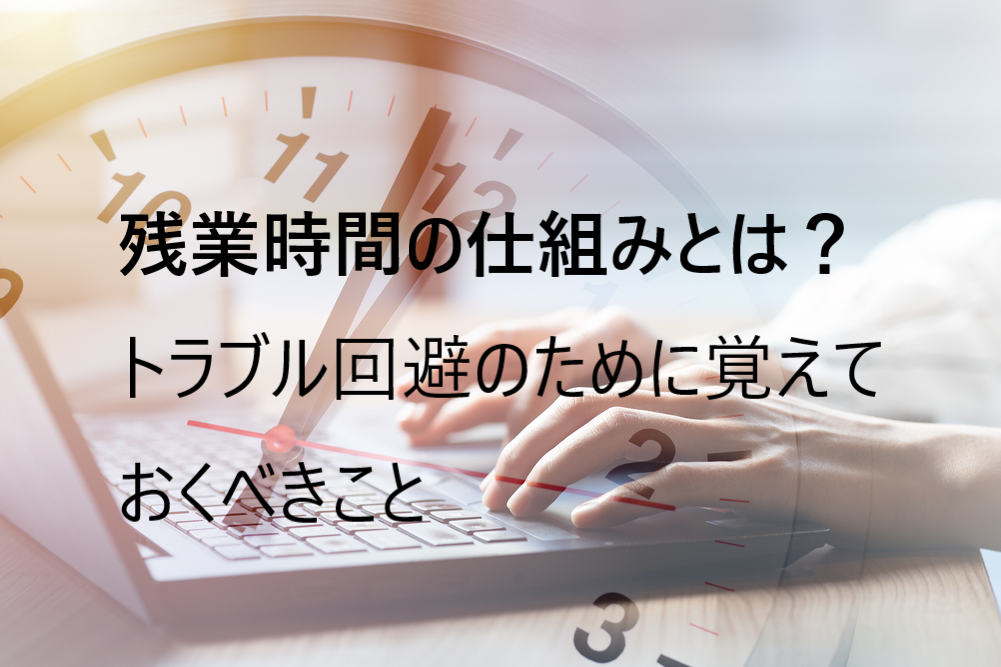目次
開業手続きの流れ
それでは、開業手続きはどのように行えばよいのでしょうか?流れを解説します。
用紙を入手する
まずは開業届の用紙を入手しましょう。税務署でもらえるほか、国税庁のホームページでPDFファイルをダウンロードすることもできます。これをプリントアウトすれば税務署に足を運ぶ手間が省ける上、パソコンで必要事項を入力することも可能です。また、青色申告をしたい場合は「青色申告承認申請書」の用紙も併せて入手する必要があります。こちらも税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
必要事項を決める
開業届に記入する各項目について考え、決めていきます。事業所の住所はどこにするか?屋号はどうするか?職業はどう記入するか?所得の種類はどれになるか?考えるべきことは人によりさまざまです。しかし一般的に記入が必要なのは、主に以下のような項目です。
・氏名
・生年月日
・個人番号
・納税地
・職業
・屋号
・届け出の区分
・所得の種類
・開業日
・開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
特に悩むのは屋号でしょう。会社で言うところの社名となります。ご自身の名前を入れたり、好きな言葉を入れたり、自分の想いを込めて命名してください。これから認知度をアップさせてクライアントを獲得することを考えると、わかりやすくて印象に残るネーミングがおすすめです。ちなみに屋号は必須項目ではありません。屋号を使う予定がない場合は空欄でも構いません。
また、職業も重要な項目です。その理由は後ほど解説しますので、しっかり押さえておいてください。
用紙に必要事項を記入する
用紙に必要事項を記入していきましょう。税務署でもらった用紙、もしくはPDFをプリントアウトしたものに手書きで記入していきます。前述のとおり、PDFであればパソコンで必要事項を入力することもできます。また、ExcelやWordで自作することもできます。手書きが面倒、書き間違えるのが心配という方には、パソコンでの作成がおすすめです。
必要書類といっしょに税務署へ提出する
開業届が作成できたら、税務署に持参するか郵送で提出します。開業届の他にも以下のものが必要となります。
・印鑑
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
他にも必要に応じて以下のものを提出します。
・青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
・青色専従者給与に関する届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・給与支払事務所開設届出書
開業届の控えに受領印を押してもらったら、手続きは完了です。開業おめでとうございます。なお、開業届は屋号名義の銀行口座や事業用のクレジットカードを作ったり、銀行で融資を受けたりする際に必要になります。紛失したり捨ててしまったりすることのないよう、大切に保管しましょう。
開業届の書き方

出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
※要注意!職業で税率が変わる
個人事業主には「個人事業税」という税金が課せられます。ほどんどの職業は税率が年率5%に設定されていますが、一部4%、もしくは3%の職業もあります。
| 事業税率 |
職業名 |
| 5% |
物品販売業 |
運送取扱業 |
料理店業 |
遊覧所業 |
| 保険業 |
船舶定係場業 |
飲食店業 |
商品取引業 |
| 金銭貸付業 |
倉庫業 |
周旋業 |
不動産売買業 |
| 物品貸付業 |
駐車場業 |
代理業 |
広告業 |
| 不動産貸付業 |
請負業 |
仲立業 |
興信所業 |
| 製造業 |
印刷業 |
問屋業 |
案内業 |
| 電気供給業 |
出版業 |
両替業 |
冠婚葬祭業 |
| 土石採取業 |
写真業 |
公衆浴場業(むし風呂等) |
公衆浴場業(銭湯) |
| 電気通信事業 |
席貸業 |
演劇興行業 |
歯科衛生士業 |
| 運送業 |
旅館業 |
遊技場業 |
歯科技工士業 |
| 医業 |
公証人業 |
設計監督者業 |
測量士業 |
| 歯科医業 |
弁理士業 |
不動産鑑定業 |
土地家屋調査士業 |
| 薬剤師業 |
税理士業 |
デザイン業 |
海事代理士業 |
| 獣医業 |
公認会計士業 |
諸芸師匠業 |
印刷製版業 |
| 弁護士業 |
計理士業 |
理容業 |
|
| 司法書士業 |
社会保険労務士業 |
美容業 |
|
| 行政書士業 |
コンサルタント業 |
クリーニング業 |
|
| 4% |
畜産業 |
水産業 |
薪炭製造業 |
|
| 3% |
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業 |
文筆業(ライター)やプログラマー、翻訳家、芸術家、スポーツ選手などは上記の職業にあてはまらないため、事業税はかかりません。しかし、仮にこれらの職業の人が課税される職業を選択して開業した場合には、税金がかかってしまいます。たとえば、画家の人がポスターやチラシなどのデザインの仕事もしていて、「デザイン業」として届け出れば5%の事業税を支払わなければなりません。逆に、デザイナーをしている人が「画家」で届け出をした場合、事業税はかかりません。
ただし、職業を偽って届け出をするとトラブルにつながるリスクもあります。実質的にデザイン業の収入がメインの人が「画家」として届け出た場合、税務調査などで指摘される可能性も考えられますので、職業欄は実態に即して正確に記入しましょう。
開業届についてのよくある疑問
ここからは、皆さんが開業届に関して抱きがちな疑問にQ&A形式で回答していきます。ぜひ参考にしてください。
自宅として使っている賃貸物件を住所に設定しても問題ない?
その物件の規定によります。「事務所可」もしくは「事務所利用可」となっていれば、住所に設定しても問題ないでしょう。「不可」の場合は、他に事業用物件を借りるか、事務所利用が可能な物件に引っ越す必要があるかもしれません。
そもそもこうした規定は、近隣住民とのトラブル防止やセキュリティの確保、固定資産税の税額の違い(事業用物件のほうが税率は高くなる)などの観点から定められています。
たとえば、アパートやマンションの一室を店舗にすると、不特定多数の人が出入りして騒音などのトラブルが発生する、セキュリティ面で不安視される、あるいは物件が事業用とみなされて大家さんが支払う固定資産税が上がってしまうといった可能性があるため、断られることも考えられます。一方で、ライターやプログラマーのように、店舗が不要で自宅のパソコンを使ってできる事業であれば、認められる可能性もあります。
賃貸物件にお住まいで開業を考えられている方は、まずは大家さんや管理会社に相談してみましょう。
開業届を提出するときにお金はかかる?
結論から言うとお金はかかりません。開業届を書いて税務署に提出さえすれば、個人事業主としての届け出は完了です。手数料なども必要ありません。強いて言うなら、税務署まで行く交通費や郵送する際の切手代がかかるぐらいです。
会社を設立するとなるとさまざまな手続きが必要で、登録免許税や定款の認証・謄本手数料、会社印鑑の作成費用や印鑑登録費用などがかかります。個人事業の場合はこうした手続きは不要なので、出費を抑えられます。
まずは元手がかからない個人事業からスタートして、売上が増えたり従業員を雇用したりするなど、事業規模が拡大したら会社を設立するという方が多いようです。
会社員も開業届を出せる?
会社員の方でも開業届を出すことは可能で、副業で二足のわらじを履くことができます。特に副業による売上が増えたら、65万円の所得控除が受けられる青色申告を行ったほうが節税できます。必要に応じて開業届と青色申告承認申請書の提出を検討してみましょう。
ただし、開業すると失業手当を受給できない、副業していることが会社にバレる(副業禁止の会社の場合は会社規則に違反していることが発覚する)といったデメリットや注意点があり、しっかり確認することが必要です。
開業届は出さなくてもいい?
原則として、個人事業を開業したら1ヶ月以内に所管する税務署(長)宛に開業届を提出することになっていますが、出さなかったとしても罰則はありません。しかし、青色申告ができない、屋号名義の銀行口座やクレジットカードを作れない、融資を受けられない、補助金や助成金の申請ができないなど、デメリットも数多くあります。個人事業を始めるなら、極力開業届は提出しましょう。
開業届の控えを無くしたらどうすればいい?
税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出することで、開業届のコピーをもらうことができます。手数料は1件あたり300円で、保有個人情報開示請求書の他に本人確認書類が必要です。ただし、税務署に足を運ばなければならない、あるいは郵送で請求しなければならないので手間がかかります。このようなことにならないよう、開業届の控えをわかるところに保管しておく、コピーしておく、スキャンしてパソコンに保存しておくなどしてしっかり管理しましょう。