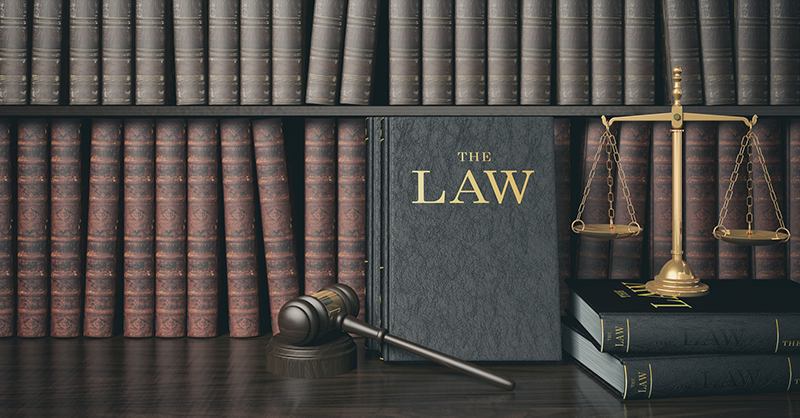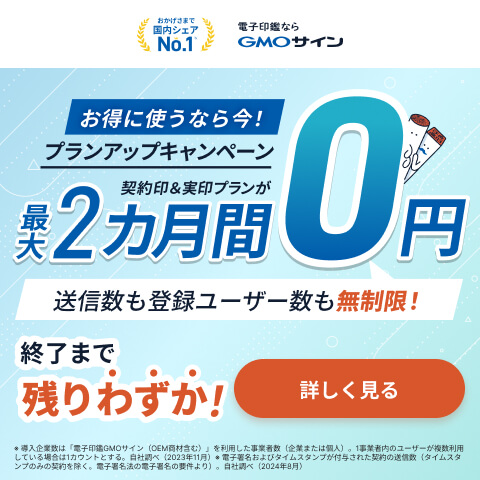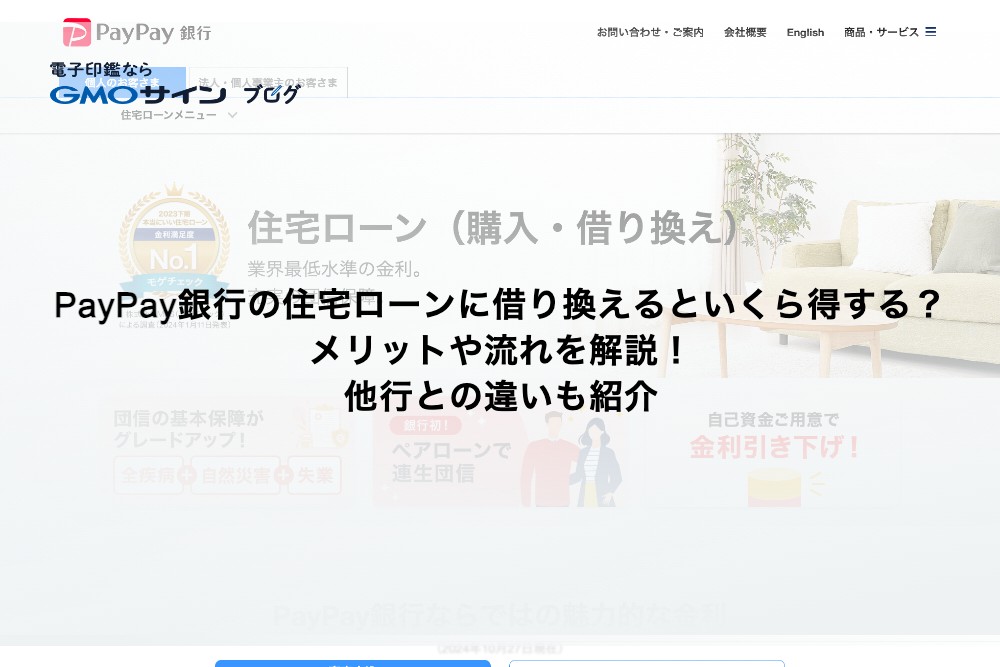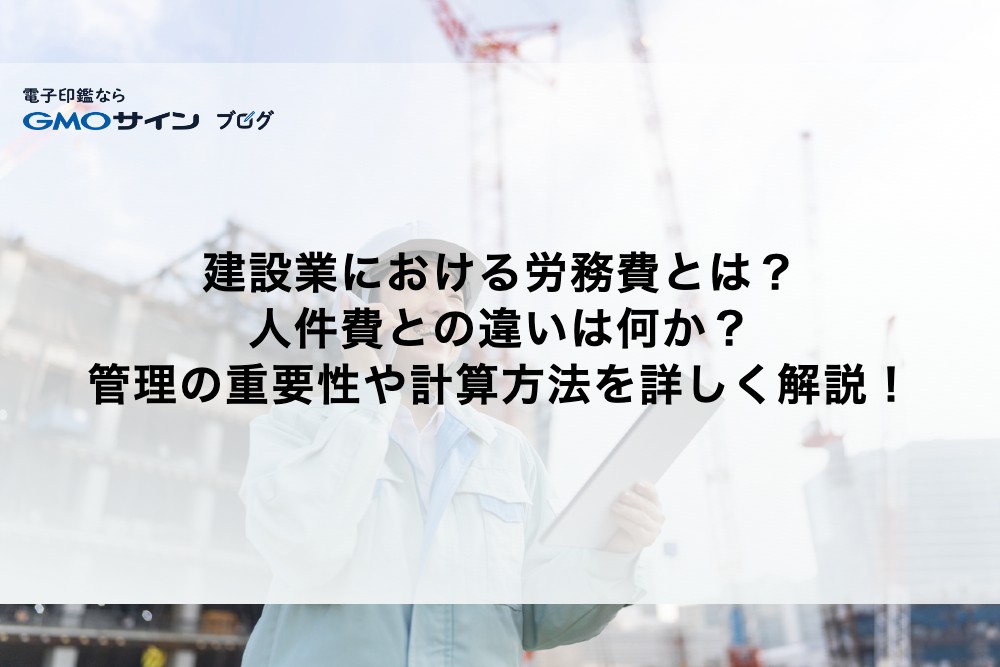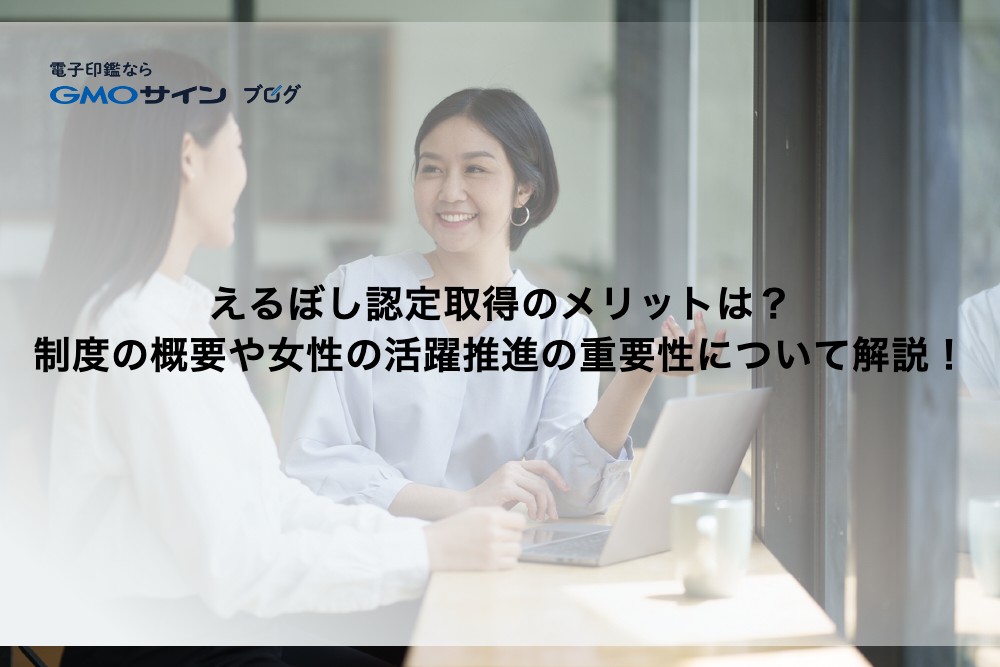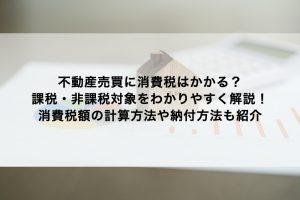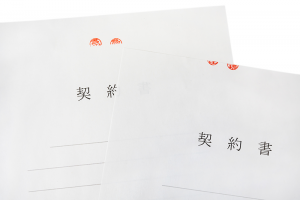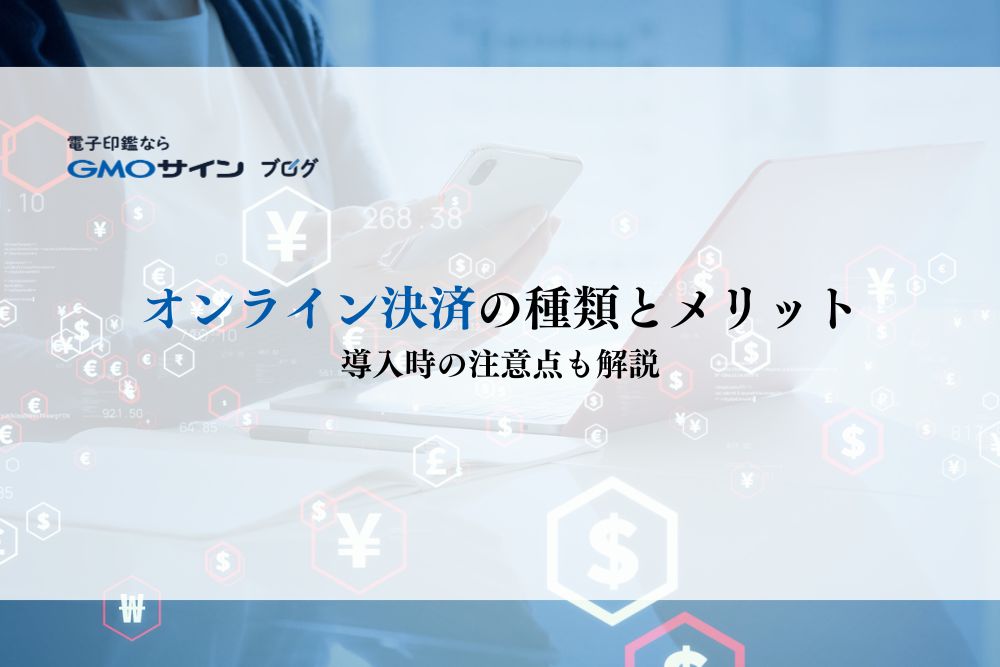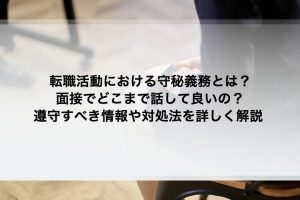2019年(令和元年)12月に施行された通称デジタルファースト法(デジタル手続法)は行政に関する手続きや申請をデジタル化することによって、国民生活の利便性の向上などを目的として制定された、法律です。
しかしその名称だけを見ても、具体的にどのような変化があるのか、わかりにくいでしょう。ここでは、デジタルファースト法(デジタル手続法)によって現状進められている施策を紹介するとともに、企業にどのような対応が求められているのかについて解説します。
目次
デジタルファースト法(デジタル手続法)とは?
デジタルファースト法(デジタル手続法)とは、行政手続きを原則、電子申請に統一する法律です。
正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」と、長いため「デジタルファースト法」(「デジタルファースト法案」)、「デジタル手続法」などと呼ばれています。
なお、ここでは、「デジタルファースト法」と呼び、解説しています。

この法律は取り扱う内容が広く、全体を把握することは難しいのですが、基本的には情報通信技術を活用した行政手続きの利便性の向上、行政運営の簡素化や効率化を図る、といった方針を実現するためのものです。また、この法律は一度に推し進めるのではなく、少しずつ施行されます。
①デジタルファースト:
行政手続きの処理をデジタル優先にし、オンラインで完結させる
②ワンスオンリー:
情報の入力は一度で済ませ、同じ情報の提供を求めない
③コネクテッド・ワンストップ:
複数の行政機関をまたがる手続きを一度の申請で完了させる
このデジタルトランスフォーメーション(デジタル化、オンライン化で生活を豊かにすること)によって便利になる具体例を一部紹介します。
まず、身近な存在であるマイナンバーカードについて見てみることにしましょう。これまで海外転出者は原則として、マイナンバーカードを返却する必要がありました。
しかし、今後は返却の必要がなく、手続きにマイナンバーカードが利用できるようになり、本人確認や各種手続きが可能となります。現在はすでに、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにもなっており、利便性の向上が実現されつつあります。
また役所での手続きにおいては、これまで登記事項証明書などの添付書類が必要だった場合でも、役所間での情報連携が行われることにより、それら書類の添付が不要となります。
なお、マイナンバーカードの普及を目的として2020年(令和2年)5月25日に通知カードが廃止されたのもこの法律の一環です。さらに、国民からのニーズが高い各種手続きや、⺠間サービスを含めた手続きの簡略化推進についてもデジタル化が目指されています。
デジタルファースト法の施行による企業への影響
デジタルファースト法は個人だけでなく、企業にとってもさまざまな影響を及ぼします。こちらでは、そのメリット・デメリットなどを見てみることにしましょう。

デジタルファースト法のメリット
個人だけでなく、企業にも多くのメリットが期待されます。例えば、助成金や補助金などの申請は多くの書類を作成した上で、履歴事項証明書といった公的な書類を取得して添付し、郵送するといった大変時間のかかるものでした。
しかし、前述のようにデジタルファースト法が順次施行されることにより、オンラインで一度情報を入力するだけで、書類を添付する必要がなくなり、容易に申請できるようになります。
さらに、申請された書類を役所などが確認を行う際にも、情報連携によって確認が短時間で行えるようになるため、申請から給付までの時間は大変短くなるとされています。すでに一部の制度では取り組みが始まっており、IT系導入補助金など電子申請できる助成金・補助金は徐々に増加しています。
また、これまで原紙の保管が義務付けられていた紙の書類についても電子化が可能になりました。書類を電子化すれば、いざその書類が必要となった場合でも検索が容易となり、業務効率の向上が見込める上、書類の保存場所の問題も解決できます。
デジタルファースト法のデメリット
これら各種手続きを便利に利用するには、ICTを含むITツールを使いこなす必要があります。そのため、パソコンなどのITツールを使いこなせていない企業は、インフラコストだけでなく技術的なコストが必要です。
さらに今後、各種申告作業の電子化が前提となっていくと、従来のように紙の書類では税金の控除額が下がってしまう可能性も考えられます。実際、個人の確定申告(青色申告)については、電子申告のほうが控除額が大きくなっています。デジタル化にむけた迅速な対応が迫られていることを忘れてはなりません。
デジタルファーストを実現するために求められる企業の対応

現在、デジタルファースト化によって行政上、数多くの革新的制度の運用がすでに開始され、あるいはこれから開始されつつあります。このような状況において企業にはどのような対応が求められるのでしょうか。
まず資本金1億円を超える大企業では、2020年度(令和2年度)より法人税、消費税などの納税申告は、すでに電子申告が義務化されており、書面による申告では無申告扱いとされます。また、大企業では年末調整手続きも電子化が義務付けられています。このように、ビジネス環境は大きく変化しているのです。
こうした背景から、中小企業でも準備が必要であると考えられます。もし社内においてパソコンやネットワークといったITインフラの整備が進んでいないのであれば、導入を急ぎましょう。電子化できる書類は、早い段階で電子化しておき今後に備えておけば、電子申告が義務化された場合でも慌てずに済むことでしょう。
一方、ゼロから「デジタルファースト化」をすすめ、インフラやシステムの構築から行うのは難しいため、クラウド型のサービスを利用し、情報基盤の整備を進めることも検討しましょう。これは、経費精算システムの導入や、電子化を促進できる電子契約システムの導入などが挙げられます。
デジタルトランスフォーメーションのトレンドについて解説
まとめ:デジタルファースト化は現在も進行中、企業は早急に対応を!
デジタルファースト法の目的は、行政手続きを電子化することによって個人や企業の負担を軽減しメリットをもたらすものであることが分かりました。しかし、今後デジタルファースト化が進むにつれ、企業としてどう対応すべきか迫られていることも事実です。どこから手を付ければよいか分からない場合は、まずは、クラウド型の経費精算システムや、電子印鑑GMOサインをはじめとする電子契約システムの導入を進めることが、電子化を成功させるポイントです。
電子印鑑GMOサインは、契約締結やその後の管理などビジネスにおける契約業務の課題を解決いたします。詳細は、GMOサインの特長・選ばれる理由にてご紹介しています。