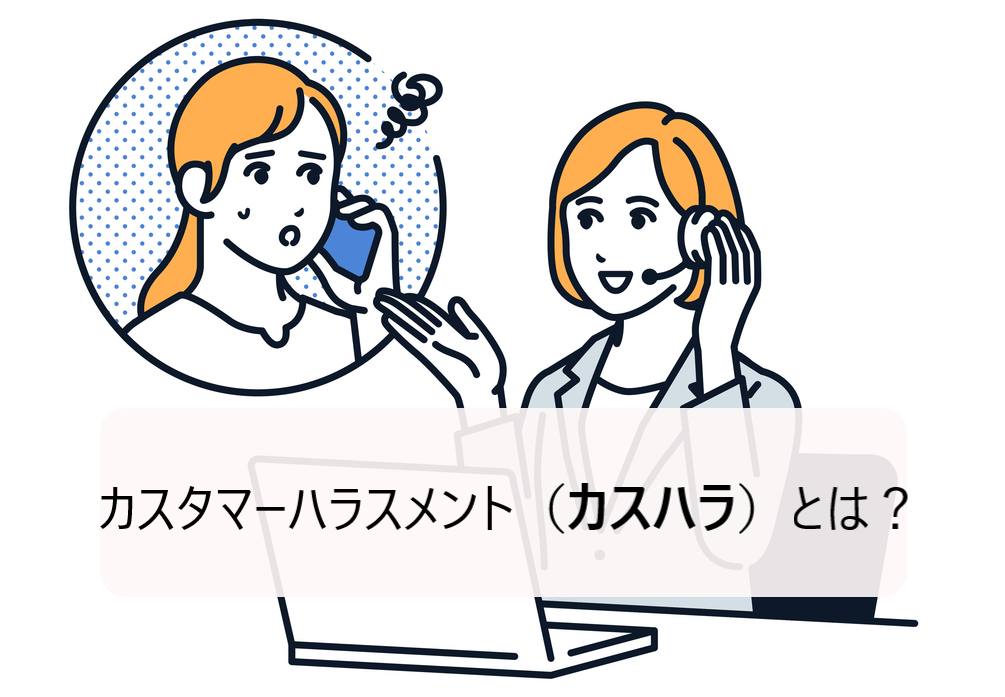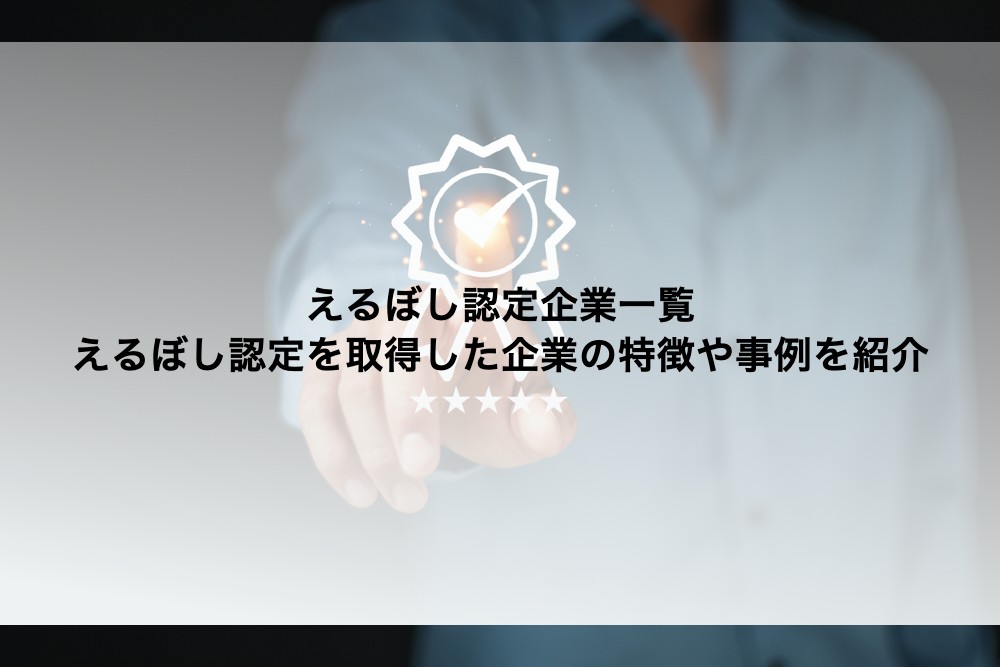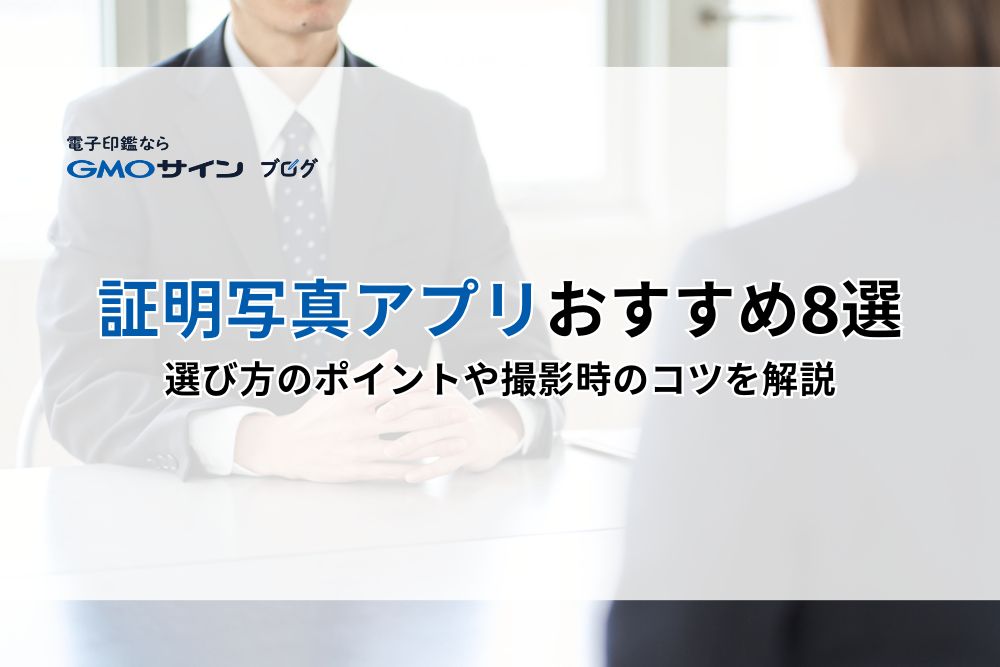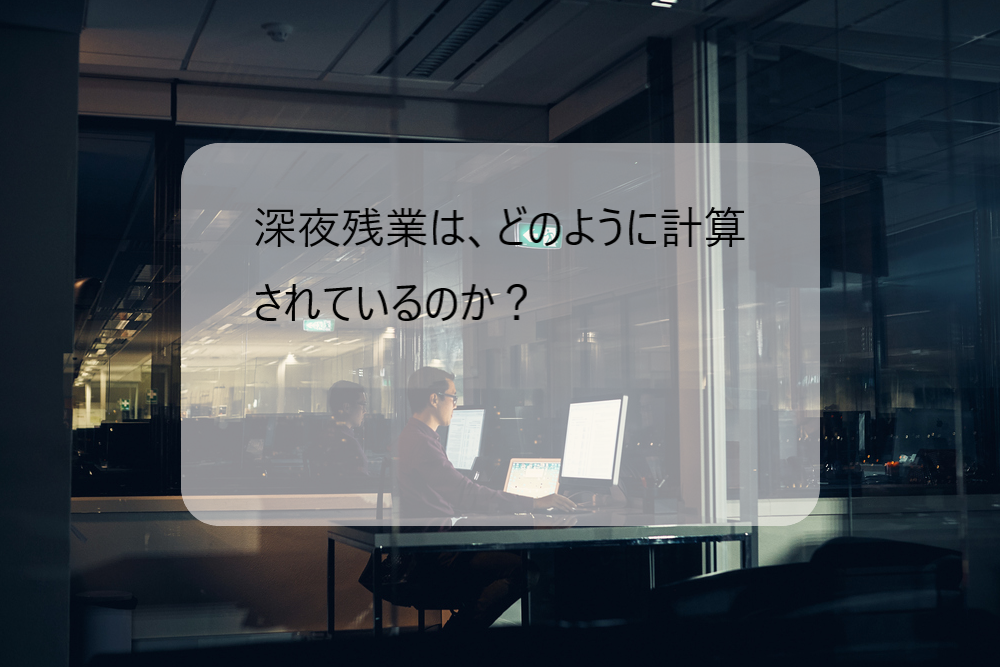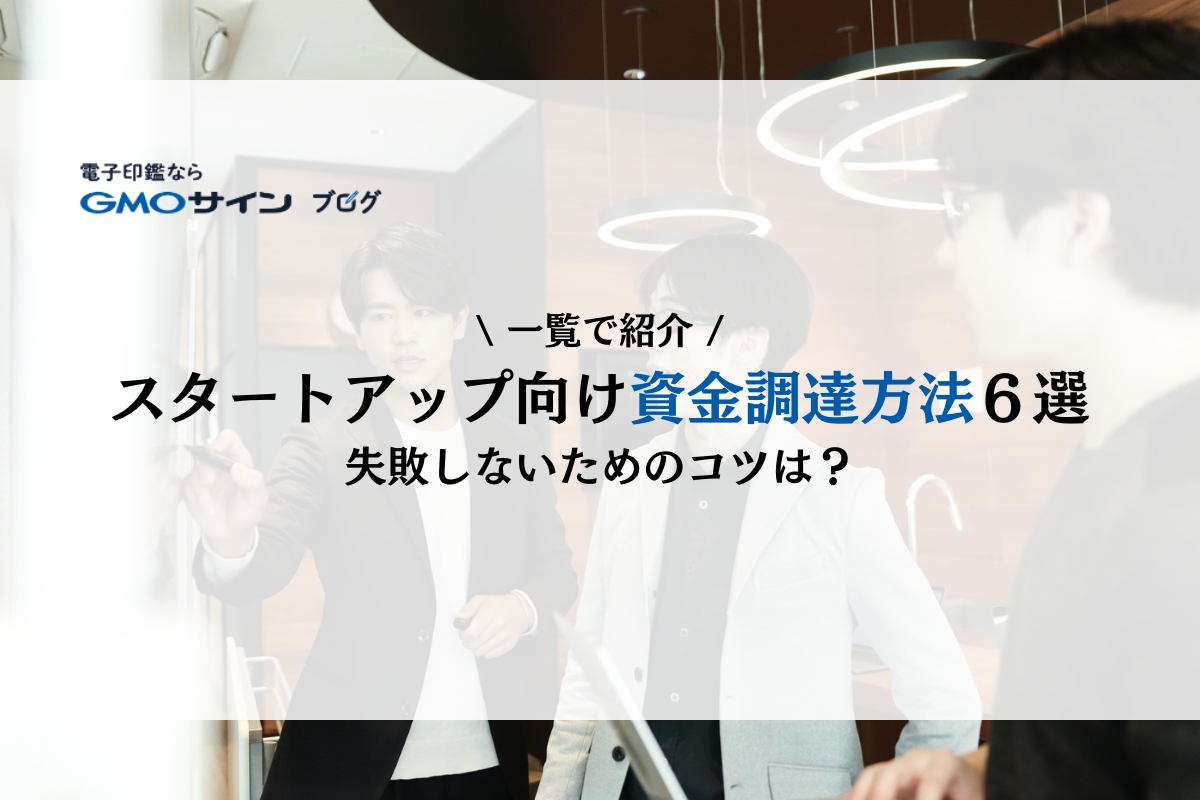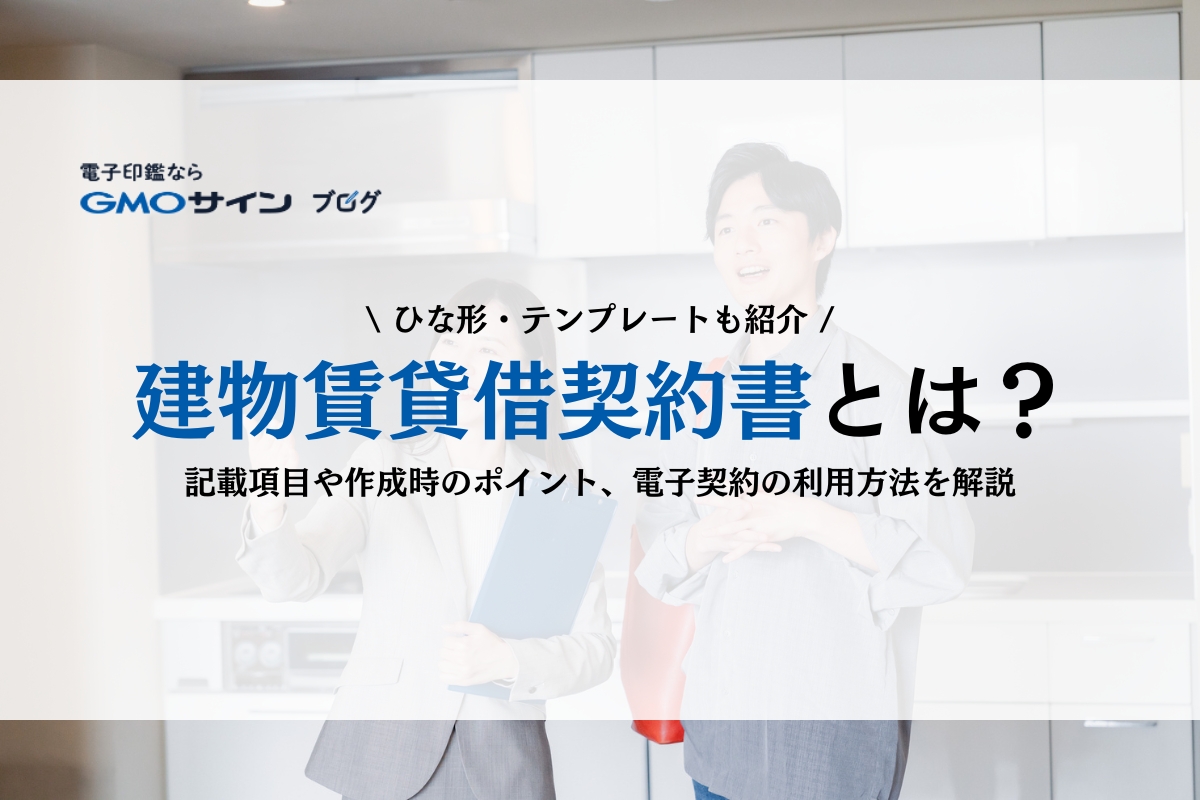職場内におけるセクシャルハラスメント(セクハラ)対策は事業主の義務です。そのため、経営者や管理者は責任を持って、セクハラの防止や問題解決にあたらなければなりません。
日頃からセクハラのない環境で、男女ともにいきいきと働ける職場づくりに取り組むことにより、社員が本来のスキルや持ち味を発揮できるようになります。
このことは、事業の発展にもつながるでしょう。セクハラの防止は、法で定められた内容を守るだけでなく、職場環境や個々にあわせて柔軟に対応していくことが必要です。
目次
セクハラとは?セクハラの定義
男女均等雇用法によるセクハラの定義とは、職場のなかで行われる行為で、なおかつ被害を受けた労働者の意思に反してされるセクシャルハラスメント(性的ないやがらせ)のことです。
またセクハラに対して労働者が対応した際に、当該労働者が労働条件において不利益を被ったり、就業環境を害されたりすることもセクハラに含まれます。
「職場のなか」とは
職場とは、労働者が通常就業している場所だけではありません。会社のために業務を行う場所はすべて職場となるため、通常就業している場所以外であっても職場とみなす場合があります。
たとえば、打ち合わせ先や出張先、業務中の車の中、宴会や懇親会、送別会などの場も含まれます。
そのため、業務に関係していれば、飲食店や接待の場も職場となります。勤務時間外でも、業務の一環として認められる行為であれば、当該行為場所は職場となりますが、その判断は一概には決められません。参加が強制されたものかどうか、業務と関係しているのかなど、個別具体的な判断が必要です。
労働者とは
男女雇用機会均等法における労働者とは、正規雇用労働者だけではありません。パート従業員や契約社員などの非正規を含むすべてが対象です。
一方、派遣社員については、派遣元となる事業主だけではなく、派遣先の事業主もみずからが雇用する労働者と同じセクハラ対策を取る必要があるため注意しましょう。
セクハラとなる行為者
セクハラは、性的な言動または性的な接触により引き起こされます。事業主や上司、同僚に限定せず、取引先の顧客や患者、学校の生徒などもセクハラの行為者となるケースがあります。また異性だけではなく同性に対して行う場合も、セクハラは成立するため注意が必要です。
性的な言動とは、性的な話を広めることや性的な事実関係を問う行為のことです。ほかにも、性的な揶揄や断ったのに何度もしつこく食事に誘ってくること、個人的な性的エピソードを聞かされることなどがセクハラにあてはまります。
一方、性的な接触とは、性的な関係の強要や必要以上のからだへの接触、わいせつな内容の図面を配ることなどです。
セクハラ被害は職場内で予想以上に多い
職場内のセクハラは、実は予想以上に多いのが現状です。
都道府県労働局への男女雇用機会均等法に関する相談のうち、セクシュアルハラスメントに関する相談が最も多かったようです。
【参考】https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001274451.pdf
会社の相談窓口に相談がなかったとしても、社内でセクハラが起こっていないとはいえません。都道府県労働局への相談内容として、「 相談できる職場ではない」「相談窓口が使いづらい」などもあげられているからです。
相談窓口に相談がなかったとしてもセクハラ被害はないとは決めつけずに、社内の実態をきちんと把握し、効果的な対策を取ることが肝心です。
セクハラ対策は事業主の義務
セクハラ対策は事業主の義務として、男女雇用機会均等法11条1項にその内容が定められています。男女雇用機会均等法は2019年に改正がなされ、セクハラ相談や事実確認の協力を行ったことにより、労働者が不利益をこうむることを禁止する内容が追加されました。
また11条の2第2項では、事業主がセクハラ問題に対する理解や関心に努めて、研修などを行うように努力義務規定をもうけています。この項では、労働者についても、努力義務を定めていることが特徴です。言動に気をつける、セクハラ対策を実施している会社に協力するという内容が盛り込まれています。
第二節 事業主の講ずべき措置等
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113
男女雇用機会均等法に違反した事業主は、厚生労働大臣から助言や指導、勧告などの措置が取られることがあります。厚生労働省からの勧告に事業主が従わない場合は、社名と当該勧告の内容に従わなかったことが公表されるケースがあります。
直接的な罰則はありませんが、セクハラ被害者を出し、その勧告に従わなかったことを公表されてしまうと会社は社会的な信用を失ってしまうかもしれません。経営上の不利益が発生し、採用にも影響を出してしまう可能性はいなめません。
セクハラを防止しないと会社は責任追求を受けることもある
セクハラを防止するための条文である男女雇用機会均等法11条1項に違反しても、会社は直接的な罰則は受けません。しかし、民法上の債務不履行責任や使用者責任の違反によって、セクハラ被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
債務不履行責任は、民法415条1項に規定されています。簡単にいえば、会社が本来しなければならない義務を果たさなかった場合は、社員はそのせいでこうむった損害の賠償を請求できるというものです。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
つまり、会社は社員と雇用契約を結んでおり、契約上の義務として社員が快適に働けるような環境を整える必要があるということです。
もし、セクハラがあった場合は、その快適な環境整備を行っていなかったことになるため、セクハラを受けた被害者は会社に対して債務不履行責任を追求し、損害賠償を求めることができるのです。
一方、使用者責任とは、民法715条1項に規定されており、会社は社員が第三者に損害を与えた場合の責任を取る義務があるというものです。
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
つまりは、セクハラ加害者が被害者に行った責任を会社も負うことになる(使用者責任)というものです。ただし、会社側が相当の配慮を行っていたときや相当の配慮を行っていたとしても防げなかった場合は、このかぎりではないとしています。
債務不履行責任や使用者責任は、どちらも違う責任のため、両方の責任が追求されるケースが多いです。
セクハラの種類
セクハラには、対価型セクハラと環境型セクハラの2種類が存在します。
対価型セクハラとは、労働者が性的な要求を断ったことなどを理由に、解雇や降格、減給などの不当な扱いを受けるセクハラの形態です。
たとえば、上司が部下に対して性的な関係を強要し、それを部下が断ったことで解雇されたなどです。また昇給を約束することを条件に、上司が部下に性的な関係を強要することも対価型セクハラのひとつです。
一方、環境型セクハラとは、労働者が性的な言動をされたことにより深く傷つき就業意欲が下がったり、仕事に集中できなかったりするなどの就業環境を害されるセクハラの形態です。
たとえば、上司が部下の体を必要以上に触ってきたり、休憩時間中に性的な内容の会話を毎日のように聞かされたりして不快感で業務に集中できないなどの場合です。このほか、事務所内に性的なポスターを貼ったり、飲み会でお酌を強要したりすることも環境型セクハラになります。
どこからがセクハラとなるのか
労働者がセクハラの行為者とならないように、また効果的なセクハラ対策を行うために、セクハラとなってしまう言動を把握しておく必要があります。
しかし、さまざまなセクハラが存在するため、上記のようなわかりやすいもの以外に、判断に困るものも多々あります。
そのため、どこからがセクハラとなるかを断定することは難しいでしょう。判断する際は、一つひとつの案件について個別に精査していく必要があります。
セクハラを判断するときは、基本的にはセクハラ被害者の主観面を重視しています。しかし、一定の客観性も必要となることから、厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策マニュアルを作成しセクハラ認定の判断基準を定めています。
マニュアルには、1回でも労働者の意に反して身体的な接触をされて、強い精神的苦痛が生じた場合はセクハラとなりうると書かれています。
一方、継続的にまたは繰り返しを要件とする内容であっても回数だけでは判断できません。毅然と抗議しているのに放置されている、または行為により心身に重大な影響を受けている状態にいたってはセクハラと判断する場合もあるとされています。
またセクハラには、性的マイノリティに関する性的指向や性自認への偏見による言動なども含まれます。たとえば性的マイノリティについて否定したり、偏見にみちた発言をしたりすることはセクハラにあたるため、注意が必要です。
セクハラ対策として事業主が取らなければならない措置
男女雇用機会均等法11条に事業主が取らなければならないセクハラ対策措置が書かれています。必要となる対策は以下の4つです。
・方針の明確化および周知や啓発
・適切な相談窓口の設置
・事実確認や適切な対応、再発防止措置
・その他の措置
方針の明確化および周知や啓発
事業主はセクハラに対する方針を明確化して、管理者などを含むすべての労働者に対して周知や啓発を徹底する必要があります。セクハラに対する方針を就業規則に定める、社内報や自社ホームページなどに掲載する、セクハラに対する研修や講習を実施するなどにより、労働者の意識改革を行いましょう。
またセクハラ行為者に対する懲戒規定を定め、その旨をすべての労働者に対して周知や啓発する必要もあります。
適切な相談窓口の設置
事業主は、セクハラ被害にあった労働者からの相談に対応できるように、適切な相談窓口を設置しなければなりません。相談窓口は労働者が利用しやすいように整備し、その存在を周知させておく必要があります。
また相談方法は対面だけでなく、電話やメール、オンラインなど複数の方法が取れるように工夫しましょう。相談後にすみやかに対処できるようなフォロー体制もととのえておくとよいでしょう。
事実確認や適切な対応、再発防止措置
事業主はセクハラの相談があった場合、迅速かつ正確に事実確認を行う必要があります。事実確認は相談者と行為者とされる社員の両方に行います。もし事実確認でセクハラ行為が認定された場合は、すみやかに被害者に対して適正な処置を行うことが肝心です。
たとえば、被害者と行為者が会わないように配置換えをする、行為者に謝罪してもらうなどです。そして、二度とセクハラ行為が起こらないように、再発防止措置を取る必要があります。
その他の措置
その他の対策として、セクハラ被害者または行為者のプライバシー保護につとめる必要があります。また相談窓口を利用しやすくするためにも、プライバシー保護措置について、労働者に周知させることが必要です。
あわせて読みたい
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?罪に問われることはあるのか。正当なクレームとの違いや対策...
近年ではセクハラやパラハラなどの言葉をよく耳にしますが、新しくカスハラというハラスメントも記事やニュースで出てくるようになりました。カスハラはカスタマー(顧...