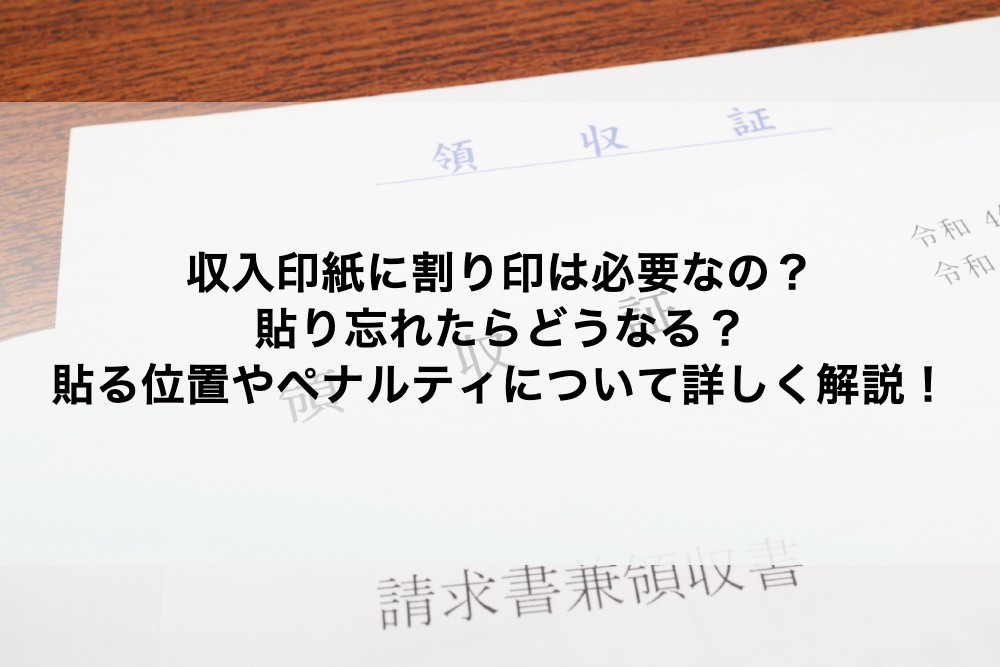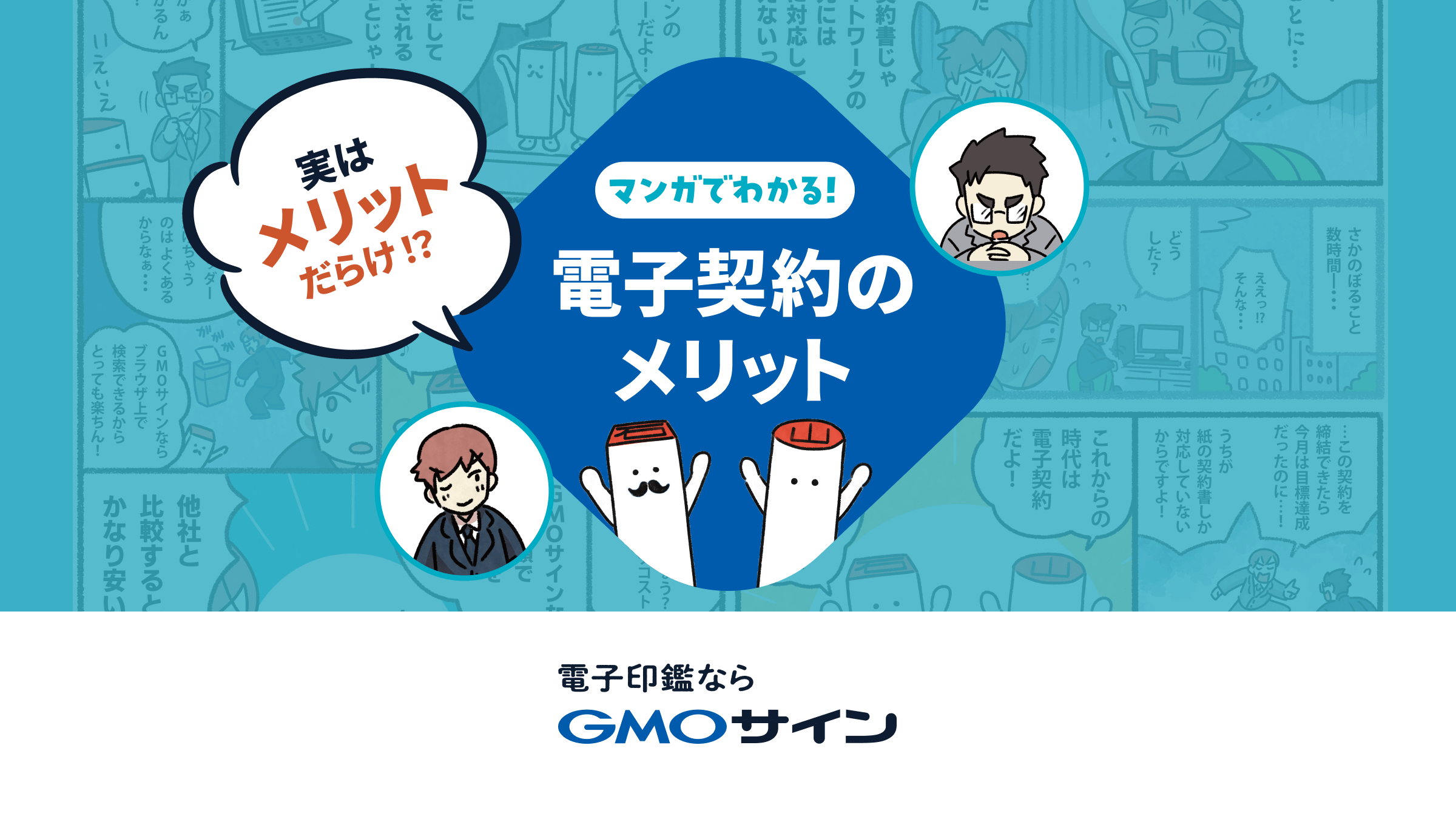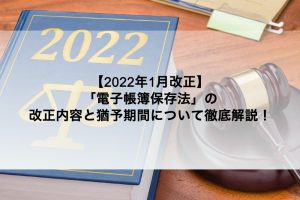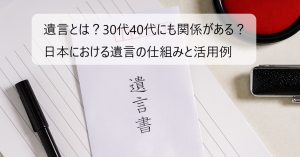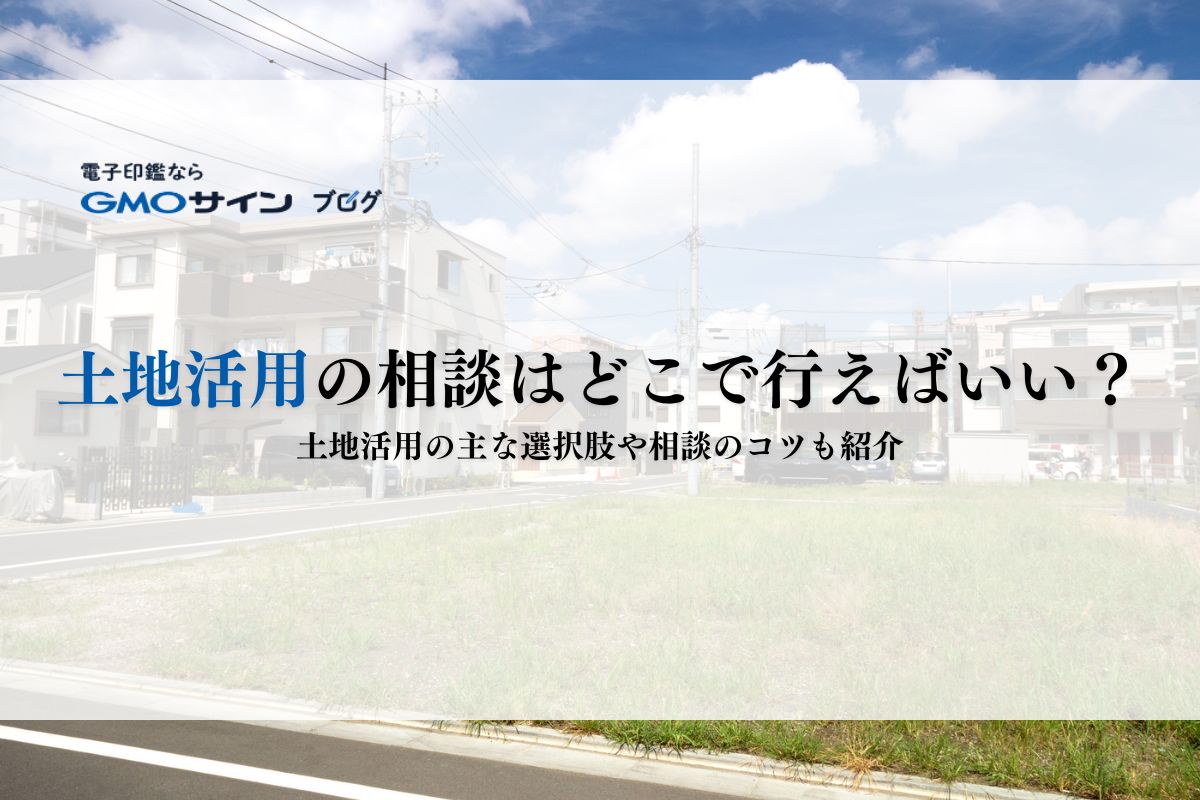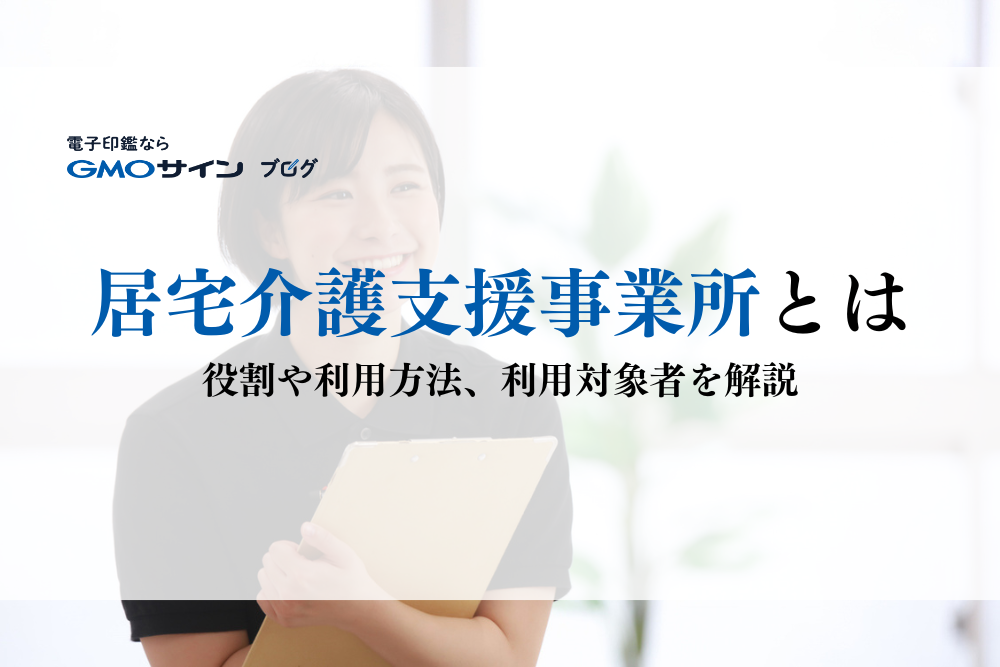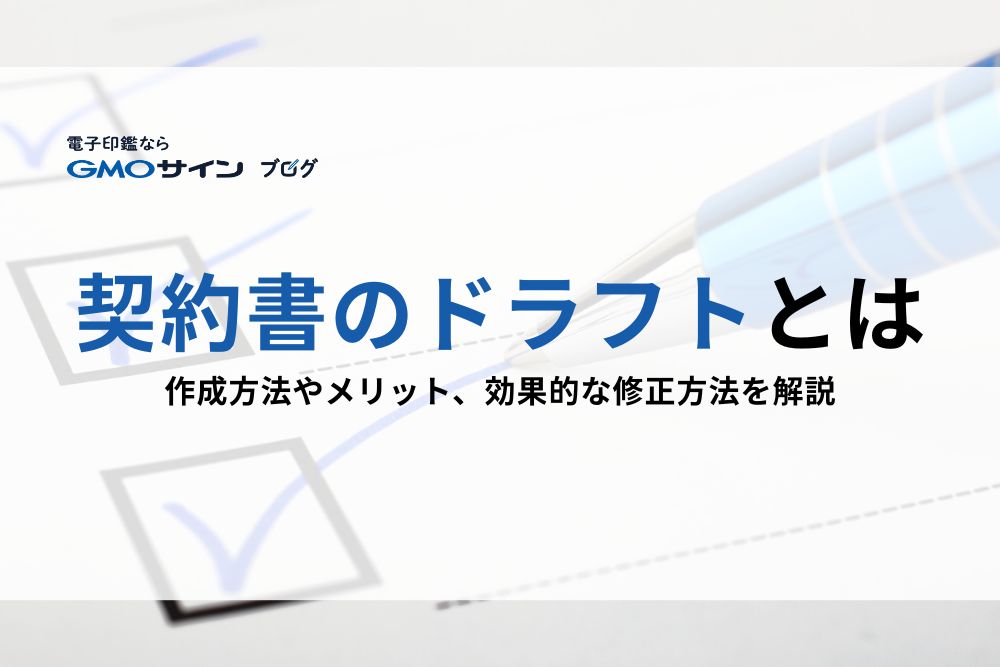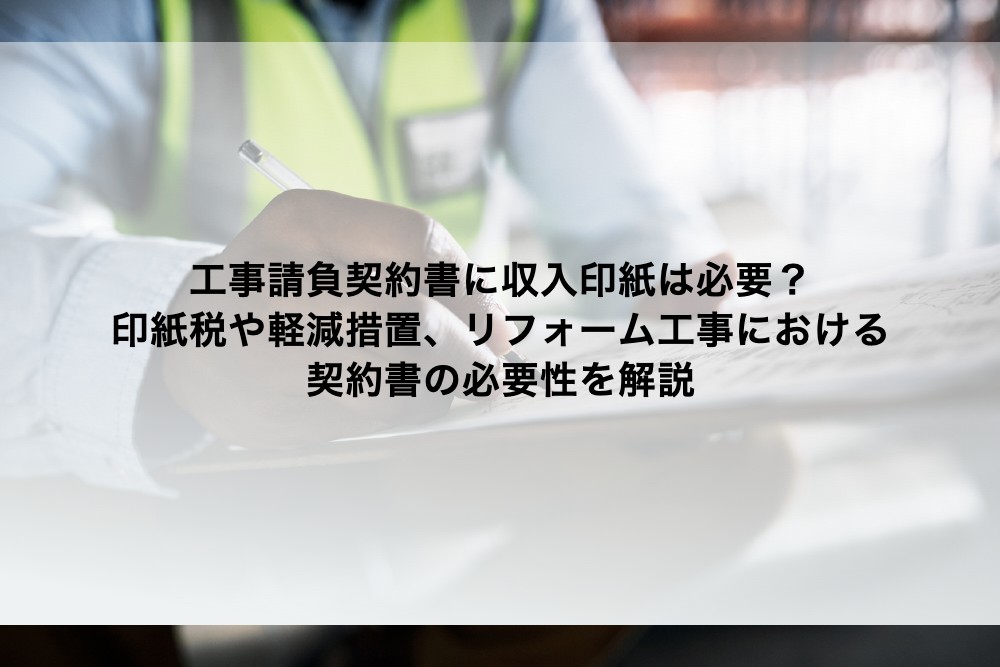企業で用いられる契約書などの文書には、収入印紙が必要です。また収入印紙を貼り付けた後には割り印を押さなければなりません。これらの一連の作業は印紙税という法律によって規定されており、ミスや間違いがあるとペナルティがあります。
そこで本記事では、文書を適切に作成するための収入印紙と割り印のルールについて詳しく解説します。ペナルティを避けるために詳細な部分もお伝えしますので、ぜひご覧ください。
目次
収入印紙とは?
収入印紙とは、税金や手数料を納付するために使われる国が発行する証票です。収入印紙は、印紙税法で「課税文書」として規定されている書類に用います。対象となる課税文書は印紙税法「別表第一 課税物件表」に記載されており、20種類の文書が指定されています。
代表的な課税文書は、以下の通りです。
・企業間の取引契約書
・工事や建築の請負契約書
・不動産売買契約書
・土地賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
また身近な文書として使われている領収書も場合によっては、収入印紙が必要です。通常領収書では収入印紙は使われませんが、金額が5万円以上となる場合には貼付しなければなりませんので気をつけましょう。
収入印紙には割り印も必要
課税文書に収入印紙を貼り付けた後には、割り印も必要です。その収入印紙が使用されたことを証明するために法律で規定されているので、注意してください。
収入印紙を忘れたらどうなるのか?
収入印紙は印紙税法によって貼付が定められた帳票であるため、貼り忘れなどがあるとペナルティがあります。そこで収入印紙の適切な使い方を詳しく解説しますので、ご覧ください。
収入印紙を貼り忘れると、「過怠税」が課される
課税文書で収入印紙を貼り忘れた場合には、「過怠税」が課されるケースがあります。過怠税は印紙税額の2倍であり、本来貼るべき収入印紙の金額と合わせると3倍の金額を支払わなければならなくなります。
ただし、印紙税不納付事実申出書を提出すれば印紙税額の1.1倍で済みますので、万が一貼り忘れた場合は必ず作成して提出しましょう。
収入印紙はどこに貼るのか
収入印紙の貼付場所は特に定められていないため、課税文書上のどこに貼っても問題ありません。領収書などで「収入印紙貼付欄」といったスペースが設けられている場合には、そこに貼りましょう。契約書では、文書の左上に貼付するのが一般的です。
また印紙税が細かくなる場合や大きな額の収入印紙を用意できなかった場合などには、1枚の文書に多くの収入印紙を貼るケースもあります。このようなときには、収入印紙が重ならないようにして、必要な金額の収入印紙が貼付されていることが分かるように気をつけましょう。
電子契約なら収入印紙が不要
近年電子契約サービスの浸透により、パソコンで契約書をやり取りして取引を完了させる企業も増えています。電子契約はスピーディーに取引を完了できたり、書類を保管しやすくなったりするといった様々なメリットがありますが、収入印紙が不要という大きな利点も存在します。
特に企業間では高額な契約が交わされるケースが多く、契約金額が高くなれば印紙税も高くなります。場合によっては数万円以上かかることもあり、その上回数が多くなると比例して費用も増えてしまいます。
そのため、印紙税対策のためにも電子契約サービスを導入することをおすすめします。
収入印紙に必要な割り印について
課税文書に収入印紙は必須ですが、貼付した後には割り印を押す必要があります。割り印は納税の証明に利用され、主に印鑑が使われますが署名でも大丈夫です。
割り印の付与は印紙税法で規定されている
割り印は貼り付けた収入印紙が使用済みであることを証明して、かつ再使用できなくするために付与されます。印紙税法によって、割り印の付与は義務化されているため必ず押すように気をつけましょう。
割り印を失念したら過怠税が課される
収入印紙に対する割り印は、印紙税法で規定されています。そのため割り印を忘れてしまった場合には、過怠税として印紙税額の3倍がかかるため、入念にチェックしておきましょう。
電子契約サービスを導入して、コストを削減しましょう!
契約書などの課税文書には、収入印紙が必要です。その金額も日々積み重ねていくと、かなりのコストがかかる計算になります。特に毎日のように経済活動を行っている企業にとっては、金額だけでなく収入印紙を購入する手間や時間も負担になってしまいます。
そこでおすすめするのが、「電子印鑑GMOサイン」です。電子契約ならば印紙税を全額カットでき、収入印紙を用意するコストもかかりません。金銭の節約だけでなく、無駄な業務時間の短縮にも役立ちますので、経営のスマート化に大きく貢献します。
電子印鑑GMOサインは無料でご利用いただけますので、ぜひ企業で使ってみてください。