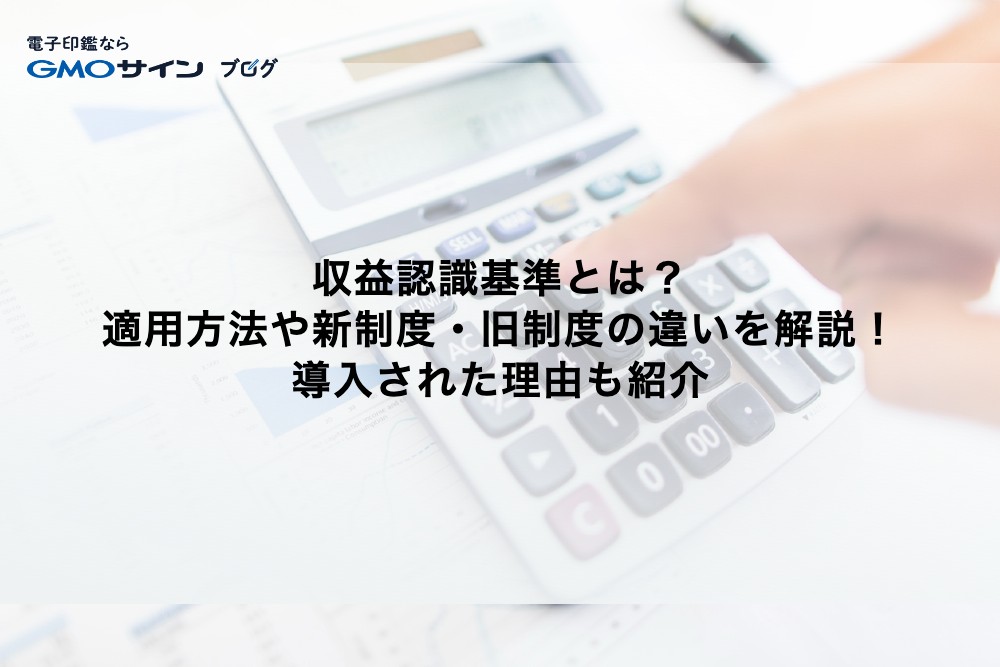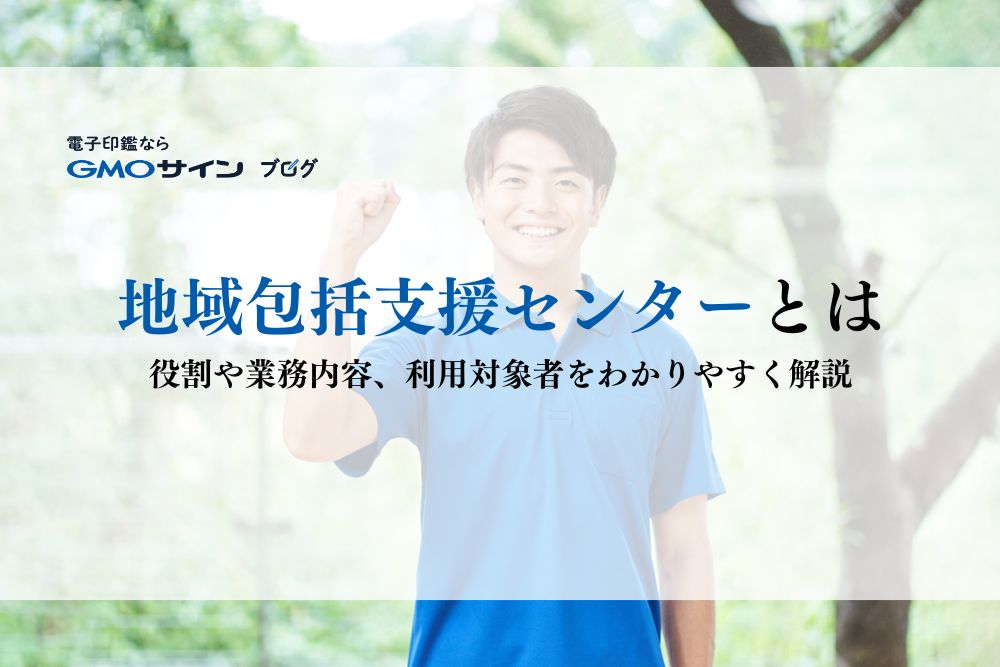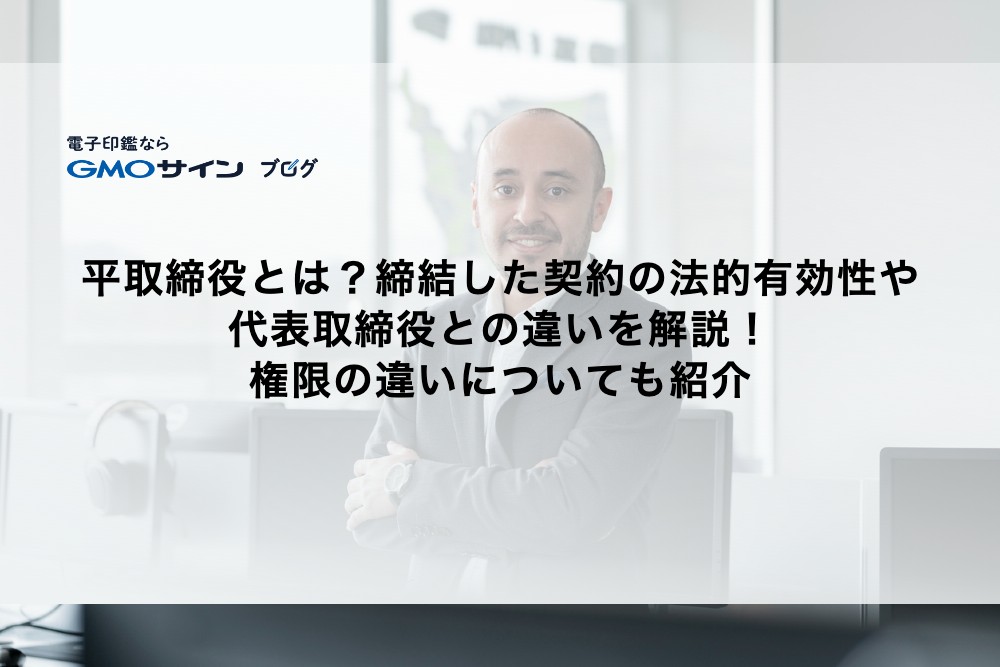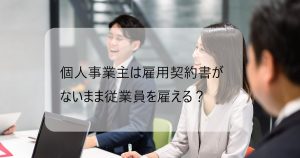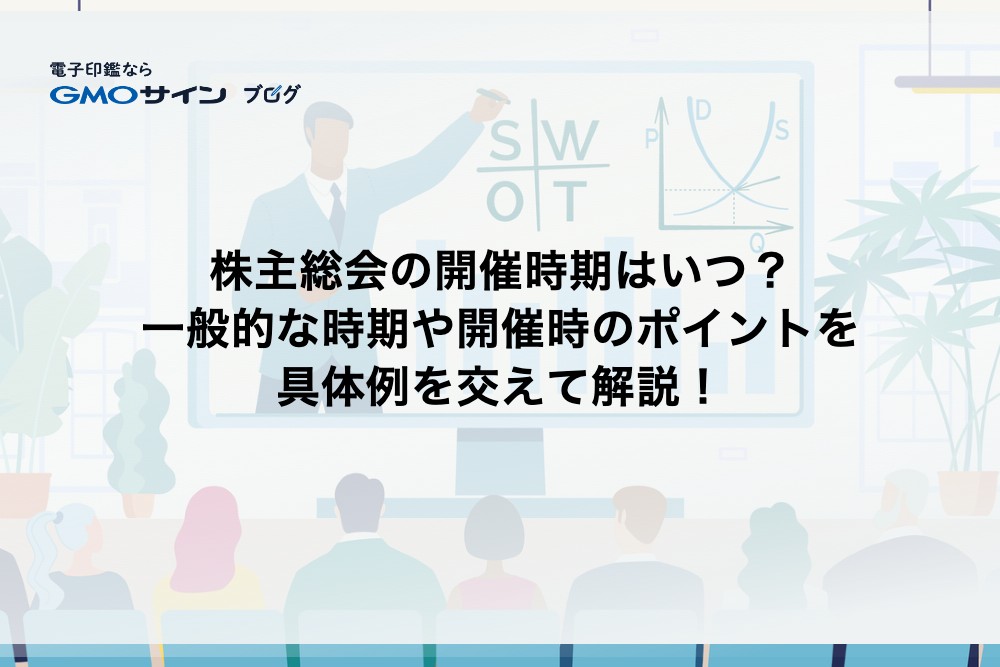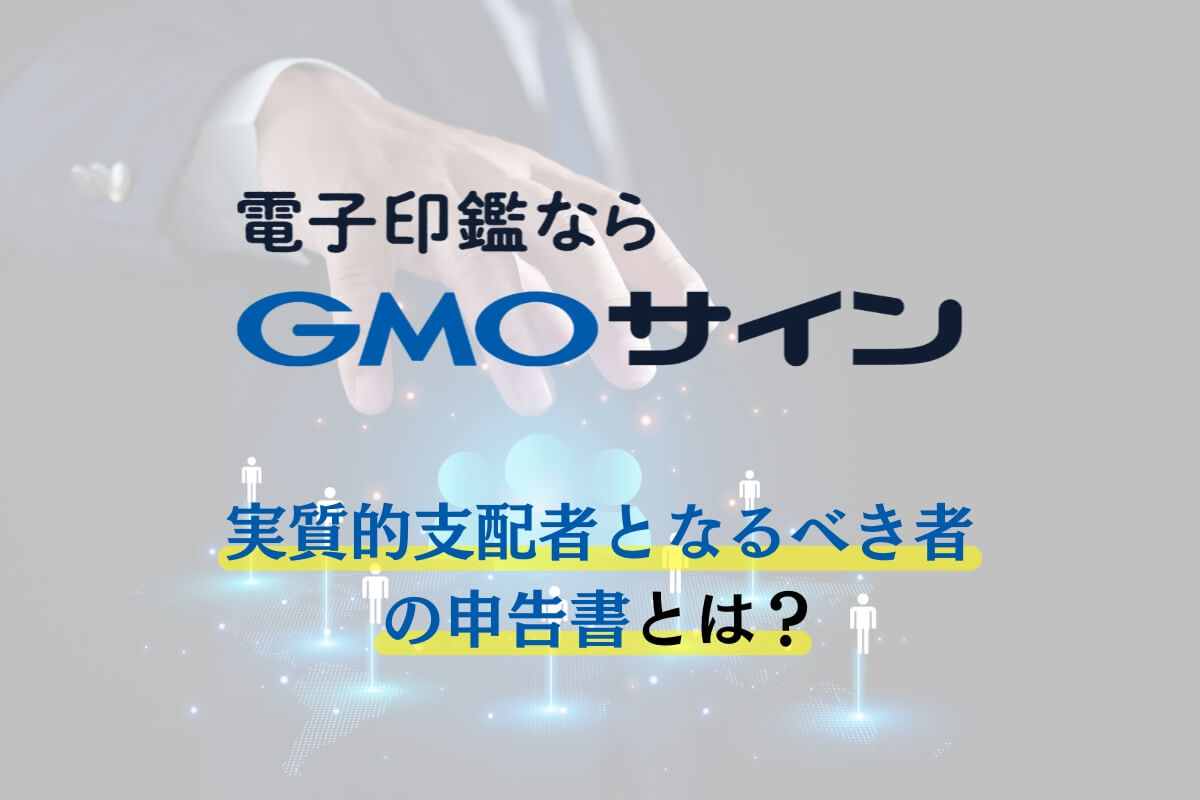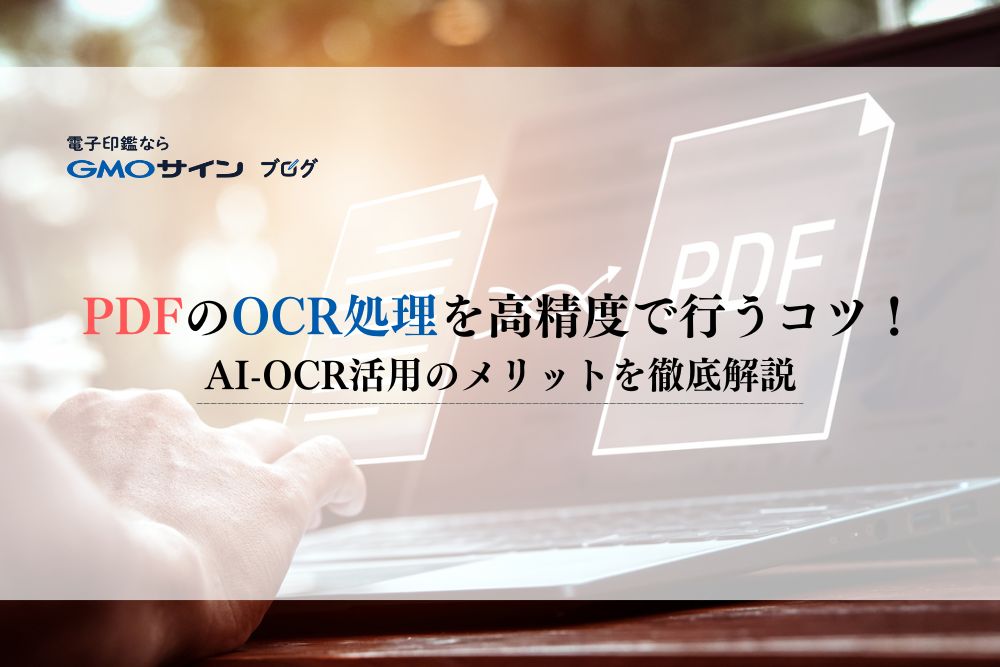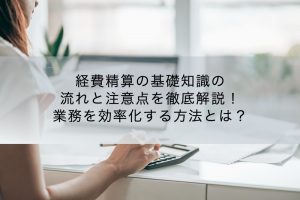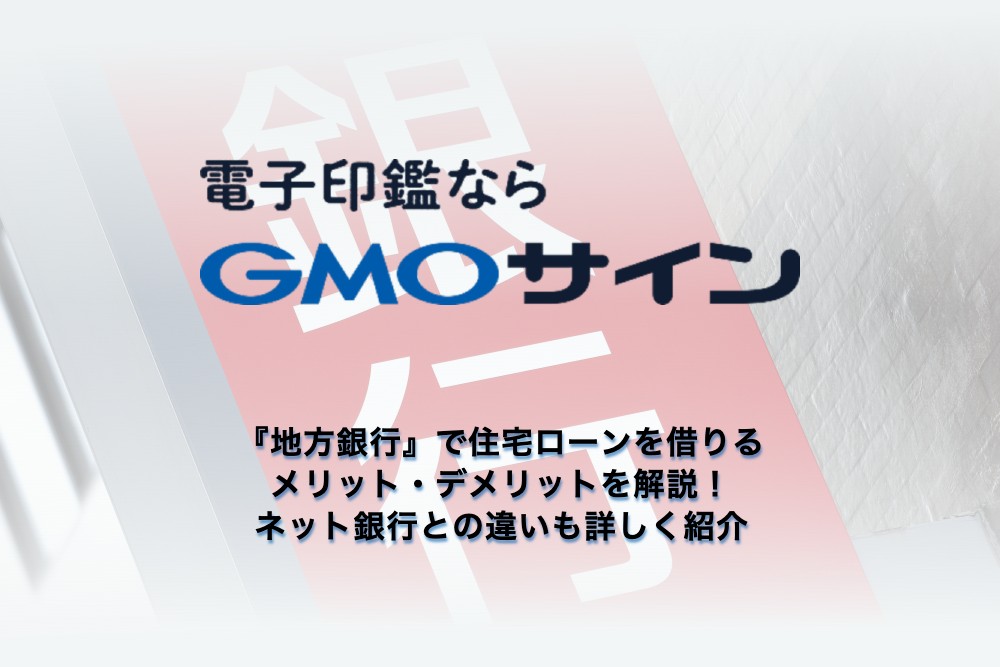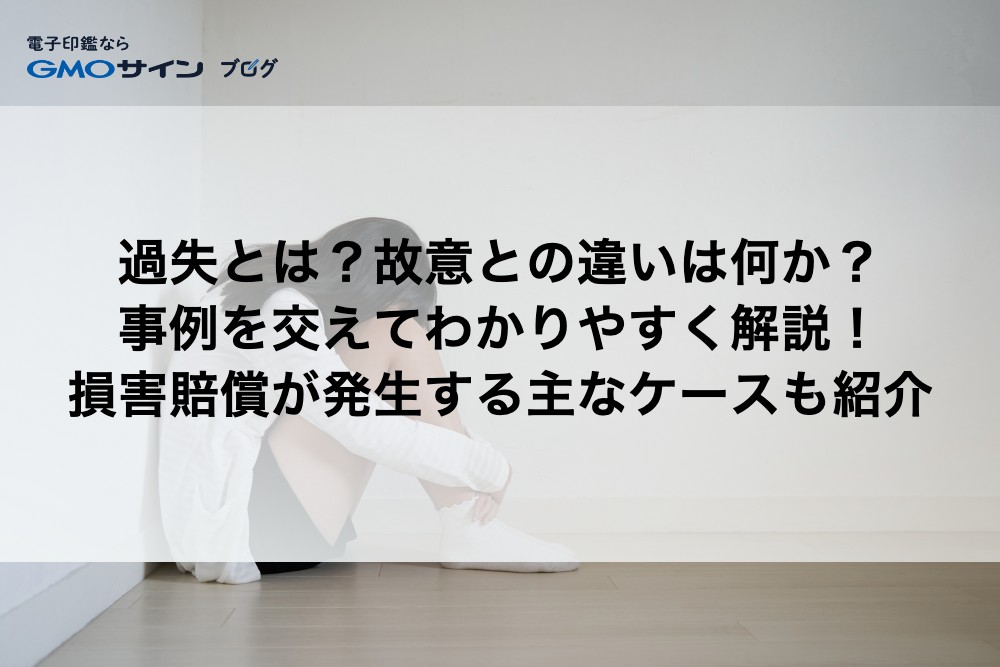2021年の4月から新しい収益認識基準の適用が始まりました。
これは全ての企業が会計処理をする際に適用される新たな基準ですが、中小企業であれば従来の方法で会計処理をしても問題ありません。しかし、今後どのように変更されるかは明確にわかっていないため、備えておくことは大切です。
収益認識基準とは何か
会社の売上をどう認識するのか、どのタイミングで財務諸表に反映させるのかを定めた基準となります。
しかし、2021年4月から新たに収益認識基準が適用される運びとなり、特に上場企業などの大きな会社は、2021年より新収益認識基準が適用されることとなりました。新しく制定された収益認識基準は、5つのステップを通して算出された金額を収益として計上します。
収益認識基準が導入された理由
なぜ新たな収益認識のための基準が導入されたのでしょうか。前述したように、2021年3月までの日本には、収益を認識するための包括的な基準がありませんでした。当時の日本の企業の会計処理におけるルールは実現主義に基づいて行うということだけが共通のルールとして存在していました。
しかし、近年は様々な事業が登場し、企業の事業内容も多様かつ複雑になっています。そのような中で、実現主義だけを共通のルールとする収益認識では、会計処理を行うことに限界が生じるようになってきました。そのため、新しく収益認識の基準となる制度が必要となり、新基準が導入される運びとなったわけです。
取引が実現するタイミングとは商品、またはサービスが提供され、対価として報酬を受け取っている状態のことです。
現金の受け取りがなされた時に収益を認識する現金主義という考え方があり、記帳が簡単なことがメリットとして挙げられます。しかし、現金の受け取りを収益認識とする関係上、掛取引などの場合には売上と費用の計上時期が合わなくなってしまうため、法人で適用できないという点がデメリットとして挙げられます。
しかし、発生主義は受注から始まり契約、生産や納品などの過程をもつ企業にとってはどの段階を取引の発生とするかを認識するのが難しい点がデメリットです。
発生主義は費用を認識する点では問題ありませんが、収益を認識する場合、実際に商品を販売する前であっても売上が計上できるため、業績の粉飾も可能になってしまいます。そのため、これまで日本では費用の認識に発生主義を、そして収益の認識には実現主義が用いられてきました。しかし、多様化する企業への対応が求められるようになり、同一の基準が導入されることになりました。
なお、日本で新しく収益認識基準が導入される前に、国際会計基準審議会(IASB)が米国財務基準審議会(FASB)と共に収益認識基準を開発しています。こうした国際情勢の動きもまた日本における収益認識の新しい基準を導入するために大きな影響を与える出来事となりました。日本も新しく収益認識基準を導入することにより、世界的な会計基準と歩調を合わせることができるようになるわけです。
収益認識基準の適用方法
新しく導入された収益認識の基準では、5つのステップを通して売り上げを計上します。
契約の識別
まず一つ目のステップは、契約の識別です。契約の識別では商品、またはサービスの提供に関する契約の確認を行います。これには正式に書面で交わした契約はもちろん、商慣行や口頭における約束なども含まれます。
履行義務の識別
二つ目のステップは、履行義務の識別です。履行義務とは契約内容における約束事のことです。たとえば、何かの商品を販売する契約に、商品の保守サービスも含まれているとします。そのような契約の場合、履行義務は商品の販売だけでなく保守サービスも含まれるため2つの履行義務があると考えられます。履行義務の識別では、これまで契約そのものを一体として認識していたのに対し、契約内容に含まれる履行義務を個別に認識するのが大きな特徴です。履行義務という考え方は日本の従来の会計基準にはありませんでした。
取引価格の算定
三つ目のステップは、取引価格の算定です。これは契約が履行された際に全体の取引価格を算定するステップです。新しく導入された収益認識基準では、取引価格の算定の際に、ポイントやクーポンを適用した提供額を差し引くことになりました。これまでの会計基準では、商品やサービスの販売がなされた場合には売上金額の全てを計上することができましたが、新しい収益認識基準ではそれができなくなったことが大きな特徴です。
履行義務への取引価格の配分
四つ目のステップは、履行義務への取引価格の配分です。これは二つ目のステップと三つ目のステップを合わせる工程になります。契約全体の取引価格を個別に分けた履行義務に配分する工程です。たとえば、契約全体の取引金額が10万円、そして契約内容に沿って商品販売と保守サービスの2つの履行義務があるとします。そのような場合には商品販売に7万円、そして保守サービスに3万円といった具合に履行義務ごとの価格を設定します。
収益の認識
そして、最後となる五つ目のステップが収益の認識です。四つ目のステップで履行義務とその取引価格が決まりましたが、収益はこれらの履行義務が果たされたタイミングで認識されることとなります。四つ目のステップの例で説明すると、商品販売の履行義務は商品が実際に顧客の手に渡ったタイミングで果たされます。この時の取引価格7万円はこの時点で計上されます。一方、商品の保守サービスの履行義務は一定の契約期間を経て果たされます。たとえば、2年間の保守サービスが契約上交わされていた場合、初年度に1万5,000円の取引価格が、二年目に残りの1万5,000円が計上されます。
新しい収益認識基準の適用方法
新しい収益認識基準は2021年から適用されてきましたが、これから適用を考えている企業はどのように対応すべきでしょうか。これにもいくつかのステップがあるので、順次適用していくことで大きな混乱を避けることができます。
現状の把握
まず一つ目のステップは、現状の把握です。収益認識基準の適用方法で説明したように、この新しい基準は契約全体における履行義務に基づいています。そのため、まずは自社の商品やサービスの契約内容を改めて見直し、契約にどのような個別の履行義務があるのかを把握します。さらに現状の把握では、個別に分けた履行義務に従って収益が認識された際にどんな問題やリスクが発生する可能性があるのかも確認します。この時、現在使用している会計ソフトやシステムが新しい収益認識に対応しているかも確認するようにしましょう。もし対応していない場合にはアップデートが可能なのか、それともシステムを見直す必要があるのかも検討します。
新基準の適用となる取引の絞り込み
次に行う二つ目のステップは新基準の適用となる取引の絞り込みです。企業は全ての契約において新しい収益認識基準を適用しなければならないわけではありません。そのため、どの契約を新しい収益認識基準に適用させるのかを取捨選択します。この時、契約そのものの性質も考慮すべきです。また、大きな企業の場合には会計部門で働く人たちの負担などを考慮に入れつつ、重要度の高いものから優先的に新たな収益認識基準に適用させていくと良いでしょう。
決定方針の実行
そして最後、三つ目のステップは決定方針の実行です。新たな収益認識基準を適用するにあたって、どのくらいの労力と費用がかかるのかを算出し、人員確保やスケジュール調整を行って決定したことが確実に実行されるようにしましょう。そして、実際に運用が始まった後も問題が発生していないか計上金額などを適宜チェックしていくことで、新しい収益認識基準を定着させていくことができます。
まとめ
2021年4月から適用されることとなった収益認識基準は、日本企業の収益認識を統一させる目的があります。
収益認識は契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、履行義務への取引価格の配分、収益の認識の五つのステップで行います。この新しい基準を適用させるためには現状の把握を行い、次に新基準の適用となる取引の絞り込みを行います。そのうえで、決定方針を実行していけば、問題なく適用していくことができるでしょう。