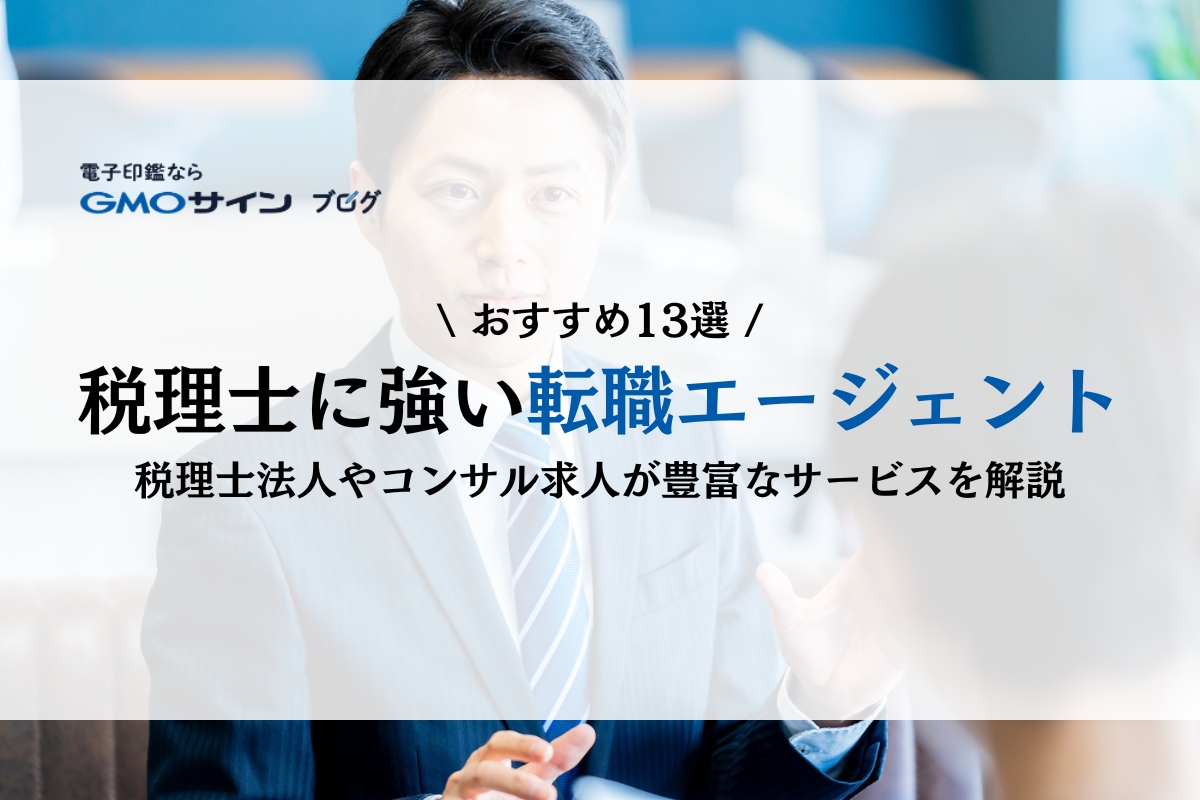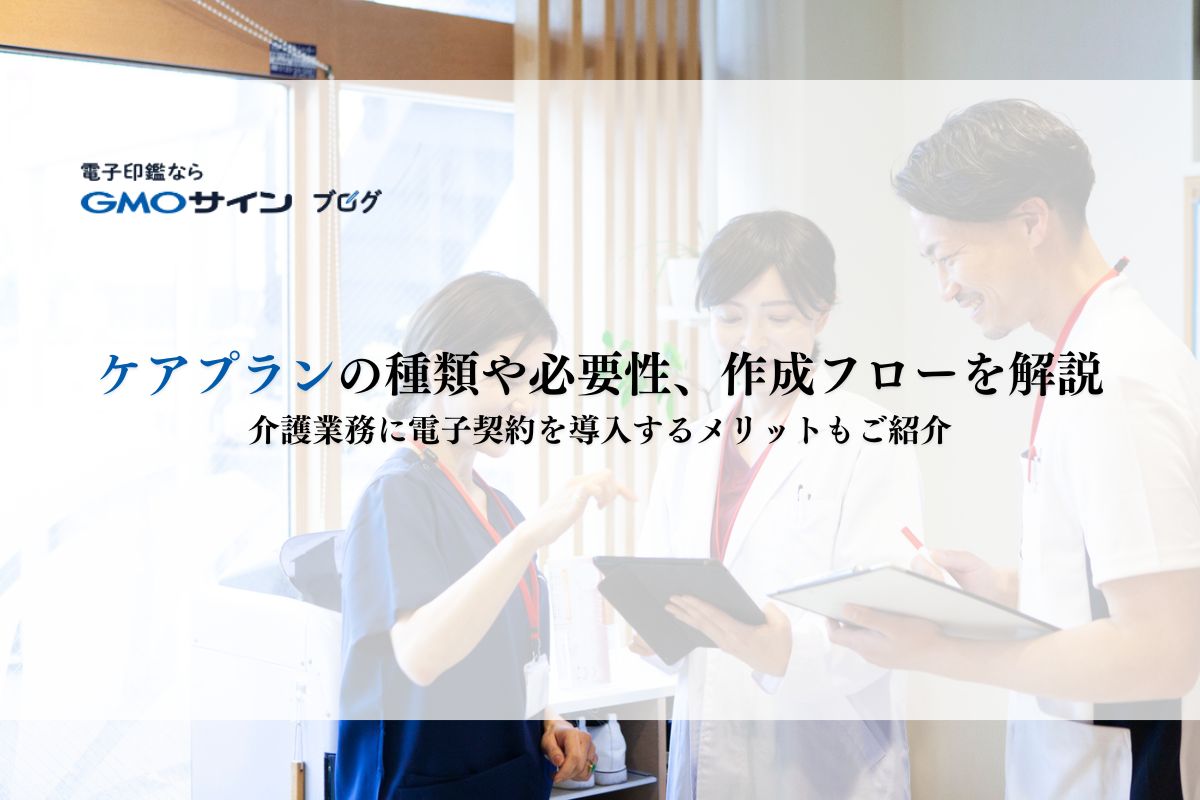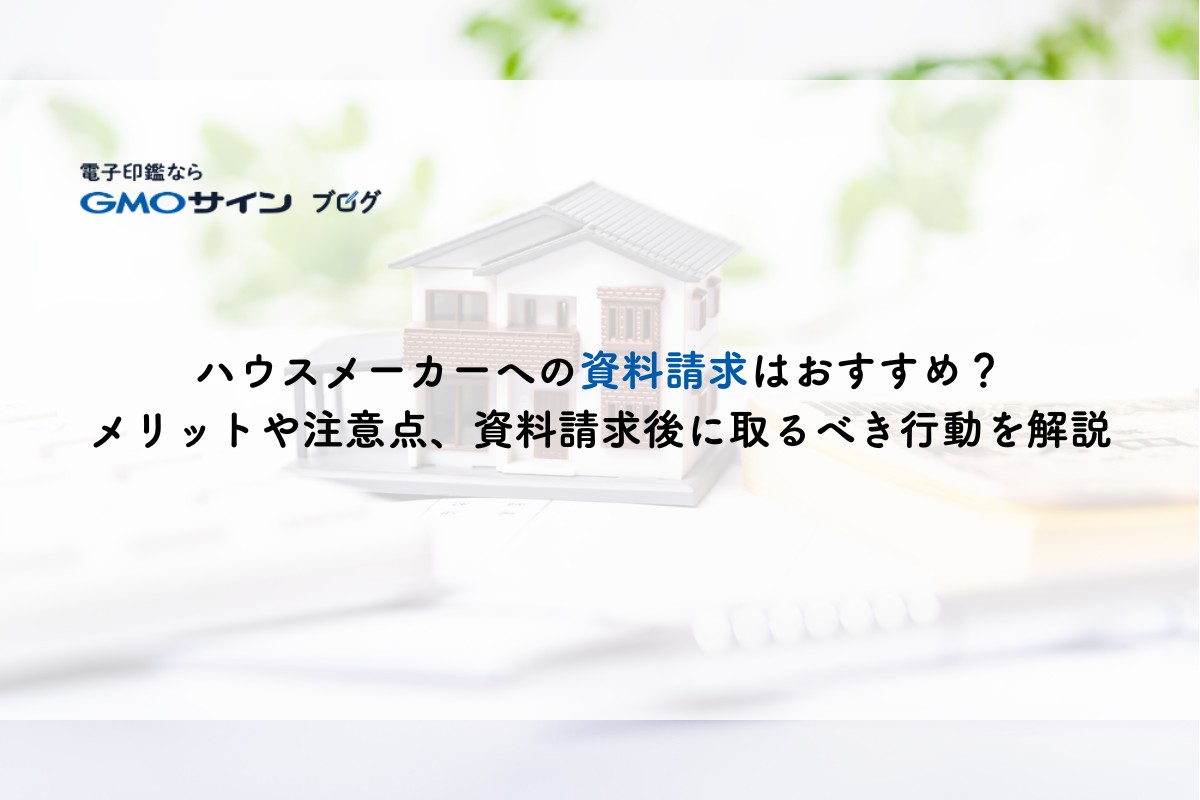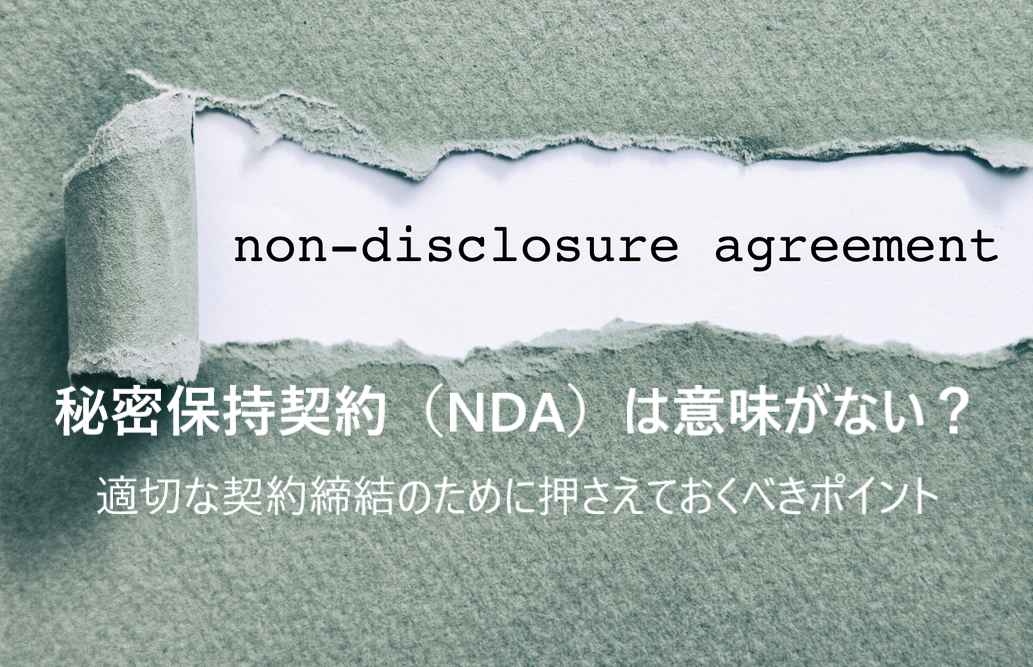\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /

\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /

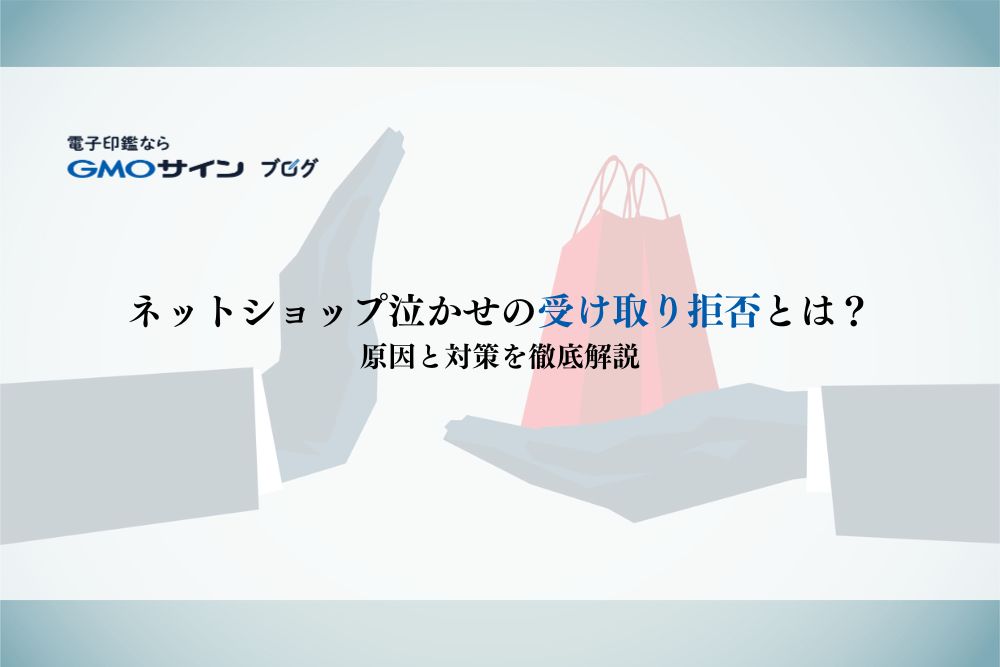
ネットショップの普及に伴い「受け取り拒否」という問題が深刻化しています。受け取り拒否とは、配送時に注文商品の受け取りが拒否され、商品がショップへ返送されることを指します。
ショップにとって「受け取り拒否」は死活問題ともいえる深刻なものです。商品代金の損失、送料・手数料の負担、梱包資材費、人件費など、さまざまな損害が発生するだけでなく、顧客からのクレーム対応や再発防止策の検討といった精神的な負担も伴うでしょう。
さらに、一部の悪質なケースでは、転売目的で複数の商品を注文し、市場価格の変動に応じて選択的に受け取り拒否を行うユーザーも存在します。転売者は自身のリスクを最小限に抑えつつ、利益機会を最大化しようとしているのです。
本記事では、こういった事例を踏まえて、ネットショップを悩ませる受け取り拒否の原因と、その対策について詳しく解説します。
受け取り拒否は、ネットショップにとって深刻な問題です。商品代金の損失や再発防止策の検討など、さまざまな負担が発生するだけでなく、悪質なケースでは法的措置が必要になる場合もあります。ここでは、受け取り拒否の具体的なケースと、それぞれの詳細について解説します。
可能性として、注文者ではなくネットショップ側に原因があり、受け取り拒否をされているケースもあります。ここでは一例をご紹介します。
このほかにも、配送業者のミスや自然災害の影響で、受け取り拒否が発生する可能性があります。
受け取り拒否のケースの中でもとくに多い、以下の5つのケースについて、対策を解説します。
決済手段を複数用意することで、購入者の利便性を高め、支払い能力の不足による受け取り拒否を減らすことが期待できます。
購入後に支払い方法を変更したいというケースも考えられます。注文確定後でも支払い方法を変更できる機能を導入することで、購入者の利便性を高め、受け取り拒否を減らすことが期待できるでしょう。
支払いに関する情報を注文ページや注文確認画面、FAQページなどにわかりやすく掲載することで、購入者が支払いに関する情報を事前に確認し、支払い能力不足による受け取り拒否を防げるでしょう。
悪意のあるユーザーを特定し、ブラックリスト化することで、悪質なユーザーによる注文を抑制できます。また、高額商品や転売目的と思われる注文には注意します。高額商品の注文や複数個同じ商品を注文しているケースは、転売の可能性が考えられるでしょう。上記のような注文には注意し、必要に応じて本人確認などを行います。
なお、悪質なユーザーが何度も受け取り拒否を繰り返す場合や、高額な商品を騙し取って転売するような悪質な行為を行った場合は、法的措置の検討が必要です。
注文時に、長期不在期間や不在先住所、転送先住所、連絡先などの入力欄を用意して、購入者から情報を収集しましょう。注文確認メールで、長期不在期間中に商品が届くことをあらためて通知し、転送サービスの利用や不在連絡先への連絡を促します。
ショップは、配送業者の保管期限を確認し、購入者に事前に通知します。
受け取り拒否を防ぐためには、ショップ側の不備をなくすことが重要です。ここでは、主に3つの観点から具体的な対策を解説します。
商品情報の充実は、顧客の期待と実際の商品のギャップを埋める重要な要素です。高画質な商品画像を複数枚掲載し、静止画だけでなく動画も活用しましょう。さらに、詳細なサイズ表や着用イメージ画像、360度回転画像やVR画像なども効果的です。スマートフォンやタブレット端末でも利用できる拡大鏡機能を導入すれば、顧客の利便性が大幅に向上します。
商品説明文では、素材、サイズ、重量、色味、機能などを具体的に記載し、専門用語は避けて平易な言葉で説明することが大切です。商品のメリットだけでなくデメリットも正直に伝え、オプションや付属品、使用上の注意やお手入れ方法なども漏れなく記載しましょう。
注文規約は、注文方法、支払い方法、送料、返品・交換条件、クーリングオフ制度、個人情報保護方針などをわかりやすく簡潔に記載し、目立つ場所に掲載します。注文確定画面にも規約へのリンクを設けることで、顧客の理解を促進できます。
顧客情報の管理は、不正注文を防ぐ上で非常に重要です。注文時には、電話番号やメールアドレス、SMS認証、クレジットカード情報による本人確認を徹底しましょう。場合によっては本人確認書類の提出を求めることも検討してください。
過去の注文履歴をデータベースで管理し、受け取り拒否やキャンセルが多いユーザー、虚偽の注文情報を入力しているユーザーを特定してブラックリスト化することも効果的です。
同時に、顧客情報の暗号化、不正アクセス対策、情報漏洩対策などのセキュリティ対策を強化し、顧客の個人情報を厳重に保護することが信頼につながります。
発送の遅延は受け取り拒否の大きな要因となります。これを防ぐためには、まずサプライヤーとの連携を強化し、商品の入荷状況を正確に把握することが重要です。納期遅延の可能性がある場合は、速やかに顧客に連絡を入れましょう。
注文処理システムの導入や人員配置の見直しにより、注文処理体制を効率化することも有効です。また、信頼できる配送業者を選定し、迅速かつ丁寧な配送サービスを提供することで、顧客満足度の向上につながります。
以上の対策を総合的に実施することで、ショップ側の不備による受け取り拒否を大幅に減少させることができるでしょう。常に顧客目線で改善を重ね、信頼されるショップ運営を心がけることが重要です。
これまで述べてきた対策を実施することで、受け取り拒否の問題に大きく対処できるでしょう。しかし、ネットショップの運営をさらに効率化し、顧客との信頼関係を強化するには、もう一歩進んだ取り組みが必要です。その解決策として、電子契約の導入が非常に効果的です。
電子契約サービスは、従来の紙の契約書に比べて多くのメリットがあり、ネットショップ事業者にとってとくに有用なツールとなります。以下に、その主要なメリットを詳しく見ていきましょう。
オンライン上で簡単に契約を締結できるため、紙ベースでのやり取りが不要になります。契約締結にかかる時間を大幅に短縮でき、「発送の遅延」問題の解決にも貢献します。顧客の待ち時間が減ることで、満足度向上にもつながるでしょう。
契約書を電子データで保存することで、物理的な保管スペースが不要になります。また、検索機能やフィルター機能を利用して必要な契約書をすぐに見つけられるため、「顧客情報の管理不備」の問題解決にも役立ちます。過去の取引履歴を即座に確認できることで、顧客対応の質も向上するでしょう。
電子契約では、契約書の内容を簡単に改訂・更新できます。これにより、商品情報や取引条件の変更を迅速に反映でき、「商品情報や注文規約の不備をなくす」という目標をより確実に達成できます。常に最新の情報を提供することで、顧客とのミスコミュニケーションを防ぎ、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
法的効力のある電子署名やタイムスタンプの利用により、契約内容の改ざんを防ぐことができます。これは、悪質な受け取り拒否や不正注文を抑止する効果があり、ショップの法的リスクを低減します。同時に、正当な顧客の権利も明確に保護されるため、双方にとって安心できる取引環境を構築できるのです。
電子契約の導入は、これまで説明してきた受け取り拒否対策を補完し、さらに強化する役割を果たします。顧客との信頼関係構築、業務効率化、リスク管理の観点から、ネットショップ運営の次なるステップとして強くおすすめします。
電子契約の導入を考えている小売業・販売業の方におすすめなのが、電子契約サービス国内シェアNo.1(※)の電子印鑑GMOサインです。GMOサインをおすすめする理由には以下が挙げられます。
※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)
電子印鑑GMOサインは、送信料1通あたり110円(税込)という業界最安水準の料金で利用できます。お試しフリープランもあるため、気軽に試すことが可能です。
電子印鑑GMOサインは、基本的な機能はもちろんのこと、以下のような豊富な機能が備わっています。
電子署名により、契約書の改ざんや偽造を防止できます。GMOサインの署名方法は以下の3通りです。
メール認証により本人性を担保できる電子署名方法です。月額基本料無料の「お試しフリープラン」でも利用することが可能です。スピーティーな契約締結に向いており、法人・個人を問わずに利用できます。
第三者機関である電子認証局による本人確認によってより厳格な本人性を担保できる電子署名方法です。月額9,680円(税込)の契約印&実印プランで利用可能です。法人実印相当の法的効果が認められます。
個人との契約において、マイナンバーカードを使うことで厳格な本人確認が可能な電子署名方法です。個人との契約で実印の代替となります。
※マイナンバー実印はオプション機能です。
そのほかにも、以下の機能が標準搭載されています。
タイムスタンプとは、電子文書の非改ざん性を担保するための技術的な仕組みです。タイムスタンプを付与することで以下の2点を証明します。
タイムスタンプは時刻認証局(TSA)によって付与され、時刻配信局(TA)が提供する正確な時刻を基にしています。そのため、文書作成時刻が信頼できる第三者によって客観的に保証されます。
電子契約で使用する電子署名やタイムスタンプには検証可能な期間が定められており、電子署名は1〜3年、タイムスタンプは約10年です。10年を超える契約の場合、タイムスタンプの有効期間内に追加のタイムスタンプを押すことで、検証可能期間を延長できます。
GMOサインでは、契約締結後に保管された文書に対し、システム上に最新暗号技術に基づくタイムスタンプを10年ごとに自動で付与します。長期保存が必要な契約も安全に管理可能です。
1回の送信で複数の文書を送信可能です。2文書以上送信した場合でも、1件あたりの送信料は変わりません。
署名依頼画面を「URL化」できます。不特定多数との契約などを効率化につながります。
スマートフォンやタブレットなどの端末を用いて、手書きでのサインにも対応しています。
電子契約で署名する際に、見た目を再現する印影を登録可能です。
設定された複数の署名者のうち、いずれか1名が署名をすれば完了する送信方法に設定可能です。
先方の担当者が署名依頼メールを紛失した際にも、署名依頼メールの再送が可能です。
フォルダごとに閲覧範囲を設定できます。そのため、部外秘の文書などの保管にも向いています。
GMOサインでは、導入時のサポートだけでなく、導入後のサポートも充実しています。標準サポートは、平日10:00~18:00で、電話・メール・チャットでのサポートを利用可能です。
また、機能別に使い方の説明動画が用意されているのも特徴です。さらに、活用方法を紹介するセミナーも随時開催されています。
電子印鑑GMOサインは、高度なセキュリティ対策を施しており、第三者による不正アクセスやデータ改ざんを防ぐことができます。取得済みの認証は、以下の通りです。
基本料金無料で使用できるお試しフリープランでは、以下の機能が利用できます。
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | ||
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | |
| 署名順設定(順列/並列) | ||
| アクセスコード認証 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
気軽にGMOサインを試したい方、電子契約の使い⽅や締結までの流れを知りたい方におすすめのプランです。また、契約印&実印プランでは対面契約オプションなど店舗向けのサービスも提供されています。
\ 月額料金&送信料ずっと0円 /
受け取り拒否は、ネットショップにとって深刻な問題です。しかし、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑えることは可能です。それぞれのケースに合わせた具体的な対策を参考に、自分たちのショップに合った対策を検討します。そうすることで、ショップの利益を守り、顧客満足度の高い運営を実現できるでしょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。